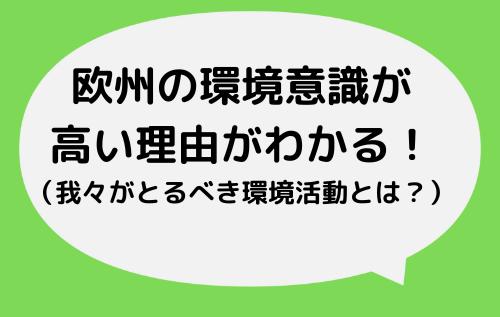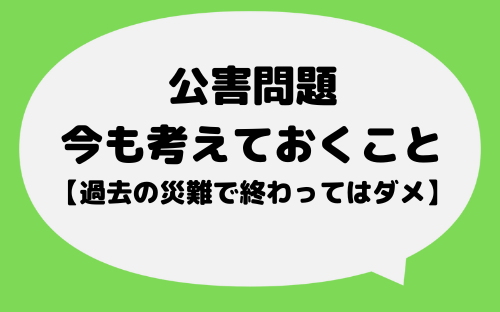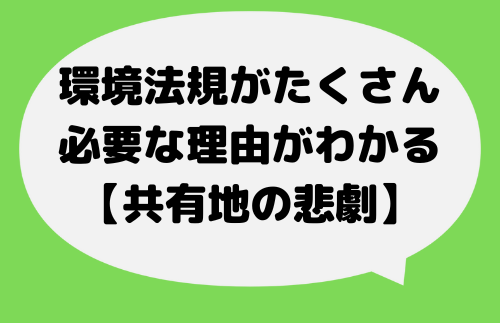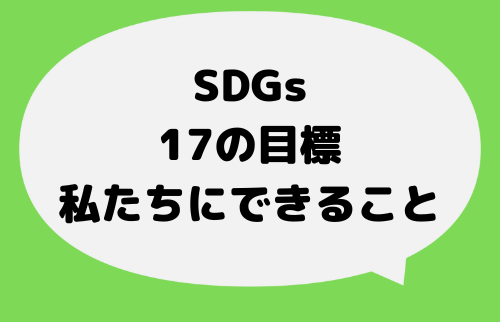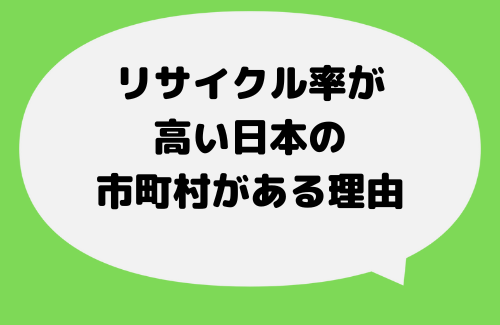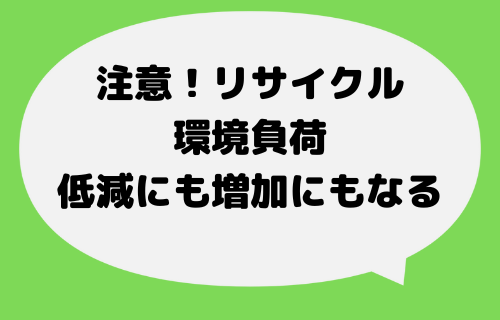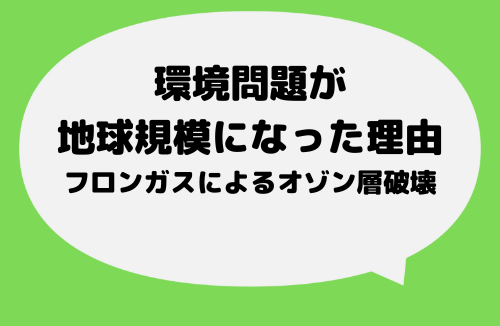★ 本記事のテーマ
- ①「ヨーロッパの環境意識が高い」よくある理由
- ②ヨーロッパの環境意識の背景を再考する
- ③ヨーロッパは環境意識が強いホントウの理由
- ④我々日本が取るべき環境活動
①「ヨーロッパの環境意識が高い」よくある理由
ヨーロッパ諸国は環境意識が高く、日本の見習うべきものがあります。
- 歴史的背景:産業革命以降の公害経験
- 市民の強い問題意識:生活や健康に直接影響
- 強力な政策と国際的リーダーシップ
どれも素晴らしい理由ばかりです。

②ヨーロッパの環境意識の背景を再考する
確かにヨーロッパ諸国の環境への取り組みは素晴らしいですが、
- 高い税金かけても環境を守りたいか?
- 細かいルールや法令などを律儀に守り切れるのか?
- 環境意識の低い超大国に経済力、政治的にビハインドにならないのか?
となると、疑問に思うのが
・日本にいる我々はここまでやる必要があるのか?
気になりませんか?
そこを理解した上で日本にいる我々は日本独自の環境意識を磨けばいい
と考えた方がよいでしょう。
冷静に見極める必要があります。
③ヨーロッパは環境意識が強いホントウの理由
とは何か?
を考えてみましょう。
ホントウの理由を列挙
ヨーロッパ諸国の地理条件を考えると、
- 1.ヨーロッパは1つの大陸にたくさんの国々がある。
- 2.戦争の歴史で領土、国境は神経質。
- 3.一方、他大陸(特に、アメリカ、中国、日本)との国際力の競争が激しい。
という、
ヨーロッパ内部の課題
と
ヨーロッパ外部の課題
があります。

ヨーロッパ内部の課題
- 1.ヨーロッパは1つの大陸にたくさんの国々がある。
- 2.戦争の歴史で領土、国境は神経質。
1つの大陸に10以上の国があり、戦争の歴史でもあります。
EU統合とはいえ、基本は利害関係がある国々です。
そのため、以下の環境課題に敏感にならざるを得ません。
- 越境大気汚染⇒国家間の問題
- 国際河川での水質汚濁⇒国家間の問題
- 廃棄物による埋立⇒領地、国境問題でもめる
となります。
興味深いのがが、
国際河川での水質汚濁も
廃棄物による埋立も
他大陸(特に、日本、アメリカ)にはあまり利害が発生しないもの
もちろん、環境法規を遵守しなければなりませんが、
公害被害による健康安全のリスク
に加えて、
周辺各国との関係
も神経質にならざるを得ないことを
我々は理解しましょう。
ヨーロッパ外部の課題
- 3.一方、他大陸(特に、アメリカ、中国、日本)との国際力の競争が激しい。
よく、電気自動車の環境への良いイメージとガソリン車の環境の悪いイメージがありますが、
前者は、ヨーロッパ諸国、後者は日本・アメリカ
と比較されることがあります。
ヨーロッパ諸国にとって、
世界市場(シェア)を奪われることがリスク
と考えます。
ヨーロッパ諸国の環境事情は結構大変であることがわかりましたね。
ヨーロッパの課題を逆に強みにするには?
あなたがヨーロッパ諸国のリーダとします。
世界の中で優位な位置に立つにはどうしたらよいでしょうか?
を考えるはずです。
その答えが
ヨーロッパ諸国の環境意識・活動のすばらしさをアピールし、
環境負荷がかからないヨーロッパ諸国の優位性を確立すること
となるわけですね。これが、見習うべきヨーロッパ諸国の環境活動や意識となると考えることができます。

④我々日本が取るべき環境活動
冷静に判断しよう!
我々日本は輸出型ではありますが、GDPの大半は国内です。
確かに、四大公害病などの苦しみの歴史があるため、環境対策は世界レベルであるべきは当然ですが、
自分たちが苦しむことがない点だけ注意が必要です。
国際機関からの提案があったとしても、
私たちにとって本当に必要か?
特に
誰も否定できない概念や仕組
は要注意!
そして、
相手の【見えない下心も】がある可能性があります。
日本独自で環境を考えるべき1つの例は、
ガソリン車は環境に悪いから禁止!
は本当に正しいのか?
確かにガソリン車は環境負荷が多いとする地域があるかもしれませんが、
そうでない地域もあります。
冷静な判断が必要です。
冷静に判断するにはどうすればよいか?
環境系を研究すると、常に悩むのが、
本当に正しいのか?
見えない嫌なもの(既得権益、癒着、一部の利益搾取)
がないか?
を一度疑うこと
でも、こういう人はおそらく環境系の仕事していない可能性も高く、
こういうことを口に出すと村八分にされる気がします。
だからこそ、
本当に正しいのか?
を一度疑うこと
クリティカルシンキングなどを活用して物事を俯瞰して客観的に見ていく必要があります。
まとめ
以上、「ヨーロッパの環境意識が高い理由がわかる」を解説しました。
- ①「ヨーロッパの環境意識が高い」よくある理由
- ②ヨーロッパの環境意識の背景を再考する
- ③ヨーロッパは環境意識が強いホントウの理由
- ④我々日本が取るべき環境活動