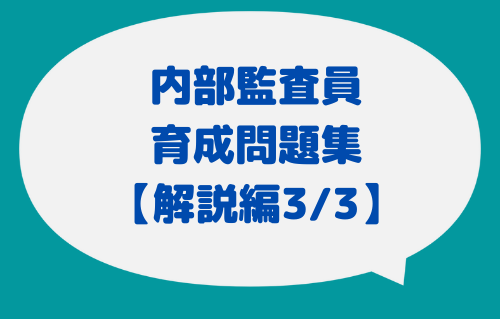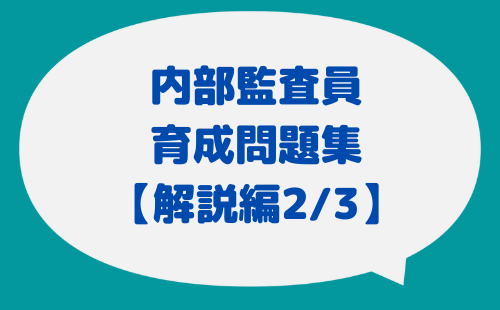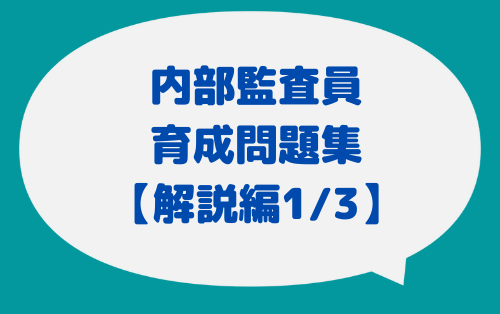カテゴリー: 第三者監査(外部審査)
-
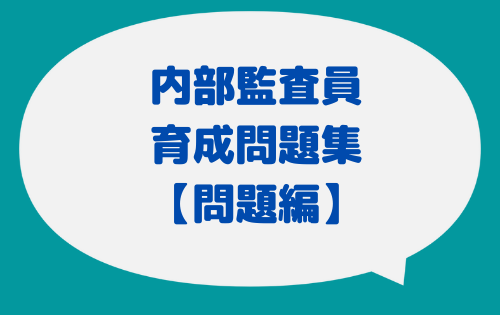
ISO9001 2015 内部監査員育成する問題集【問題編】
★ 本記事のテーマ
ISO9001 2015 内部監査員育成する問題集【問題編】問題内容を説明します。
★ 本記事のテーマ
ISO9001 2015 内部監査員育成する問題集【問題編】★おさえておきたいポイント
- ①本問題集を作った思い・背景
- ➁本問題集は「問題テキスト」と「問題&解説ブログ」があります
- ➂問題編
- ➂問題編
- ➃演習問題を公開します
- ➄購入方法
①本問題集を作った思い・背景
内部監査員、外部審査員を
養成するための問題集の
問題内容を説明します!
–
●ISO9001 2015要求事項のおさらい
●ISO9001 2015要求事項を満たす文書群の作成
●内部監査(外部審査)の模擬演習
●監査後の受審側の改善対応
●内部・外部の課題の変化との順応
を1冊の問題集で演習できます!–
一般的な品質監査員の養成教育は
・2日コースで、2日間丸々拘束される
・一日目(終日)がISO9001 2015の復習、監査の基本的なやり方
・二日目(終日)が終日演習
・ディスカッション時間が多く、自分で考える時間が少ない
・監査報告書を書きやすくするために粗が多い問題設定が多くリアリティーに欠ける
・費用が5万円~10万円と高いなど、費用のわりに、やや不完全燃焼な講義しかないのが現状です。
そこで、
・自分の好きな時間で勉強ができて、
・ISO9001 2015の復習もできて、
・監査演習ができて、
・他にはない、監査後の改善活動まで考える演習ができる
・数千円で可能な問題集を作りました!➁本問題集は「問題テキスト」と「問題&解説ブログ」があります
問題テキスト
「➄購入方法」で説明します。
問題&解説ブログ
問題編(本サイト)と3つの解説ブログ(パスワード付き)があります。演習を進めると、解説ブログを読むことができます。
- 問題編(本ブログ)
- 解説編1(パスワードあり)
- 解説編2(パスワードあり)
- 解説編3(パスワードあり)
➂問題編
舞台は街中のパン屋さん
パン屋さんの概要
30歳の夫婦Aさん(夫)、Bさん(妻)(子供はいないが欲しいと願っている)でパン屋が今回の舞台。2人とも数年間修業して今回 街中に出店した。パン屋さん兼住宅を購入。
●営業時間:6:00-17:00
●定休日:月曜日(祝日なら火曜日)、年末年始、お盆パン屋さんの周辺は、半径200mにマンション 300世帯(1000人、車を持っている)、 戸建30世帯(100人、車を持っている)と、空地が多いが、今後建屋が増える見込みである。もう少し行って300m先に大きな高架駅がある。駅周辺に、10数階建ての大きなオフィスビル4棟が駅を囲むようにある。
なお、街1km2にパン屋さんは少ない。また、住宅は1戸20m×30mくらいと大きな家が多く、土地が広いため、自動車を使う世帯が多い。パン屋さんに数台の駐車スペースがある。自分の店の強みの1つとして、ISO9001 2015を取得しようと、ISOプロのあなたにコンサル・内部監査官を依頼している。
パン屋さんと街中のイメージ
地図と、周辺の状況がわかる動画をYou Tubeにアップしています。ご確認ください。
★ 地図

★●パン屋さん内部(ここからダウンロードできます)

★●動画(You Tube) 10分程度
パンの製造工程
専門性を高くする必要はありませんが、販売しているパンの種類と製造方法を列挙します。
パンの製造工程は
①ミキサ
➁フロアータイム(1次発酵)
➂分割
➃成型
➄ベンチタイム
⑥ホイロ(2次発酵)
⑦焼成
と一般的な工程でパンの種類によらず、一定の時間がかかるとします。販売パンは7種類
A:レーズン
B:食パン
C:ソフトフランス
D:フランス
E:菓子パン
F:ドーナツ
G:バターロール
とします。
実際、パン屋工房内には、オーブンが1台しかないため、オーブンをフル活動できるように時間調整しながらパン製造をしていきます。
パン屋さんの情報は以上です。だいぶイメージが付いたかと思います。では、ISO9001 2015と品質監査に向けた準備をしてきましょう。
➃演習問題を公開します
21問あります。紹介します。
第1章 ISO901 2015要求事項を満たす文書群を作成
舞台の街中パン屋さんに必要なISO9001 文書群を構築します。ISO9001 の復習・応用演習になります。
–
★【1】ISO90012015の適用範囲
パン屋さんで取得する場合の、ISO9001 2015の適用範囲をどう設定するか、考えよ。★【2】外部の課題、内部の課題
ISO9001 2015の要求事項4.1において、「パン屋」の外部の課題、内部の課題を列挙せよ。また、あなたがAさんになって、パン屋さんの数年間の中計を立てよ。【3】~【15】は略(ご購入後、確認できます。
–
★【16】内部監査
ISO9001 2015の要求事項9.2において、「パン屋」の内部監査の監査実施結果報告書のフォーマットを作成せよ。第1章で構築した文書群にさらに内容を肉付けして、第3章の内部監査の準備を整えましょう。第2章 初めての内部監査
【17】~【18】は略(ご購入後、確認できます。
–
★【19】監査員役であるあなたによる内部監査評価
【17】【18】の資料をもとに、内部監査を実施したとする。その監査結果を評価し、内部監査報告書にまとめよ。第3章 初めての内部監査
本問題集にしかないオリジナル問題で、監査後のフィードバックや継続的改善も演習しましょう。監査は手段、目的は改善ですからね!
–
★【20】不適合の是正処置
【19】監査結果から不適合箇所がある。その不適合箇所の是正処置をあなたがAさんの立場で実施せよ。第4章 Aさんパン屋さんのハプニング
本問題集にしかないオリジナル問題で、ISO9001取得組織にはあまりない事象かもしれませんが、常に内外の環境変化に対応していく強さも必要です。パン屋さんに降りかかるリスクを洗い出し、品質文書群のどこをどう更新・変更すればよいかを考える章です。
–
★【21】ハプニング発生時の対応
次のハプニングが起こった場合、それぞれのリスクや機会を考えて、ISO文書群のどこをどう変更管理すればよいかを考えよ。
(1) 実は、思っていたほど売上がなく、赤字になった場合
(2)(3)略
(4) 近くに競合パン屋さん(Aさんのパン屋さんより大きなパン屋さん)が開店した場合問題は以上となります。
●ISO9001 2015要求事項のおさらい
●ISO9001 2015要求事項を満たす文書群の作成
●内部監査(外部審査)の模擬演習
●監査後の受審側の改善対応
●内部・外部の課題の変化との順応
を1冊の問題集で演習できます!解説も充実!
丁寧な解説ページやQCプラネッツのブログ記事を活用してわかりやすく解けますので、ご安心ください。
是非、ご購入ください。
➄購入方法
本ブログとメルカリとnoteから販売しております。
「QCプラネッツ」で検索ください。本ブログからのご購入
ご購入いただけます。ご購入後、QCプラネッツからアクセスサイト先(アクセスのみ可)をご案内いたします。データの拡散を防ぐため、ダウンロードと印刷は不可とさせていただきます。
メルカリでの販売
「QCプラネッツ」で検索ください。

3000円/1冊
とさせていただきます。ご購入よろしくお願いいたします。noteでの販売
電子販売もしています。こちらへアクセスください。

noteからでもご購入できます! まとめ
「ISO9001 2015 内部監査員育成する問題集」を販売します」、ご購入よろしくお願いいたします。
- ①本問題集を作った思い・背景
- ➁本問題集は「問題テキスト」と「問題&解説ブログ」があります
- ➂問題編
- ➂問題編
- ➃演習問題を公開します
- ➄購入方法