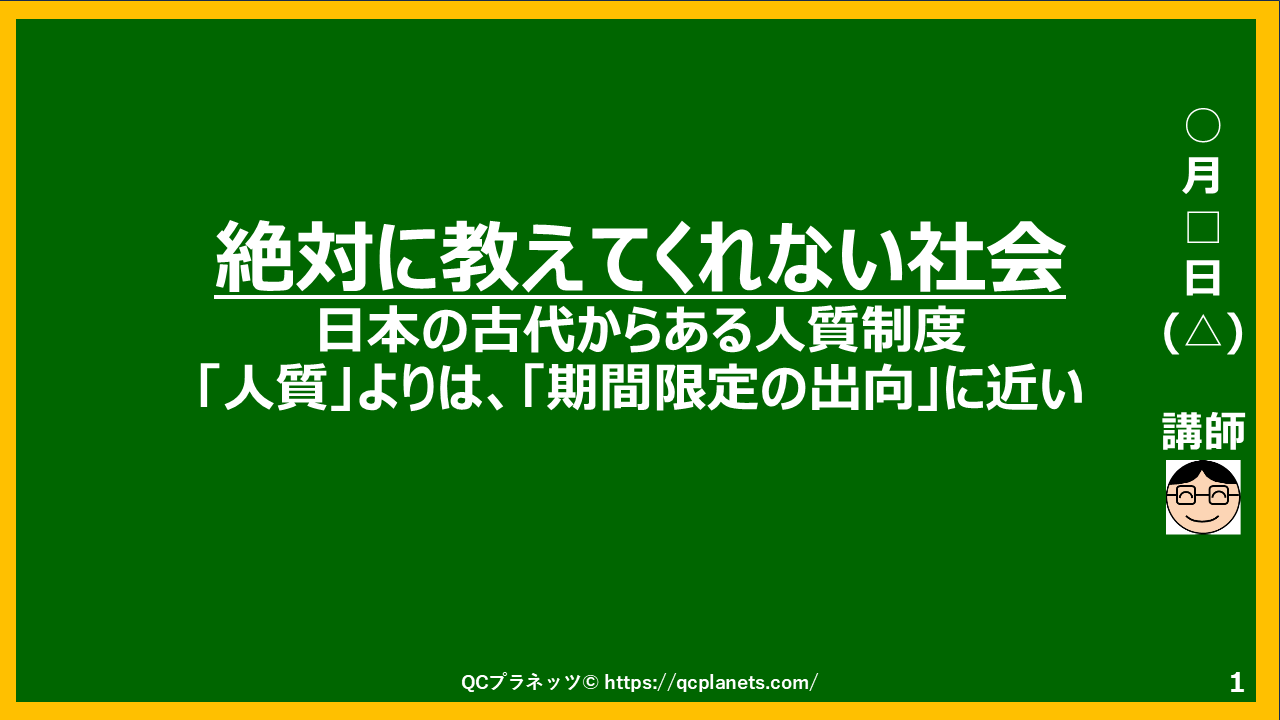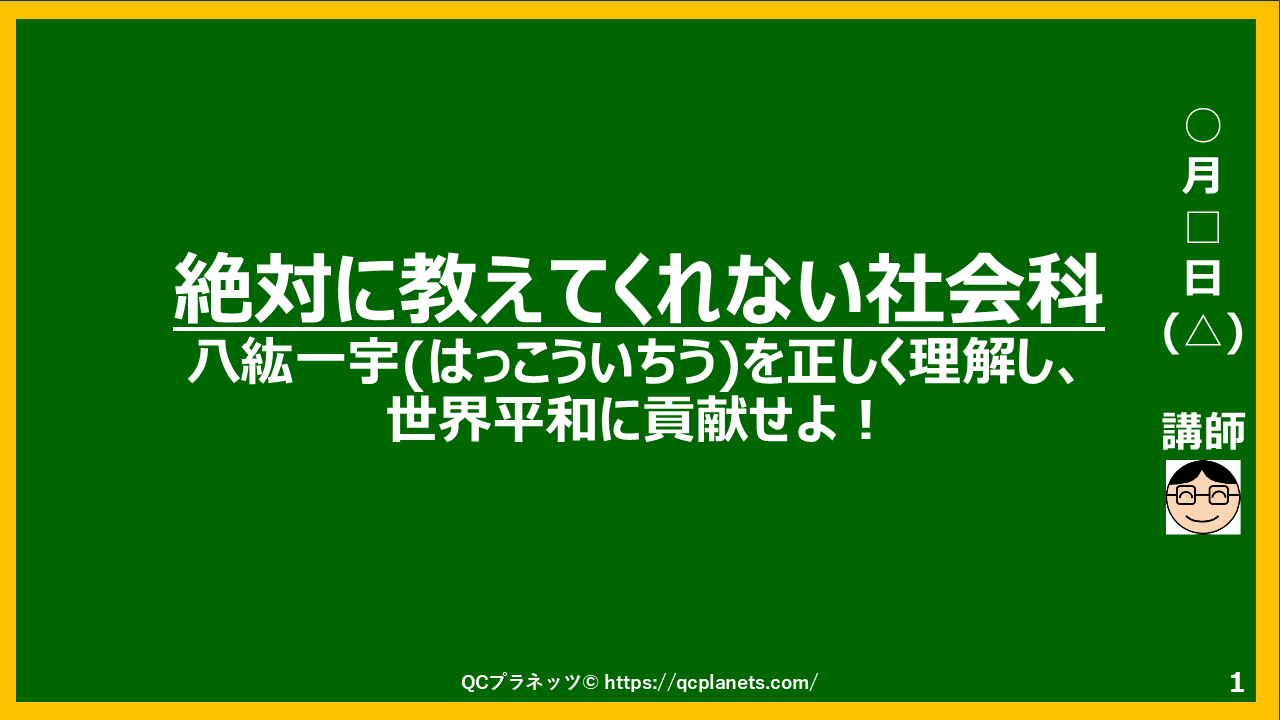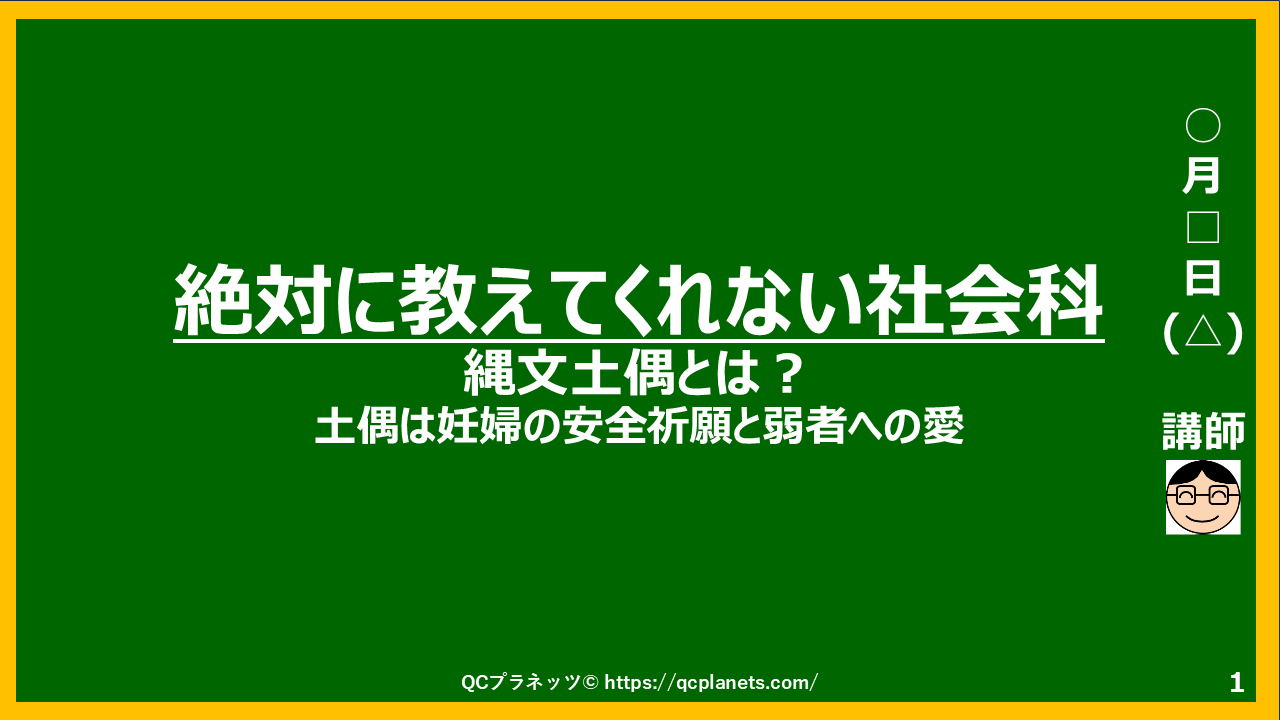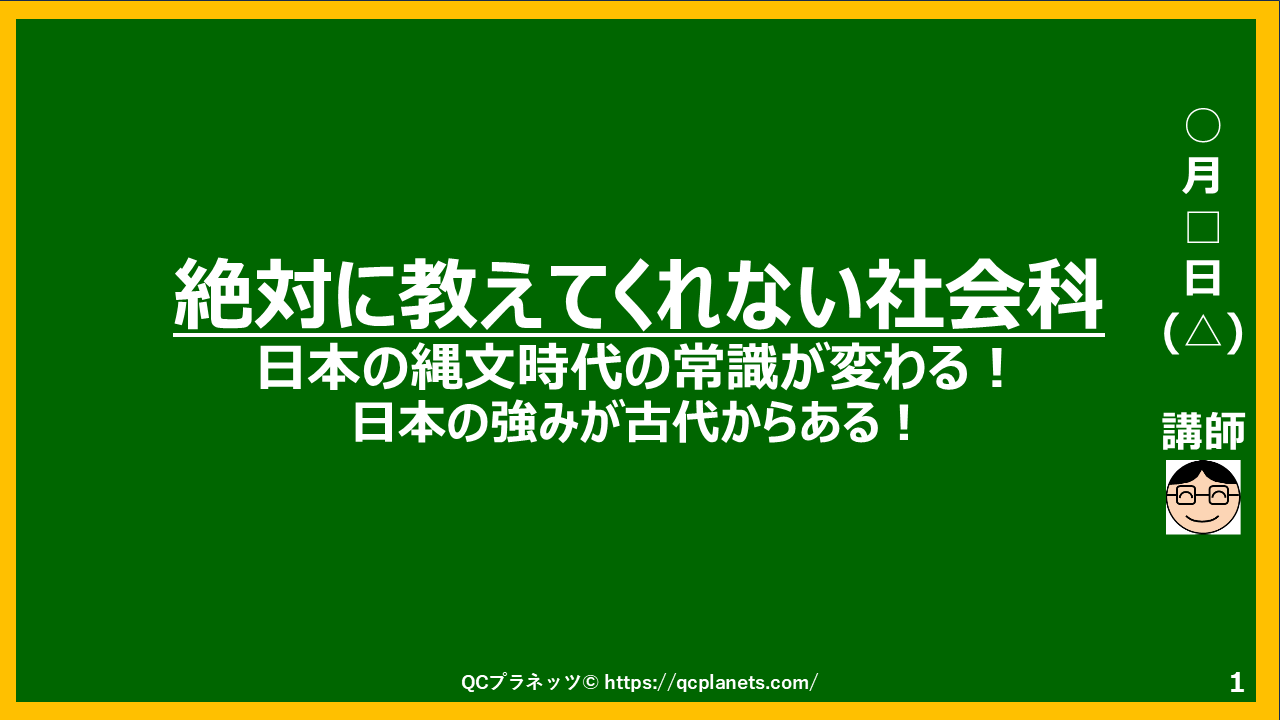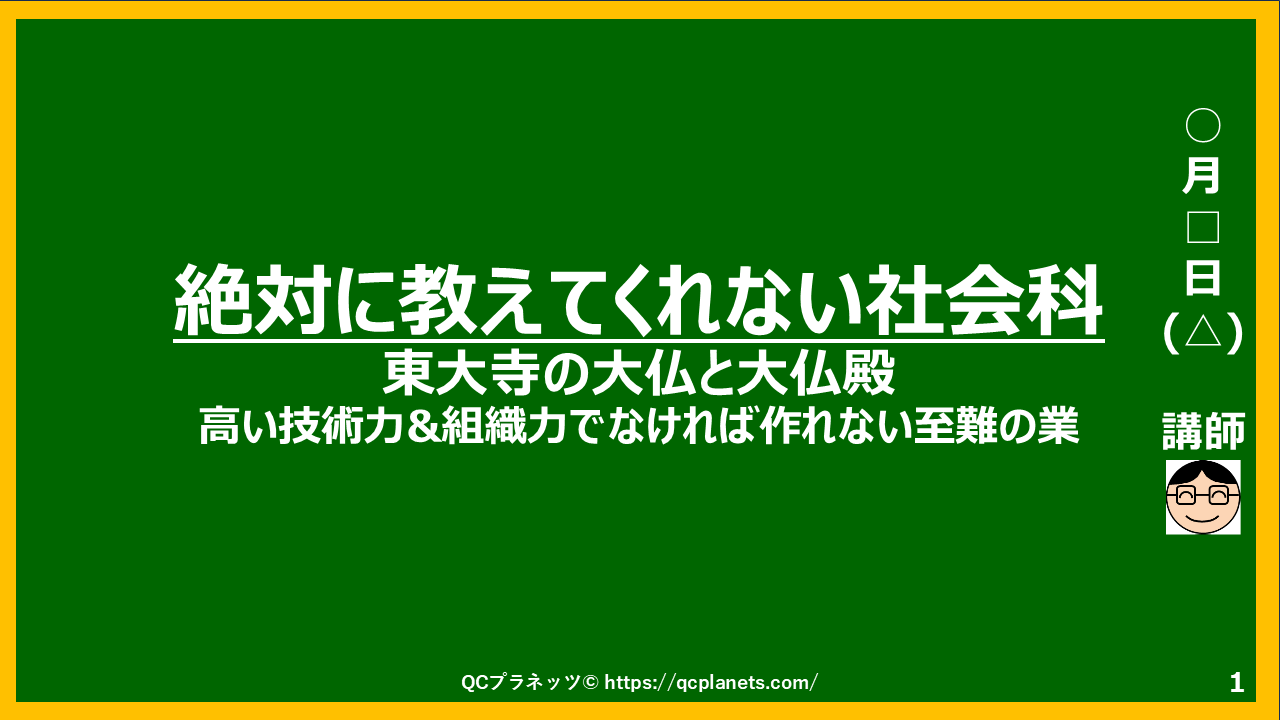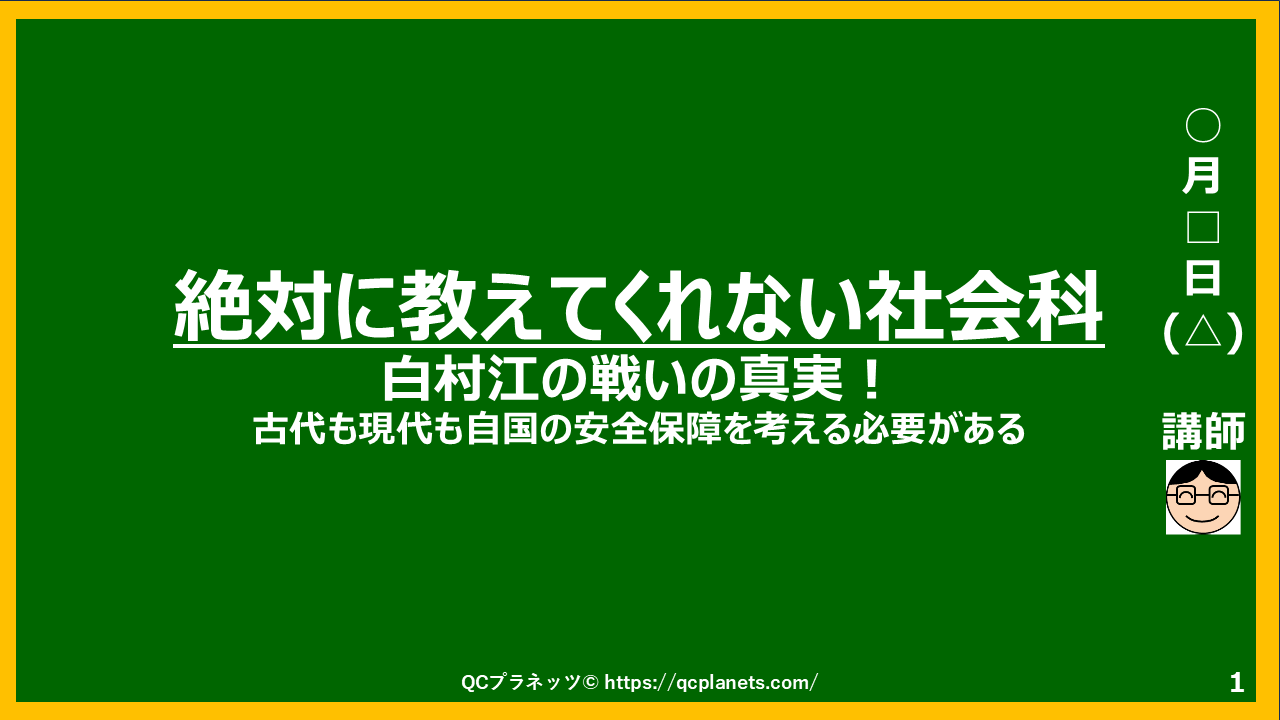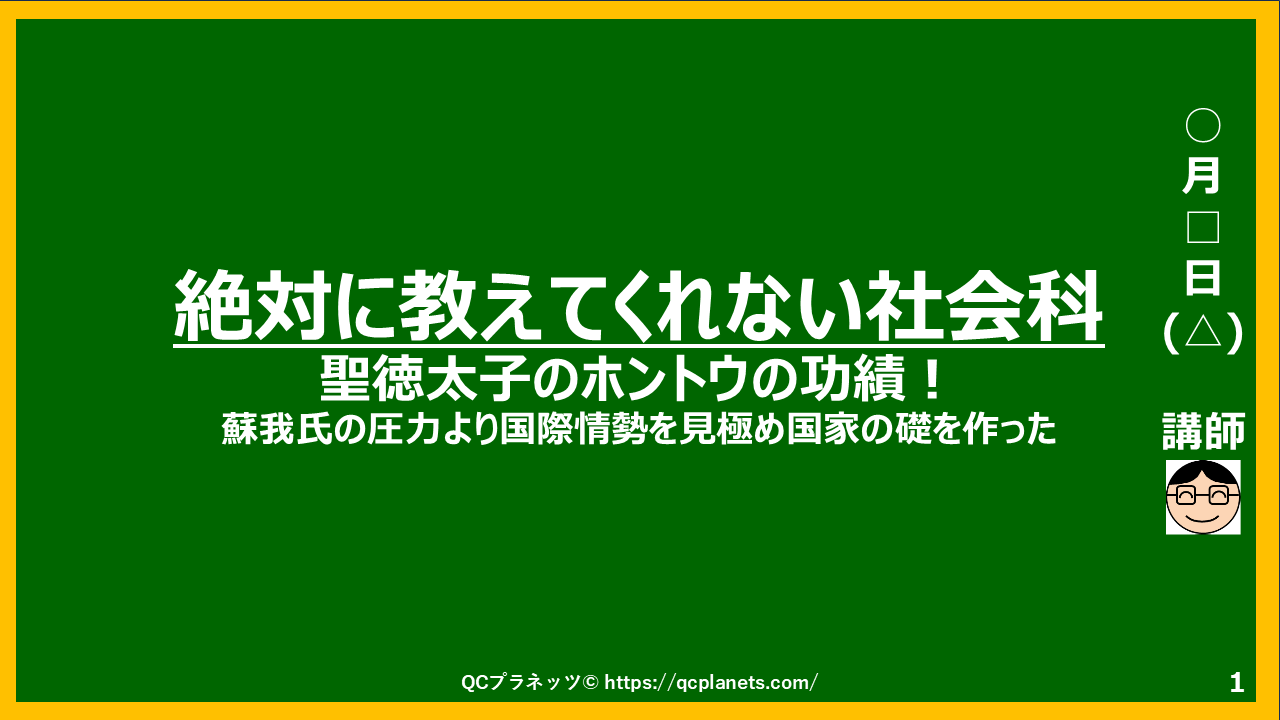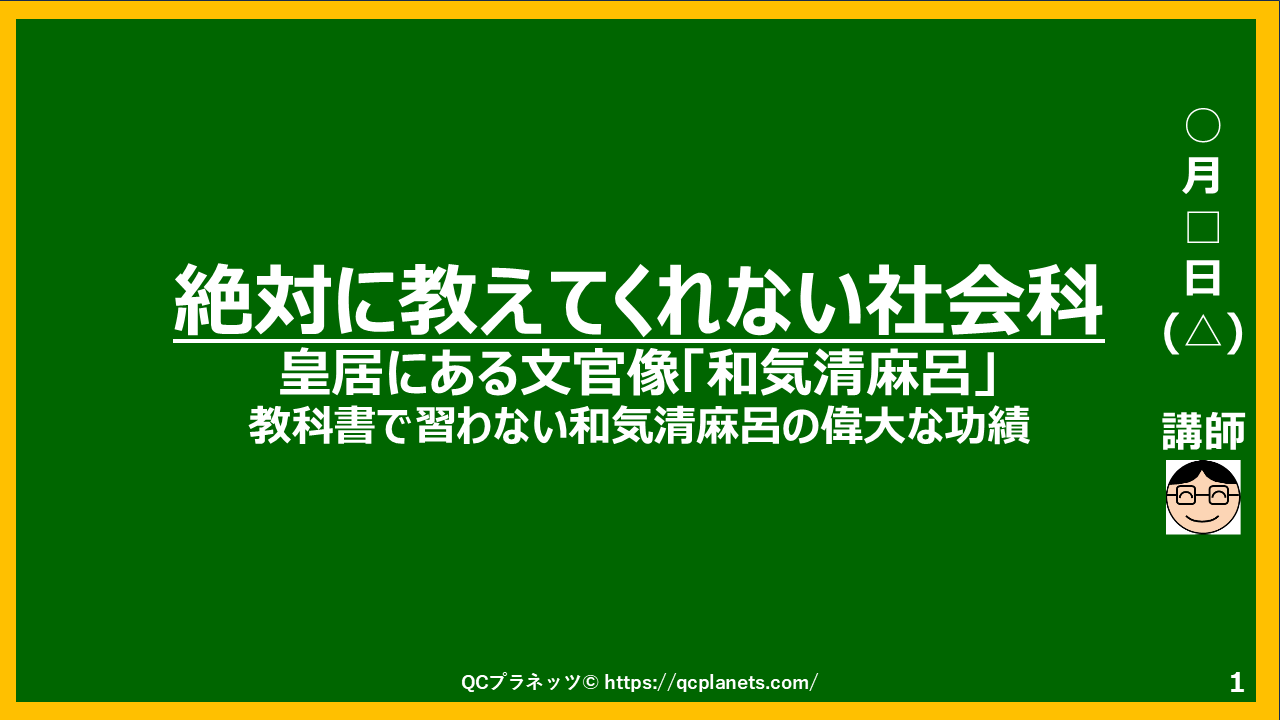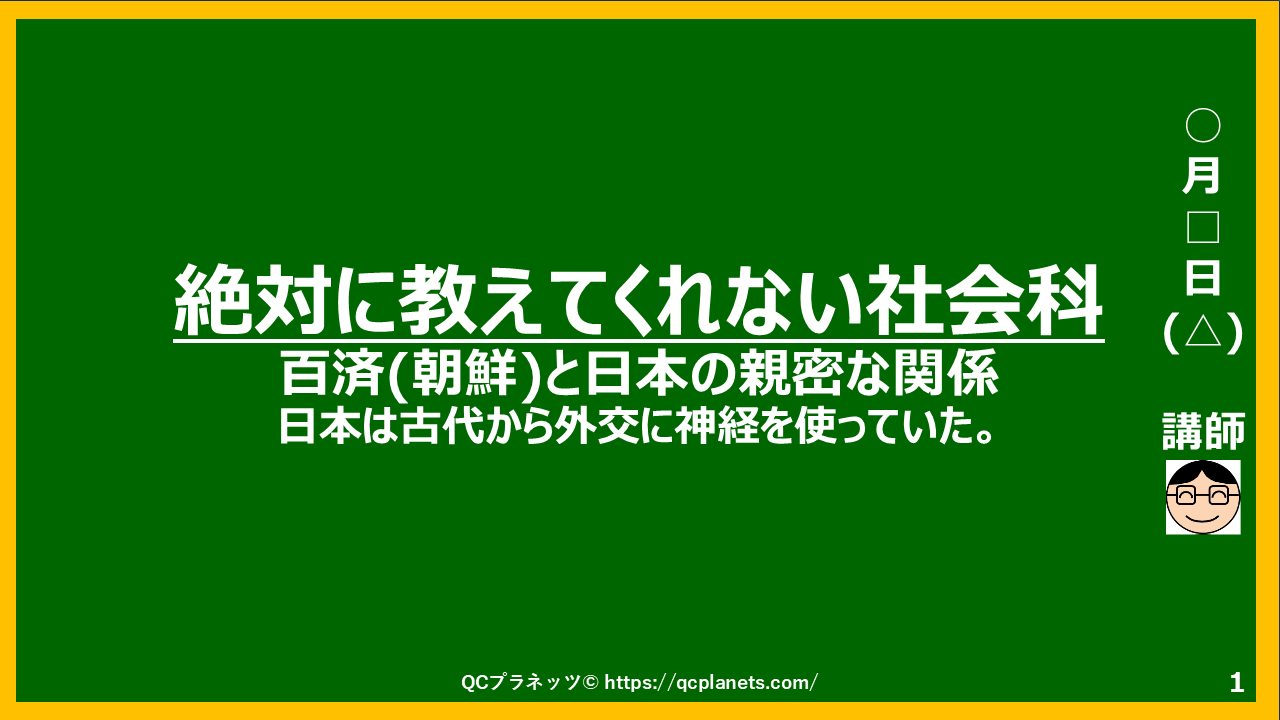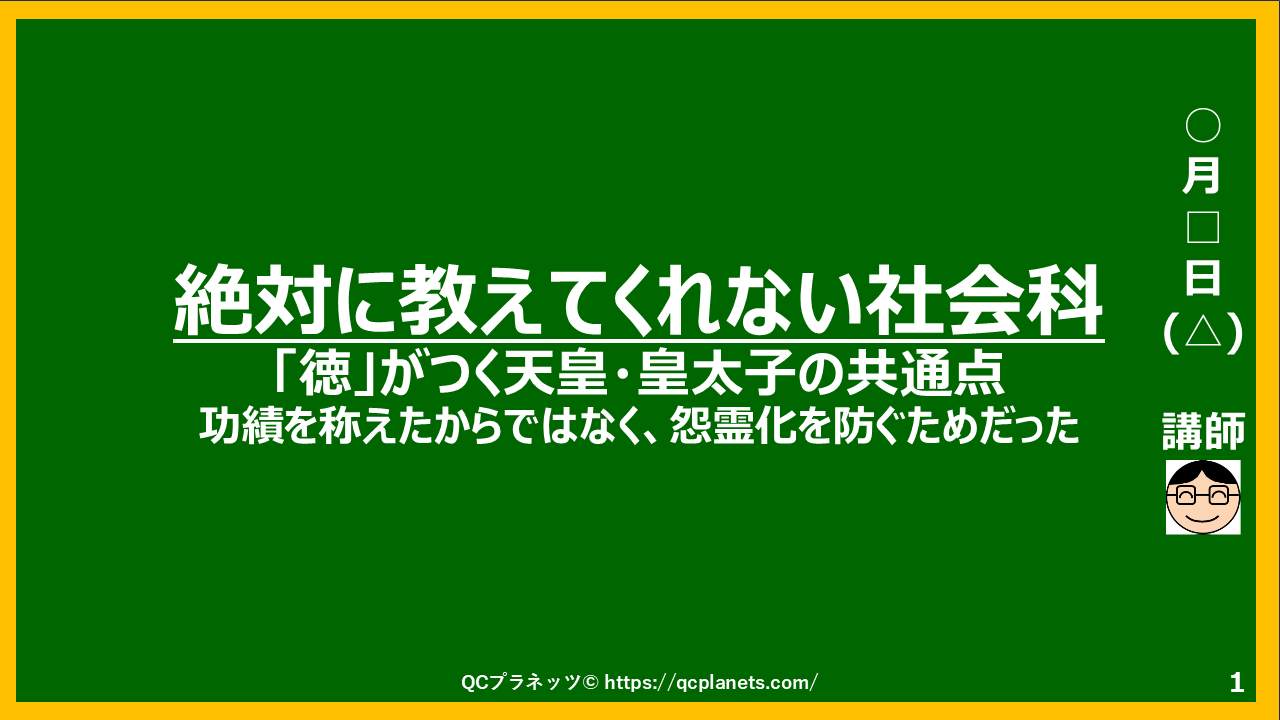★ 本記事のテーマ
百済(朝鮮)と日本の親密な関係
日本は古代から外交に神経を使っていた。
★おさえておきたいポイント
- ①通説
- ➁通説に対する疑問点・気になる点
- ➂通説を検証して見えた真相
学校や試験対策の社会では、
真相はわからない!
自分で調べて考え抜く
本当の社会科を勉強しよう!
①通説
古代の日本と朝鮮の関係(通説)
教科書、学校、塾、親から教えてくれる内容は以下ですよね!
- 古墳時代から飛鳥時代にかけての朝鮮半島の三国と日本の関係
- 百済は倭国と友好関係を築き、仏教・漢字・儒教など文化が伝わった
- 技術者や渡来人が日本の古墳文化や律令制度の形成に貢献。
- 百済は高句麗・新羅との戦いで日本に軍事支援を要請し、倭国は援軍を送った。
- 391年に日本が朝鮮半島に出兵し、百済と新羅を破った。
- 600年任那滅亡による新羅征討のため出兵。
- 663年白村江の戦いで倭国は唐・新羅連合軍に敗北
飛鳥時代以前も朝鮮との深い関係があり、何度も出兵していたことがわかる
➁通説に対する疑問点・気になる点
調べると気づく疑問点
参考文献やYoutube動画を調べていくと、通説と異なることがわかります。それを陰謀論として片づけてしまってもよいですが、物事は多面的に見て、客観視する必要があります。QCプラネッツは品質管理を専門としています。品質管理は客観視が必須です。同じ姿勢で取り組みます!
日本は何度も危険を冒してでも対岸の朝鮮半島へ乗り出したのか?
いかがでしょうか?疑問が湧きますよね!
・海の隣国までわざわざ攻め込んだのはなぜか?
・対岸の火事として大人しく見ておけばよかったのではないか?
真相を説明します。
➂通説を検証して見えた真相
考えるポイント
★ 古代の日本の安全保障
下図に、日本の脅威をまとめました。

①日本にとっての脅威(どの時代も)
・日本と朝鮮は超大国中国からの脅威にさらされてきた。
・日本は独立、朝鮮は冊封(属国化)を歩んできた。
・日本にとっての脅威は中国からの侵略または、中国と朝鮮が手を組んで日本に侵略することである。
・そのため朝鮮との外交、中国に使いを送り対等な関係を作り独立を守る必要があった。
②中国が内乱状態のときは脅威ではない
・中国国内が内乱状態の場合、日本に侵略するリスクは低い。
・中国に使いは送る必要はない(危険な航海するメリットがない)。
・朝鮮を支配するチャンスであるが、日本はそれをしなかった。
(自国の安全保障が最重要)
③5世紀の中国・朝鮮・日本
・中国に宋、北魏があり、強い国高句麗が朝鮮にあった。
・北魏と高句麗が良い関係になり、両者が連携して、百済、日本に攻めるリスクが高まった。
・日本から宋へ使いを送り、北魏のリスクをさげようとした。
④663年 白村江の戦い
(日本にとって最悪の事態)
・唐と新羅が同盟を組み、百済を滅亡させた。
・対馬海峡を越えて日本に攻めてくるリスクが非常に高まった
・百済救済のため、朝鮮出兵した。
いかがでしょうか?
常に、隣国からの脅威に対して、自国の安全保障が重要なことがわかります。
これが、飛鳥時代における聖徳太子の政治に強く影響を与えたのではないか?
律令政治、万全な日本の国家体制構築につながっていったのではないか?
と考えることできます。
★ 日本は基本安全保障による行動をとってきた
日本にいれば、周辺を支配したいという考えにならにくい。
周囲からの脅威があり、自分で守るための行動によることがほとんど
日本の歴史では、確かに他国への統治や出兵がありますが、どれも、侵略・略奪よりは、日本を守るための方が強い理由であることがわかります。一例をあげます。
| 例 |
理由(の1つ) |
| 663年 白村江の戦い |
唐(中国)・新羅(朝鮮)が日本に攻めてくる脅威が現実化しかけたから。 |
| 1174年 元寇 |
元が日本に攻めてきたから。 |
| 1592年 豊臣秀吉朝鮮出兵 |
スペインが明を支配した場合、スペインが日本に侵略するリスクが高まった。明、朝鮮より強い日本を見せる必要があったから。 |
| 1910年 韓国併合 |
列強による支配を恐れ、日本が朝鮮を統治したから。 |
| など |
– |
上表以外の理由もありますが、
日本の安全保障はどの時代もしっかり考えておく必要があり、常に神経を使っていたことがわかります。それが日本の独立できた理由の1つと言えます。
百済、新羅があった時代について細かく見てみましょう。
真相
主に3つの視点で見ましょう。
- 古代から何度も朝鮮半島へ外交・出兵を繰り返してきた。
- 朝鮮南部は当時の日本の生命線といえるほど重要な地域だった。
- 朝鮮には日本にとって厄介な新羅と高句麗があった。
★ ①古代から何度も朝鮮半島へ外交・出兵を繰り返してきた。
- 仲哀9年(200年)に朝鮮に出兵し、新羅は戦わずして降伏し、高句麗と百済も服従した。(日本書紀)
- 神功皇后51年(251年)に百済が日本に最初の朝貢。以降、日本は百済の鉄資源を独占。(日本書紀)
- 391年に日本が朝鮮半島に出兵し、百済と新羅を破って臣下にし、399年日本と百済が強固な同盟を結んだが、400年に高句麗が新羅を助けて日本側を追撃。(好太王碑文)
- 大和朝廷が朝鮮半島に出兵し百済を助けるために高句麗と戦い負けた。(好太王碑文)
★ ②朝鮮南部は当時の日本の生命線といえるほど重要な地域だった。
- 古代の朝鮮半島南部は日本に採れない鉄資源が豊富。任那、百済と親密な関係が必要だった。(日本は百済でとれる鉄・大陸の文化を欲し、百済は日本からの安全保障を求めた。)
- 百済の王族は日本で暮らしていた。皇太子時代は日本で暮らし、王の即位時に百済に戻った。(三国史記)
- 朝鮮半島南部に日本しかないとされていた前方後円墳が発掘され、大和朝廷が朝鮮南部に拠点をもっていた。
★ ③朝鮮には日本にとって厄介な新羅と高句麗があった。
- 新羅「あるときは韓(中国)に属し、あるときは倭(日本)に属した」(梁職貢図(りょうしょくこうず)
- 新羅は日本の臣下の振りをして裏切り高句麗や唐と組んで日本と戦った。
- 高句麗は騎馬民族であり強敵であった。馬の戦力を知り、日本へ馬が伝来した。
どの時代も、日本は大国中国と朝鮮半島との外交を注視しなければならない。
古代からも外交重視し、日本の独立を守って来た
まとめ
「百済(朝鮮)と日本の親密な関係
日本は古代から外交に神経を使っていた。」を解説しました。
- ①通説
- ➁通説に対する疑問点・気になる点
- ➂通説を検証して見えた真相