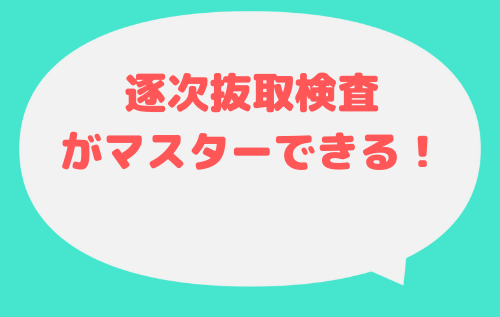【まとめ】逐次抜取検査がわかる

「逐次抜取検査がわからない」、「逐次抜取検査の資料や本が少なく勉強できない」など困っていませんか?
こういう疑問に答えます。
本記事のテーマ
- ①逐次抜取検査がわかる
- ②逐次抜取検査は合格判定線が必須
- ③逐次抜取検査できる種類と関連記事のご紹介
- ④逐次抜取検査の注意点がわかる
計数値逐次抜取検査、計量値の抜取検査の基礎についての関連記事を紹介します。併せて読んでください。
●JISZ9010計量値逐次抜取検査(σ既知)の事例演習
●JISZ9010計量値逐次抜取検査(σ既知)の場合がわかる
●JISZ9010計量値逐次抜取検査(σ未知)の事例演習
●JISZ9010計量値逐次抜取検査(σ未知)の場合がわかる
●計数逐次抜取検査(JISZ9009)の理論がわかる(ポアソン分布)
●計数逐次抜取検査(JISZ9009)の理論がわかる(二項分布)
●計数逐次抜取検査の特徴がわかる
●逐次抜取検査の合格判定線を作るときの注意点
①逐次抜取検査がわかる
ある合格基準があり、合格基準を満たせば、検査は合格として終了。
不合格基準を満たせば、検査は不合格として終了。
どちらでも無く決着がつかなければ、検査を続行するものです。
②逐次抜取検査は合格判定線が必須
合格判定線、不合格判定線を下図に描きます。

青線は、不良個数が検査で増加しても、合格判定領域に入ったため、合格と判断できます。一方、赤線は、不合格領域に入ったため、不合格と判断できます。
合格、不合格の領域線が直線であるため、検査続行、検査終了の判断がしやすいですね。
逐次抜取検査の合格判定線の特徴について関連記事で詳細に解説しています。
 |
計数逐次抜取検査の特徴がわかる 計数逐次抜取検査(JISZ9009)にて、合格判定線の傾きと切片の導出と、変数(第1種の誤りα、第2種の誤りβ、不良率p0,p1)による合格判定線の変化を解説します。計数逐次抜取検査をマスターしたい方は必見です。 |
では、判定線をどのように作るのかを、解説します。
③逐次抜取検査できる種類と関連記事のご紹介
合格判定線ができるもの
- 計数抜取検査(二項分布)
- 計数抜取検査(ポアソン分布)
- 計量抜取検査(標準偏差σ既知)
- 計量抜取検査(標準偏差σ未知)
の4種類です。
それぞれ詳細に解説した関連記事を紹介します。
(i)計数抜取検査(二項分布)
OC曲線に親しみのある計数値の二項分布から学びましょう。
計数逐次抜取検査(JISZ9009)の二項分布の理論を詳細に解説した関連記事です。
 |
計数逐次抜取検査(JISZ9009)の理論がわかる(二項分布) 計数逐次抜取検査(JISZ9009)の理論を解説します。OC曲線から逐次検査続行か、終了かを判断する判定式を詳細に解説します。また、平均検査個数の式も紹介します。逐次抜取検査をマスターしたい方は必見です。 |
(ii) 計数抜取検査(ポアソン分布)
OC曲線にあまり出ない、苦手意識のあるポアソン分布も学びましょう。
計数逐次抜取検査(JISZ9009)のポアソン分布の理論を詳細に解説した関連記事です。
 |
計数逐次抜取検査(JISZ9009)の理論がわかる(ポアソン分布) 計数逐次抜取検査(JISZ9009)のポアソン分布に従う場合の理論を解説します。OC曲線から逐次検査続行か、終了かを判断する判定式を詳細に解説します。逐次抜取検査をマスターしたい方は必見です。 |
計量抜取検査(標準偏差σ既知)
(iii) 計量抜取検査(標準偏差σ既知)
確率密度関数を使って合格判定線を作ります。
計量逐次抜取検査(JISZ9010)では、標準偏差σが既知の場合と未知の場合において、それぞれ合格判定線が作れます。
標準偏差σが既知の場合の関連記事を紹介します。なお、理論だけではわかりにくいので、実際の数値を入れた例題も解説しています。
●理論がわかる関連記事
 |
JISZ9010計量値逐次抜取検査(σ既知)の場合がわかる 計量値逐次抜取検査(JISZ9010)の理論がわかる(標準偏差σが既知)場合の理論を解説します。確率密度関数を定義して、合格判定条件式を作り、逐次抜取検査における合格判定線の導出が理解できます。計量値の逐次抜取検査をマスターしたい方は必見です。 |
●例題がわかる関連記事
 |
JISZ9010計量値逐次抜取検査(σ既知)の事例演習 JISZ9010計量値逐次抜取検査(σ既知)の事例演習を解説します。合格判定線の作り方を実際の演習問題を解きながら解説します。逐次抜取検査をマスターしたい方は必見です。 |
(iv) 計量抜取検査(標準偏差σ未知)
標準偏差σが未知の場合の関連記事を紹介します。なお、理論だけではわかりにくいので、実際の数値を入れた例題も解説しています。
●理論がわかる関連記事
 |
JISZ9010計量値逐次抜取検査(σ未知)の場合がわかる 計量値逐次抜取検査(JISZ9010)の理論がわかる(標準偏差σが未知)場合の理論を解説します。確率密度関数を定義して、合格判定条件式を作り、逐次抜取検査における合格判定線の導出が理解できます。計量値の逐次抜取検査をマスターしたい方は必見です。 |
●例題がわかる関連記事
 |
JISZ9010計量値逐次抜取検査(σ未知)の事例演習 JISZ9010計量値逐次抜取検査(σ未知)の事例演習を解説します。合格判定線の作り方を実際の演習問題を解きながら解説します。逐次抜取検査をマスターしたい方は必見です。 |
④逐次抜取検査の注意点がわかる
しかし、合格判定線の精度は良くない点に注意が必要です。
なぜ、合格判定線の精度が良くないのかを解説した関連記事をご覧ください。
 |
逐次抜取検査の合格判定線を作るときの注意点 逐次抜取検査の合格判定線を作るときの注意点を解説します。理論をしっかりしていますが、やや強引な導出があるため、精度は良くありません。理論と実状をよく理解するために必読です。本記事が理解できれば逐次抜取検査はほぼすべて理解できているといって過言ではありません。 |
以上、逐次抜取検査の方法、種類、検査の注意点について詳細に解説しました。教科書にはあまり書いていない内容です。10本の関連記事を読めば、ほぼ逐次抜取検査の内容はマスターできます。
まとめ
逐次抜取検査について解説しました。
- ①逐次抜取検査がわかる
- ②逐次抜取検査は合格判定線が必須
- ③逐次抜取検査できる種類と関連記事のご紹介
- ④逐次抜取検査の注意点がわかる
逐次抜取検査の関連記事
計数値逐次抜取検査、計量値の抜取検査の基礎についての関連記事を紹介します。併せて読んでください。
●JISZ9010計量値逐次抜取検査(σ既知)の事例演習
●JISZ9010計量値逐次抜取検査(σ既知)の場合がわかる
●JISZ9010計量値逐次抜取検査(σ未知)の事例演習
●JISZ9010計量値逐次抜取検査(σ未知)の場合がわかる
●計数逐次抜取検査(JISZ9009)の理論がわかる(ポアソン分布)
●計数逐次抜取検査(JISZ9009)の理論がわかる(二項分布)
●計数逐次抜取検査の特徴がわかる
●逐次抜取検査の合格判定線を作るときの注意点
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/qcplanets/qcplanets.com/public_html/wp-content/themes/m_theme/sns.php on line 119