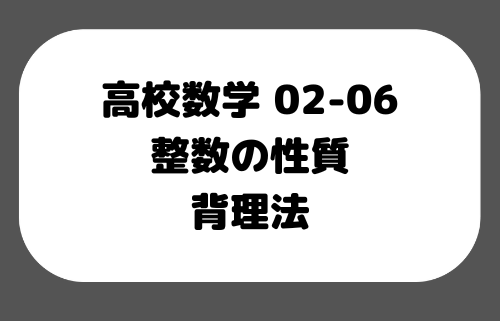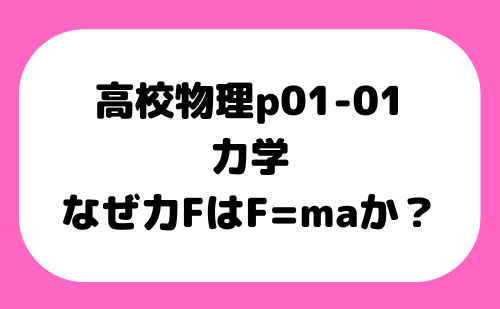「背理法がよくわからない」、などと困っていませんか?
こういう疑問に答えます。
本記事のテーマ
- ①背理法は高校数学で最高級の証明方法
- ➁おさえるべき重要問題
- ➂解法
- ➃全問題の解説は問題集にあります
数と式は、基礎は簡単
でも、発展は最難な領域
「数Ⅲの微積」という人は単に力がないだけ
数学ができる人は、「数Aの数と式」と答える
逆に「数Aの数と式」は基礎は簡単な分、いくらでも難しくできる!難関大学の論証問題はすべて「数Aの数と式」!
基礎をしっかりおさえつつ
難関問題の入り口まで解説します。
①背理法は高校数学で最高級の証明方法
背理法は京大レベル以上
高校数学には、数学的帰納法、背理法、などいろいろな証明方法がありますが、
\(\sqrt{3}\)を無理数と証明する特殊な証明方法
という解釈でいい
背理法が私も受験生時代も使いこなせていなかったですね。
むしろ機械的に処理できる数学的帰納法の方が圧倒的に簡単でしたね。
背理法は何が難しいのか?
では、背理法は何が難しいのか?を解説すると
反例の導き方は決まっていない
自分で考えて論じていくのが高校生にはキツイ
国語で反論する内容を数式で解いて、相手を説得させる難しさが背理法にはあります。
背理法は1つ反論を導けばOK
とはいえ、手法はシンプルで、
反論を論述するアプローチが難しい
1つは過去問やパターンの問題を集めて、そこ範囲から出題される問いはしっかり回答できるようにしておく必要がありますが、
単に解き方を覚えるより、矛盾する反例をどう論じるかを考え抜くことが大事です。でも、これが難しいし、予備校でも解き方は教わるけど、習得方法までは身につかない
このような高級な論証方法が入っているから、
「高1の数と式が、高校数学の中で一番難しいんですよ」
そんな難しい背理法の大事な問題を解説します。
➁おさえるべき重要問題
問1
(1)\(\sqrt{5}\)が無理数であることを示せ。
(2)\(\frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{1}{\sqrt{3}}\)が無理数であることを示せ。
ただし、\(\sqrt{3}\)が無理数であることは証明せず使ってよい。
問2
方程式\(2x^3-x-3\)=0は有理数の解がないことを示せ。
➂解法
背理法を解くポイント
ポイントは4つあります。
- 無理数を証明するパターンで背理法の流れを理解する
- 逆を仮定した場合に1つ矛盾する例を導き出す
- 矛盾を導き方は問題によるので、ここは経験しかない
- 京大以上の大学を目指さないなら、背理法は捨ててもいい
上の4つを意識して解いてみましょう。
問1の解法
では、解いてみましょう。
問(1)
教科書に絶対ある問いですね。流れを理解しましょう。
①逆を仮定する
\(\sqrt{5}\)が有理数と仮定し、
\(\sqrt{5}\)=\(\frac{m}{n}\)
(\(m,n\)は整数で互いに素)と置く。
➁①の仮定が矛盾する例を見つける
(両辺)を2乗すると、
5=\(\frac{m^2}{n^2}\)
5\(n^2\)=\(m^2\)
となる。
\(n\)は整数なので、(左辺)は5の倍数になる。
(右辺)も5の倍数が必要だから、\(m\)は5の倍数になる必要がある。
\(m\)=5\(c\) ((\(c\)は整数)と置くと
5\(n^2\)=\((5c)^2\)
\(n^2\)=5\((c)^2\)
となる。これを満たすには、
\(n\)は5の倍数になる必要がある。
となると、\(m,n\)が共に5の倍数になる必要があり、互いに素の条件に反する。
よって、\(\sqrt{5}\)は無理数になる。
無理矢理もっていっているのがわかりますね。
これを高1の学生に教えるから、皆ピント来ないよね。
「こいつが犯人」と決めても、どうも矛盾する条件があるから
「こいつは犯人じゃない」という流れと同じです。
問(2)
解き方は問(1)と同じです。どう反例を導くか? ここが難しい!
①逆を仮定する
\(\frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{1}{\sqrt{3}}\)が有理数と仮定し、
\(\frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{1}{\sqrt{3}}\)=\(r\)
(\(r\)は有理数)と置く。
➁①の仮定が矛盾する例を見つける
\(\frac{1}{\sqrt{2}}\)=\(r\)+\(\frac{1}{\sqrt{3}}\)と変形して
(両辺)を2乗すると、
\(\frac{1}{2}\)=\(r^2\)+\(\frac{2}{\sqrt{3}}r\)+\(\frac{1}{3}\)
\(\frac{2}{\sqrt{3}}r\)=\(\frac{1}{6}\)-\(r^2\)
\(\sqrt{3}\)=\(\frac{1-6r^2}{4r}\)
ここで、 (右辺)は有理数であるが、(左辺)は無理数であるため、矛盾する。
よって、\(\frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{1}{\sqrt{3}}\)は無理数である。
問2の解法
同様に応用例を解きましょう。
問(1)
①逆を仮定する
方程式\(2x^3-x-3\)=0は有理数の解\(x\)=\(\frac{m}{n}\)
(\(m,n\)は互いに素な整数)とおく。
ここで、
と3つ仮定を入れています。力技で矛盾する反例を見つけるためです。
方程式\(2x^3-x-3\)=0は
\(2(\frac{m}{n})^3-(\frac{m}{n})-3\)=0
より、式を整理すると、
2\(n^3\)=\(m^2(3m+n)\)
ここで、\(m\)が偶数、\(n\)が奇数として
●\(m\)=\(2a+1\)
●\(n\)=\(2b\)
(\(a,b\)とおく)
とおくと
(両辺)は
16\((b)^3\)=\((2a+1)^2(2(3a+b)+1)\)
となり、(左辺)は16の倍数であるが、(右辺)は奇数になり、
(両辺)一致に矛盾する。
よって、方程式\(2x^3-x-3\)=0は有理数の解がない
最初は背理法のパターン演習で慣れてから
応用はとにかく矛盾する例を探す!
矛盾するような仮定、条件、条件式を作って
矛盾する反例を1つ見つけましょう。
この論証が難しいですが、ビジネスにも活かせます!
➃全問題の解説は問題集にあります
「第2章 数と式」で、大学受験も大学以降でも習得すべき、
数と式の重要問題を解説しています。
目次を紹介します。
第2章 数と式
02-01 恒等式
02-02 因数分解
02-03 整式の剰余
02-04 整数の性質
02-05 方程式の整数解
02-06 背理法
02-07 根号を含む計算
02-08 指数と対数
02-09 常用対数
02-10 式の値
02-11 不等式の証明・相加相乗平均
問題集はメルカリでご購入いただけます。
(現在問題集作成中。)
問題集イメージ図(予定)
是非、ブログを参考にいただき、ご購入よろしくお願いいたします。
まとめ
「02-06_背理法がわかる」を解説しました。
- ①背理法は高校数学で最高級の証明方法
- ➁おさえるべき重要問題
- ➂解法
- ➃全問題の解説は問題集にあります