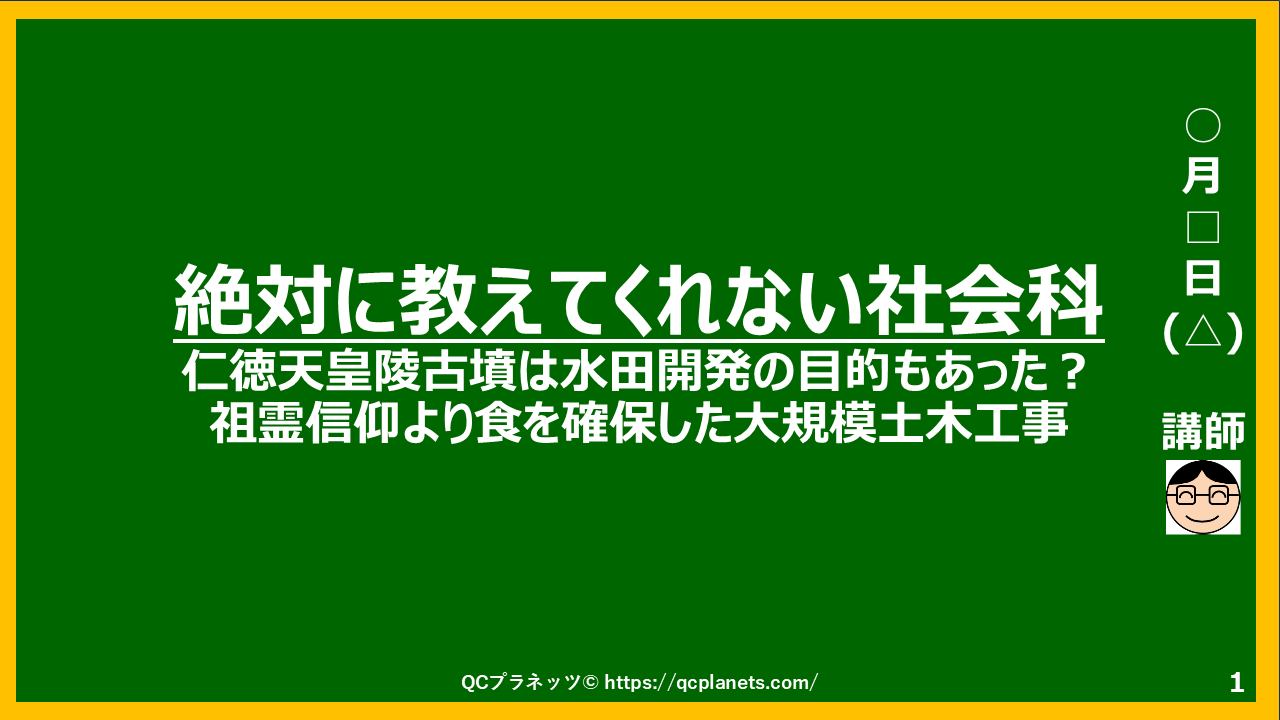★ 本記事のテーマ
「仁徳天皇陵古墳は水田開発の目的もあった?」がわかる
★おさえておきたいポイント
- ①通説
- ➁通説に対する疑問点・気になる点
- ➂通説を検証して見えた真相
学校や試験対策の社会では、
真相はわからない!
自分で調べて考え抜く
本当の社会科を勉強しよう!
真相はわからない!
自分で調べて考え抜く
本当の社会科を勉強しよう!
①通説
仁徳天皇陵とは?((通説)
教科書、学校、塾、親から教えてくれる内容は以下ですよね!
★仁徳天皇陵とは
・仁徳天皇陵は世界三大墳墓
・墳丘の大きさは支配者の権威を可視化したもの。
・古墳時代は墓の在り方で統治する珍しい統治形態。
・古墳は死者を神格化し、祖霊信仰と結びつける場。
・西暦200年奈良から西の方へ伝播し日本各所へ。
・古墳は大型化するが、徐々に小型化し西暦700年くらいになって古墳がなくなる。
・仁徳天皇陵は世界三大墳墓
・墳丘の大きさは支配者の権威を可視化したもの。
・古墳時代は墓の在り方で統治する珍しい統治形態。
・古墳は死者を神格化し、祖霊信仰と結びつける場。
・西暦200年奈良から西の方へ伝播し日本各所へ。
・古墳は大型化するが、徐々に小型化し西暦700年くらいになって古墳がなくなる。

つまり
古墳時代の信仰は、自然や祖先への畏敬を基盤としたアニミズム的世界観に根ざしており、後の神道につながった。
➁通説に対する疑問点・気になる点
調べると気づく疑問点
参考文献やYoutube動画を調べていくと、通説と異なることがわかります。それを陰謀論として片づけてしまってもよいですが、物事は多面的に見て、客観視する必要があります。QCプラネッツは品質管理を専門としています。品質管理は客観視が必須です。同じ姿勢で取り組みます!
仁徳天皇陵古墳で気になる点
1. 人工の山をわざわざ作る必要があるのか?近くの山に墓作ればいいだけの話ではないか?
2. 当時仁徳天皇陵を作るには、一日2000人で約15年もかかる。工員の食事(コメ、水)はどうやって用意したのか?権力支配の強制な手段で古墳が作れるか?平民からの不満が出るのではないのか?
2. 当時仁徳天皇陵を作るには、一日2000人で約15年もかかる。工員の食事(コメ、水)はどうやって用意したのか?権力支配の強制な手段で古墳が作れるか?平民からの不満が出るのではないのか?
精神面や支配だけで巨大な土木工事の完遂は無理ではないか?
いかがでしょうか?疑問が湧きますよね!
真相を説明します。
➂通説を検証して見えた真相
水田開発の目的もある
1. 地図から仁徳天皇陵の周辺は平野で升目上に開発された地域とわかる。つまり古墳周辺の広大な領域が田んぼだったとわかる。
2. 自然の地形は凹凸があり、広大でまっ平な田んぼを作るには土木工事が必須。
3. 大量の残土処理が必要になるが、人力では運搬できない。そのため、盛り土を作った古墳を作った。
4. 仁徳天皇は「民のかまどは賑わいにけり」で飢えがない保存できるコメが大量生産できる世の中を創った。
5. 天皇の権威は時代によらず同じであるが、古墳のサイズが小さくなったのは、周囲の新田開発の領域がだんだん縮小していき、人口をまかなうだけの田んぼができたため、最終的に古墳が不要となった。
2. 自然の地形は凹凸があり、広大でまっ平な田んぼを作るには土木工事が必須。
3. 大量の残土処理が必要になるが、人力では運搬できない。そのため、盛り土を作った古墳を作った。
4. 仁徳天皇は「民のかまどは賑わいにけり」で飢えがない保存できるコメが大量生産できる世の中を創った。
5. 天皇の権威は時代によらず同じであるが、古墳のサイズが小さくなったのは、周囲の新田開発の領域がだんだん縮小していき、人口をまかなうだけの田んぼができたため、最終的に古墳が不要となった。
つまり、
水害防止、食料増大させるために大規模土木工事が進み、その副産物として、大きな盛り土からなる古墳がたくさん作られた
水田開発し、食から生活を豊かにする土木工事の結果、残土の処理で古墳を作った。古墳も周りを掘りで囲み、灌漑施設を兼任するように整備した。と考えると、国民も納得して参加したと考えることできます。
教科書では「古墳は水田開発」までは言い切っていませんが、水田開発により国を豊かにし、それを支えた人を称える大きな墓となったと考えると納得感が増しますね。
まとめ
「仁徳天皇陵古墳は水田開発の目的もあった?がわかる」を解説しました。
- ①通説
- ➁通説に対する疑問点・気になる点
- ➂通説を検証して見えた真相