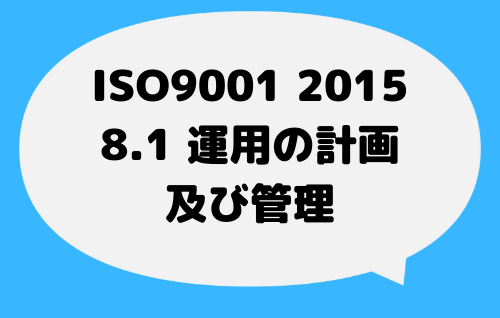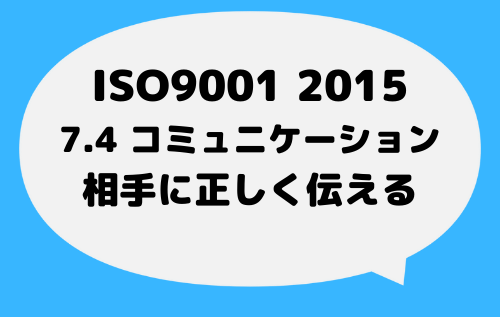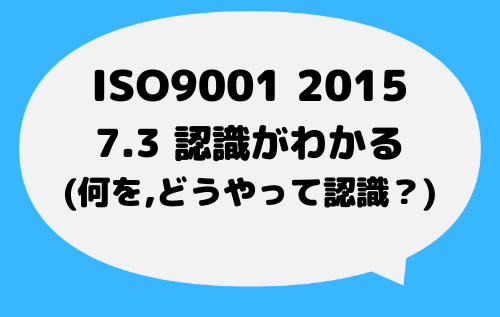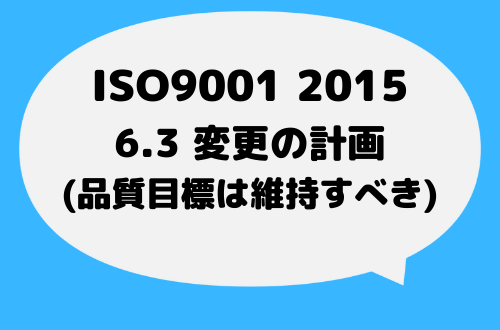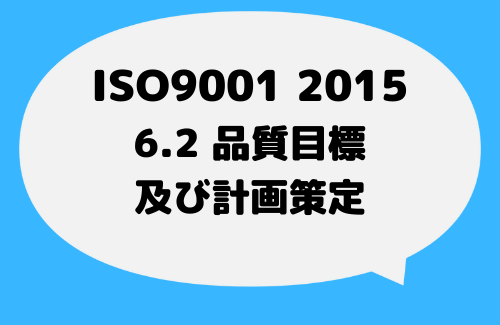「運用の計画及び管理って何をやればいいの?」、と困っていませんか?
こういう疑問に答えます。
本記事のテーマ
- ①要求事項の簡略化
- ②ISO9001要求事項 8 運用の構成図
- ③プロセスって何?
- ④事例紹介
①要求事項の簡略化
ISO9001要求事項
組織は,次に示す事項の実施によって,製品及びサービスの提供に関する要求事項を満たすため,並びに箇条6で決定した取組みを実施するために必要なプロセスを,計画し,実施し,かつ,管理しなければならない(4.4参照)。
a) 製品及びサービスに関する要求事項の明確化
b) 次の事項に関する基準の設定
1) プロセス
2) 製品及びサービスの合否判定
c) 製品及びサービスの要求事項への適合を達成するために必要な資源の明確化
d) b) の基準に従った,プロセスの管理の実施
e) 次の目的のために必要な程度の,文書化した情報の明確化,維持及び保持
1) プロセスが計画どおりに実施されたという確信をもつ。
2) 製品及びサービスの要求事項への適合を実証する。
この計画のアウトプットは,組織の運用に適したものでなければならない。 組織は,計画した変更を管理し,意図しない変更によって生じた結果をレビューし,必要に応じて,有害な影響を軽減する処置をとらなければならない。 組織は,外部委託したプロセスが管理されていることを確実にしなければならない(8.4参照)。
難しいですね。わかりやすく理解するために、ポイントを部分的に取り出しましょう。
組織は,プロセスを,計画・実施・管理する。
a) 製品及びサービスに関する要求事項の明確化
b) プロセスと合否判定を管理する
c) 必要な資源
e)文書化した情報の維持及び保持
1) プロセスの計画と実績の管理
2) 要求事項への適合を実証
組織は,変更を管理し,必要に応じてリスクの対する処置をとる
こう簡略すると、理解しやすいですね。
●ISO9001 2015 8.1は8章の構成を書いたものです。全体の構成図を次に解説します。
②ISO9001要求事項 8 運用の構成図
構成図
あなたが所属する組織(会社、組織)の関係性とプロセスについて下図にまとめます。

縦が人間の関係性、横が業務のプロセスの関係性です。
縦の関係性、横の関係性
●縦は、上から顧客・エンドユーザ、下は自社です。自社はさらに三段階に分けて、Top,Middle,Bottomに分かれます。それぞれの段階で求められる品質の要求事項があります。
●横は、自社のプロセスの流れと関係性です。ISO9001はあらゆる業種に対応していますが、大まかに、
受注・仕様⇒設計・開発⇒購買⇒製造⇒引渡(出荷)⇒不適合(保守)
の流れで製品及びサービスを提供します。
ISO9001 要求事項
縦と横の関係性とISO9001の要求事項の関係をまとめます。
●横は8章のプロセスの在り方(プロセスアプローチ)について
と分けて考えるとわかりやすいです。
品質監査でも、
●前半は4,5,6,7,9,10章を監査して
●後半は8章のプロセス(具体的な製造及びサービスの現在進行形な業務)を監査します。
③プロセスって何?
プロセスって何?
●プロセスは日本語では、工程、過程とよく訳します。
しかし、プロセスアプローチなどの用語になるとプロセスって何か?が理解しにくくなります。
●品質におけるプロセスは、次のように解釈するとわかりやすいです。
インプットをアウトプットに変えるもの

漠然としていますね、わかったようで、わからない(笑)。
プロセス=工程、過程よりもう少し広い意味でとらえるとよいです。

上の図を見ると、いろいろなものがプロセスとして定義できることがわかります。

●数学の関数fもプロセスです。インプットxをアウトプットyに変える式ですね。
●会議もプロセスです。インプットの資料をもとに協議してアウトプットの議事録を作りますね。
●設計もプロセスです。インプットの仕様書をもとに、設計して、アウトプットの設計図に落とし込みます。
●関数、会議、設計と粒度がそれぞれ異なりますが、1つにプロセスとまとめてOKです。
インプット、アウトプットの明確化も大事
●プロセスを評価するのと同時に、インプット・アウトプットもしっかり確認します。
インプットがヌケモレや曖昧だと、よいプロセスでもアウトプットの質は良くありません。また、インプットとアウトプットが明確でもプロセスに不備がある場合もあります。
●インプット、プロセス、アウトプットを明確にヌケモレがないように注意しましょう。
インプット、アウトプットのどこをチェックすべきか?
●5W1Hが明確かを最初にチェックします。
・誰が?(Who)
・いつ(いつまでに)? (When)
・どこで? (Where)
・何を?(What)
・なぜ?(Why)
・どのように?(How)
がインプット、アウトプットともに明確かどうか?を確認します。例えば、設計プロセスを見る場合、アウトプットから逆算して、必要な要素がそろっているかを確認します。
●5W1Hが明確な場合は、インプットープロセスーアウトプット間に整合性がとれているか?
明らかに、要求のアウトプットにできない場合(レベル、期日、価格、安全性など)かどうかを見ましょう。例えば、5W1Hが明確な仕様書をもとに、その設計プロセスのレベルを見て、要求のアウトプットができるかどうかなどです。
●品質トラブルになる場合は、インプット、アウトプットが明確でない、インプットープロセスーアウトプット間に整合性が取れていないなどを疑いましょう。
④事例紹介
プロセスの具体例をいくつか挙げて、イメージしやすくしましょう。3例を挙げてみましょう。
- 装置製造などのハードウェアの工場
- システム開発などのソフトウェア会社
- ISO9001を取得した保育園
ん? 保育園? 保育園がISO9001取得しているの? そうです。取得している保育園があります。Google で「ISO9001 保育園」で検索してください。
●では、上の3例のプロセスを具体的挙げてみましょう。
装置製造などのハードウェアの工場
ハードウェアの製造業が一番ISO9001 の要求事項と相性が強いです。なぜなら、ISO9001 は1987年から規定していますが、当時はハードウェアの製造業しかなかったためです。なお、要求事項「8章運用」は、ISO9001 の初期からの名残として今も残っています。
ハードウェアの場合は、要求事項とプロセスは次の関係になります。
| No | 要求事項 | プロセス |
| 8.1 | 運用の計画及び管理 | 全般の管理 |
| 8.2 | 製品及びサービス に関する要求事項 |
受注・仕様 |
| 8.3 | 製品及びサービス の設計・開発 |
設計・開発 |
| 8.4 | 外部から提供されるプロセス, 製品及びサービスの管理 |
購買 |
| 8.5 | 製造及び サービス提供 |
製造 |
| 8.6 | 製品及び サービスのリリース |
引渡・出荷 |
| 8.7 | 不適合なアウト プットの管理 |
保守 |
システム開発などのソフトウェア会社
ここ、20年ほどでソフトウェアーやサービス業にもISO9001を取得する組織が増えています。基本的には、ハードウェアと同じプロセスを通るはずです。
ソフトウェアの場合は、要求事項とプロセスは次の関係になります。
| No | 要求事項 | プロセス |
| 8.1 | 運用の計画及び管理 | 全般の管理 |
| 8.2 | 製品及びサービス に関する要求事項 |
受注・仕様 |
| 8.3 | 製品及びサービス の設計・開発 |
設計・開発 |
| 8.4 | 外部から提供されるプロセス, 製品及びサービスの管理 |
購買 |
| 8.5 | 製造及び サービス提供 |
インプリメンテーション |
| 8.6 | 製品及び サービスのリリース |
インストール(引渡・出荷) |
| 8.7 | 不適合なアウト プットの管理 |
保守・更新 |
●製造をインプリメンテーション
●引渡、出荷をインストール
●保守に更新を追加
など、ソフトウェア独自のプロセスが入ります。
ISO9001を取得した保育園の場合
製造業なら、わかりやすいですが、保育園の運用って何でしょうね? もし、保育園を品質監査してと言われたら、あなたは何を質疑しますか?
●製造業では、
①受注・仕様⇒②設計・開発⇒③購買⇒④製造⇒⑤引渡・出荷⇒⑥保守
でした。
保育園では、どんなプロセスが該当するのでしょうか?
例えば、園児を中心に考えると、次の表の案が考えられます。
| No | 要求事項 | プロセス |
| 8.1 | 運用の計画及び管理 | 運営 |
| 8.2 | 製品及びサービス に関する要求事項 |
募集・入園 |
| 8.3 | 製品及びサービス の設計・開発 |
保育計画 |
| 8.4 | 外部から提供されるプロセス, 製品及びサービスの管理 |
購買 |
| 8.5 | 製造及び サービス提供 |
育児・保育 |
| 8.6 | 製品及び サービスのリリース |
退園・卒園 |
| 8.7 | 不適合なアウト プットの管理 |
苦情対応 |
ISO9001は手段、目的は達成したいことです。達成したい目標に向かって
インプット、プロセス、アウトプットが明確で有用に機能していることが重要です。
まとめ
ISO9001 2015 8_1 運用の計画及び管理がわかる をわかりやすく解説しました。
- ①要求事項の簡略化
- ②ISO9001要求事項 8 運用の構成図
- ③プロセスって何?
- ④事例紹介