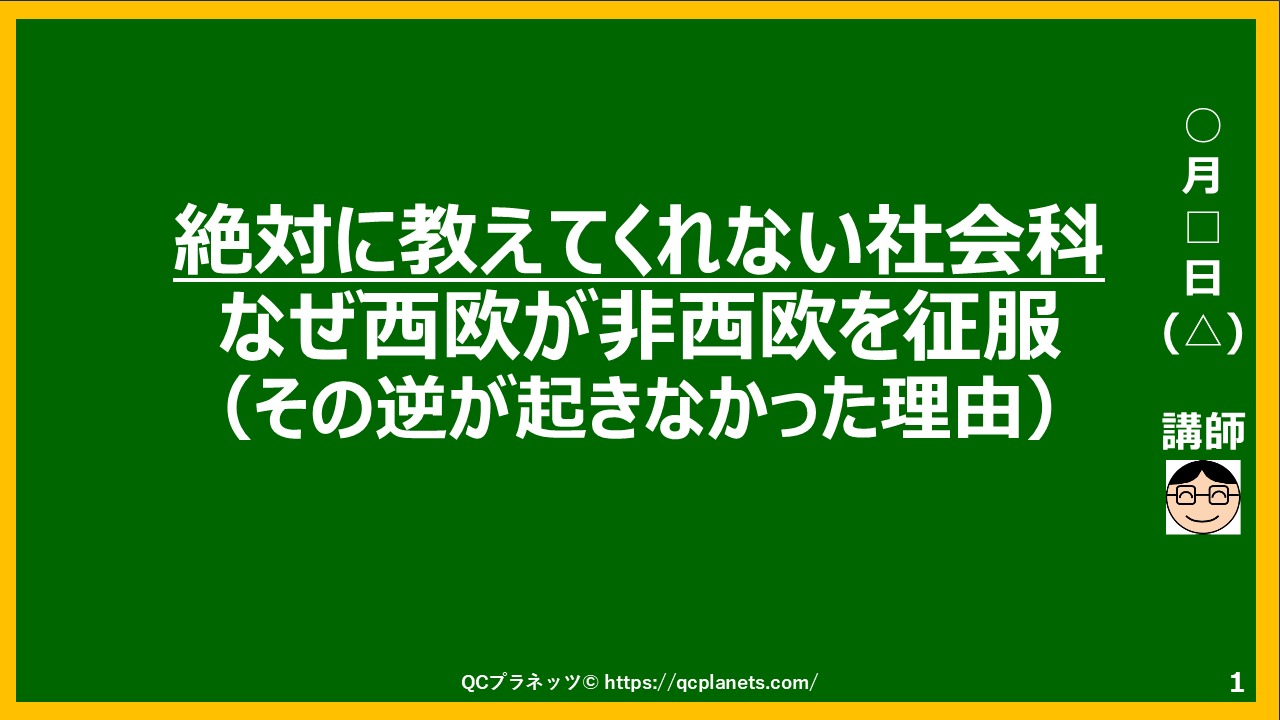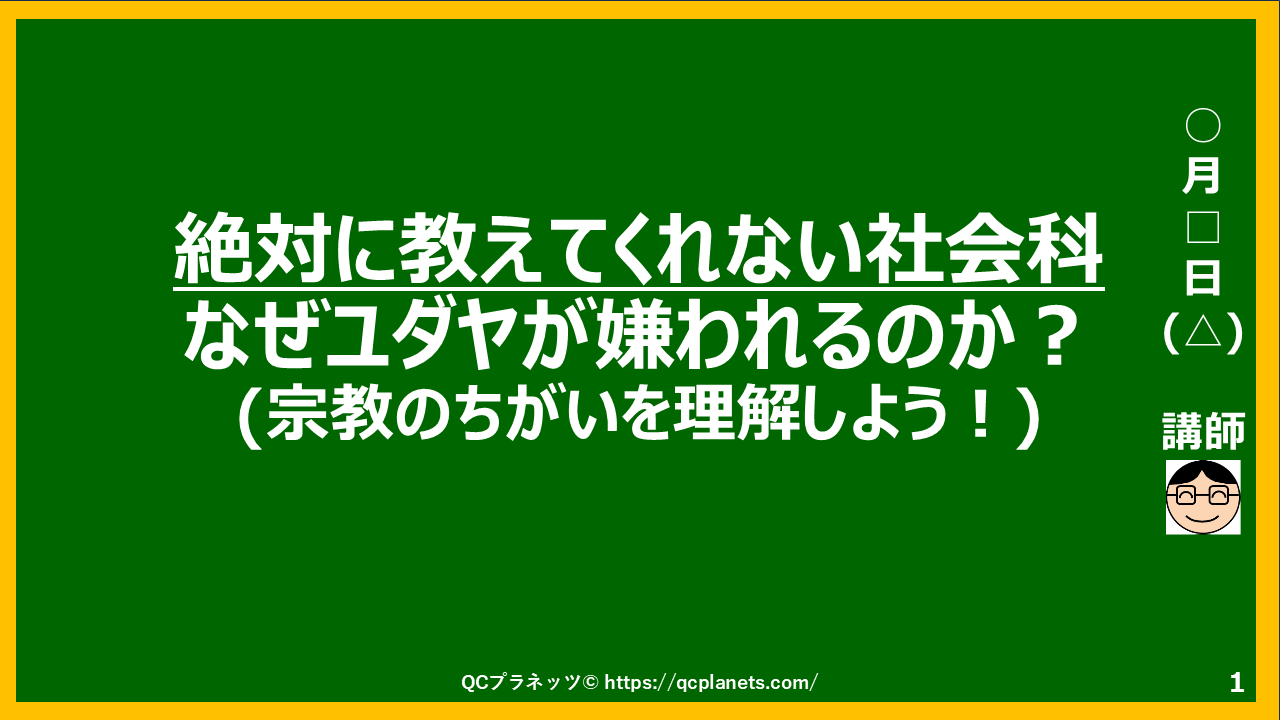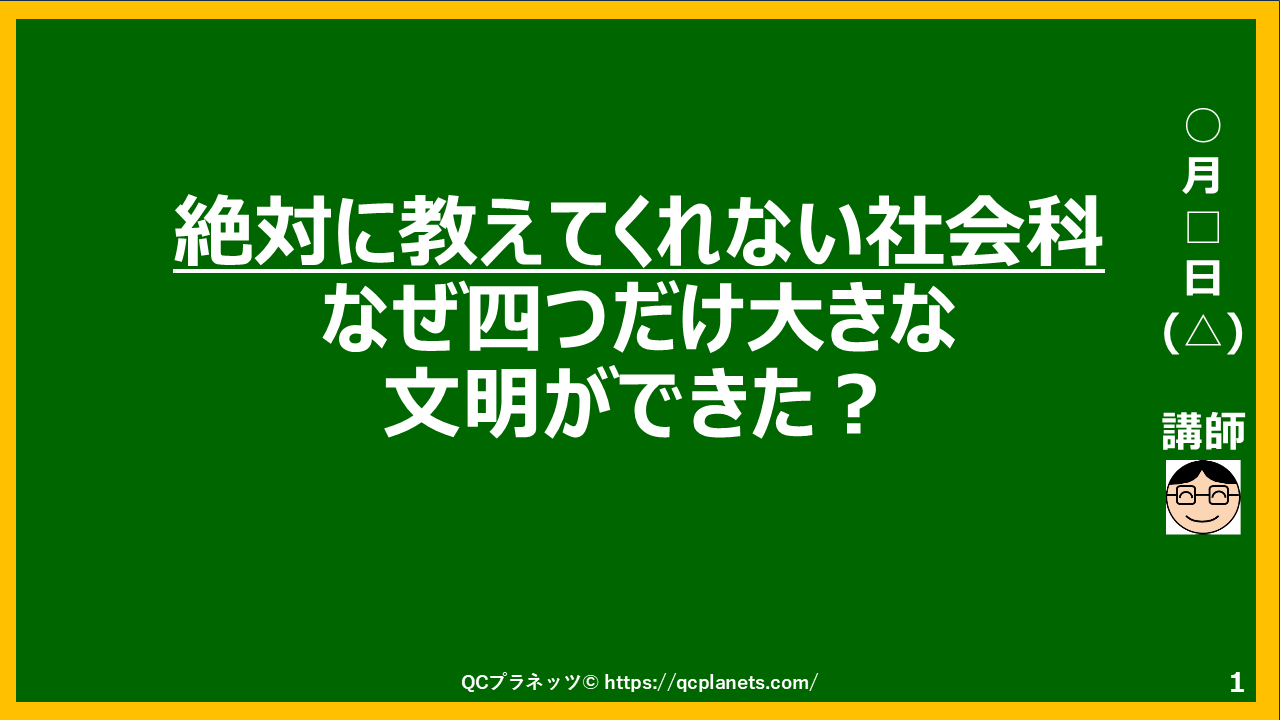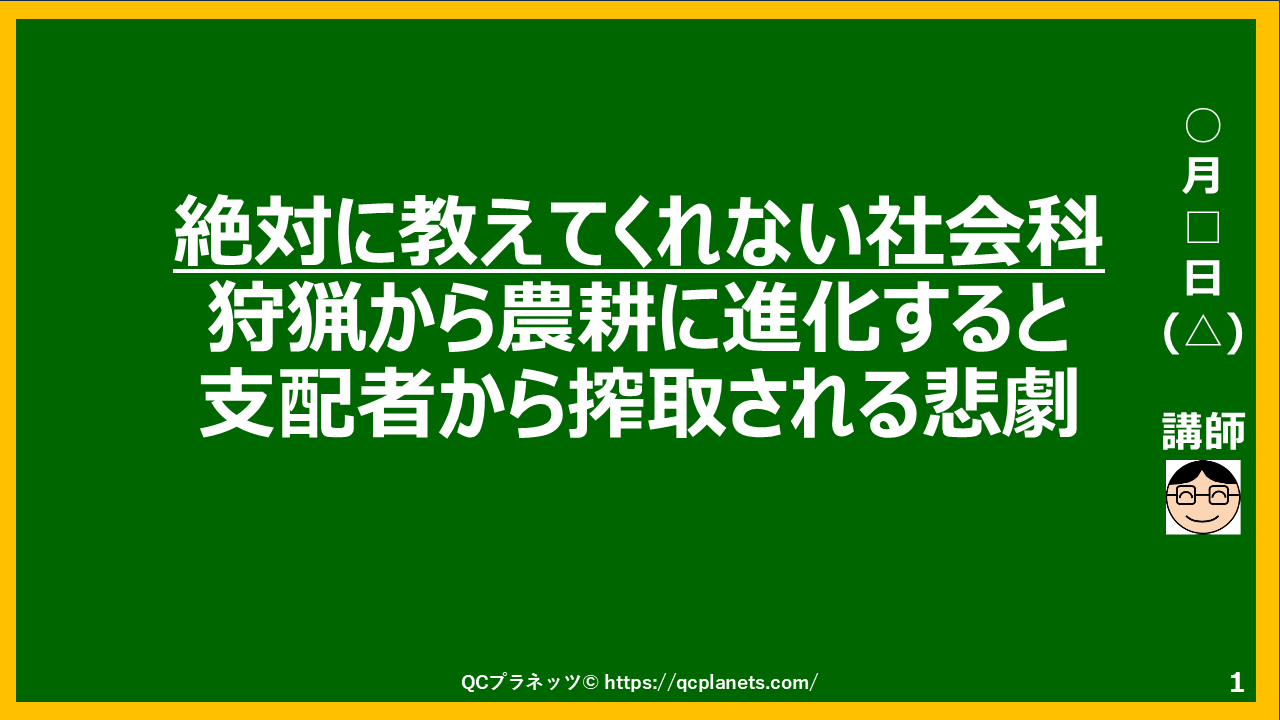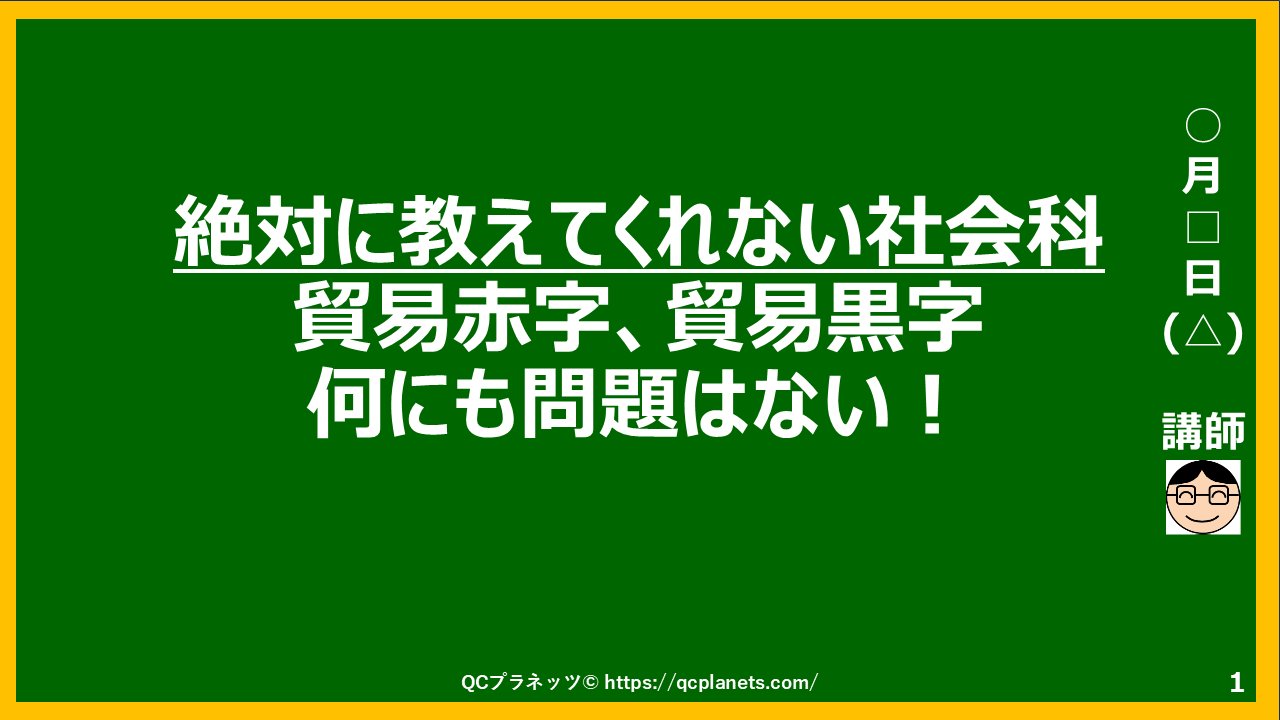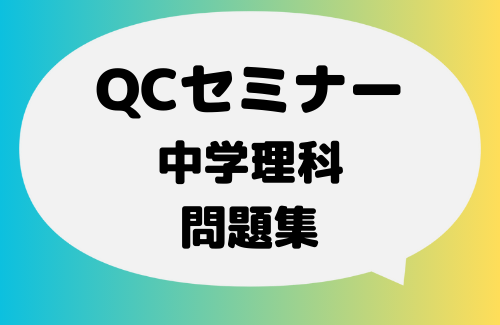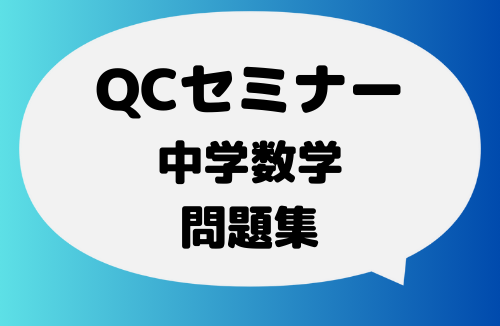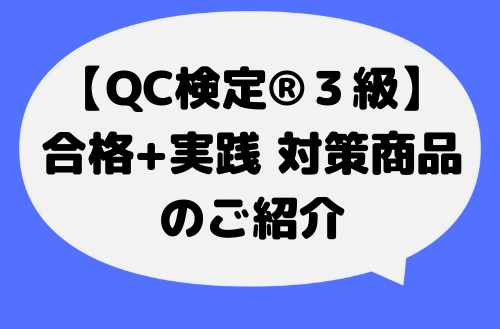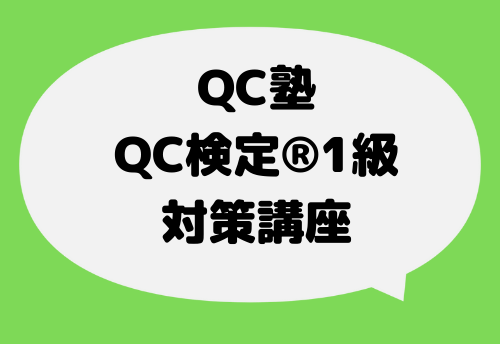こんにちはQCプラネッツです。
★ 本記事のテーマ
これからの時代に必要な学力を磨いた人材を作るために
こんにちはQCプラネッツです。
本ブログでは、『●これからの時代に必要な学力を磨いた人材を多く作るために、QCセミナーがやるべきこと』という題で、私のこのセミナーコンテンツの思いを紹介させていただきます。
【1】私たちをとりまく時代・環境は大きく変わってきている
21世紀も1/4を過ぎ、20世紀から大きく時代が変化してきました。時代の変化をいくつか挙げると
- 人生100年時代になったこと
- AI・ロボット技術の進化により便利な世の中になったこと
- 働き改革など自分らしく生きやすい社会になってきたこと
などの良い時代の変化もあれば、
- 世界規模での変化が激しい競争の時代に突入したこと
- 疫病や戦争に巻き込まれるリスクがあること
- 不安要素だらけの不確実な時代になったこと
などの不安な時代の変化もあります。
私が世の中と接する手段の1つにITがありますが、とりわけ、SNSの発達より、新たな情報が瞬時に大量に入ってくるようになり、その対応や追従だけで精一杯な毎日を暮らしています。
【2】私たちに求められる力も大きく変わってきている
未来人材ビジョンから
2020年代以降の時代において、私たちや、私たちの子供たちに求められる力(能力)も過去から大きく変わっています。
経済産業省が発行した「未来人材ビジョン(令和4年5月)」によると、
(https://www.meti.go.jp/press/2022/05/20220531001/20220531001-1.pdf)
将来の不確実性の高い社会・時代を生きる上で、人材育成の観点から
基礎能力や高度な専門知識だけではなく、
「常識や前提にとらわれず、ゼロからイチを生み出す能力」
「夢中を手放さず一つのことを掘り下げていく姿勢」
「グローバルな社会課題を解決する意欲」
「多様性を受容し他者と協働する能力」
を高めること求められてきます。
日本の教育レベルは高いが。。。
もちろん、日本人の子供たちの数学的・科学リテラシーの高さは世界トップクラスであるため、日本の教育レベルは高く、未来を切り開く可能性に満ち溢れています。
しかし、同調査において、その高いリテラシーが十分に生かされておらず、本来の「学問、科学への探求」の面白さを感じる機会が少ないことも指摘されています。知識や計算をみがくが、自分で考えて探求する思考訓練が足りない現状もあります。

(https://www.meti.go.jp/press/2022/05/20220531001/20220531001-1.pdf P74から引用)
また、日本の子供への教育レベルは高いとされながらも、社会への当事者意識が低いこともあり、過去の知識偏重の勉強による不十分さな点で課題があると言えます。

(https://www.meti.go.jp/press/2022/05/20220531001/20220531001-1.pdf P81から引用)
【3】これからの時代に活躍できる人へ鍛錬したいQCセミナーの思い
経済産業省が発行した「未来人材ビジョン(令和4年5月)」における、求められる能力(以下、再掲)を身に着けてもらうためにはどうしたらよいでしょうか?
私QCプラネッツは、下図のマッピングで左下領域から右上領域をおさえた新たな教育コンテンツが必要ではないか?と強く考えています。

横軸は勉強の仕方とし、
やり方をまねる「Learning」と、
ゼロから考え抜く「Study」の
方向とします。縦軸は不確定さに関するものとし、VUCAとSCSCとしました。
VUCAは
・Volatility(変動性)、
・Uncertainty(不確実性)、
・Complexity(複雑性)、
Ambiguity(曖昧性)
の略で不確実な要素があることがわかります。
SCSC(スクスク)は逆に、
・Stability(安定性)、
・Certainty(確実性)、
・Simplicity(単純性)、
・Clarity(明瞭性)
と確実な要素の用語としました。
(http://tap.tamagawa.ac.jp/news/news-220617.html を参照)
このマップで考えると、「今までの教育」を代表とするものは、
・「受験勉強」、
・「詰込教育」、
・「正解追求」、
・「偏差値」、
・「学歴偏重」
が挙げられます。
これらの教育は左下側の領域であることがわかります。
次に、これからの時代に求められる「これからの教育」は、
VUCA時代に自分で考え抜くことが求められますから、
・「探求」、
・「創造」、
・「(仮説)思考力」、
・「多面的評価」、
・「地頭力」
であると考えられ、右上側の領域に入ってきます。
なお、「今までの教育」と「これからの教育」において、各項目が対比関係であることもわかります。
| 「今までの教育」 |
⇔ |
「これからの教育」 |
| 「受験勉強」 |
⇔ |
「探求」 |
| 「詰込教育」 |
⇔ |
「創造」 |
| 「正解追求」 |
⇔ |
「(仮説)思考力」 |
| 「偏差値」 |
⇔ |
「多面的評価」 |
| 「学歴偏重」 |
⇔ |
「地頭力」 |
私QCプラネッツも、現役エンジニアとして、父として、将来の教育のあり方について真剣に考えてきました。
上のマッピングにそって、QCプラネッツから提供する学習コンテンツ「QCセミナー」の各科目のあり方をプロットしました。

国語は苦手なので(ごめんなさい)、残りの4科目の中学、高校の教育コンテンのあり方を私なりに考えた結果をまとめます。
- 数学と英語は、あらゆる学問の基礎であるため、時代によらず本質をしっかりおさえたコンテンツとすべき。
- 理科と社会は、単なる暗記や公式代入ではなく、理科は科学の探求心をみがくもの、社会は顕在・潜在する問題を的確に抽出し考え抜く力を養うコンテンツとすべき。
上の教育コンテンツ方針に沿って、QCセミナーとして教育コンテンツを提供しております。
QCセミナーの教育を活用いただき、
将来の不確実性の高い社会・時代を生きる上で、人材育成の観点から
基礎能力や高度な専門知識だけではなく、
「常識や前提にとらわれず、ゼロからイチを生み出す能力」
「夢中を手放さず一つのことを掘り下げていく姿勢」
「グローバルな社会課題を解決する意欲」
「多様性を受容し他者と協働する能力」
を十二分に鍛錬できる役立つものとして世の中に貢献したいことを願ってやみません。
QCセミナーのため、私QCプラネッツも日々精進してまいります。
【4】QCセミナーが提供するコンテンツ
QCセミナーコンテンツで一番意識した点は以下の方針に準拠した点です。
- 1冊を何度も繰り返してその学問を網羅的にマスターできること
- 読むだけでも力が付くよう、ムダが一切ない構成
- エンジニアを経験も含めて、これからの時代に勝つには何が必要かを網羅的に詰め込んでいること
- 目先の利益より本質をしっかりおさえること
| 科目 |
中学 |
高校 |
| 数学 |
● |
● |
| 英語 |
(開発中) |
(開発中) |
| 理科 |
● |
化学(開発中) |
| 物理(開発中) |
| 社会 |
● |
– |
この私の思いをつめた、オリジナルコンテンツをそれぞれ紹介します。
中学レベル
★①中学数学
単なる点数稼ぐための数学ではなく、他科目へのベースや、高校数学、理系への高い基礎力を養うためにコンテンツを作成しました。
- 文章から式をつくる力
- 文章から正しい図形を描き出し要求された長さ・面積・体積を方程式など駆使して解ける力
- 高校数学もつまづかないために先取りしておさえておくべきポイントをおさえる力
★②中学英語(開発中)
何といっても文法が一番大事です。難関高校入試や学校の実力試験のように無味乾燥な長文問題は正直やる意味はありません。正直、基礎文法の徹底が一番大事です。長文の読み方や、難しい英作文・和訳は高校英語でやればよく、また、その解き方があります。QCセミナーでは、中学英語で一番大事と考える文法をおさえた問題集を用意しています。
リンク(作成中)
★③中学理科
暗記科目と、公式代入でそれなりにできるのが中学理科ですが、それが一番マズイです!
法則や結果を知った上での勉強では何が面白いのかがわからないし、理科で概念がわからず結果を暗記させようとするので、理解できない子供が大勢います。
そして、中学理科で成績が良かったのに、高校理科で脱落する人が大勢います。理系国家を目指す日本にとって、これは一問題ではありませんか?
本来、理科(サイエンス)は古代からわからなかった原理・法則を長年の研究者が苦労して、それが証明されるまで数十年かかって認められたものを体系化したものです。知らない・わからない・見えないものを、限られた環境条件の中、どうやって発見や証明していくかを探求することこそ、理科でサイエンスするとQCプラネッツは思います。
科学の探求心をみがくための問題を作る際、既成の問題集・高校入試の設問を参考にしましたが、全くダメでした。QCプラネッツがゼロから科学への探求心をみがく問題集を全問作成しました。是非活用してみてください。
★④中学社会
地理、歴史、公民分野ですが、暗記問題や断片的な説明解答で終わっていませんか?社会を勉強したわりに、今世界で起きていることや、あなた自身に影響することを本質的に説明できている状態にはなっていないはずです。
過去の事実関係を知るのが社会ではなく、本来、社会問題の本質を見抜くことが社会で学ぶべきではないでしょうか?
QCセミナーでは、暗記はせず、事実から客観的な視点で本質を見抜いたり、あなた自身が知的にも経済的にもあらゆる面で強く、たくましく生きていけるための知恵をみがく社会の教材を提供いたします。
歴史は暗記するのではなく、「なぜ」を考え抜くもの
そして、「日本とは何か?」、「日本人とは何か?」を
高校レベル
★①高校数学
高校以降の学問を優位に活用できるためにも、高校数学レベルはしっかり乗り越えたいところです。しかし、ほとんどの人が高1の数学に敗れ、文系行きを選択する人が多いです。高校数学ができなくなる理由は
- 中学数学と高校数学は全くの別の科目であり、戦い方が違うことをなかなか認めず、ずるずるいくこと
- 高校数学ができなくなる教材や教師などの環境
があります。
あまり言いたくありませんが学歴で勝ちたいなら、中高の途中経過より高校数学で勝てばよいのです。
- 勝つための勉強方法
- 高校数学をみがくための無駄が一切ない優れた教材
- QCプラネッツによるオリジナル解説
を用意しています。
②高校英語(開発中)
③高校化学(開発中)
④高校物理(開発中)
まだまだ、開発中なものばかりですが、
理系エンジニアとして、父として、社会の皆様に
伝えるべきメッセージとして、役立つコンテンツを紹介してまいります。
是非、QCプラネッツとともに、これからの社会を強く、賢く、楽しく生きてきましょう。よろしくお願いいたします。
まとめ
「これからの時代に必要な学力を磨いた人材を作るために」を解説しました。