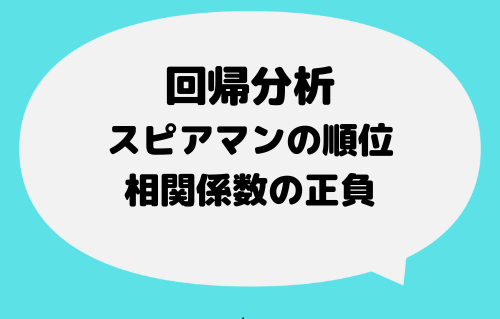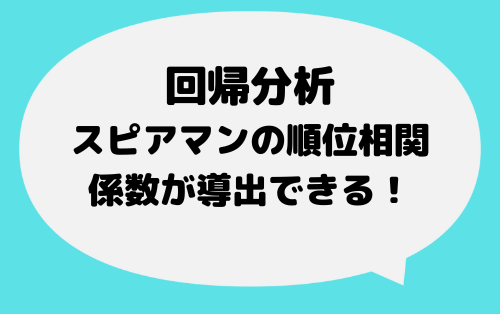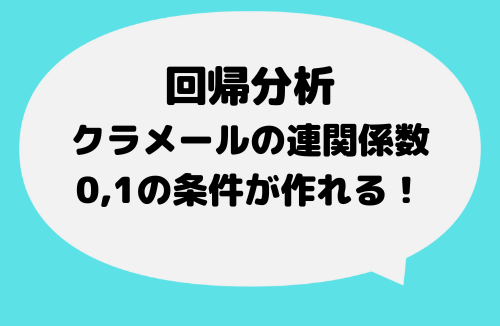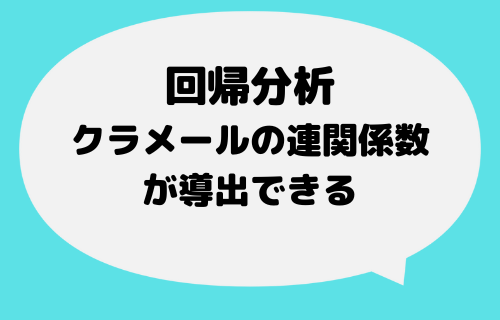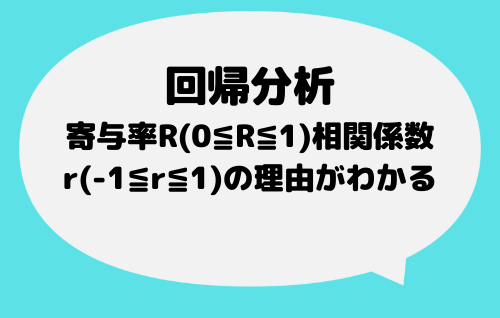「スピアマンの順位相関係数がよくわからない」など、疑問に思いませんか?
こういう疑問に答えます。
本記事のテーマ
おさえておきたいポイント
- ➀スピアマンの順位相関係数の正負が変わる条件
- ➁スピアマンの順位相関係数の正負が入れ替わる理由
【QC検定®1級合格】回帰分析問題集を販売します!
 |
【QC検定®合格】「回帰分析(単回帰分析・重回帰分析)」問題集を販売します! 内容は、①単回帰分析の基本、➁特殊な単回帰分析、➂単回帰分析の応用、➃重回帰分析の基礎、⑤重回帰分析の応用、の5章全41題を演習できる問題集です。 |
導出過程は関連記事で確認ください。
 |
スピアマンの順位相関係数が導出できる スピアマンの順位相関係数は導出できますか?本記事では、一般的に使うピアソンの相関係数からスピアマンの順位相関係数を導出します。公式暗記は不要で自力で導出できるので、マスターしましょう |
➀スピアマンの順位相関係数の正負が変わる条件
正負の入れ替え方
それは、
●\(x\)、\(y\)の両方の順位を入れ替えるとスピアマンの順位相関係数の正負は2回入れ替わるので、もとの正負に戻る。
正負の入れ替え事例
実際にやってみましょう。
下表のように4つ条件を作ります。
- 条件1:元データ
- 条件2:\(x\)だけ順位を入れ替えた場合
- 条件3:\(y\)だけ順位を入れ替えた場合
- 条件4:\(x,y\)両方順位を入れ替えた場合
| – | 条件1 | 条件2 | 条件3 | 条件4 | ||||
| No | x | y | x | y | x | y | x | y |
| 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 8 | 10 | 8 |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 10 | 9 | 10 |
| 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 9 | 8 | 9 |
| 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| 5 | 5 | 9 | 6 | 9 | 5 | 2 | 6 | 2 |
| 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 |
| 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | 9 | 10 | 2 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | 10 | 4 | 1 | 4 | 10 | 7 | 1 | 7 |
黄色マーカー部分が順位が入れ替わったところです。
各条件のスピアマンの順位相関係数\(r\)を計算
実際に、各条件のスピアマンの順位相関係数\(r\)を計算すると下表のようになります。
| – | 条件1 | 条件2 | 条件3 | 条件4 |
| \(S_{xx}\) | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
| \(S_{yy}\) | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
| \(S_{yx}\) | 51.5 | -51.5 | -51.5 | 51.5 |
| \(r\) | 0.624 | -0.624 | -0.624 | 0.624 |
●\(x\)、\(y\)の両方の順位を入れ替えるとスピアマンの順位相関係数の正負は2回入れ替わるので、もとの正負に戻る。
確かに、正負が入れ替わっていますよね。でも、なぜそうなるか?わかりますか?
➁スピアマンの順位相関係数の正負が入れ替わる理由
元の条件における平方和の式を立てる
正負が入れ替わる理由を数式で説明します。
もともとの平方和は、
●\(S_{xx}\)=\(\sum_{i=1}^{n}(x_i -\bar{x})^2\)
●\(S_{yy}\)=\(\sum_{i=1}^{n}(y_i -\bar{y})^2\)
●\(S_{xy}\)=\(\sum_{i=1}^{n}(x_i -\bar{x})(y_i-\bar{y})\)
ですよね。
\(x\)が\((n+1)-x\)、
\(y\)が\((n+1)-y\)、
に変換することです。
例えば、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10を逆にすると、
10,9,87,6,5,4,3,2,1ですよね。
1を10に変えるには、1を(10+1)-1に変えればOKです。
これを文字式で書いただけです。
文字を入れ替えた場合の平方和に「’」をつけて計算します。
(条件2)\(x\)だけが入れ替わる場合
平方和は次のように式が変わります。
●\(S’_{xx}\)=\(\sum_{i=1}^{n}(((n+1)-x_i )-((n+1)-\bar{x}))^2\)
●\(S_{yy}\)=\(\sum_{i=1}^{n}(y_i -\bar{y})^2\)
●\(S’_{xy}\)=\(\sum_{i=1}^{n}(((n+1)-x_i )-((n+1)-\bar{x})) (y_i-\bar{y})\)
「’」のついた平方和だけ式を変形すると、
●\(S’_{xx}\)=\(\sum_{i=1}^{n}(((n+1)-x_i )-((n+1)-\bar{x}))^2\)
=\(\sum_{i=1}^{n}(-x_i +\bar{x})^2\)
=\(S_{xx}\)
と元の\(S_{xx}\)に一致します。
●\(S’_{xy}\)=\(\sum_{i=1}^{n}(((n+1)-x_i )-((n+1)-\bar{x})) (y_i-\bar{y})\)
=\(\sum_{i=1}^{n}(-x_i+\bar{x}) (y_i-\bar{y})\)
=-\(S_{xy}\)
と元の\(S_{xy}\)と正負が入れ替わります。
これが、スピアマンの順位相関係数\(r\)の正負が入れ替わる理由ですね。
\(r’\)=\(\frac{S’_{xy}}{\sqrt{S’_{xx}}{S_{yy}}}\)
=-\(\frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}}{S_{yy}}}\)
=-\(r\)
なるほど、よくわかりますね!
(条件3)\(y\)だけが入れ替わる場合
平方和は次のように式が変わります。
●\(S_{xx}\)=\(\sum_{i=1}^{n}(x_i -\bar{x})^2\)
●\(S’_{yy}\)=\(\sum_{i=1}^{n}(((n+1)-y_i )-((n+1)-\bar{y}))^2\)
●\(S’_{xy}\)=\(\sum_{i=1}^{n}(x_i -\bar{x})(((n+1)-y_i )-((n+1)-\bar{y}))\)
同様に解くと、
●\(S’_{yy}\)=\(S_{yy}\)
●\(S’_{xy}\)=-\(S_{xy}\)
から
これが、スピアマンの順位相関係数\(r\)の正負が入れ替わる理由ですね。
\(r’\)=\(\frac{S’_{xy}}{\sqrt{S_{xx}}{S’_{yy}}}\)
=-\(\frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}}{S_{yy}}}\)
=-\(r\)
なるほど、よくわかりますね!
(条件4)\(x,y\)両方が入れ替わる場合
平方和は次のように式が変わります。
●\(S’_{xx}\)=\(\sum_{i=1}^{n}(((n+1)-x_i )-((n+1)-\bar{x}))^2\)
●\(S’_{yy}\)=\(\sum_{i=1}^{n}(((n+1)-y_i )-((n+1)-\bar{y}))^2\)
●\(S’_{xy}\)=\(\sum_{i=1}^{n}(((n+1)-x_i )-((n+1)-\bar{x})(((n+1)-y_i )-((n+1)-\bar{y}))\)
同様に解くと、
●\(S’_{xx}\)=-\(S_{xx}\)
●\(S’_{yy}\)=-\(S_{yy}\)
●\(S’_{xy}\)=\((-1)^2 S_{xy}\)
から
これが、スピアマンの順位相関係数\(r\)の正負が元に戻る理由ですね。
\(r’\)=\(\frac{S’_{xy}}{\sqrt{S’_{xx}}{S’_{yy}}}\)
=\(\frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}}{S_{yy}}}\)
=\(r\)
なるほど、よくわかりますね!
データを再度見て確認しよう!
データを再掲すると、計算通りの結果になっていますよね。
| – | 条件1 | 条件2 | 条件3 | 条件4 |
| \(S_{xx}\) | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
| \(S_{yy}\) | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
| \(S_{yx}\) | 51.5 | -51.5 | -51.5 | 51.5 |
| \(r\) | 0.624 | -0.624 | -0.624 | 0.624 |
ちゃんと、説明がつきましたね!
まとめ
「スピアマンの順位相関係数の正負の入れ替えがわかる」を解説しました。
- ➀スピアマンの順位相関係数の正負が変わる条件
- ➁スピアマンの順位相関係数の正負が入れ替わる理由