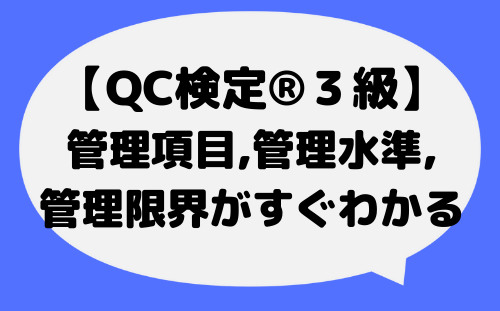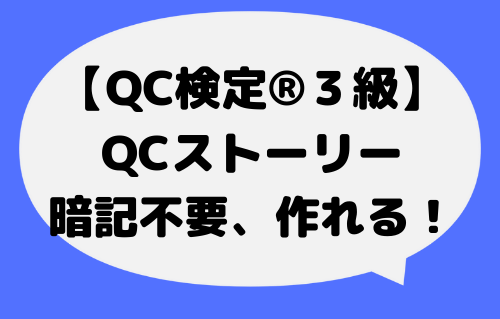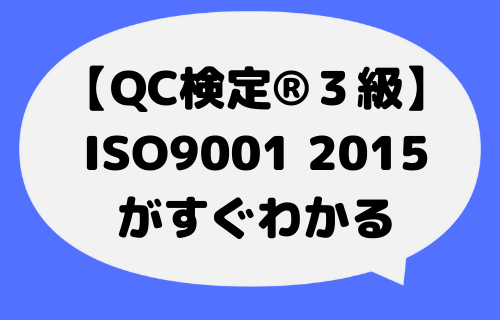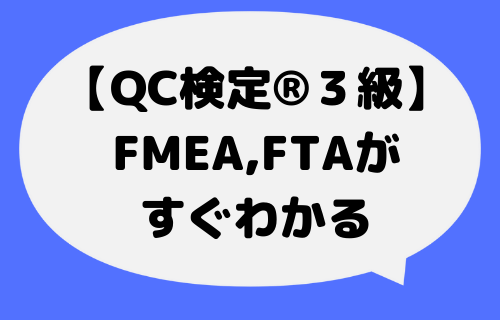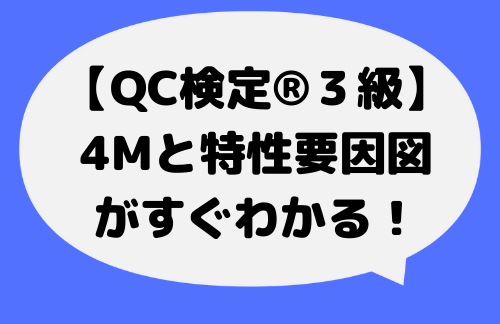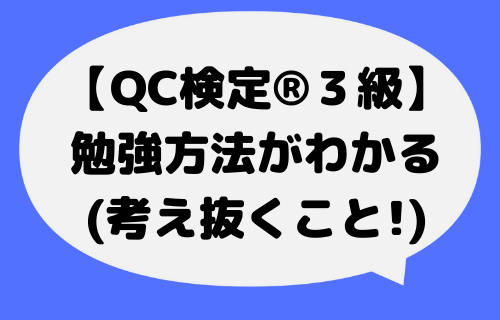★ 本記事のテーマ
- ⓪(QC検定®3級共通)QC勉強方法がわかる
- ①管理項目とは?
- ②管理水準と管理限界の違いとは?
★ QC検定®3級 合格 「必勝メモ」+「必勝ドリル」+「品質管理入門」をセット販売します!
 |
QC検定®3級 合格 「必勝メモ」+「必勝ドリル」+「品質管理入門」を販売します! 受験対策はもちろん、実務に活かせるポイントをしっかりおさえるよう、わかりやすく解説したおススメ商品! |
★ QC模試受験しよう!
 |
QC模試(品質技量の腕試し&QC検定®対策) 品質技量の実力を試したい! QC検定®合格対策に活用したい! 1,000円で提供します! 公式、暗記で終わらず、自分のものにできているかを試すオリジナル試験問題です! |
①QC検定®と品質管理検定®は、一般財団法人日本規格協会の登録商標です。
➁このコンテンツは、一般財団法人日本規格協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。
➂QCプラネッツは、QC検定®と品質管理検定®の商標使用許可を受けています。
●リンクページ
⓪(QC検定®3級共通)QC勉強方法がわかる
QCプラネッツでは、QC検定®3級受験者、および品質管理初心者の方に、馴染みにくい品質管理用語や概念をわかりやすく解説します。
QC検定®3級共通として、まず、勉強方法を読んでください。
 |
【QC検定®3級】勉強方法がわかる QC検定®3級受験や品質管理を初めてのあなたへ、勉強方法を解説します。直前の丸暗記の合否だけではなく、品質管理を得意・好きになれる方法をわかりやすく解説します。試験合格、品質管理の理解を深めたい方は必見です。 |
考えて活かせる品質管理を伝授します。
★★【QC検定®3級】勉強に必須な27項目をまとめました。
以前、ブログ解説していましたが、1つのPDFにまとめました。勉強に役立ててください
 |
【QC検定®3級】QCプラネッツプレミアムテキスト QCプラネッツがQC検定®3級に必要なエッセンスをまとめました! |
①管理項目とは?
管理項目とは?
●管理する対象を選ぶことです。
管理項目を実務で活かすには、
管理項目を考える例題
●簡単な例で考えましょう。例えば、レンガを製造するメーカに所属したとしましょう。レンガの品質を管理せよ!と言われたら、何を管理項目に挙げて管理しますか?
どうやって考えて管理項目を選びますか?
- 寸法
- 重量
- 表面の粗さ、傷の数
- 吸水性
- 強さ(圧縮強さ)
- 脆さ(割れにくさ)
など、下図のようにいろいろ管理項目の候補が列挙できますね。

●全部の管理項目を管理図に落として、全個数管理するのは大変ですね。
管理項目の選び方
●当然、優先順位をつけますよね。管理する時間、コストも考慮しないといけませんよね。
優先順位のつけ方はいろいろありますが、例えば、
- 重要な品質特性を優先
- 簡単に管理できて、調べにくい品質特性が推定できるもの
でしょう。やみくもに全部管理する必要はありません。
例題のレンガにおいて、「重要な品質特性」と「簡単に管理できて、調べにくい品質特性が推定できるもの」とはどんな管理項目が該当しますか?
ケースによりますが、例えば、
●「強度を売りにしたいので、圧縮強さは手間をかけても試験機で検査して管理したい。」
●「加工表面の綺麗さを売りにしたいので、凹凸の数を管理したい」
●「数万個のレンガを配置する顧客が多いので、寸法誤差を管理したい」
といろいろ選び方があります。
自社、顧客の戦略に合わせて、管理項目を選びましょう。
②管理水準と管理水準の違いとは?
●日常管理に出て来る用語は「管理水準」
●管理図に出て来る用語は「管理限界」
どう違うのかを考えます。意外とどこにも解説がないので、本記事で解説します。
管理水準(Control Level)とは?
方針管理や日常管理の単元でよく使う用語です。
管理限界(Control Limit)とは?
管理図を作るときによく使う用語です。
管理水準と管理限界の違いとは?
あれ?と思いませんか?
「正常と異常の判断基準」
で同じじゃん!
教科書や他のwebサイトを調べると、同じ定義に見えます。
2つの用語は出て来る単元や教科書のページ数が異なるので違いように見えますけど。
英語をよく見ると、
管理水準はLevel
管理限界はLimit
と違いますね。
何がちがうのか?まだわかりません。
そこで、違いがわかる図を用意しました。

●管理水準と管理限界も
「管理する程度」としては同じ軸になる(上図の右方向の矢印の方向になる)ので、混合しやすいです。
でも、
●管理水準は、管理の程度として、どこら辺を狙うか?のレベルを決めるもの
●管理限界は、管理水準の中で、平均とばらつきが正常と決めた範囲に収まるかどうかを調べるために使うもの
として区別しています。
まず、管理水準を決めるのが先ですね。どこら辺を狙うか?
次に決めた管理水準のレベルで、管理限界を決めることになります。
大事なこと
実務上は1つの用語に統一して使ってもOKです。
目的は、管理して品質を作りこむことです。
例に挙げた「レンガの品質を高めて組織の成長につなげるにはどうすればよいか」に最も注力しましょう。これがわかれば、管理方法も自分で考えて決めることができます。
まとめ
【QC検定®3級】管理項目、管理水準、管理限界をわかりやすく解説しました。
- ⓪(QC検定®3級共通)QC勉強方法がわかる
- ①管理項目とは?
- ②管理水準と管理限界の違いとは?