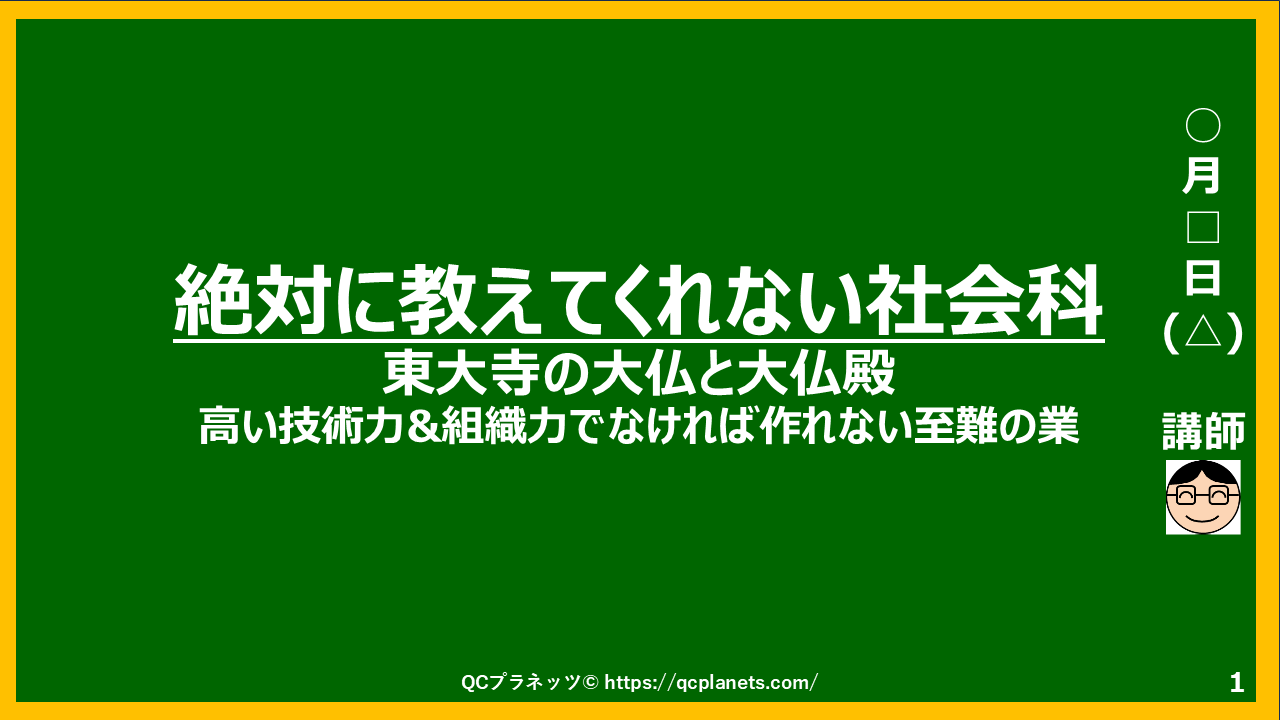★ 本記事のテーマ
東大寺の大仏と大仏殿
高い技術力&組織力でなければ作れない至難の業
高い技術力&組織力でなければ作れない至難の業
★おさえておきたいポイント
- ①通説
- ➁通説に対する疑問点・気になる点
- ➂通説を検証して見えた真相
学校や試験対策の社会では、
真相はわからない!
自分で調べて考え抜く
本当の社会科を勉強しよう!
真相はわからない!
自分で調べて考え抜く
本当の社会科を勉強しよう!
①通説
東大寺の大仏(通説)
教科書、学校、塾、親から教えてくれる内容は以下ですよね!
- 盧舎那仏(るしゃなぶつ)高さ15m 重さ500トン以上
(世界最大級の青銅製仏像) - 仏殿高さ48.7m,幅57m、奥行50m
(木造軸組建築としては世界最大級) - 聖武天皇が疫病・飢饉・戦乱などの社会不安を鎮めるために建立を発願。民衆の協力を呼びかけた国家的事業。
- 国家仏教の象徴としての政治的・宗教的意義も非常に大きく、聖武天皇の理想が形になった空間
奈良時代における東大寺の大仏は、国家の安定と統治理念の具現化という深い意味をもつ重要な建造物。
➁通説に対する疑問点・気になる点
調べると気づく疑問点
参考文献やYoutube動画を調べていくと、通説と異なることがわかります。それを陰謀論として片づけてしまってもよいですが、物事は多面的に見て、客観視する必要があります。QCプラネッツは品質管理を専門としています。品質管理は客観視が必須です。同じ姿勢で取り組みます!
- 当時の技術で、とても作れるものではない!
- どうやって巨大な大仏と、巨大な木造建築物を作ったの?
①大量の銅をどうやって採掘、運搬、鋳造したのか?
②大仏、木造建築物の強度、それに耐える木材の選定は?
③大仏の表面を金でどうやって覆ったのか?
いかがでしょうか?疑問が湧きますよね!
重機がない時代だし、設計計算するにも数学・物理・化学を知らない時代
どうやって作ったのだろうか?
どうやって作ったのだろうか?
真相を説明します。
東大寺のすごさを技術面で見てみましょう。
➂通説を検証して見えた真相
★ ①大仏の銅
- 銅山から採掘するが、銅を溶かすには1000℃以上の高温が必要。当時の窯ではせいぜい8,900℃。
- 古代の日本人は鉱山発掘の経験から9%のヒ素を含む銅は融点が900℃まで下がることを知っており、この銅を使って溶かしていた。(山口県長登(ながのぼり)銅山の大切製錬遺跡)(「ながのぼり」の語源は「奈良のぼり」)
- 低い融点で銅を製錬し鋳型に流し込んで金属塊を作り、船に奈良まで運び、再び溶かして鋳造仏を作る手間を惜しまない技術の高さ。
★ ②大仏、建物の強度計算
経験値と、ミニチュアを試作、試行錯誤によって建設したと思われるが、それにしても技術が高い!
→大仏の内部は空洞になっている(銅を節約するため)。上の銅の厚み、形、角度によってかかる荷重、底辺部が座屈しないために必要な銅の量や厚さ
→大仏殿(建屋)も当時世界最大級の建築物。強度をもつ木材の選定と運搬、立派な柱をくみ上げる構造。
→地震が多い日本だけに耐震強度も求められる。経験値とはいえ、その技術は高すぎる。
→大仏の内部は空洞になっている(銅を節約するため)。上の銅の厚み、形、角度によってかかる荷重、底辺部が座屈しないために必要な銅の量や厚さ
→大仏殿(建屋)も当時世界最大級の建築物。強度をもつ木材の選定と運搬、立派な柱をくみ上げる構造。
→地震が多い日本だけに耐震強度も求められる。経験値とはいえ、その技術は高すぎる。
★ ③大仏の表面を金メッキする化学技術
大仏の表面を削り研磨し、水銀と金で溶かしたアマルガムを塗り付け、水銀を蒸発させ金を表面に残す。
(ただし、蒸発した水銀による住民の水銀中毒問題もあとで起きてしまう。。。)
(ただし、蒸発した水銀による住民の水銀中毒問題もあとで起きてしまう。。。)
以上をまとめると、
・仏教で国民を守る思いだけでなく大仏を建設できる当時の技術力の高さ。
・世界にも巨大なモニュメントはあるが、ほとんどが石やコンクリートで、比較的容易。
・奈良の大仏は金属の巨大建造物であり、至難の業といえる。
・世界にも巨大なモニュメントはあるが、ほとんどが石やコンクリートで、比較的容易。
・奈良の大仏は金属の巨大建造物であり、至難の業といえる。
まとめ
「東大寺の大仏と大仏殿
高い技術力&組織力でなければ作れない至難の業」を解説しました。
- ①通説
- ➁通説に対する疑問点・気になる点
- ➂通説を検証して見えた真相