★ 本記事のテーマ
- ①多変量解析で困っていませんか?
- ➁問題集のメリット
- ➂内容の範囲
- ➃【問題集ご購入方法】
究めた結果、多変量解析がわかりましたので、問題集にしました!
①QC検定®と品質管理検定®は、一般財団法人日本規格協会の登録商標です。
➁このコンテンツは、一般財団法人日本規格協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。
➂QCプラネッツは、QC検定®と品質管理検定®の商標使用許可を受けています。
●リンクページ
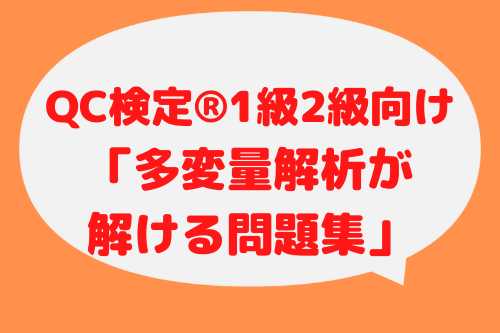
★ 本記事のテーマ
次の点で困っていませんか?
QCプラネッツが研究したオリジナルブログ記事にまとめています。一番詳しく書けたサイトであると自負します。ご確認ください。
 |
【まとめ】多変量解析を究める 重回帰分析,主成分分析,判別分析,因子分析,クラスター分析,コレスポンデンス分析,数量化Ⅰ類~Ⅳ類まで多変量解析に必ず出て来る分析方法をわかりやすく解説しています。 |
多変量解析はQC(品質管理)にも大事ですが、
データサイエンス、AIにも大事です。
逆にデメリットは
是非、ご購入いただきたいです。
次に、全問題の内容を紹介します!
42題の問題内容と単元を紹介します!
★第1章 回帰分析 単回帰分析・重回帰分析 の復習 (4題)
「QCに必要な回帰分析が身につく問題集(単回帰分析&重回帰分析)」 41題におさめた重要問題のうち、多変量解析で必要な重要な問題を復習します。
★第2章 主成分分析 (14題)
「主成分分析=固有値解」という思い込みを捨ててほしいため、主成分分析の解法からじっくり演習します。主成分分析を自力で導出することで、手法の目的をしっかり学べます。
★第3章 判別分析 (11題)
線形判別関数やマハラノビス距離の使い方より、導出過程を学ぶ方が大事です。導出から丁寧に演習します。手法の意味を導出過程から理解し、判別分析の学習効果を高めていきます。
★第4章 因子分析 (5題)
因子分析だけに、因子をどう抽出するかをベースに問題構成しています。計算が難しくなる因子分析をなるべく理解できるように演習していきます。
★第5章 数量化分析 (8題)
数量化○類と分類方法と解法を暗記して頭が混乱していませんか? 手法名より解析目的をしっかり理解しながら演習します。最後に多変量解析の目的を整理する問いを用意しています。
| 章 | 第 | 問題 |
| 1 | 1 | 単回帰分析の頻出問題 |
| 1 | 2 | 重回帰分析の回帰式の導出1 |
| 1 | 3 | 重回帰分析の回帰式の導出2 |
| 1 | 4 | 重回帰分析とハット行列 |
| 2 | 5 | 2 次元の主成分分析の導出(その1) |
| 2 | 6 | 2 次元の主成分分析の導出(その2) |
| 2 | 7 | 2 次元の主成分分析の頻出問題 |
| 2 | 8 | 2 次元の主成分分析と単回帰分析 |
| 2 | 9 | 3次元の主成分分析の導出 |
| 2 | 10 | m 次元の主成分分析の導出 |
| 2 | 11 | 3 次元の主成分分析 |
| 2 | 12 | 5次元の主成分分析 |
| 2 | 13 | 主成分分析の各変数の意味 |
| 2 | 14 | 主成分分析(重解がある場合) |
| 2 | 15 | 因子負荷量の導出 |
| 2 | 16 | 主成分方向の平方和と固有値が一致する理由 |
| 2 | 17 | 固有ベクトルが直交する理由がわかる |
| 2 | 18 | 固有値・固有ベクトル(平方和行列vs相関係数行列) |
| 3 | 19 | 線形判別関数に慣れる |
| 3 | 20 | 線形判別関数の平方和の分解 |
| 3 | 21 | 線形判別関数の導出1 相関比 |
| 3 | 22 | 線形判別関数の導出2 ラグランジュの未定係数法 |
| 3 | 23 | 線形判別関数の導出(2 次元で3 群以上分割する場合 |
| 3 | 24 | マハラビノス距離の導出(その1) |
| 3 | 25 | マハラビノス距離の導出(その2) |
| 3 | 26 | マハラビノス距離の計算 |
| 3 | 27 | マハラビノス距離と相関係数の関係 |
| 3 | 28 | マハラビノス距離からの判別分析 |
| 3 | 29 | マハラビノス距離と線形判別関数からの判別分析 |
| 4 | 30 | 因子分析の1 因子モデルの導出 |
| 4 | 31 | 因子分析の1 因子モデルの計算 |
| 4 | 32 | 因子分析の2 因子モデルの導出 |
| 4 | 33 | 因子分析の2 因子モデルの計算 |
| 4 | 34 | 因子分析と主成分分析の違い |
| 5 | 35 | クラスター分析 |
| 5 | 36 | 数量化3 類 |
| 5 | 37 | 数量化4 類 |
| 5 | 38 | コレスポンデンス分析 |
| 5 | 39 | 数量化1 類と重回帰分析 |
| 5 | 40 | 数量化2類(ラグランジュの未定係数法) |
| 5 | 41 | 数量化2類 マハラビノス距離 |
| 5 | 42 | 多変量解析のまとめ |
5つの章に分けてしっかり解いていきましょう。
丁寧な解説ページやQCプラネッツのブログ記事を活用してわかりやすく解けますので、ご安心ください。
是非、ご購入ください。
ご購入いただけます。ご購入後、QCプラネッツからアクセスサイト先(アクセスのみ可)をご案内いたします。データの拡散を防ぐため、ダウンロードと印刷は不可とさせていただきます。
「QCプラネッツ」で検索ください。

1500円/1冊
とさせていただきます。ご購入よろしくお願いいたします。
電子販売もしています。こちらへアクセスください。
 |
【QC検定®1級,2級合格!】QCに必要な「多変量解析」問題集を発売します! |
「【QC検定®合格】「多変量解析」問題集を販売します」、ご購入よろしくお願いいたします。
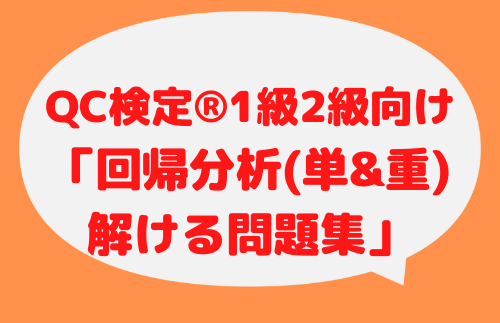
★ 本記事のテーマ
次の点で困っていませんか?
それは、
QCプラネッツが研究したオリジナルブログ記事にまとめています。一番詳しく書けたサイトであると自負します。ご確認ください。
★【まとめ】単回帰分析がわかる
 |
【まとめ】単回帰分析がわかる 単回帰分析まとめ記事です。相関係数、回帰直線、分散分析、回帰母数の検定と推定、繰返しのある単回帰分析、符号検定、スピアマンの順位相関係数、クラメールの連関係数について、数式導出しながら本質がわかるよう単回帰分析のすべて丁寧に解説します。 |
★【まとめ】重回帰分析がよくわかる
 |
【まとめ】重回帰分析がよくわかる 重回帰分析の考え方、理解すべきポイント、重回帰分析の特徴をわかりやすく解説し、公式の導出過程を詳しく解説します。公式暗記、解法暗記で終わらせずに、本質を学ぶことができます。 |
回帰分析はQC(品質管理)にも大事ですが、
データサイエンス、AIにも大事です。
逆にデメリットは
是非、ご購入いただきたいです。
次に、全問題の内容を紹介します!
41題の問題内容と単元を紹介します!
★第1章 単回帰分析の基本 (7題)
単回帰分析式の導出、データの構造式から平方和の分解、寄与率の導出と範囲、無相関の検定と単回帰分析の頻出問題に出て来る重要公式をすべて自力で導出します。
★第2章 特殊な単相関係数 (6題)
単回帰分析をベースにクラメールの連関係数、スピアマンの順位相関係数、大波の相関・小波の相関・符号検定について、大事な式をすべて自力で導出します。
★第3章 単回帰分析の応用 (6題)
回帰分析と実験計画法を比較、回帰直線の区間推定の導出、回帰母数の検定と推定、繰返しのある単回帰分析へと応用問題を解きます。これらも自力で解けるし公式暗記は不要です。
★第4章 重回帰分析の基礎 (13題)
重回帰分析の回帰式の導出、平方和の分解、重回帰分析の寄与率、推定区間、偏相関係数の導出、多重共線性と、重回帰分析に重要な演習をします。すべて自力で導出できます!
★第5章 重回帰分析の応用 (9題)
偏回帰係数に関する検定と推定、変数増減法、ハット行列とテコ比、ダービンワトソン比についても詳しく演習します。数学力も高めることができる大事な章です。
| 章 | 第 | 問題 |
| 1 | 1 | 単回帰分析式の導出 |
| 1 | 2 | 平方和の分解 |
| 1 | 3 | 寄与率R の導出 |
| 1 | 4 | 相関係数とグラフ例 |
| 1 | 5 | コーシ・シュワルツの不等式と相関係数 |
| 1 | 6 | 無相関の検定 |
| 1 | 7 | 単回帰分析の頻出問題 |
| 2 | 8 | クラメールの連関係数の導出 |
| 2 | 9 | クラメールの連関係数(0と1条件) |
| 2 | 10 | スピアマンの順位相関係数の導出 |
| 2 | 11 | スピアマンの順位相関係数の正負の入替 |
| 2 | 12 | スピアマンの順位相関係数とピアソンの相関係数を比較 |
| 2 | 13 | 大波の相関・小波の相関・符号検定 |
| 3 | 14 | 回帰分析と実験計画法を比較 |
| 3 | 15 | 回帰直線の区間推定の導出(その1) |
| 3 | 16 | 回帰直線の区間推定の導出(その2) |
| 3 | 17 | 回帰母数の検定と推定 |
| 3 | 18 | 繰返しのある単回帰分析の分散分析 |
| 3 | 19 | 相関係数のz変換 |
| 4 | 20 | 重回帰分析の回帰式の導出(その1) |
| 4 | 21 | 重回帰分析の回帰式の導出(その2) |
| 4 | 22 | 重回帰分析における平方和の分解 |
| 4 | 23 | 重回帰分析の寄与率 |
| 4 | 24 | 単回帰分析と重回帰分析の比較 |
| 4 | 25 | 重回帰分析の推定区間の式の導出(その1) |
| 4 | 26 | 重回帰分析の推定区間の式の導出(その2) |
| 4 | 27 | 偏相関係数の導出(その1) |
| 4 | 28 | 偏相関係数の導出(その2) |
| 4 | 29 | 重回帰分析の多重共線性 |
| 4 | 30 | 重回帰分析は単位への影響(その1) |
| 4 | 31 | 重回帰分析は単位への影響(その2) |
| 4 | 32 | ダミー変数と重回帰分析 |
| 5 | 33 | 偏回帰係数に関する検定と推定 |
| 5 | 34 | 変数増減法 |
| 5 | 35 | 重回帰分析とハット行列 |
| 5 | 36 | 重回帰分析とハット行列とテコ比(その1) |
| 5 | 37 | 重回帰分析とハット行列とテコ比(その2) |
| 5 | 38 | 単回帰分析とハット行列とテコ比(その1) |
| 5 | 39 | 単回帰分析とハット行列とテコ比(その2) |
| 5 | 40 | ダービンワトソン比(その1) |
| 5 | 41 | ダービンワトソン比(その2) |
5つの章に分けてしっかり解いていきましょう。
丁寧な解説ページやQCプラネッツのブログ記事を活用してわかりやすく解けますので、ご安心ください。
是非、ご購入ください。
ご購入いただけます。ご購入後、QCプラネッツからアクセスサイト先(アクセスのみ可)をご案内いたします。データの拡散を防ぐため、ダウンロードと印刷は不可とさせていただきます。
「QCプラネッツ」で検索ください。

1500円/1冊
とさせていただきます。ご購入よろしくお願いいたします。
電子販売もしています。こちらへアクセスください。
 |
【QC検定®1級,2級合格!】QCに必要な「回帰分析(単回帰分析&重回帰分析)」問題集を発売します! |
「【QC検定®合格】「回帰分析(単回帰分析&重回帰分析)」問題集を販売します」、ご購入よろしくお願いいたします。
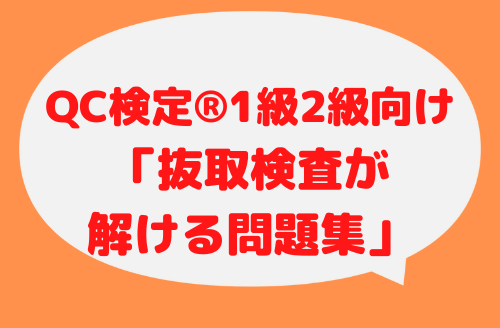
★ 本記事のテーマ
QC検定®2級、QC検定®1級で抜取検査の問題がでますが、
です。勉強が大変だけど、丸暗記で点数とれるし、合格するとわかった気になってしまいます。
とはいえ、
または、
QCプラネッツが研究したオリジナルブログ記事にまとめています。一番詳しく書けたサイトであると自負します。ご確認ください。
 |
【まとめ】究める!抜取検査 抜取検査は使い方だけ理解して終わっていませんか?実務で活用するには、抜取検査の理論の習得が必須です。本記事では、抜取検査全体の理論をわかりやすく解説します。品質にかかわる技術者は必読です。 |
そこで、単なる、JISの使い方だけではなく、抜取検査の理論や本質まで理解できる問題集を作りました。
以下の点でマスターしていただきたいので、確認ください。不安要素があれば、本問題集で解決していただきたいです。
そこで、今回「抜取検査」の問題集を作成しました。
逆にデメリットは
是非、ご購入いただきたいです。
次に、全問題の内容を紹介します!
47題の問題内容と単元を紹介します!
★第1章 抜取検査の基本 (8題)
抜取検査の使い方より大事な、抜取検査の歴史、抜取検査のベースとなる二項定理・二項分布・ポアソン分布の復習や、検査のあり方、主抜取表で当たり前なことのなぜ?を確認します。
★第2章 2回抜取検査 (6題)
2回抜取検査メリット・デメリットについて、OC曲線を作りながら理解を深めていきます。抜取検査法を覚えるのではなく、なぜ2回抜取検査が必要か?の問いから学んでいきます。
★第3章 選別型抜取検査 (6題)
選別型抜取検査とは何か。規準型抜取検査との違いや、選別型抜取検査のメリット・デメリットが理解できる章です。覚えにくいAOQ,AOQLの暗記より、理論の理解が大事です。
★第4章 計量抜取検査 (11題)
検出力と同様に、関係図をしっかり記述してから関係式を導出することが計量抜取検査の一番大事な所です。種々の検査方法より、1つの理論ですべて理解できることを学習します。
★第5章 逐次抜取検査 (5題))
逐次抜取検査は判定線で判断することです。判定線をOC曲線から導出する過程をしっかり演習します。
★第6章 調整型抜取検査 (10題)
「なみ、ゆるい、きつい」の定義、それぞれの主抜取表の定義をOC曲線から導出する過程をしっかり演習します。単なる暗記問題で終わりがちですが、本質を理解する問題を用意しました。
★第7章 抜取検査のまとめ (1題)
最後の問いで、「抜取検査」の本質が理解できたかを確かめる問題です。十分回答できない場合は上の47問のどこかがまだ不十分であるということです。何度も問いてください。
| 章 | 第 | 問題 |
| 1 | 1 | 抜取検査の歴史 |
| 1 | 2 | 二項定理・二項分布 |
| 1 | 3 | ポアソン分布の関係式 |
| 1 | 4 | 全数検査と抜取検査と無検査 |
| 1 | 5 | OC 曲線(二項分布、ポアソン分布)手計算 |
| 1 | 6 | OC 曲線(二項分布、ポアソン分布)プログラム |
| 1 | 7 | 検査誤りの影響 |
| 1 | 8 | 抜取検査表と標準数 |
| 2 | 9 | 2回抜取検査 のロット合格率L(p) (二項分布) 1 |
| 2 | 10 | 2回抜取検査 のロット合格率L(p) (二項分布) 2 |
| 2 | 11 | 2回抜取検査 のロット合格率L(p) (ポアソン分布) |
| 2 | 12 | 2回抜取検査 のOC 曲線(二項分布、ポアソン分布) |
| 2 | 13 | OC 曲線から抜取検査表を作る |
| 2 | 14 | 2回抜取方式の注意点 |
| 3 | 15 | 選別型抜取検査とは |
| 3 | 16 | 選別型抜取検査の平均検査量I(その1) |
| 3 | 17 | 選別型抜取検査の平均検査量I(その2) |
| 3 | 18 | 選別型抜取検査の平均出検品質AOQ |
| 3 | 19 | 選別型抜取検査の平均出検品質限界AOQL1 |
| 3 | 20 | 選別型抜取検査の平均出検品質限界AOQL2 |
| 4 | 21 | 標準偏差既知で下限規格値が既知の抜取方式1 |
| 4 | 22 | 標準偏差既知で下限規格値が既知の抜取方式2 |
| 4 | 23 | 標準偏差既知で下限規格値が既知の抜取方式3 |
| 4 | 24 | 標準偏差既知で上限規格値が既知の抜取方式1 |
| 4 | 25 | 標準偏差既知で上限規格値が既知の抜取方式2 |
| 4 | 26 | OC 曲線のサンプル数と合格判定個数の関係1 |
| 4 | 27 | OC 曲線のサンプル数と合格判定個数の関係2 |
| 4 | 28 | 計量規準型一回抜取検査の抜取表にあるn,k を計算 |
| 4 | 29 | 標準偏差既知で下限合格判定値が既知の抜取方式 |
| 4 | 30 | 標準偏差既知で上限合格判定値が既知の抜取方式 |
| 4 | 31 | 標準偏差が未知の場合の計量抜取検査 |
| 5 | 32 | 二項分布における逐次抜取検査1 |
| 5 | 33 | 二項分布における逐次抜取検査2 |
| 5 | 34 | 変数の変化と判定線の関係 |
| 5 | 35 | ポアソン分布における逐次抜取検査 |
| 5 | 36 | 計量値逐次抜取検査 |
| 6 | 37 | なみ検査の主抜取表 |
| 6 | 38 | 抜取検査を考える |
| 6 | 39 | AQL(合格品質水準) |
| 6 | 40 | 調整型抜取検査(1 回方式)の主抜取表の作り方 |
| 6 | 41 | 1 回方式の主抜取表の作り方 |
| 6 | 42 | 2 回方式の主抜取表の作り方 |
| 6 | 43 | 調整型抜取検査の検査水準 |
| 6 | 44 | 調整型抜取検査の切替えルール |
| 6 | 45 | 抜取検査設計補助表 |
| 6 | 46 | 調整型抜取検査で説明できてほしいこと |
| 7 | 47 | 抜取検査で説明できてほしいこと |
7つの章に分けてしっかり解いていきましょう。
丁寧な解説ページやQCプラネッツのブログ記事を活用してわかりやすく解けますので、ご安心ください。
是非、ご購入ください。
ご購入いただけます。ご購入後、QCプラネッツからアクセスサイト先(アクセスのみ可)をご案内いたします。データの拡散を防ぐため、ダウンロードと印刷は不可とさせていただきます。
「QCプラネッツ」で検索ください。

1500円/1冊
とさせていただきます。ご購入よろしくお願いいたします。
電子販売もしています。こちらへアクセスください。
 |
【QC検定®1級,2級合格!】QCに必要な「抜取検査」問題集を発売します! |
「【QC検定®合格】「抜取検査」問題集を販売します」、ご購入よろしくお願いいたします。
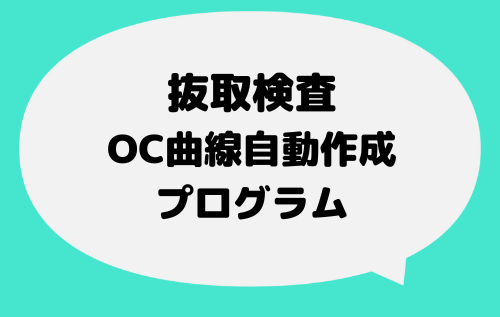
★ 本記事のテーマ
4つのファイルをダウンロードしてお使いいただけます。
★本物の「抜取検査」問題集を販売します!
 |
【QC検定®合格】「抜取検査」問題集を販売!①二項分布・ポアソン分布、OC曲線、➁多回抜取検査、➂選別型抜取検査、➃計量抜取検査、⑤逐次抜取検査、⑥調整型抜取検査、⑦抜取検査まとめ の7章全47題! |
ダウンロードすると、4つのファイルがあります。確認ください。
●1_oc-curve1.xlsm
●2_oc-curve2.xlsm
●3_aoql.xlsm
●4_oc-curve_ad.xlsm
インターネットからダウンロードしたマクロファイルなので、保護ビューのままを勧めることがありますので、一旦フォルダーに移動して保存してください。

★ 1.代入
ここで、
不良率の間隔pの値により、計算する行数が変化します。
例えば、
・p=1%の時は、 100/p=100/1=100行計算します。
・p=2%の時は、 100/p=100/2=50行計算します。
★ 2.計算
黄色枠をダブルクリックしてください。自動計算が開始します。
★ 3.計算結果
緑枠に計算結果が出ます。
●各不良率pにおけるロット合格率
●不良率100-α(%)におけるロット合格率p0
●不良率β(%)におけるロット合格率p1
p0とp1は主抜取表の値を求めるときに使います。
二項分布、ポアソン分布と2つのシートがありますが、使い方は共通です。
ただし、ポアソン分布においては、
●不良率100-α(%)におけるロット合格率p0
●不良率β(%)におけるロット合格率p1
はありませんので、ご注意ください。

★ 1.代入
ここで、
不良率の間隔pの値により、計算する行数が変化します。
例えば、
・p=1%の時は、 100/p=100/1=100行計算します。
・p=2%の時は、 100/p=100/2=50行計算します。
★ 2.計算
黄色枠をダブルクリックしてください。自動計算が開始します。
★ 3.計算結果
緑枠に計算結果が出ます。
●各不良率pにおけるロット合格率
●不良率100-α(%)におけるロット合格率p0
●不良率β(%)におけるロット合格率p1
p0とp1は主抜取表の値を求めるときに使います。
二項分布、ポアソン分布と2つのシートがありますが、使い方は共通です。
ただし、ポアソン分布においては、
●不良率100-α(%)におけるロット合格率p0
●不良率β(%)におけるロット合格率p1
はありませんので、ご注意ください。

★ 1.代入
ここで、
不良率の間隔pの値により、計算する行数が変化します。
例えば、
・p=1%の時は、 100/p=100/1=100行計算します。
・p=2%の時は、 100/p=100/2=50行計算します。
★ 2.計算
黄色枠をダブルクリックしてください。自動計算が開始します。
★ 3.計算結果
緑枠に計算結果が出ます。
●各不良率pにおけるロット合格率
●不良率100-α(%)におけるロット合格率p0
●不良率β(%)におけるロット合格率p1
p0とp1は主抜取表の値を求めるときに使います。
二項分布、ポアソン分布と2つのシートがありますが、使い方は共通です。

★ 1.代入
ここで、
不良率の間隔pの値により、計算する行数が変化します。
例えば、
・p=1%の時は、 100/p=100/1=100行計算します。
・p=2%の時は、 100/p=100/2=50行計算します。
また、
調整の選択として、なみ、ゆるい、きついは
●なみ : m=1
●ゆるい: m=1.584
●きつい: m=0.631
として計算しています。
mの値については、関連記事をもとに計算していますので、ご確認ください。
 |
【簡単】AQL(合格品質水準)がすぐわかる AQL(合格品質水準)はOC曲線上でどの値なのかが説明できますか?JISや教科書の説明ではわからないため、本記事で解説します。 |
★ 2.計算
黄色枠をダブルクリックしてください。自動計算が開始します。
★ 3.計算結果
緑枠に計算結果が出ます。
●各不良率pにおけるロット合格率
●不良率100-α(%)におけるロット合格率p0
●不良率β(%)におけるロット合格率p1
p0とp1は主抜取表の値を求めるときに使います。
調整型抜取検査は二項分布のみです。
自動計算結果から、
(n,c)=(20,0)のとき、p0=0.174%,p1=6.87%ですから、
●p0=0.174の行と
●p1=6.87の列に
(n,c)=(20,0)が主抜取表に来るということです。
さまざまな(n,c)のパターンによるOC曲線を自動で描いて、p0,p1を計算して、その結果から主抜取表を作ればJISの調整型抜取検査の主抜取表ができます。
「OC曲線の自動作成プログラムの使い方」を解説しました。