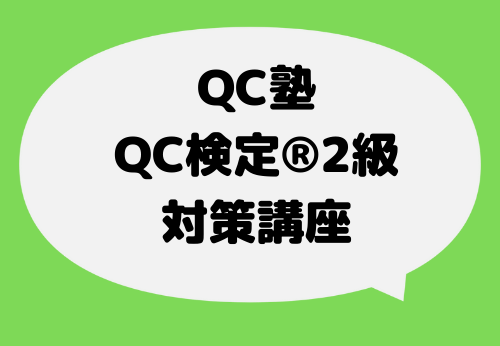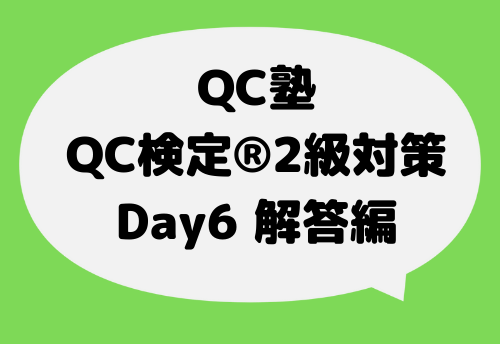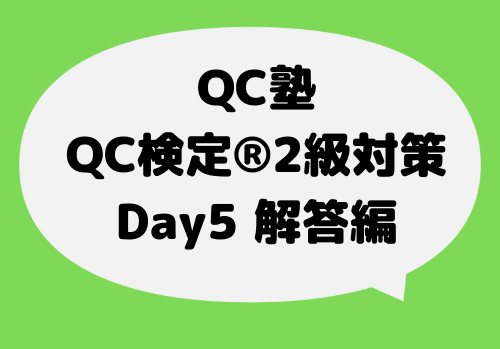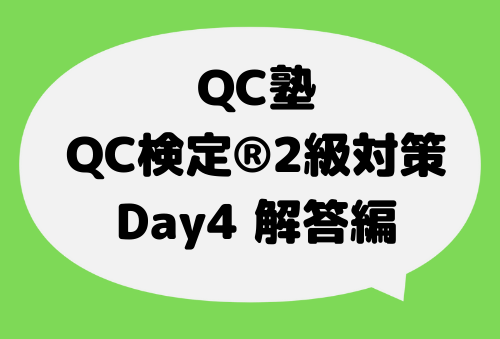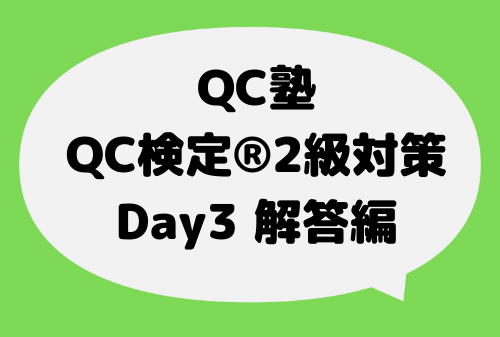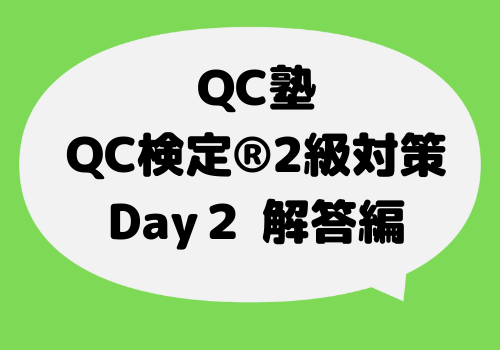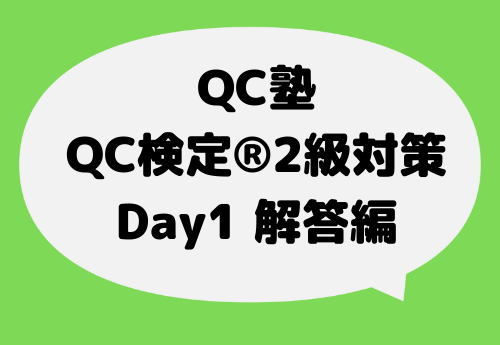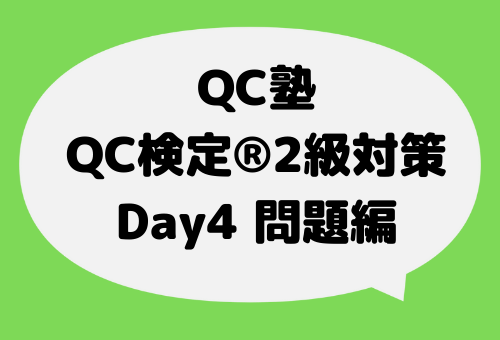★ おさえておきたいポイント
- ①科目概要
- ➁受講対象者
- ➂各回の学習内容
- ➃購入方法
①科目概要
本講座の目的です。
- QC検定® 2級合格を勝ち取る!
- 用語、公式の暗記ではなく、意味・本質を理解する!
- QC検定® 1級受験のベースを作る!
- 資格獲得で終わらず、実務で活かす力をつける!
品質中級から上級へつなぐための大事な科目です。
➁受講対象者
- QC検定® 2級、1級受験者
- 品質管理業務の方
- 組織・職場の品質改善・改革が必要な方
➂各回の学習内容
各回のテーマ
| Day | テーマ | 問題数 |
| Day1 | 数理、基本統計量、確率分布 | 10 |
| Day2 | サンプリング、検定と推定 | 10 |
| Day3 | 抜取検査、管理図、単回帰分析 | 10 |
| Day4 | 実験計画法、信頼性工学 | 9 |
| Day5 | 品質用語、標準規格、TQM、製造物責任 | 10 |
| Day6 | QC道具、QCサークル、方針管理、勝てる解き方 | 10 |
問題への思い
- QC検定® 2級全回過去問がベース
- 過去問にさらにQCプラネッツが改良した良問
- 本質を理解するための必須問題
解説方法
解説ブログページで解説し、文章・動画解説します。
QCプラネッツの実際の解き方・解くスピード・解答までに何を解くか・書くかなど、試験の実践に役立つポイントが分かるために、ワープロ書きではなく、手書き動画で解説しています。QC検定® 2級,1級一発合格したQCプラネッツの実践を見ながら、演習を深めてください。
➃購入方法
直接ご購入いただけます。
(c) 2024 QCプラネッツ