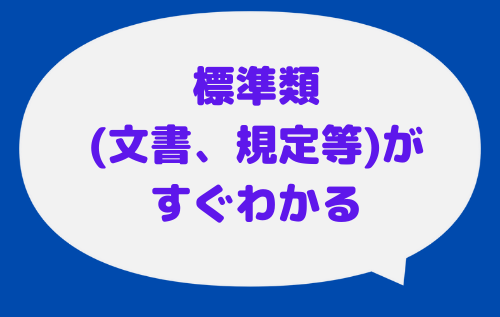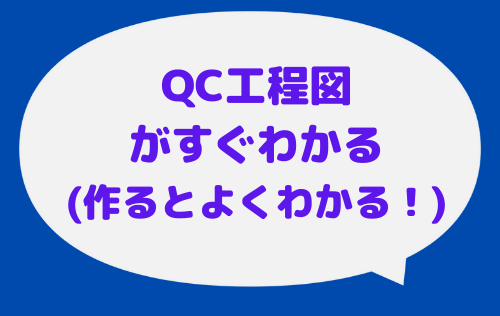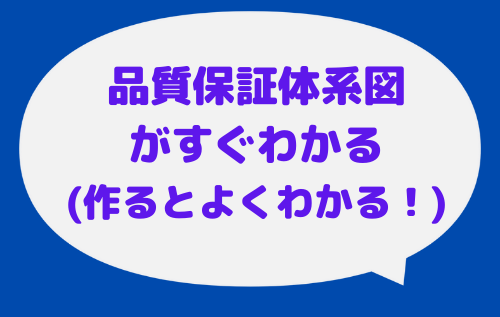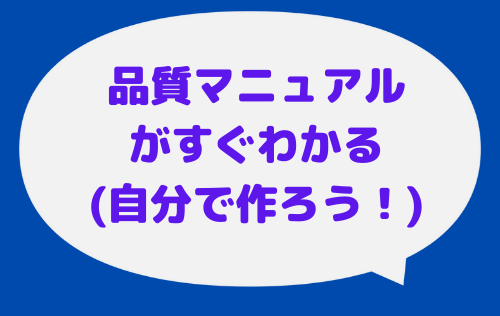★ 本記事のテーマ
- ①標準類に何があるのか?
- ②標準類を作る理由
- ③標準類を作る方法
- ④標準類を更新する理由
①標準類に何があるのか?
標準類とは何か?
●難しい用語です。
「標準」が難しいし、
「類」って何?
ですよね。品質管理用語としても、品質監査にしても重要なので、わかりやすく解説していきます。
★標準類とは
次に、どういうものを標準類にするかを解説します。
★標準類にするもの
●具体的には、以下でしょう。
- 繰り返し行う頻度の高い業務
- 全員が行う業務
- 頻度は低いがミスしやすい煩雑で難しい業務
- 継承が必須な業務
- 法令・規格への届け出
- プログラミング
最後のプログラミングをあえて入れました。システムを導入するほどではないけど、集計や処理を個人レベルで作ってうまく運用していることが多々あります。
そういうプログラミングは担当者が独学で学んで作ったものが多く、その担当者が異動でいなくなると、その業務が継承されなくなります。
標準類の具体例
●具体例をいろいろ挙げましょう。組織にはいろいろな文書やルール、会議がありますね。
- 作業手順書
- 工程管理表
- 会議録
- 費用清算書
- 発注書
- 組織内規定
- 品質保証体系図
最初は、目の前のある業務を標準化して、徐々に組織全体を俯瞰できるルールを標準類に入れました。これ以外にも必要なものは随時、標準類に含めましょう。
標準類のメリットとデメリット
●当然、メリットの方が大きいですが、メリット・デメリットを両方考えてみましょう。
★標準類のメリット
●作業効率性、作業ばらつき、改善が期待できますね。
- 担当者による業務ばらつきが低減
- 業務改善(皆同じ標準類を使っているから気づきやすい)
- 教育資料に活用
同じ標準類を皆で改善し、標準類を教育すれば、新人も早く、正しい仕事を覚えてくれます。
★標準類のデメリット
- 標準類作成に人と時間がかかる
- 標準類に慣れるまでは、業務はかえって時間がかかる
- 標準文書を作ることが業務目的になりがち
標準類は皆のためとはいえ、皆にとって使えにくいものだったりします。
でも読んでも一発では理解できないでしょう!
皆に合わせると抽象化したり、細かくなりすぎます。それに慣れるまでに時間がかかります。
また、標準文書を作ることが業務目的になりがちになり、業務の本来の意味を理解していない若手・中堅が増加します。標準類に合わせるのに必死で、それ以上はできません。
経験上、標準類に慣れるには3年はかかります。慣れるまでは、面倒な書類ばかり作る日々で、「モノづくりしたいから入社したのに、何で毎日ムダな文書作成と修正ばかりなの?」と思うでしょう。
これが標準類のデメリットですが、そこを乗り越えると、標準類を活用して組織やチームを運用することができるようになります。
②標準類を作る理由
最初から標準類があるわけではない
●組織が若い時は、組織の成功パターンが醸成するまで四苦八苦します。
どのやり方が良いかを模索しながら業務するので、各担当者の独自の業務方法になりがちです。
標準類を作るきっかけ
●ある程度、組織が醸成してくると、担当者が同じ業務をやっていることがわかります。
●すると、ルールを作って、それに準拠した方が、業務効率が上がるとわかるので、標準類を作成するようになります。
組織にとってメリットがあるから標準類を作るのです!
または、将来ISO9001取得を目指すためという理由もあります。
誰が標準類を作るか
●組織共通の標準類なので、全体を見渡せる人、細部までチェックできる人などその組織で評価の高い人を選んで作った方がよいでしょう。
- 管理職
- 後輩や周囲の人に業務方法を伝達するのが上手な人
- おおざっぱな性格でも全体を俯瞰できる人
- 細部までチェックできる人
いろいろな性格のタイプを挙げましたが、いろいろなタイプを集めて作らせるとよいでしょう。
③標準類を作る方法
●標準類を作るステップがあります。標準類も成熟するまでに数年はかかるものです。
- 目の前の業務を標準化(工程管理表、作業手順書、会議録、発注書、費用清算書)
- 各部門の業務をルール化(組織内規定、ルール)
- 複数の部門業務を標準化(営業、技術、品質、保守 各部門を共通化)
最初は、担当者の目の前の業務に使うものから標準化します。
次に、標準化が進んでくると、部門内のルールを整備が必要になります。
三段階目は、ISO取得で必須なので、品質保証体系図を作るようになり、各部門の共通業務を標準化していきます。
成熟した組織に配属されると、最初から品質保証体系図や規定、標準文書があります。これらが作られた背景を知らずに、標準類に慣れていく必要がありますが、最初から標準類があったわけではありません。
④標準類を更新する理由
●一度、標準類が出来たら終わりではなく、随時更新していく必要があります。主に次の3つの理由で更新が必要です。
- 業務変更
- 法令・規格の変更
- 苦情トラブルの是正処置
●最初の業務変更はわかりやすいですね。ルール、やり方、文書が変わるからですね。
●法令・規格も随時更新されていきます。それまでは許可だったことが禁止になったり、その逆もあります。法令遵守の精神のもと、組織も対応していく必要があります。
●苦情・トラブルが発生した後、なぜ発生したのか?を振り返ります。トラブルの原因が作業工程によくあります。同じミスを繰り返さないために、業務方法を改善し、それを標準類に追加していく必要があります。
例えば、「他部門への引継ぎが曖昧だったため、仕様モレがあった」としたら、標準類を
・引継書を新規に作成
・引継ぐ時にレビューを必ず開催し、会議録を残す
・引継ぎ書を受領したことを受領側が明記する
などのルールが作られるでしょう。これらを標準類に追加していきます。
だけではありません。
作業自体をシンプルにした方法にして、
「改善」=「標準類の圧縮・シンプル化」
した方がよいでしょうね。
標準類の増加・煩雑化は簡単ですが、
標準類の圧縮・シンプル化は難しいです。
でも、是非「標準類の圧縮・シンプル化」を目指す方がよいです。
まとめ
業務に欠かせない標準類についてわかりやすく解説しました。
- ①標準類に何があるのか?
- ②標準類を作る理由
- ③標準類を作る方法
- ④標準類を更新する理由