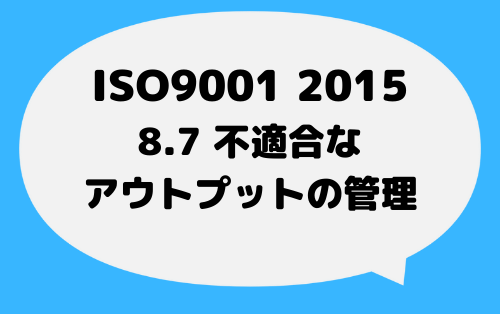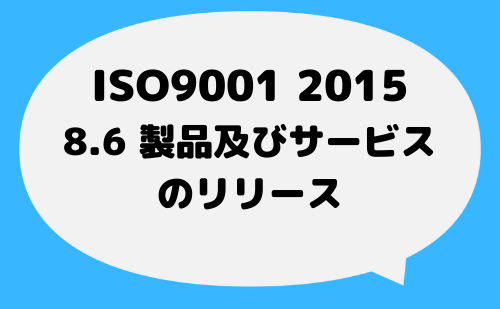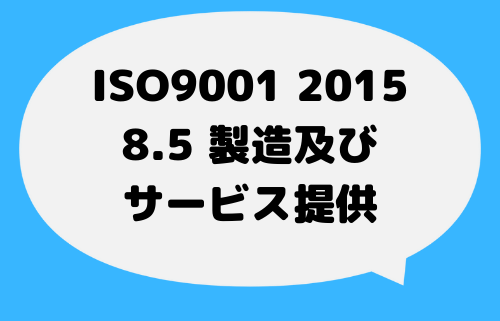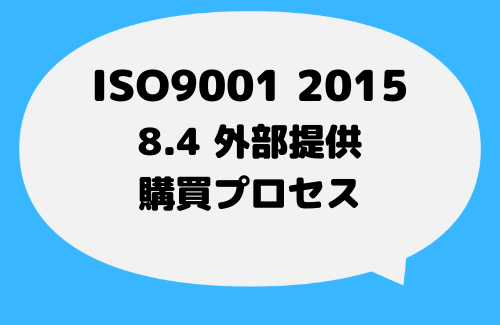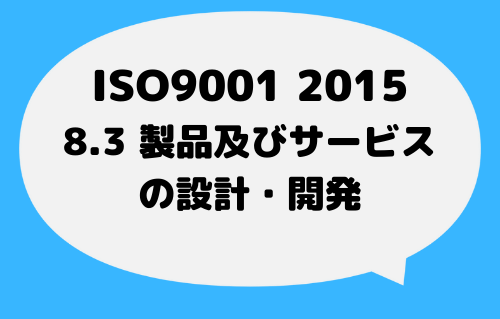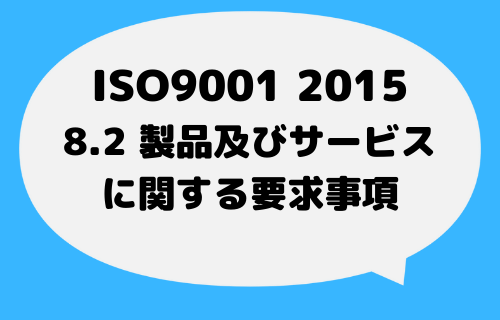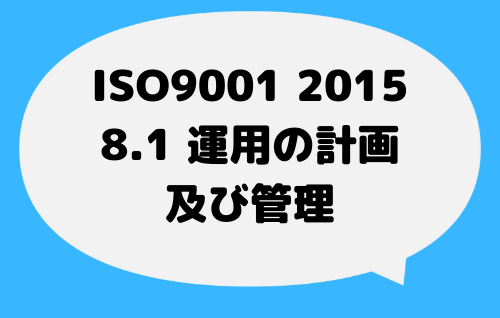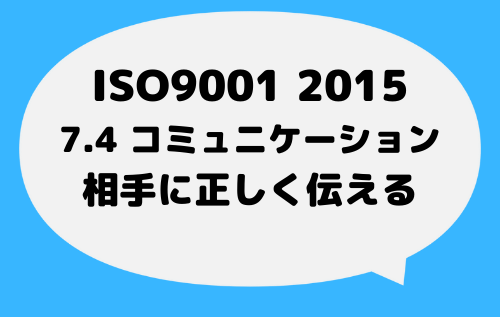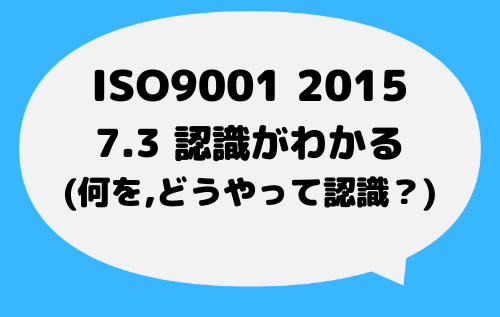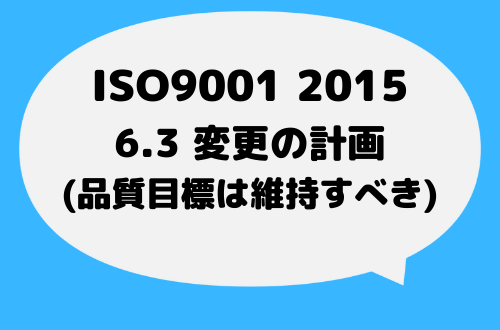「不適合やトラブルが発生したら何をしたらよいかがわからない?」、と困っていませんか?
こういう疑問に答えます。
本記事のテーマ
- ①要求事項の簡略化
- ②不適合発生前提で考えておくこと
- ③不適合に対する迅速な対応ができる組織力
- ④特別採用(トクサイ)の拡大解釈に注意
①要求事項の簡略化
ISO9001要求事項
ちょっと長いですが、掲載しますね。
8.7.1 組織は,要求事項に適合しないアウトプットが誤って使用されること又は引き渡されることを防ぐために,それらを識別し,管理することを確実にしなければならない。 組織は,不適合の性質,並びにそれが製品及びサービスの適合に与える影響に基づいて,適切な処置をとらなければならない。これは,製品の引渡し後,サービスの提供中又は提供後に検出された,不適合な製品及びサービスにも適用されなければならない。 組織は,次の一つ以上の方法で,不適合なアウトプットを処理しなければならない。
a) 修正
b) 製品及びサービスの分離,散逸防止,返却又は提供停止
c) 顧客への通知
d) 特別採用による受入の正式な許可の取得 不適合なアウトプットに修正を施したときには,要求事項への適合を検証しなければならない。
8.7.2 組織は,次の事項を満たす文書化した情報を保持しなければならない。
a) 不適合が記載されている。
b) とった処置が記載されている。
c) 取得した特別採用が記載されている。
d) 不適合に関する処置について決定する権限をもつ者を特定している。
シンプルにまとめます。
8.7.1 組織は,不適合の性質と与える影響について,適切な処置をとる。これは,製品の引渡し後も含む。
a) 修正
b) 製品及びサービスの分離,散逸防止,返却又は提供停止
c) 顧客への通知
d) 特別採用による受入の正式な許可の取得
8.7.2 組織は,文書化した情報を保持する。
a) 不適合を記載。
b) とった処置を記載。
c) 取得した特別採用を記載。
d) 不適合処置を決定する権限者を特定。
②不適合発生前提で考えておくこと
リスク前提で進めるのが現状
不適合やトラブルは発生させたくはありませんよね。業務は気持ちよく終わりたいし、トラブル処置のための追加業務はダルイです。
でも、
他人ができないからあなたが業務しているので、
他人ができないリスクはあなたを常に狙っています!
リスクは、組織力、経験、関係者との協力で極力減らせますが、0にはなりません。
リスクに対して、対価が支払われているともいいます。
不適合発生しても仕方がないと割り切ること
トラブルは発生したら、パニックになるし、怒られるし、自分を責めようとなります。
真面目で一生懸命な人ほどそうです。
ですが、
他人ができないからあなたが業務しているので、
他人ができないリスクはあなたを常に狙っています!
組織を頼りながら対処しよう
と割り切ってください。
トラブルは、
組織で対処します。割り切ってください。
③不適合に対する迅速な対応ができる組織力
トラブルは組織で対処します。なぜなら、誰もトラブル対応したくないから。他人の業務を手助けする程度の気持ちとして淡々と冷静に判断するマインドが必要です。
そうなると、日ごろの組織力がどれほど高いかどうかが問われます。
現場担当者からの組織内への素早い報告
日頃の信頼関係が必要
担当者と組織管理者との日頃の信頼関係が必要になります。
と怒らず
「早急の連絡ありがとう!」
と管理者は必ず褒めてあげてください。
トラブル発生時に、「やばい!怒られる!」として隠すのが最悪です。上司に報告できるような関係が日常必要です。
5W1Hを明確に報告
落ち着いて、わかった状況を隠さずに5W1Hを組織に報告しましょう。
管理職間の連携、応急処置
管理職間の連携
管理職間の連携が必須です。大きな組織の場合、情報共有できる電子システムがあるでしょう。その電子システムに入力すると、全社内の関係者に同時発信して情報をさらに共有できるでしょう。
上司は、トラブル経験を経て出世しているわけですから、落ち着いて対処できるでしょうし、現場の担当者をなだめつつ解決方法を提案してあげてください。
応急処置
現場のトラブルに中で、応急処置ができるなら、担当者に指示します。図面や、対処できる他の担当者への現場派遣などの対応が必要になります。
良かれと思った行動が逆効果になり、かえって悪い結果になることもあります。
臨機応変な対応が、逆効果になり、被害拡大や費用増加になることもあります。すぐ片づけたいですが、冷静に対処しましょう。
恒久処置としての是正処置
組織外関係者との調整
●応急処置ができたら、恒久処置・再発防止、未然防止などの策を組織内や顧客・関係者と協議して詰めていきます。
被害の程度によっては、製品及びサービスのリリースの一旦禁止になる場合もあり、組織長が顧客へ説明し、リリース禁止の許可をもらう手続きも必要な場合もあります。
組織内での是正処置
●組織内で実施することは、次の4つです。
- 不適合理由の真因分析
- 是正処置(恒久対策)による再発防止、未然防止
- 他組織内への情報展開
不適合理由の真因分析
原因の調査です。よく使う分析方法を2つ紹介します。
- 現在から過去に戻って原因分析(なぜなぜ分析など)
- 過去から現在に進むときにハマった罠を分析(失敗学など)
●なぜなぜ分析などでは、
さらに深堀して真因追究するなかで、何が不足だったか?、何ができなかったか?を抽出します。顧客や組織内上層部などの相手に説明する(なだめる)ために、●●ができなかったと反省の念をこめるのがポイントです。
●一方、失敗学などでは、
担当者が、正しいと思った行動が、実はミスだったという罠にどうはまったか?を再現するもので、担当者が自分事として理解するのに適しています。
●前者の「なぜなぜ分析」が有名ですが、よくある分析結果は、○○が不足なため網羅的に調べて準備しておく必要があるのような、「全部やります!」と書く文書が多く見えられます。
担当者はできないし、担当者は何をすればよいかわからない。
森を見て木を見ず状態になります。
●後者の「失敗学」は有名ではありませんが、間違うのは仕方がない、正しいと思ったと一旦正当化すると、担当者がミスした経緯がはっきり見えます。ただし、顧客や組織内上層部などの相手に説明すると炎上するので、担当者向けの分析とした方がよいです。
是正処置(恒久対策)による再発防止、未然防止
ポイントは、
今後は気合入れてミスしませんは確率論なので、不適合が再発します。そうしないように、チェック機構、文書などの明確化、承認フローへの追加で、人や機械でもいいので、ミスしないためのチェックを設ける事が重要です。
他組織内への情報展開
不適合は恥ずかしいと思わず、組織内の在り方を見直すチャンスでもあります。
他の部門や組織でも同じ不適合に合わないためにも、情報展開しておきましょう。
不適合で1,000万円損失しても、各組織への情報展開によって未然に1億円の損失を防ぐことができれば、これは立派な投資でもあります。ピンチをチャンスに変えることが品質管理で重要です。
④特別採用(トクサイ)の拡大解釈に注意
顧客要求より厳しい社内規定
不適合、トラブル回避のために顧客要求レベルより高いレベルを達成するように社内で規定します。
しかし、超短納期やコストカット要求が厳しいなどで、社内規定レベルに届かない場合、例外的に特別採用として顧客要求レベルでも社内合格とする場合があります。
もちろん、顧客、自組織内の了承を得る事が前提です。
品質不正の温床に注意
しかし、トクサイが常態化したり、自組織の品質に過信して、顧客が困ってないなら少々社内規定以下でも大丈夫と勝手に判断すると、品質不正の温床につながります。
トクサイの扱いは注意しましょう。人間は楽になる方へ進みたいからです。

図のように、最初は、顧客要求レベルより上になる社内規定レベルですが、トクサイに甘んじると徐々に社内の品質やモラルが低下します。一方、顧客要求レベルは時間が経つにつれて高まる方向になります。
顧客要求レベルと社内品質レベルが同じになると、不適合や品質トラブルが一気にあふれ出し、隠しきれなくなります。
よく、経営陣が記者会見で謝罪するシーンになってしまうので、注意しましょう。
社内の品質向上に必要な投資を実施すべき
以上、不適合なアウトプットの管理について注意すべきポイントを解説しました。
まとめ
ISO9001 2015 8.7 不適合なアウトプットの管理 をわかりやすく解説しました。
- ①要求事項の簡略化
- ②不適合発生前提で考えておくこと
- ③不適合に対する迅速な対応ができる組織力
- ④特別採用(トクサイ)の拡大解釈に注意