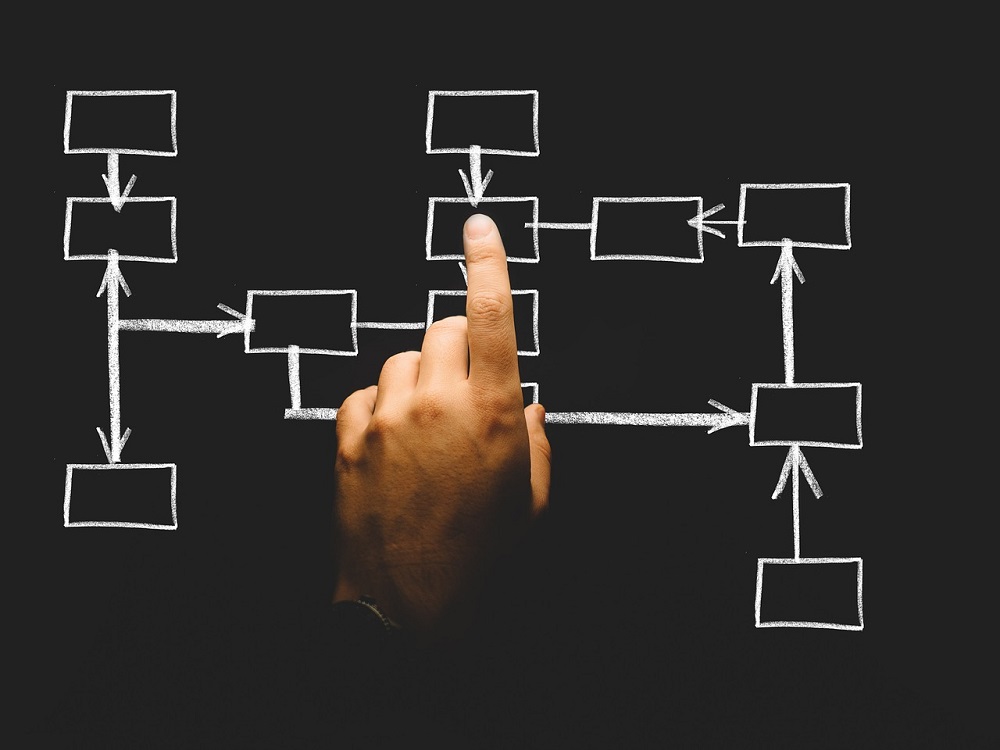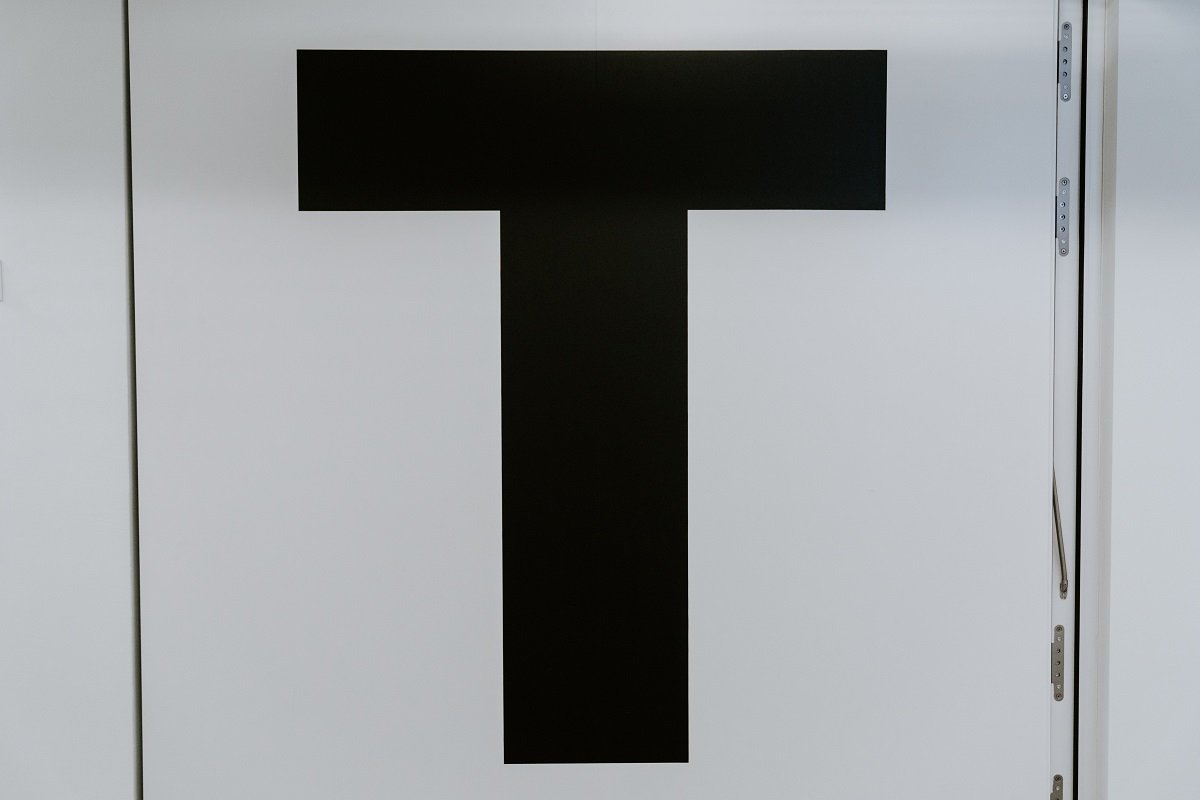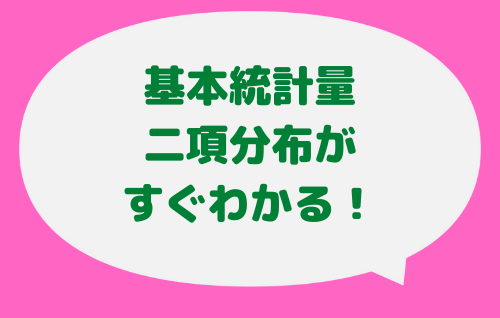★ 本記事のテーマ
確率変数の期待値と分散が計算できる【初心者向け】
確率分布、確率密度関数、期待値、分散のアレルギーをなくし、統計学に自信をつけましょう!
➀確率密度関数から確率・期待値・標準偏差が計算できる
②コイン・サイコロの期待値が解ければOK
③期待値の計算式を一般化する過程に慣れる
④期待値E[X]と分散V[X]の関係式がわかればOK
⑤確率変数の期待値と分散が解ける演習問題1
⑥確率変数の期待値と分散が解ける演習問題2
⑦確率変数の期待値と分散が解ける演習問題3
⑧確率変数の期待値と分散が解ける演習問題4
①②③を最初に学び
➀確率密度関数から確率・期待値・標準偏差が計算できる
確率密度関数とは
分布に関係なく、確率密度関数があります。その特徴は何でもよいですが、
区間全域の積分値が1
確率密度関数の例
何でもいいので、確率密度関数という難しい言葉へのアレルギーを回避しましょう。
\(f(x)=\frac{1}{2500}(-(x-50)^2+2500)\)
グラフを描いてみましょう。分布関数の感じが出て、その関数の全区間の積分値が1となっています。
これが確率密度関数です。
確率・期待値・分散を計算
●確率は、∫f(x)dx です。2 ]=∫x2 f(x)dx です。2 – E[X2 ]です。
公式に慣れるよう、記事を進めます。
●You tube動画もあります。ご確認ください。
VIDEO
●You tube動画ご覧ください。
VIDEO
②コイン・サイコロの期待値が解ければOK
いきなり、
E[X]=\(\int x_ip_i dx\) E[aX+b]=aE[X]+b V[X]=E[\(X^2\)]-E\([X]^2\)
がすぐわかる例題を紹介します。
【問】等確率なサイコロ(1から6の目)が1個ある。
期待値の計算方法は、確率×出る目の合計ですよね。
目
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
確率
\(\frac{1}{12}\)
\(\frac{1}{12}\)
\(\frac{1}{12}\)
\(\frac{1}{12}\)
\(\frac{1}{12}\)
\(\frac{1}{12}\)
\(\frac{1}{12}\)
\(\frac{1}{12}\)
\(\frac{1}{12}\)
\(\frac{1}{12}\)
\(\frac{1}{12}\)
期待値E=\(\frac{2×1+3×2+・・・+12×1}{12}\)
③期待値の計算式を一般化する過程に慣れる
期待値の計算方法を一般化する
統計の難解な数式に早く慣れる方法を提案します。数学の得意・不得意関係なく、数式の意味を読み取るには結構時間がかかります。よく使う方法が2つあります。
★ 難しい数式の読み方
●式を言葉で読んでみて意味を理解する
先の、サイコロ1との出る目の期待値の計算は。
出る目を\(x_i\)、出る目\(x_i\)の確率を\(p_i\)、和をΣで書き直します。
E=\(\sum_{i=1}^{n} x_i p_i\)
ここで確率\(p_i\)を確率密度関数f(x)に変えて定義することもあります。その場合、2つ定義を変えます。
●確率\(p_i\)を確率密度関数f(x)に変える
期待値Eは
期待値の加法性を理解する
★ 期待値の加法性
a,bは定数、X,Yは変数とする。
加法性に慣れるポイントについて、期待値の基本はサイコロの出た目の計算 ですね。
➀等確率で出るサイコロA(1から6)を1個1回振り、その出た目を3倍にする。
➀は(\(1×\frac{1}{6}\)+・・・+\(6×\frac{1}{6}\))=\(\frac{21}{6}\)=3.5
②は(\(1×\frac{1}{4}\)+・・・+\(4×\frac{1}{4}\))=\(\frac{10}{4}\)=2.5
さらに5を足すので、期待値は10.5+5+5=21.5です
一方、期待値の加法性を使うと、
期待値の加法性の公式を使ってもよいし、サイコロの出る目の式のまま解いてもよいのです。
★ 期待値の加法性がわかるポイント
3つの式がイメージできること。(サイコロの例で理解しましょう)
期待値E[X]のXにいろいろ値を入れて慣れる
期待値の加法性に少し慣れたら、次の計算をしてみましょう。
➀E[3X+2]
➀は加法性で出たE[aX+bY+c]=aE[X]+bE[Y]+cを使えばよいです。でも、E[\(X^2\)]はどうしましょうか? 抵抗感がありますが、次の例題で解決します!
等確率で出るサイコロ(X=1から6)の期待値を求めよ。
➀は(\(1×\frac{1}{6}\)+・・・+\(6×\frac{1}{6}\))=\(\frac{21}{6}\)=3.5ですね。機械的にそのまま2乗を式に入れます 。
E[\(X^2\)]=(\(1^2×\frac{1}{6}\)+・・・+\(6^2)×\frac{1}{6}\)
\(x^2\)の期待値とはどういう意味か?が気になりますが、あまり気にしないで代入してください 。
ですから、E[\(X^3\)]を求めようとすると、
出る目Xを変数にして、いろいろな変数を代入することに慣れてください。 ここが分散の導出に必要です。期待値Eはサイコロの出る目の計算であることは変わりませんが、E[X]に変数Xをいろいろ代入するように慣れていきましょう。
④期待値E[X]と分散V[X]の関係式がわかればOK
分散の定義を理解する
★ 分散の定義
V[X]=E[\((X-E[X])^2\)]=E[\(X^2\)]-\(E[X]^2\)
上の式が理解するための3つのポイントを解説します。
★ 分散の定義で理解したポイント
(A)E\([(X-E[X])^2]\)の意味?
★ (A)E\((X-E[X])^2\)の意味
分散の定義は、各データと平均との差を2乗した和を個数で割る値 ですね。式で書くと、
ここで、
(あ)(い)は文字を変えるだけで理解しやすいです。(う)は理解しづらいので解説します。
個数nで割るは、全体を平均値とすると同じですね。なので、全体に期待値E[]をつけることになります。
★ (B)\(E[X^2]-E[X]^2\)になる理由
次で解説します。
分散の式を展開してE[X]に慣れる
E[X]に慣れるために、教科書やwebサイトのように途中経過を省かずに計算します。
V[X]
各項をばらばらにしました。
さらに、定数μ=E[X]に戻します。ここの変形が強引ですけど。
分散の導出過程をよく見て、期待値E[X]、E[\(X^2\)]アレルギーを無くしていきましょう。ここがクリアーすれば、回帰分析、分散分析、検定などの理解が早くなります。
では、いくつか演習問題を解いて、公式に慣れましょう。
ある点の確率をプロットしたのが確率分布関数で
という感覚でOKです。
⑤確率変数の期待値と分散が解ける演習問題1
問題
【問1】
回答
【解】大学入試で出題された問題です。実際に書き出して、期待値と分散を計算します。
上表をもとに、数列を使って期待値、分散を計算します。
●期待値E(X)は
●分散V(X)は
数列を使った1問でした。
⑥確率変数の期待値と分散が解ける演習問題2
問題
【問2】
回答
サイコロの問題は超有名なので、是非解きましょう。
1つ目のサイコロの目と2つ目のサイコロの目の出方はそれぞれ独立とします。2 )=\(\frac{1}{6}(1^2+2^2+3^2+4^2+5^2+6^2)\)=\(\frac{91}{6}\)
期待値E(X2 )の計算も慣れましょう。
(1)2 )=E(X2 )+2E(X)E(Y)+E(Y2 )2 )- E(X+Y) 2
(2)2 )=E(X2 )・E(Y2 )= \(\frac{91}{6}\)・\(\frac{91}{6}\)= \(\frac{8281}{36}\)2 )- E(XY) 2 =\(\frac{8281}{36}\)-\(\frac{2401}{16}\)=\(\frac{11515}{144}\)
機械的に計算しながら、公式や数列の計算に慣れていきましょう。
⑦確率変数の期待値と分散が解ける演習問題3
問題
【問3】
回答
【問3】、【問4】は積分の演習問題です。
高校数学ですね。簡単な式で期待値、分散の積分計算に慣れていきましょう。
(1) \( \displaystyle \int_{-3}^{3} f(x)dx \)=\( \displaystyle \int_{-3}^{3} \frac{1}{36}(-x^2+9)dx \)全区間の積分、つまり、全確率は合計1です。そりゃ、そうですよね!
(2)
●E[X2 ]= \( \displaystyle \int_{-3}^{3} x^2f(x)dx \)=\( \displaystyle \int_{-3}^{3} \frac{1}{36}x^2(-x^2+9)dx \)2 ]―E[X] 2 =\(\frac{9}{5}\)
積分慣れていきましょう。2 ]= \( \displaystyle \int_{a}^{b} x^2 f(x)dx \)
⑧確率変数の期待値と分散が解ける演習問題4
問題
【問4】
回答
(1)は離散系なので数列∑、(2)は連続系なので積分を使います。同じ問題ですが、連続系と離散系で計算結果が若干変わる点が面白いので、解いてみましょう!
(1)
(2)2 )-E(X) 2 =\( \displaystyle \int_{0}^{n} x^2 f(x)dx \)-\((\frac{n}{2})^2\)=\(\frac{n^2}{12}\)
表にすると、離散系と連続系で結果が若干かわります。
–
離散系
連続系
期待値E
\(\frac{1}{2}(n+1)\) \(\frac{1}{2}n\)
分散V
\(\frac{1}{12}(n+1)(n-1)\) \(\frac{n^2}{12}\)
以上、数列・積分を使って、確率・期待値・分散が計算できることを確認しました。
まとめ
「確率変数の期待値と分散が計算できる【初心者向け】」を解説しました。
➀確率密度関数から確率・期待値・標準偏差が計算できる
②コイン・サイコロの期待値が解ければOK
③期待値の計算式を一般化する過程に慣れる
④期待値E[X]と分散V[X]の関係式がわかればOK
⑤確率変数の期待値と分散が解ける演習問題1
⑥確率変数の期待値と分散が解ける演習問題2
⑦確率変数の期待値と分散が解ける演習問題3
⑧確率変数の期待値と分散が解ける演習問題4