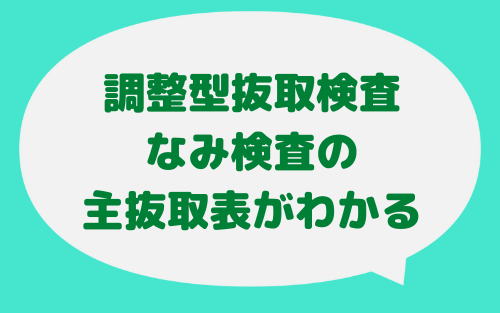「調整型抜取検査がわからない」、「調整型抜取検査の資料や本が少なく勉強できない」など困っていませんか?
こういう疑問に答えます。
本記事のテーマ
- ①調整型抜取検査もOC曲線描けばすべてわかる
- ②なみ検査、ゆるい検査、きつい検査の基準がわかる
- ③なみ検査、ゆるい検査、きつい検査の主抜取表の作り方がわかる
- ④調整型抜取検査は自分で考えて設計できる
本物の「抜取検査」問題集を販売します!
 |
今回、【QC検定®合格】「抜取検査」問題集を販売します! 内容は、①二項分布・ポアソン分布、OC曲線、➁多回抜取検査、➂選別型抜取検査、➃計量抜取検査、⑤逐次抜取検査、⑥調整型抜取検査、⑦抜取検査まとめ の7章全47題を演習できる問題集です。しっかり勉強しましょう。 |
①検査基準と検査水準を決めて
②抜取回数と合格判定数をJIS規格表から求めたらOK!
ですが、
調整型抜取検査の理論は説明できますか?
抜取検査の理論が説明できることが重要です。
なぜなら、品質を決める検査は、必ず顧客から説明責任が求められます。
なので、QCプラネッツでは、JISでも教科書にも書いていない、抜取検査の理論をしっかり解説します。
調整型抜取検査についての関連記事を紹介します。併せて読んでください。個別に内容紹介をしていきます。
●調整型抜取検査(1回方式)の主抜取表の作り方がわかる
●調整型抜取検査のなみ検査の主抜取表がわかる
●なみ検査、ゆるい検査、きつい検査の主抜取表(一回抜取方式)の作り方がわかる
●なみ検査、ゆるい検査、きつい検査の主抜取表(二回抜取方式)の作り方がわかる
●調整型抜取検査の本質がわかる
●検査のきびしさの切替え方法はJISに頼るな!(調整型抜取検査)
●調整型抜取検査の検査水準がわかる
①調整型抜取検査もOC曲線描けばすべてわかる
OC曲線は抜取検査の根幹です。
すべての抜取検査は、OC曲線で設計できます。
●計数抜取検査、
●計量抜取検査、
●選別型抜取検査、
●逐次抜取検査、
●調整型抜取検査
すべて共通です。
必ず1つの考えたや式で
すべてのパターンが理解できるように、
まとめることが重要です。
●実験計画法なら、データの構造式ですべてわかること
●抜取検査なら、OC曲線ですべてわかること
が重要です。なぜなら、理解しやすいからです。
OC曲線から調整型抜取検査を考える方法
合格品質水準AQL,サンプル数n,合格判定個数Ac
これに、検査のきびしさ、検査水準が加わるだけです。
OC曲線は抜取検査の母です。

OC曲線から
●第1種の誤りとなる不良率p0=AQL(合格品質水準)
●第2種の誤りとなる不良率p1がわかります。
●また曲線を構成する、サンプル数n,合格判定個数Acもわかります。
②なみ検査、ゆるい検査、きつい検査の基準がわかる
OC曲線から必要なデータが読めたら、検査のきびしさを考えましょう。
最初に、OC曲線から、なみ検査の主抜取表が作れることを関連記事で解説します。
OC曲線(二項分布とポアソン分布)を使って、合格品質水準AQLが0~1000における、合格判定個数Acと合格品質水準AQLの関係を解説しました。主抜取表を作る過程は是非知っておいてください。魔法の表でもなく、あなたも作ることができます。
 |
調整型抜取検査(1回方式)の主抜取表の作り方がわかる 調整型抜取検査の抜取表のAc,Reの値の求め方やAQLが100以上のAc,Reの求め方について説明できますか?本記事では、OC曲線を描きながら調整型抜取検査の重要な値の導出方法を解説します。主抜取表を自分で作れるくらいマスターしたい方は必見です。 |
自分で作ると、主抜取表が身近な存在になります。
調整型抜取検査の主抜取表を見ると、サンプル数nとAQLの値の間隔がある一定の法則であることや、合格判定個数Ac,不合格判定個数Reが主抜取表の対角線上に同じ値となり、きれいにまとまっていることがわかります。これ、なぜそうなるのか?を次の関連記事で解説しています。
 |
調整型抜取検査のなみ検査の主抜取表がわかる 調整型抜取検査の主抜取表にあるAQL,サンプルサイズの値や合格判定数Ac,不合格判定数Reの値の 決まり方は知っていますか?本記事では、主抜取表の値をOC曲線から導出し、自力で主抜取表が 作れることを解説します。調整型抜取検査をマスターしたい方は必見です。 |
以上の2つの関連記事から、なみ検査の場合の主抜取表の作り方が理解できます。
どこにも主抜取表の作り方が書いていないので、研究して調べたら自分でも作れることがわかりました。
③なみ検査、ゆるい検査、きつい検査の主抜取表の作り方がわかる
OC曲線を使って、なみ検査、ゆるい検査、きつい検査の違いの定義を明らかにし、3つの検査共通の合格品質水準AQLが何であるかもはっきりさせました。調整型抜取検査でわからないことはすべてOC曲線が解決してくれます。
 |
なみ検査、ゆるい検査、きつい検査の主抜取表(一回抜取方式)の作り方がわかる 調整型抜取検査のなみ検査、ゆるい検査、きつい検査の違いを説明できますか?本記事ではJISの抜取表に頼らずに、自分で考えて調整型抜取検査を設計できるように解説しました。調整型抜取検査をマスターしたい方は必見です。 |
1回抜取検査だけでは物足りないので、2回抜取検査についても、なみ検査、ゆるい検査、きつい検査の主抜取表をOC曲線から求めた結果を解説しています。手計算ではきびしく、Excelなどの解析ツールが必須です。
 |
なみ検査、ゆるい検査、きつい検査の主抜取表(二回抜取方式)の作り方がわかる 調整型抜取検査のなみ検査、ゆるい検査、きつい検査の違いを説明できますか?本記事ではJISの抜取表に頼らずに、自分で考えて二回抜取方式の調整型抜取検査を設計できるように解説しました。調整型抜取検査をマスターしたい方は必見です。 |
ここまで、来れば、JIS規格が定義する、なみ検査、ゆるい検査、きびしい検査がマスターできます。
しかし、1つ問題があります。
品質に問題があれば、顧客から説明責任が問われる。
「JISどおり検査した」では顧客は納得しない。
JIS規格を参考にしながら
自分で考えて検査して、その結果を説明できることが重要。
検査は、顧客への説明責任を負います。
自分で考えて抜取検査を設計することが重要です。
これについても、関連記事で詳しく解説します。
お勉強だけでは通用しません。
④調整型抜取検査は自分で考えて設計できる
検査の選択する考え方をまとめました。基本はJIS,教科書ですが、あなたが担当する製品やシステム、顧客要求に合わせて抜取検査を実施することが重要です。関連記事で詳しく解説します。
 |
調整型抜取検査の本質がわかる 調整型抜取検査では、AQL、検査水準、検査のきびしさなどを選びますが、 この抜取検査が何をやっているのかが、論理的に説明できますか? 本記事では、調整型抜取検査の理論が説明できる力がつくように解説しています。 調整型抜取検査をマスターしたい方は必見です。 |
検査のきびしさの切替え方法は、JISにあります。しかし、このルールの根拠は数学的に解けませんし、
あなたが担当する製品やシステム、顧客要求によって、切替え方法は変わります。よく吟味すべきであることを関連記事で詳しく解説します。
 |
検査のきびしさの切替え方法はJISに頼るな!(調整型抜取検査) 調整型抜取検査の「なみ検査、ゆるい検査、きつい検査」の切替え基準が説明できますか? 本記事では、JISZ9015にある検査を切り替える方法と実務での注意点について解説します。 調整型抜取検査をマスターしたい方は必見です。 |
検査水準(特別検査水準、通常検査水準)とロットサイズとサンプル数の関係もJISに規定されています。しかし、そのまま使うべきかどうかは、あなたが担当する製品やシステム、顧客要求を考慮するべきです。よく考えて、抜取検査を設計してほしいことを、関連記事で詳しく解説します。
 |
調整型抜取検査の検査水準がわかる 調整型抜取検査の検査水準の使い方は知っているけど、水準の規準は何か説明できますか?本記事では、検査水準の中身を解説し、JIS規格の活用と、自分で抜取検査を設計するポイントを解説します。 調整型抜取検査をマスターしたい方は必見です。 |
その抜取検査の理論が非常にわかりにくい!
わかりにくい理由は抜取検査規格の歴史にあります。
QCプラネッツは自分で研究して、仮説を立てながら、抜取検査の理論をほぼ解明しました。その結果は、すべてOC曲線で抜取検査は設計できることです。
調整型抜取検査の関連記事をぜひご覧ください。
まとめ
調整型抜取検査について解説しました。自分で設計できるレベルになっていますよ。
- ①調整型抜取検査もOC曲線描けばすべてわかる
- ②なみ検査、ゆるい検査、きつい検査の基準がわかる
- ③なみ検査、ゆるい検査、きつい検査の主抜取表の作り方がわかる
- ④調整型抜取検査は自分で考えて設計できる
調整型抜取検査の関連記事
●調整型抜取検査(1回方式)の主抜取表の作り方がわかる
●調整型抜取検査のなみ検査の主抜取表がわかる
●なみ検査、ゆるい検査、きつい検査の主抜取表(一回抜取方式)の作り方がわかる
●なみ検査、ゆるい検査、きつい検査の主抜取表(二回抜取方式)の作り方がわかる
●調整型抜取検査の本質がわかる
●検査のきびしさの切替え方法はJISに頼るな!(調整型抜取検査)
●調整型抜取検査の検査水準がわかる
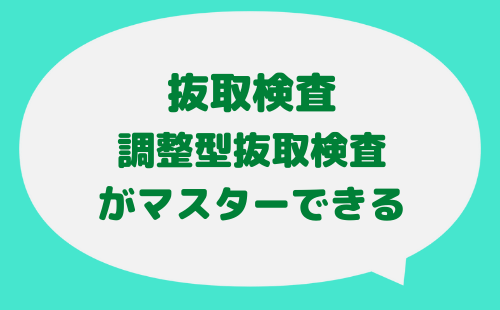
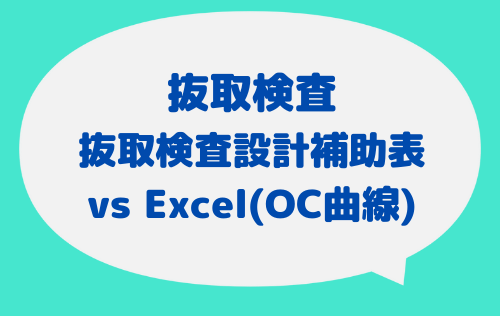
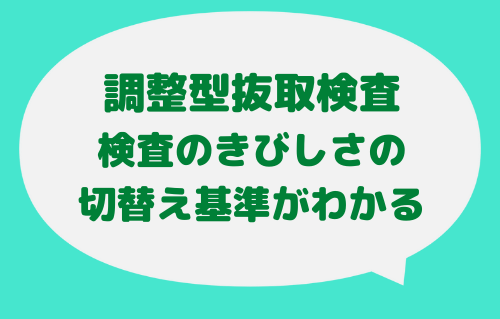


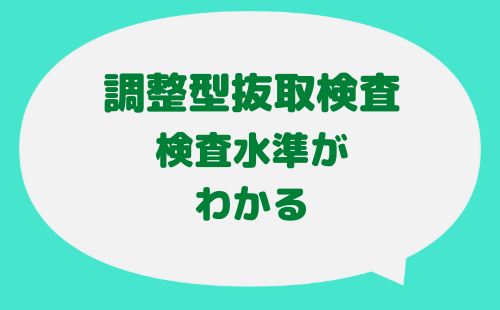




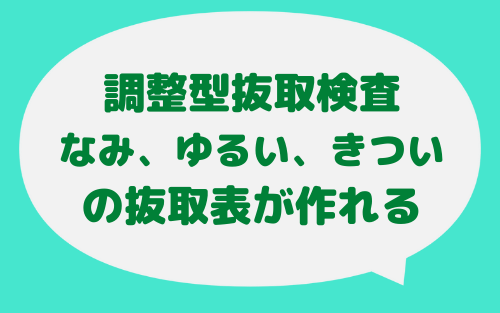



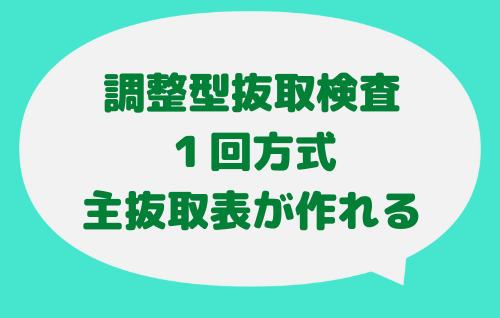




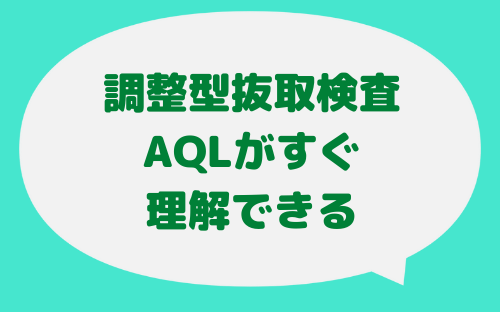



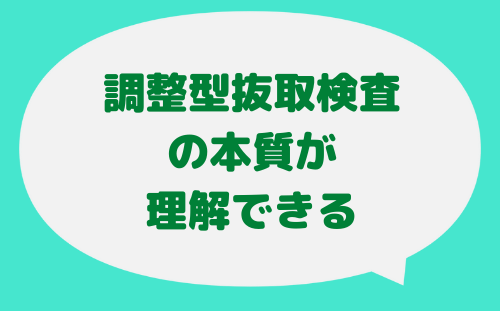
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/21e91abf.1d5906ad.21e91ac0.35595f72/?me_id=1213310&item_id=10835501&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5425%2F54250259.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)