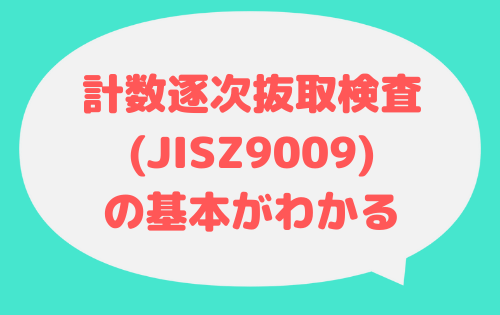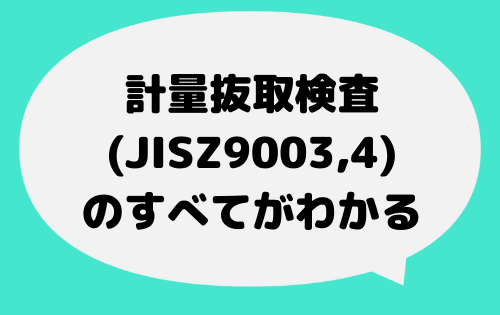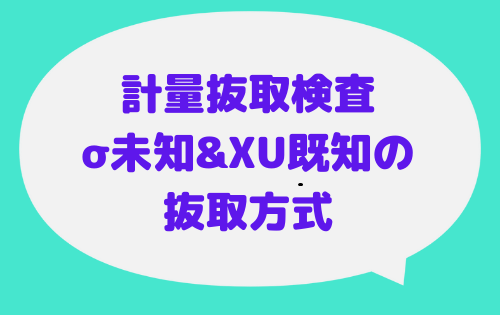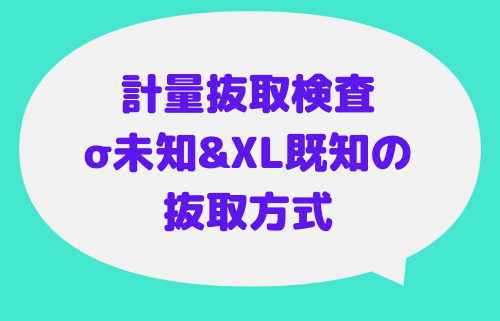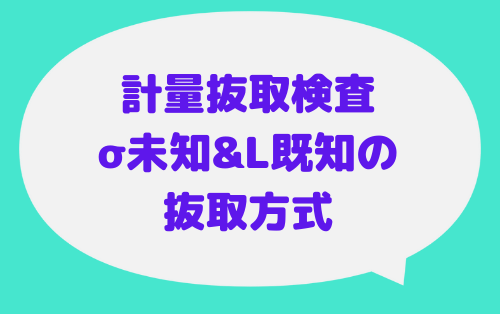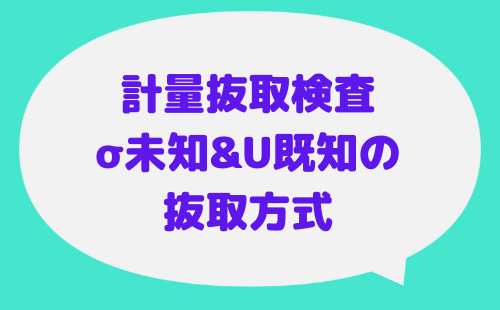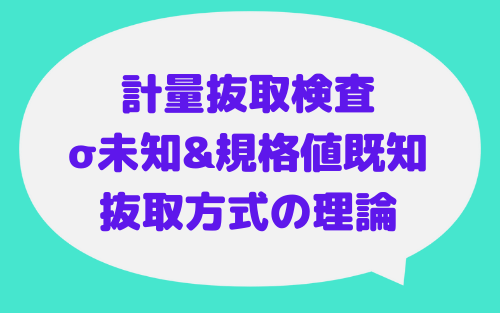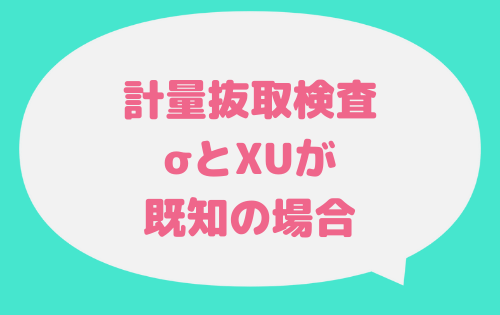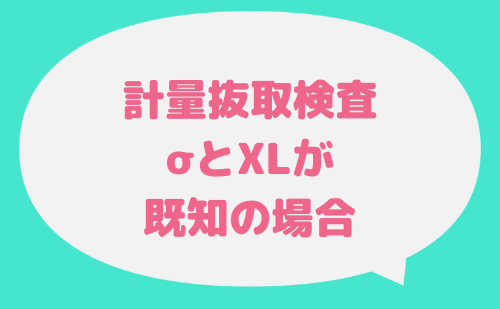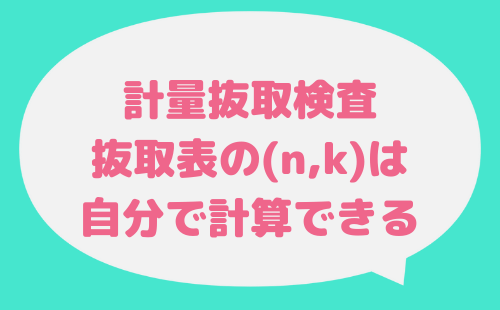「計数逐次抜取検査(JISZ9009)がよくわからない」、「合格判定線や平均検査個数の導出方法がわからない」など困っていませんか?
こういう疑問に答えます。
本記事のテーマ
計数逐次抜取検査(JISZ9009)の理論がわかる(二項分布)
- ①逐次抜取検査とは何かがわかる
- ②合格判定線が必要な理由がわかる
- ③合格判定線の作り方がわかる
- ④平均検査個数の計算方法はあるが、導出方法がわからない
本物の「抜取検査」問題集を販売します!
 |
今回、【QC検定®合格】「抜取検査」問題集を販売します! 内容は、①二項分布・ポアソン分布、OC曲線、➁多回抜取検査、➂選別型抜取検査、➃計量抜取検査、⑤逐次抜取検査、⑥調整型抜取検査、⑦抜取検査まとめ の7章全47題を演習できる問題集です。しっかり勉強しましょう。 |
①逐次抜取検査とは何かがわかる
ある合格基準があり、合格基準を満たせば、検査は合格として終了。
不合格基準を満たせば、検査は不合格として終了。
どちらでも無く決着がつかなければ、検査を続行するものです。
②合格判定線が必要な理由がわかる
合格判定線、不合格判定線を下図に描きます。

青線は、不良個数が検査で増加しても、合格判定領域に入ったため、合格と判断できます。一方、赤線は、不合格領域に入ったため、不合格と判断できます。
合格、不合格の領域線が直線であるため、検査続行、検査終了の判断がしやすいですね。
では、判定線をどのように作るのかを解説します。
③合格判定線の作り方がわかる
OC曲線から関係式を導出
OC曲線を描きます

赤枠はロットの不合格領域で、青枠がロットの合格領域です。
生産者危険を示す不良率p0、消費者危険を示す不良率p1とロット不良率について図から読むと
q0n=1-α、1-q0n=α
q1n=β、1- q1n=1-β
となります。
ここで、q0n, q1nを次のように定義します。
サンプル数nを抜き取り、n個の中にd個の不良品があるとして、
q0n:不良率p0であるときにロットが合格する確率
q1n:不良率p1であるときにロットが合格する確率
とします。
q0nとq1nの式を作ります。
\(q_{0n}\)=\({}_nC_d p_0^d(1-p_0)^{n-d}\)
\(q_{1n}\)=\({}_nC_d p_1^d(1-p_1)^{n-d}\)
注意として、不良品数dに限定します。通常はロットの合格率はΣの和となりますが、今回はΣを入れません(強引な感じがしますけど)
合格判定条件式を導出
合格判定条件式
不良率p0, p1におけるロットの合格率を
\(q_{0n}\)=\({}_nC_d p_0^d(1-p_0)^{n-d}\)
\(q_{1n}\)=\({}_nC_d p_1^d(1-p_1)^{n-d}\)
としました。
次に合格、不合格の判定条件式を作ります。
①合格:\(\frac{q_{1n}}{q_{0n}}\) ≤ \(\frac{β}{1-α}\)
②不合格:\(\frac{1-β}{α}\) ≤ \(\frac{q_{1n}}{q_{0n}}\)
③検査続行:\(\frac{β}{1-α}\) < \(\frac{q_{1n}}{q_{0n}}\) < \(\frac{1-β}{α}\)
(③は①と②の間のイメージです。)
OC曲線の図を見ながら、判定式を確認しましょう。\(\frac{1-β}{α}\)と\(\frac{β}{1-α}\) の意味を理解するのに、時間がかかるかもしれません。

ここで、\(\frac{1-β}{α}\)と\(\frac{β}{1-α}\)の大小関係を確認します。
\(\frac{1-β}{α}\)-\(\frac{β}{1-α}\)
=\(\frac{(1-α)(1-β)-αβ}{α(1-α}\)
=\(\frac{1-(α+β)}{α(1-α}\) > 0
(α=0.05,β=0.10などと小さい値をとるので、1-(α+β) > 0)
よって、
\(\frac{1-β}{α}\) > \(\frac{β}{1-α}\)
合格判定条件式を計算
\(\frac{q_{1n}}{q_{0n}}\)を計算します。
\(\frac{q_{1n}}{q_{0n}}\)=\(\frac{{}_nC_d p_1^d(1-p_1)^{n-d}}{{}_nC_d p_0^d(1-p_0)^{n-d}}\)
=\(\frac{p_1^d(1-p_1)^{n-d}}{p_0^d(1-p_0)^{n-d}}\)
指数が多いので、\(log_{10}\)を取ります。微分しないので、対数はeより10を選択します。
\(log \frac{q_{1n}}{q_{0n}}\)=d\(log \frac{p_1}{p_0}\)+(n-d) \(log \frac{1-p_1}{1-p_0}\)
合格判定式について式を変形します。
①合格:d\(log \frac{p_1}{p_0}\)+(n-d) \(log \frac{1-p_1}{1-p_0}\) ≤ \(log \frac{β}{1-α}\)
②不合格:\(log \frac{1-β}{α}\) ≤ d\(log \frac{p_1}{p_0}\)+(n-d) \(log \frac{1-p_1}{1-p_0}\)
③検査続行:\(log \frac{β}{1-α}\) < d\(log \frac{p_1}{p_0}\)+(n-d) \(log \frac{1-p_1}{1-p_0}\)< \(log\frac{1-β}{α}\)
大変な式に見えますが、大丈夫です。
ここで 以下のように変数を定義して整理します。
\(a\)=\(log \frac{1-β}{α}\)
-\(b\)=\(log \frac{β}{1-α}\)
\(g_1\)=\(log \frac{p_1}{p_0}\)
-\(g_2\)=\(log \frac{1-p_1}{1-p_0}\)
合格判定式について式を変形します。
①合格:d\(g_1\)-(n-d)\(g_2\) ≤ -\(b\)
②不合格:\(a\) ≤ d\(g_1\)-(n-d)\(g_2\)
③検査続行:-\(b\) < d\(g_1\)-(n-d)\(g_2\) < \(a\)
合格判定式についてさらに、式を変形します。
①合格:d ≤ \(\frac{-b}{g_1 + g_2}\)+\(\frac{g_2}{g_1 + g_2} n\)
②不合格:\(\frac{a }{g_1 + g_2}\)+\(\frac{g_2}{g_1 + g_2} n\) ≤ d
③検査続行:\(\frac{-b}{g_1 + g_2}\)+\(\frac{g_2}{g_1 + g_2} n\) < d < \(\frac{a }{g_1 + g_2}\)+\(\frac{g_2}{g_1 + g_2} n\)
さらに、変数を置き換えて見やすく整理します。
\(h_1\)=\(\frac{b}{g_1 + g_2}\)
\(h_2\)=\(\frac{a}{g_1 + g_2}\)
s=\(\frac{g_2}{g_1 + g_2}\)
合格判定式をまとめます。
①合格:d ≤ -\(h_1\)+sn
②不合格: \(h_2\)+sn ≤ d
③検査続行:-\(h_1\)+sn < d < \(h_2\)+sn
直線の領域を表現する式に整理することができました。

合格判定線を作成
かなりの変数を置き換えたので一旦整理します。
| a=\(log\frac{1-β}{α}\) | \(h_1\)=\(\frac{b}{g_1+g_2}\) | 合格判定線 |
| -b=\(log\frac{β}{1-α}\) | \(h_2\)=\(\frac{a}{g_1+g_2}\) | y=-\(h_1\)+sn |
| \(g_1\)=\(log\frac{p_1}{p_0}\) | s=\(\frac{g_2}{g_1+g_2}\) | 不合格判定線 |
| \(g_2\)=\(log\frac{1-p_1}{1-p_0}\) | – | y=\(h_2\)+sn |
具体事例
α=0.01,β=0.05,p0=0.1,p1=0.2の場合の判定線を計算します。
上の表を使って計算すると、
a=1.97,b=1.29,g1=0.30,g2=0.05,h1=3.68,h2=5.61,s=0.145
が導出できます。
結果が下図の通りとなります。

④平均検査個数の計算方法はあるが、導出方法がわからない
JISで規定されている導出方法(でも導出方法がわからない)
\(\bar{n_{p0}}\)=\(\frac{(1-α)h_0-αh_1}{s-p_0}\)
\(\bar{n_{p1}}\)=\(\frac{(1-β)h_1-βh_0}{p_1-s}\)
で与えられる
なぜこの式で導出できるか?はわかりません。
導出方法が書いていないことと、私も式から見て導出方法を考えたのですが、見当もつきません。もしわかっている方がいれば教えてください。
まとめ
計数逐次抜取検査(JISZ9009)で二項分布の合格判断基準について、解説しました。
- ①逐次抜取検査とは何かがわかる
- ②合格判定線が必要な理由がわかる
- ③合格判定線の作り方がわかる
- ④平均検査個数の計算方法はあるが、導出方法がわからない