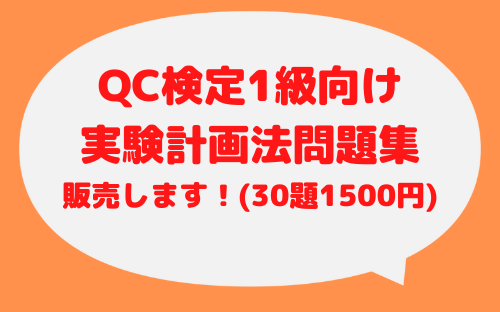★ 本記事のテーマ
- ①管理図と工程管理能力で困っていませんか?
- ➁問題集のメリット
- ➂内容の範囲
- ➃【問題集ご購入方法】
究めた結果、管理図と工程管理能力がわかりましたので、問題集にしました!
①QC検定®と品質管理検定®は、一般財団法人日本規格協会の登録商標です。
➁このコンテンツは、一般財団法人日本規格協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。
➂QCプラネッツは、QC検定®と品質管理検定®の商標使用許可を受けています。
●リンクページ
①管理図と工程管理能力で困っていませんか?
QCプラネッツも相当、管理図を研究しましたが、次の4つが苦労するところと考えています。
- 覚えることが多いからすぐ忘れる
- QC検定®1級になると激ムズになる管理図
- 管理図はちゃんと勉強すると結構難しい
- 工程能力指数は区間推定になると一気に難しくなる!
QC検定®2級レベルは、管理図の種類と管理限界の式、管理図の係数表のJISの見方だけなので簡単ですが、ちゃんとデータを考えて層別して平方和、分散を求めて、管理限界範囲を考えるのは難しいんですよ。それがQC検定®1級の厳しさですが、最初から難しいことを知った上で勉強開始した方がよいでしょうね。
覚えることが多いからすぐ忘れる
次の内容で苦手意識があるかどうかをチェックしましょう!
- 管理限界の公式が多すぎて、すぐ忘れる!
- 問題文からどの管理図を選べばよいかがわからない!
- なんで管理図はたくさん種類があるかがわからない!
- 本質がわからないけど、JISどおりやればいい!でも意味がわからない!
いかがでしょうか? 多くの方が苦手となるポイントばかりですね。
QC検定®1級になると激ムズになる管理図
ここがQC検定®1級で最難関!
QCプラネッツも管理図は試験で壊滅しました。
研究した結果
\(σ_w\)=\(\frac{R}{d_2}\)
の式は数学的にイマイチわからない。
管理図のデータは管理されているから
実データの平方和を分解するところから始めるべき!
という結論で問題を作りました。
教科書の公式代入がいつも正しいとは限らない!
ちゃんと式の意味を吟味しよう!
管理図はちゃんと勉強すると結構難しい
QCプラネッツが研究したオリジナルブログ記事にまとめています。一番詳しく書けたサイトであると自負します。ご確認ください。
 |
【まとめ】簡単だけど難しい管理図を究める 管理図の係数表の値の導出、異常判定ルールの理由、管理図と検定力の関係など、重要な理論を学ぶ必要があります。しかし、JISや教科書にほとんど書いていません。QCプラネッツでは、管理図の本質に迫る28の記事を紹介します。 |
工程能力指数は区間推定になると一気に難しくなる!
工程能力指数の入門は、
範囲を6σで割るだけで簡単!
ですが、
しかも、両側規格と片側規格で式が別々。
両側規格はχ2乗分布で手計算で導出できるが、
片側規格はムリ
工程能力指数は区間推定の導出や、応用問題も必要ですね!
以上、一見簡単そうだけど
激ムズな管理図と工程能力指数を
さっと解けるようになっておきたいですよね!
そこで、今回「管理図と工程能力指数」の問題集を作成しました。
➁問題集のメリット
本問題集を学ぶメリット
- 確率分布から管理図の種類や管理限界の式が導出できる!
- JISに頼らず、考えて解くことができる!
- データの層別の仕方や、層別による平方和・分散の分解に強くなれる!
- 管理図に強くなれる!
- QC検定®1級に勝てる!
- 工程能力指数の意味や、関連公式の導出ができる!
- 管理図と、実験計画法、検定と推定などの管理図以外の単元を組み合わせた応用問題も解ける!
逆にデメリットは
- 勉強しないと習得できない
⇒それはしゃーない!ですよね(笑)
是非、ご購入いただきたいです。
次に、全問題の内容を紹介します!
➂内容の範囲
QCの「管理図と工程能力指数」問題集の全問題を紹介!
33題の問題内容と単元を紹介します!
どこが苦手かをチェックしながら各問を見ましょう。
★ 第1章 管理図の種類(1題)
管理図の種類を答える問題で、ランダムに出題されます。ランダムに出題される問題を何度も解いて試験に臨みましょう。36問用意しました。
★第2章 管理限界、管理図係数表の導出(6題)
計量値、計数値すべての管理図の管理限界、係数表の公式、値を導出します。公式は暗記せず理解して解けるようになる大事な6題です。
★第3章 群間変動と群内変動(13題)
QC検定®1級向けの応用問題、理解しにくい分散公式を使った問題ですが、実データから平方和、平方和の分解から分散を解く問題も作りました。実験計画法・分散分析の練習にもなります。
★第4章 工程能力指数の区間推定(6題)
χ2乗分布の式変形をベースに、区間推定の式を導出します。その式を使って演習します。
★第5章 管理図の応用問題(7題)
管理図の応用問題として、差を比較する応用問題を使って、管理図と、検定と推定の組み合わせ問題を解きます。管理図以外の単元と組み合わせた応用問題も練習しましょう。
| 章 | 第 | 問題 |
| 1 | 1 | 管理図の種類 |
| 2 | 2 | 管理限界、管理図係数表の導出1 (Xbar管理図) |
| 2 | 3 | 計量値の検定統計量の導出2 (計数値管理図) |
| 2 | 4 | 計量値の検定統計量の導出3 (s管理図) |
| 2 | 5 | 計量値の検定統計量の導出4 (R管理図) |
| 2 | 6 | 計量値の検定統計量の導出5 (管理図係数表) |
| 2 | 7 | 計量値の検定統計量の導出6 |
| 3 | 8 | 群間変動と群内変動1 (分散公式vs平方和の分解) |
| 3 | 9 | 群間変動と群内変動2 (分散公式vs平方和の分解) |
| 3 | 10 | 群間変動と群内変動3 (分散公式vs平方和の分解) |
| 3 | 11 | 群間変動と群内変動4 (検出力) |
| 3 | 12 | 群間変動と群内変動5 (σb,σwが0の場合) |
| 3 | 13 | 群間変動と群内変動6 (σ=R/d2で推定する理由) |
| 3 | 14 | 群間変動と群内変動7 (分散の公式) |
| 3 | 15 | 群間変動と群内変動8 (分散公式vs平方和の分解) |
| 3 | 16 | 群間変動と群内変動9 (分散公式vs平方和の分解) |
| 3 | 17 | 群間変動と群内変動10 (層別) |
| 3 | 18 | 群間変動と群内変動11 (分散の公式) |
| 3 | 19 | 群間変動と群内変動12 (分散の公式) |
| 3 | 20 | 群間変動と群内変動13 (分散公式vs平方和の分解) |
| 3 | 21 | 工程能力指数の区間推定1 (両側規格) |
| 3 | 22 | 工程能力指数の区間推定2 |
| 3 | 23 | 工程能力指数の区間推定3 |
| 4 | 24 | 工程能力指数の区間推定4 (片側規格) |
| 4 | 25 | 工程能力指数の区間推定5 |
| 4 | 26 | 工程能力指数の区間推定6 |
| 5 | 27 | 管理図の応用問題1 (X-Rs管理図) |
| 5 | 28 | 管理図の応用問題2 (u管理図) |
| 5 | 29 | 管理図の応用問題3 (計量値差の検定) |
| 5 | 30 | 管理図の応用問題4 |
| 5 | 31 | 管理図の応用問題5 (不良率差の検定) |
| 5 | 32 | 管理図の応用問題6 (計数値差の検定) |
| 5 | 33 | 管理図の応用問題7 (管理図合成する場合) |
5つの章に分けてしっかり解いていきましょう。
解説も充実!
丁寧な解説ページやQCプラネッツのブログ記事を活用してわかりやすく解けますので、ご安心ください。
- 管理図と工程能力指数の全パターンを網羅した問題集であること
- 暗記しがちな管理限界、係数などの公式が自力で導出できること
- QC検定®2級レベル、QC検定®1級レベルになること
- どんなパターンが出ても、どのパターンかを冷静かつ瞬時に見極める力がつくこと
- 確率分布、検定と推定、実験計画法の応用にもつなげられること
是非、ご購入ください。
➃【問題集ご購入方法】
「QCプラネッツ」で検索ください。
(1)本ブログからのご購入
ご購入いただけます。ご購入後、QCプラネッツからアクセスサイト先(アクセスのみ可)をご案内いたします。データの拡散を防ぐため、ダウンロードと印刷は不可とさせていただきます。
(2)メルカリでの販売
「QCプラネッツ」で検索ください。

1500円/1冊
とさせていただきます。ご購入よろしくお願いいたします。
(3)noteでの販売
電子販売もしています。こちらへアクセスください。
 |
【QC検定®1級,2級合格!】QCに必要な「管理図と工程能力指数」問題集を発売します! 「管理図と工程能力指数」をマスターするための重要な問題集のご紹介です。 |
まとめ
「【QC検定®合格】「管理図と工程能力指数」問題集を販売します」、ご購入よろしくお願いいたします。
- ①管理図と工程能力指数で困っていませんか?
- ➁問題集のメリット
- ➂内容の範囲
- ➃【問題集ご購入方法】

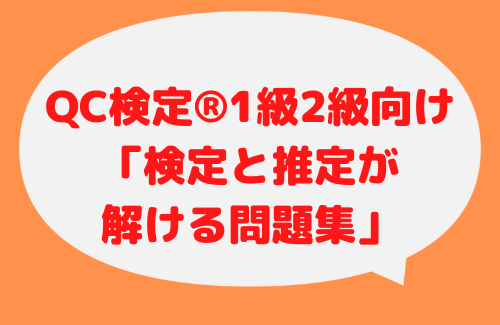



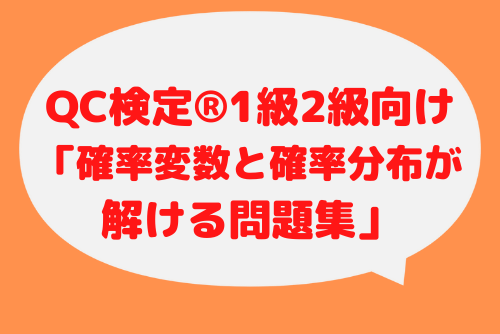






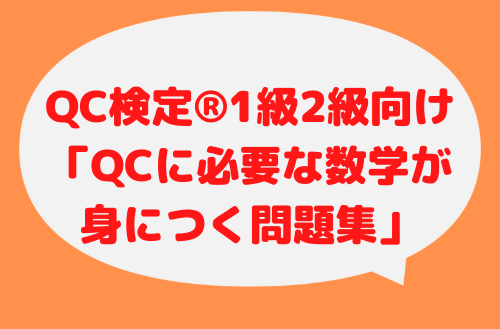



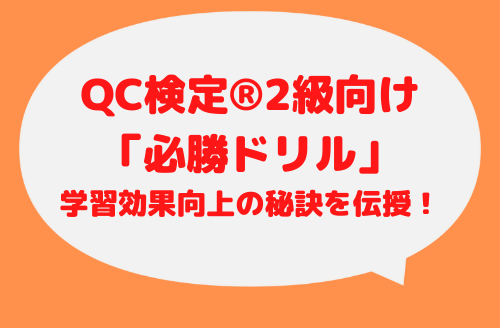



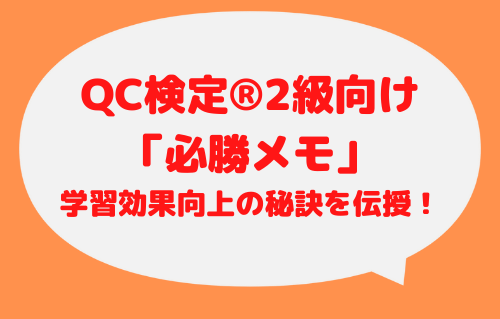

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2b635459.af87eb07.2b63545a.ad12770a/?me_id=1220950&item_id=13252497&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fneowing-r%2Fcabinet%2Fitem_img_981%2Fneobk-1897511.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/221455fc.32ff3bc1.221455fd.d54b9521/?me_id=1276609&item_id=12907212&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbooxstore%2Fcabinet%2F01104%2Fbk4542505227.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/21e91abf.1d5906ad.21e91ac0.35595f72/?me_id=1213310&item_id=17703067&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3946%2F9784542503946.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)