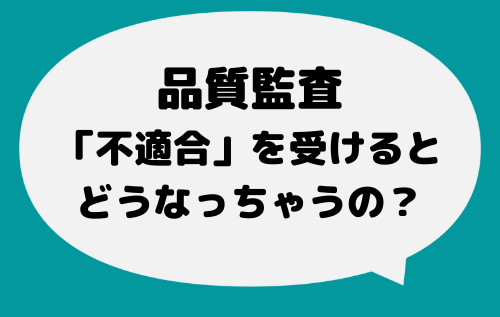品質監査で不適合を受けるとどうなるか?がわかる

「品質監査で不適合になってしまったらどうしたらいいの?」、「どんな条件で不適合を受けるのかがわからない」と困っていませんか?
こういう疑問に答えます。
本記事のテーマ
第一者監査(内部監査)、第二者監査(取引先監査)、第三者監査(外部審査)共通のテーマです。
どうなっちゃうの?
- ①何をすれば不適合になるのか?
- ②監査で不適合になるのか?
- ③不適合を受けた後の処置方法/li>
ISO9001 2015 内部監査員育成問題集をを販売します!
 |
ISO9001 2015 内部監査員育成する問題集【問題編】を紹介します。ISO9001 取得に向けてISO9001 の構築、内部監査・外部審査の実施、監査のフィードバックや、今後のリスクに対する対処方法を考え抜く問題集です。 |
何をすれば不適合になるのか?
不適合とは?
●まず、品質監査における不適合とは何か?の定義を確認しましょう。相手を知らずして恐れても仕方がありません。
不適合とは
要求事項を満たしていないこと。
ここでいう要求事項は具体的には、
(i)製品の要求事項、顧客要求事項
(ii)組織の品質マネジメントシステム要求事項
(iii)法令、標準規格
つまり、
(i)は相手からの要求
(ii)は自分で決めた品質マネジメントシステム通り業務すること
(iii)法令や標準などの第3者からの要求
をそれぞれ満たしていないと、「不適合」になります。
「満たしていない」とは?
監査で、ヌケモレなどの不備を指摘された場合、
か、それとも
「不適合」で一発アウト
となるか?
の基準がわかりません。監査員によって基準が変わると、監査をうける側はいやですね。
実務経験上、次の基準で分かれていると考えています。
●要求事項に対して活動していれば、「不適合」にはならず、「改善の機会」になる。
●「不適合」はそもそも、要求事項に対して全く何もやっていない場合になる。
不適合の具体事例を紹介します。
不適合事例
例えば、
●「顧客の要求事項に対して何をしていますか?」と審査員に質問された場合
「顧客要求事項一覧表があって、その内容を説明した」が、一部ヌケモレがあった場合は、「不適合」にはならず、「改善の機会」になる。
「顧客要求事項って何だ?何かやっているか?」、「担当者が個別にやっています」だと、顧客要求を満たす組織になっていないと判断され、「不適合」になる。
一定のルールで組織が業務遂行していれば、「不適合」にはなりません。安心してください。
長期間、ISO9001やQMS(品質マネジメントシステム) を組織が導入していると、ルール前提で業務遂行できる組織になるので、「不適合」になる場合はほぼありません。
ただし、成熟した組織でも「不適合」になりうる注意すべき点があります。
- ISO9001 2015認証なのに、2015年版にはない2008年版の業務フローが継続
- 自組織のQMSを変更したのに、一部業務が過去のQMSのまま継続
これらのケースも、「そもそも最新版の要求事項をやっていない」とみなされ、「不適合」を受ける場合があります。
不適合に罰則はあるのか?
●ありません。不適合を適合にすればOKです。
(不適合を適合に挽回する方法を後で解説します。)
でも、後味悪いですよね。
「不適合! 何やってんの?」と上から叱られるくらいはあるでしょうけど。
監査で不適合になるのか?
実務経験上、
内部監査はほぼない、
取引先監査はよっぽど相手に圧力をかけたいときだけ
(取引先を変えた方がよいでしょう)
外部審査ではありうる
外部審査は、ISO9001認証にふさわしいか?の審査です。ISO9001の要求事項に沿って業務しているかを確認しましょう。
ISOも7,8年で更新されるので、更新時に古い要求事項のままだと、「不適合」になりやすいので要注意です。
内部監査はほぼない
身内で監査するので、不適合はありません。不適合にする監査側も、監査される側も、事務局ももめるし、後処理が面倒です。
ただし、内部監査は自主的とはいえ、ISO9001の要求事項の1つなので、不適合の選択肢も用意しておく必要があります。
組織内規定で、内部監査を規定する場合、不適合の報告書と是正処置の報告書の様式を作りますが、実際は、形だけです。
実務経験上、内部監査員への説明の際も、「不適合」の話はしません。話しなければ、ほとんどの組織内の内部監査員は「不適合」を知らずに監査します。
ISO認証後すぐの組織は不適合がよくある
不適合になりやすい組織とは、
- ISO認証後すぐの組織
- ISOが更新された直後
前者は、ISO取り立ての場合、まだ、ISOに沿った業務をしていない部門がいくつかある可能性があります。そこを次年度、受審すると、「不適合」を受けやすくなります。ただ、審査側も、ISO取ったばかりという配慮もあります。審査員が助言する場合が多いです。
後者は、ISOが更新された直後は、「更新審査」として外部審査を受けます。実務経験上、ISO9001 2008から2015への更新審査では、審査のほとんどの時間が、審査員から説明時間となってしまいました。
「不適合」になりやすい状態の場合、審査する側もそれなりに配慮してくれます。「そろそろちゃんとできるよね!」という時期に、やるべきことをやっていないと「不適合」になります。
不適合を受けた後の処置方法
慌てることはありません。
- 応急処置と恒久処置をしっかりやる
- 処置は仕組化する
- しばらく経過してから再審査する
の流れです。
応急処置と恒久処置をしっかりやる
まずは、応急処置として、「不適合」箇所を修正しましょう。
仕組や文書が無いことによる「不適合」が多いので、作りましょう。
次に、恒久処置として
●応急処置で作った仕組や文書をルール化する
●ルール化したものを組織内に情報共有する
●他にも「不適合」になりうる業務がないかを確認する
などしましょう。
処置は仕組化する
再発防止や未然防止のため、気合・根性ではなく、仕組化しましょう。
仕組化とは、
●そのチェックがないと、文書ファイルが保存できなくする
●チェックリストを作って、承認の際に必ず確認する
●ルール化して、全員に周知させる
など、実務経験上は、デジタルを使って、ヌケモレがない仕組にした方がベターです。
しばらく経過してから再審査する
すぐ処置しても、再審査して「適合」にはなりません。数カ月くらい経過して処置が定着したと確認できてから再審査となります。
「不適合」はあまり、なりませんが、なると面倒です。けど、それをチャンスととらえましょう。
まとめ
品質監査で不適合を受けるとどうなるか?をわかりやすく解説しました。
- ①何をすれば不適合になるのか?
- ②監査で不適合になるのか?
- ③不適合を受けた後の処置方法/li>
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/qcplanets/qcplanets.com/public_html/wp-content/themes/m_theme/sns.php on line 119