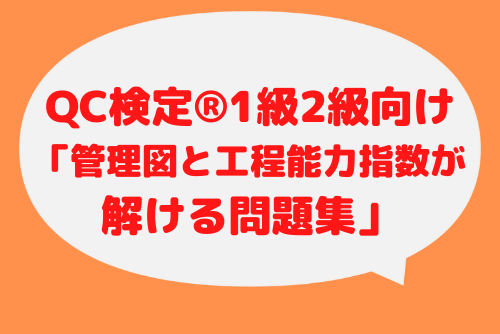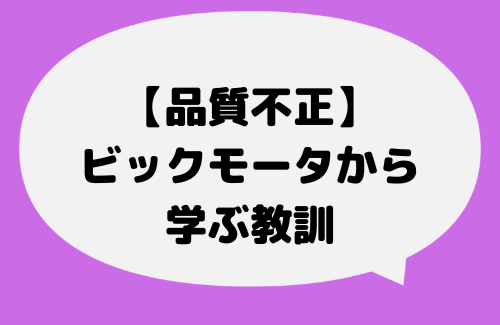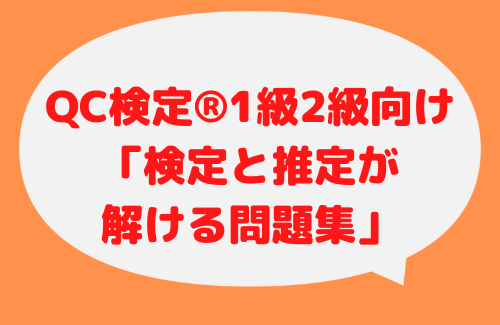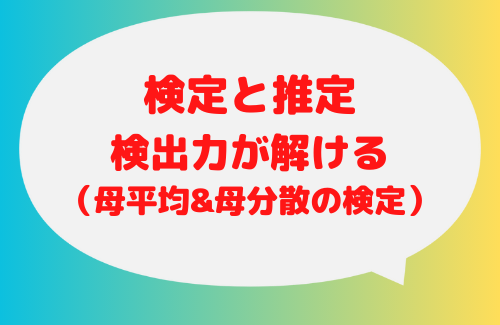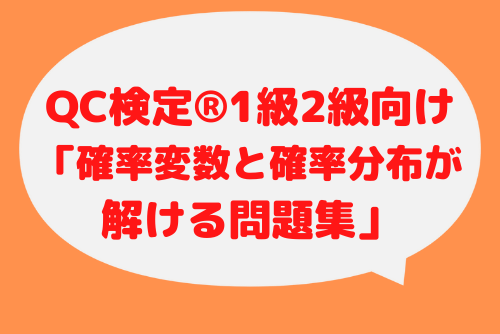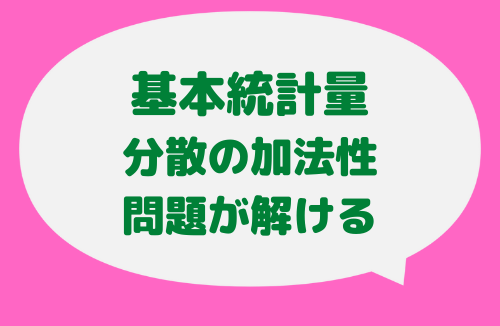★ 本記事のテーマ
【初心者必見!】検定統計量(計数値&計量値)が導出できる
- ①(計数値)計数値の検定統計量のベースとなる式
- ➁(計数値)母不適合品率の検定統計量を導出
- ➂(計数値)母不適合品率差の検定統計量を導出
- ➃(計数値)母不適合品率差の検定統計量の注意点
- ➄(計数値)母不適合数の検定統計量を導出
- ⑥(計数値)母不適合数差の検定統計量を導出
- ⑦(計量値)計量値の検定統計量のベースとなる式
- ⑧(計量値)母平均差の検定統計量を導出1
- ⑨(計量値)母平均差の検定統計量を導出2
- ⑩(計量値)母平均差の検定統計量を導出3
- ⑪(計量値)母平均差の検定統計量を導出4
- ⑫(計量値)母平均差の検定統計量を導出5
★ QCに必要な「検定と推定問題集」を販売します!
QC検定®1級合格したい方、QCに必要な検定と推定をしっかり学びたい方におススメです。
検定統計量は自力で導出しよう!
各ケースでの検定統計量の式の違いも確認しよう!
★【結論】 計数値の検定統計量
| 対象数 |
検定対象 |
統計量分布 |
検定統計量 |
| 1 |
母不適合品率
\(p\) |
二項分布 |
\(u_0\)=\(\frac{p-p_0}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}}\) |
| 2 |
母不適合品率差
\(p_A-p_B\) |
二項分布 |
\(u_0\)=\(\frac{p_A-p_B}{\sqrt{\frac{p_A(1-p_A)}{n_A}+\frac{p_B(1-p_B)}{n_B}}}\) |
| 1 |
母不適合数
λ |
ポアソン分布 |
\(u_0\)=\(\frac{\hat{λ}-λ_0}{\sqrt{\frac{λ_0}{n}}}\) |
| 2 |
母不適合数差
\(λ_A-λ_B\) |
ポアソン分布 |
\(u_0\)=\(\frac{λ_A-λ_B}{\sqrt{\frac{λ_A}{n_A}+\frac{λ_B}{n_B}}}\) |
★【結論】 計量値の検定統計量
| 検定対象 |
母分散 |
統計量分布 |
検定統計量 |
| 母平均μ |
既知\(σ^2\) |
標準正規分布 |
\(u_0\)=\(\frac{\bar{x}-μ_0}{\sqrt{σ^2/n}}\) |
| 未知 |
t分布 |
\(t_0\)=\(\frac{\bar{x}-μ_0}{\sqrt{V/n}}\) |
母平均
μ1とμ2の差 |
既知\(σ^2\) |
標準正規分布 |
\(u_0\)=\(\frac{\bar{x_1}-\bar{x_2}}{\sqrt{\frac{σ_1^2}{n_1}+\frac{σ_2^2}{n_2}}}\) |
| 未知(\(V_1\)=\(V_2\) |
t分布 |
\(t_0\)=\(\frac{\bar{x_1}-\bar{x_2}}{\sqrt{V(\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2})}}\)
(\(V\)=\(\frac{S_1+S_2}{n_1+n_2-2}\)) |
| 未知(\(V_1\)≠\(V_2\) |
t分布 |
\(t_0\)=\(\frac{\bar{x_1}-\bar{x_2}}{\sqrt{\frac{V_1}{n_1}+\frac{V_2}{n_2}}}\) |
対応のある母平均
μ1とμ2の差
δ=μ1―μ2 |
既知\(σ^2\) |
標準正規分布 |
\(u_0\)=\(\frac{\bar{d}}{\sqrt{σ_d^2/n}}\) |
| 未知 |
t分布 |
\(t_0\)=\(\frac{\bar{d}}{\sqrt{V_d/n}}\) |
①(計数値)計数値の検定統計量のベースとなる式
標準正規分布がベース
標準正規分布に従うがベースとします。関連記事にあるように、
二項分布やポアソン分布は正規分布に近づく性質があります。
ベースとなる検定統計量は
\(u_0\)=\(\frac{\bar{x}-μ_0}{σ}\)
です。この式くらいは暗記してもOKです。
ただし、1点注意なのは、サンプル数\(n\)の項は含まれていません。ここだけ注意しましょう。
二項分布の場合
二項分布の期待値と分散はそれぞれ
●E[\(k\)]=\(pn\) (\(k\)=\(pn\))
●V[\(k\)]=\(pn(1-p)\) (\(k\)=\(pn\))
です。この関係式を代入すれば二項分布の検定統計量が導出できます。
ポアソン分布の場合
ポアソン分布の期待値と分散はそれぞれ
●E[\(k\)]=\(λ\)
●V[\(k\)]=\(λ\)
です。この関係式を代入すればポアソン分布の検定統計量が導出できます。
➁(計数値)母不適合品率の検定統計量を導出
前提条件
前提条件は、
- 母不適合品率
- 二項分布に従う(正規分布近似できる)
検定統計量を導出
検定統計量の出発点は、\(u_0\)=\(\frac{\bar{x}-μ_0}{\sqrt{σ}}\)
です。
二項分布の期待値と分散はそれぞれ
●E[\(k\)]=\(pn\) (\(k\)=\(pn\))
●V[\(k\)]=\(pn(1-p)\) (\(k\)=\(pn\))
ただし、1つ注意点があります。
●E[\(k\)]=\(pn\) (\(k\)=\(pn\))
●V[\(k\)]=\(pn(1-p)\)であるが、
必要なのは、
●E[\(p\)]と●V[\(p\)]
なので、\(k=pn\)から\(p=\frac{k}{n}\)と変形して、求めます。
●E[\(p\)]=E[\(\frac{k}{n}\)]=\(\frac{1}{n}\)E[\(k\)]=\(\frac{pn}{n}\)=\(p\)
●V[\(p\)]= V[\(\frac{k}{n}\)]=\(\frac{1}{n^2}\)V[\(k\)]
=\(\frac{pn(1-p)}{n^2}\)=\(\frac{p(1-p)}{n}\)
を使います。
この関係式を代入すれば二項分布の検定統計量が導出できます。
また、二項分布は確率\(p\)を代入するので、
\(u_0\)=\(\frac{\bar{x}-μ_0}{σ/n}\)の\(n\)を入れずに、
\(u_0\)=\(\frac{\bar{x}-μ_0}{σ}\)を使います。
ここがややこしいですが、注意しましょう。
なので、この式を\(u_0\)=\(\frac{\bar{x}-μ_0}{σ}\)に代入します
●\(\bar{x}\)→\(p\)
●\(μ_0\)→\(p_0\)
●\(σ\)→\(\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\)
を代入するので、
\(u_0\)=\(\frac{\bar{x}-μ_0}{σ}\)
=\(\frac{p-p_0}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}}\)
と導出できます。
よって、検定統計量は
●\(u_0\)=\(\frac{p-p_0}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}}\)
となります。
➂(計数値母不適合品率差の検定統計量を導出
前提条件
前提条件は、
- 母不適合品率差
- 二項分布に従う(正規分布近似できる)
検定統計量を導出
検定統計量の出発点は、\(u_0\)=\(\frac{p-p_0}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}}\)
です。
分散は加法性を使って
●V(A-B)=V(A)+V(B)= \(\frac{p_A (1-p_A)}{n_A}\)+\(\frac{p_B (1-p_B)}{n_B}\)
とします。
この関係式を代入すれば二項分布の検定統計量が導出できます。
なので、この式を\(u_0\)=\(\frac{p-p_0}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}}\)に代入します
●\( p \)→\(p_A\)
●\( p_0\)→\(p_B\)
●\(σ\)→\(\sqrt{\frac{p_A(1-p_A)}{n_A}+\frac{p_B(1-p_B)}{n_B}}\)
を代入するので、
\(u_0\)=\(\frac{\bar{x}-μ_0}{σ}\)
=\(\frac{p_A-p_B}{\sqrt{\frac{p_A(1-p_A)}{n_A}+\frac{p_B(1-p_B)}{n_B}}}\)
と導出できます。
よって、検定統計量は
●\(u_0\)=\(\frac{p_A-p_B}{\sqrt{\frac{p_A(1-p_A)}{n_A}+\frac{p_B(1-p_B)}{n_B}}}\)
となります。
二項分布の検定統計量が導出できました!
➃(計数値)母不適合品率差の検定統計量の注意点
実はよく使う公式に、
検定統計量
●\(u_0\)=\(\frac{p_A-p_B}{\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})(\frac{1}{n_A}+\frac{1}{n_B})}}\)
ただし
・\(p_A\)=\(\frac{x_A}{n_A}\)
・\(p_B\)=\(\frac{x_B}{n_B}\)
・\(\bar{p}\)=\(\frac{x_A+x_B}{n_A+n_B}\)
ですが、よく確かめると
●\(u_0\)=\(\frac{p_A-p_B}{\sqrt{\frac{p_A(1-p_A)}{n_A}+\frac{p_B(1-p_B)}{n_B}}}\)
と
●\(u_0\)=\(\frac{p_A-p_B}{\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})(\frac{1}{n_A}+\frac{1}{n_B})}}\)
は一致しません。
よく式を見ると、
●\(u_0\)=\(\frac{p_A-p_B}{\sqrt{\frac{p_A(1-p_A)}{n_A}+\frac{p_B(1-p_B)}{n_B}}}\)
●\(u_0\)=\(\frac{p_A-p_B}{\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})(\frac{1}{n_A}+\frac{1}{n_B})}}\)
が一致させるには、
\(\frac{p_A(1-p_A)}{n_A}\)=\(\bar{p}(1-\bar{p})\)
かつ
\(\frac{p_B(1-p_B)}{n_B}\)=\(\bar{p}(1-\bar{p})\)
が必要ですが、
(左辺)はAまたはBのみ
(右辺)はA,B両方が含まれる値なので、
片方が実はない(0である)条件以外は結果は一致しません。
よく使う検定統計量
●\(u_0\)=\(\frac{p_A-p_B}{\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})(\frac{1}{n_A}+\frac{1}{n_B})}}\)
ですが、自分で正しく導出してきた
●\(u_0\)=\(\frac{p_A-p_B}{\sqrt{\frac{p_A(1-p_A)}{n_A}+\frac{p_B(1-p_B)}{n_B}}}\)
と結果が一致しませんので、注意ください!
●\(u_0\)=\(\frac{p_A-p_B}{\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})(\frac{1}{n_A}+\frac{1}{n_B})}}\)
は試験に出るから丸暗記とならないよう注意が必要です!
➄(計数値)母不適合数の検定統計量を導出
前提条件
前提条件は、
- 母不適合数
- ポアソン分布に従う(正規分布近似できる)
検定統計量を導出
検定統計量の出発点は、\(u_0\)=\(\frac{\bar{x}-μ_0}{\frac{σ}{\sqrt{n}}}\)
です。
ポアソン分布の期待値と分散はそれぞれ
●E[\(λ\)]=\(λ\)
●V[\(λ\)]=\(λ\)です。
二項分布と違って、\(λ\)を直接代入します。
この関係式を代入すればポアソン分布の検定統計量が導出できます。
また、ポアソン分布は\(λ\)=\(np\)を代入し\(n\)を含んでいるので、
\(u_0\)=\(\frac{\bar{x}-μ_0}{\frac{σ}{\sqrt{n}}}\)を使います。
二項分布と違って、ここがややこしいですが、注意しましょう。
なので、この式を\(u_0\)=\(\frac{\bar{x}-μ_0}{\frac{σ}{\sqrt{n}}}\)に代入します
●\(\bar{x}\)→\(λ\)
●\(μ_0\)→\(λ_0\)
●\(σ\)→\(\sqrt{\frac{λ_0}{n}}\)
を代入するので、
\(u_0\)=\(\frac{\bar{x}-μ_0}{σ}\)
=\(\frac{λ-λ_0}{\sqrt{\frac{λ_0}{n}}}\)
と導出できます。
よって、検定統計量は
●\(u_0\)=\(\frac{λ-λ_0}{\sqrt{\frac{λ_0}{n}}}\)
となります。
⑥(計数値)母不適合数差の検定統計量を導出
前提条件
前提条件は、
- 母不適合数差
- ポアソン分布に従う(正規分布近似できる)
検定統計量を導出
検定統計量の出発点は、\(u_0\)=\(\frac{λ-λ_0}{\sqrt{\frac{λ_0}{n}}}\)
です。
分散は加法性を使って
●V(A-B)=V(A)+V(B)= \(\frac{λ_A}{n_A}\)+ \(\frac{λ_B}{n_B}\)
とします。
この関係式を代入すればポアソン分布の検定統計量が導出できます。
なので、この式を\(u_0\)=\(\frac{p-p_0}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}}\)に代入します
●\( p \)→\(p_A\)
●\( p_0\)→\(p_B\)
●\(σ\)→\(\sqrt{\frac{λ_A}{n_A}+\frac{λ_B}{n_B}}\)
を代入するので、
\(u_0\)=\(\frac{\bar{x}-μ_0}{σ}\)
=\(\frac{p_A-p_B}{\sqrt{\frac{λ_A}{n_A}+\frac{λ_B}{n_B}}}\)
と導出できます。
よって、検定統計量は
●\(u_0\)=\(\frac{p_A-p_B}{\sqrt{\frac{λ_A}{n_A}+\frac{λ_B}{n_B}}}\)
となります。
ポアソン分布の検定統計量が導出できました!
以上
①~⑥は計数値について解説しました。
⑦~⑫は計量値について解説します。
⑦(計量値)計量値の検定統計量のベースとなる式
母平均\(μ\)で母分散が既知(\(σ^2\))の場合
標準正規分布に従うので、検定統計量は
\(u_0\)=\(\frac{\bar{x}-μ_0}{\sqrt{σ^2/n}}\)
となります。この式くらいは暗記してもOKです。
母平均\(μ\)で母分散が未知の場合
t分布に従うので、検定統計量は
\(t_0\)=\(\frac{\bar{x}-μ_0}{\sqrt{V/n}}\)
となります。この式くらいは暗記してもOKです。
母分散の既知、未知の違いで
従う分布関数や、検定統計量の式が若干、形が変わります。
この2つ式をベースに変形していきます。
⑧(計量値)母平均差の検定統計量を導出1
前提条件
前提条件は、
- 母平均差
- 母分散が既知でそれぞれ\(σ_1^2\),\(σ_2^2\)
>検定統計量を導出
検定統計量の出発点は、\(u_0\)=\(\frac{\bar{x}-μ_0}{\sqrt{σ^2/n}}\)
です。
2つの母集団 N1(\(μ_1\),\(σ_1^2\)), N2(\(μ_2\),\(σ_2^2\))からそれぞれn1個、n2個データを取り出し、その標本集団をそれぞれN1’, N2’とします。
平均と分散はN1’ (\(μ_1\),\(σ_1^2/n_1\)), N2’ (\(μ_2\),\(σ_2^2/n_2\))となります。
あるN1’の点\(\bar{X_1}\)と、あるN2’の点\(\bar{X_2}\)との差を検定します。その分布N1’- N2’を考えると、
●平均(期待値)は、\(μ_1\)-\(μ_2\) とそのまま差として、
●分散は、\(σ_1^2/n_1\)+\(σ_2^2/n_2\)と分散の加法性を使います。
よって、検定統計量は
●\(u_0\)=\(\frac{(\bar{x_1}-μ_1)-(\bar{x_2}-μ_2)}{\sqrt{\frac{σ_1^2}{n_1}+\frac{σ_2^2}{n_2}}}\)
=\(\frac{(\bar{x_1}-\bar{x_2})-(μ_1-μ_2)}{\sqrt{\frac{σ_1^2}{n_1}+\frac{σ_2^2}{n_2}}}\)
となります。
★ ただし! \(μ_1-μ_2\)=0とする例もあ
母平均差を検定する思いは、母平均差が無いも考えるので、よく
\(μ_1-μ_2\)=0として、
●\(u_0\)=\(\frac{\bar{x_1}-\bar{x_2}}{\sqrt{\frac{σ_1^2}{n_1}+\frac{σ_2^2}{n_2}}}\)
をよく使います。
検定統計量は
●\(u_0\)=\(\frac{\bar{x_1}-\bar{x_2}}{\sqrt{\frac{σ_1^2}{n_1}+\frac{σ_2^2}{n_2}}}\)
ただし、 \(μ_1-μ_2\)=0として、
●\(u_0\)=\(\frac{\bar{x_1}-\bar{x_2}}{\sqrt{\frac{σ_1^2}{n_1}+\frac{σ_2^2}{n_2}}}\)
⑨(計量値)母平均差の検定統計量を導出2<
前提条件
前提条件は、
検定統計量を導出
検定統計量の出発点は、\(t_0\)=\(\frac{\bar{x}-μ_0}{\sqrt{V/n}}\)
です。
2つの母集団 N1(\(μ_1\),\(V\)), N2(\(μ_2\),\(V\))からそれぞれn1個、n2個データを取り出し、その標本集団をそれぞれN1’, N2’とします。
平均と分散はN1’ (\(μ_1\),\(V/n_1\)), N2’ (\(μ_2\),\(V/n_2\))となります。
あるN1’の点\(\bar{X_1}\)と、あるN2’の点\(\bar{X_2}\)との差を検定します。その分布N1’- N2’を考えると、
●平均(期待値)は、\(μ_1\)-\(μ_2\) とそのまま差として、
●分散は、\(V/n_1\)+\(V/n_2\)=\(V(1/n_1+1/n_2)\)と分散の加法性を使います。
よって、検定統計量は
●\(t_0\)=\(\frac{(\bar{x_1}-μ_1)-(\bar{x_2}-μ_2)}{\sqrt{V(\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2})}}\)
=\(\frac{(\bar{x_1}-\bar{x_2})-(μ_1-μ_2)}{\sqrt{ V(\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2})}}\)
となります。
一方、分散\(V\)は、全平方和を全自由度で割ればいいので。
●\(V\)=\(\frac{S_1+S_2}{(n_1-1)+(n_2-1)}\)= \(\frac{S_1+S_2}{n_1+n_2-2}\)
となります。
★ ただし! \(μ_1-μ_2\)=0とする例もある
母平均差を検定する思いは、母平均差が無いも考えるので、よく
\(μ_1-μ_2\)=0として、
●\(t_0\)=\(\frac{\bar{x_1}-\bar{x_2}}{\sqrt{ V(\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2})}}\)
をよく使います。
検定統計量は
●\(t_0\)=\(\frac{(\bar{x_1}-\bar{x_2})-(μ_1-μ_2)}{\sqrt{ V(\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2})}}\)
ただし、 \(μ_1-μ_2\)=0として、
●\(t_0\)=\(\frac{\bar{x_1}-\bar{x_2}}{\sqrt{ V(\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2})}}\)
(●\(V\)=\(\frac{S_1+S_2}{(n_1-1)+(n_2-1)}\)= \(\frac{S_1+S_2}{n_1+n_2-2}\))
⑩(計量値)母平均差の検定統計量を導出3
前提条件
前提条件は、
- 母平均差
- 母分散が未知だが、分散\(V_1\)≠\(V_2\)
検定統計量を導出
検定統計量の出発点は、\(t_0\)=\(\frac{\bar{x}-μ_0}{\sqrt{V/n}}\)
です。
2つの母集団 N1(\(μ_1\),\(V_1\)), N2(\(μ_2\),\(V_2\))からそれぞれn1個、n2個データを取り出し、その標本集団をそれぞれN1’, N2’とします。
平均と分散はN1’ (\(μ_1\),\(V_1/n_1\)), N2’ (\(μ_2\),\(V_2/n_2\)となります。
あるN1’の点\(\bar{X_1}\)と、あるN2’の点\(\bar{X_2}\)との差を検定します。その分布N1’- N2’を考えると、
●平均(期待値)は、\(μ_1\)-\(μ_2\) とそのまま差として、
●分散は、\(V_1/n_1\)+\(V_2/n_2\)と分散の加法性を使います。
よって、検定統計量は
●\(t_0\)=\(\frac{(\bar{x_1}-μ_1)-(\bar{x_2}-μ_2)}{\sqrt{\frac{V_1}{n_1}+\frac{V_2}{n_2}}}\)
=\(\frac{(\bar{x_1}-\bar{x_2})-(μ_1-μ_2)}{\sqrt{\frac{V_1}{n_1}+\frac{V_2}{n_2}}}\)
となります。
★ ただし! \(μ_1-μ_2\)=0とする例もある
母平均差を検定する思いは、母平均差が無いも考えるので、よく
\(μ_1-μ_2\)=0として、
●\(t_0\)=\(\frac{\bar{x_1}-\bar{x_2}}{\sqrt{\frac{V_1}{n_1}+\frac{V_2}{n_2}}}\)
をよく使います。
検定統計量は
●\(t_0\)=\(\frac{(\bar{x_1}-\bar{x_2})-(μ_1-μ_2)} {\sqrt{\frac{V_1}{n_1}+\frac{V_2}{n_2}}}\)
ただし、 \(μ_1-μ_2\)=0として、
●\(t_0\)=\(\frac{\bar{x_1}-\bar{x_2}}{\sqrt{\frac{V_1}{n_1}+\frac{V_2}{n_2}}}\)
⑪(計量値)母平均差の検定統計量を導出4
「対応のある」とは何か?
「対応のあるとない」の違いは何でしょうか?
下図にイメージを示します。

●対応のない場合は、全く別の分布を2つ用意した場合
●対応のある場合は、異なる2つの分布とはいえ、個々のデータは関係性を持つ場合
と分けた方が考えやすいですね。
対応のある場合は、まとめて1つの分布として計算してもよいとして扱います。
★ 対応のある場合の扱い方
2つの母集団 N1, N2からそれぞれn個データを取り出し、それぞれ対応する組み合わせデータ値の差分をとった集団N1’を作ります。
前提条件
前提条件は、
- 母平均差\(δ\)
- 母分散が既知で\(σ_d^2\)
検定統計量を導出
検定統計量の出発点は、\(u_0\)=\(\frac{\bar{x}-μ_0}{\sqrt{σ^2/n}}\)
です。
差をdとしているので、
平均は\(\bar{d}\)
分散はN1’ のデータから別途求めます。今回は\(σ_d^2\)となります。
よって、検定統計量は
●\(u_d\)=\(\frac{(\bar{d}-d_0)}{\sqrt{σ_d^2/n}}\)
となります。
★ただし! \( d_0\)=0とする例もある
母平均差を検定する思いは、母平均差が無いも考えるので、よく
\( d_0\)=0として、
●\(u_d\)=\(\frac{\bar{d}}{\sqrt{σ_d^2/n}}\)
をよく使います。
検定統計量は
●\(u_d\)=\(\frac{(\bar{d}-d_0)}{\sqrt{σ_d^2/n}}\)
ただし、 \( d_0\)=0として、
●\(u_d\)=\(\frac{\bar{d}}{\sqrt{σ_d^2/n}}\)
⑫(計量値)母平均差の検定統計量を導出5
前提条件
前提条件は、
検定統計量を導出
検定統計量の出発点は、\(t_0\)=\(\frac{\bar{x}-μ_0}{\sqrt{V/n}}\)
です。
差をdとしているので、
平均は\(\bar{d}\)
分散はN1’ のデータから別途求めます。今回は\(V_d\)となります。
よって、検定統計量は
●\(t_d\)=\(\frac{\bar{d}-d_0}{\sqrt{V_d/n}}\)
となります。
★ ただし! \( d_0\)=0とする例もある
母平均差を検定する思いは、母平均差が無いも考えるので、よく
\( d_0\)=0として、
●\(t_d\)=\(\frac{\bar{d}}{\sqrt{V_d/n}}\)
をよく使います。
検定統計量は
●\(t_d\)=\(\frac{\bar{d}-d_0}{\sqrt{V_d/n}}\)
ただし、 \( d_0\)=0として、
●\(t_d\)=\(\frac{\bar{d}}{\sqrt{V_d/n}}\)
以上、よく使う検定統計量を導出しました。ちゃんと導出できるので、公式暗記に頼らず自力で導出できるようにしましょう。
まとめ
「【初心者必見!】計数値の検定統計量が導出できる」を解説しました。
- ①(計数値)計数値の検定統計量のベースとなる式
- ➁(計数値)母不適合品率の検定統計量を導出
- ➂(計数値)母不適合品率差の検定統計量を導出
- ➃(計数値)母不適合品率差の検定統計量の注意点
- ➄(計数値)母不適合数の検定統計量を導出
- ⑥(計数値)母不適合数差の検定統計量を導出
- ⑦(計量値)計量値の検定統計量のベースとなる式
- ⑧(計量値)母平均差の検定統計量を導出1
- ⑨(計量値)母平均差の検定統計量を導出2
- ⑩(計量値)母平均差の検定統計量を導出3
- ⑪(計量値)母平均差の検定統計量を導出4
- ⑫(計量値)母平均差の検定統計量を導出5