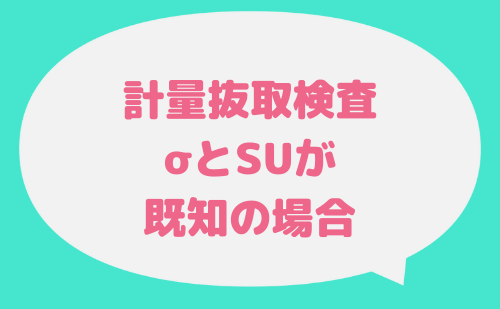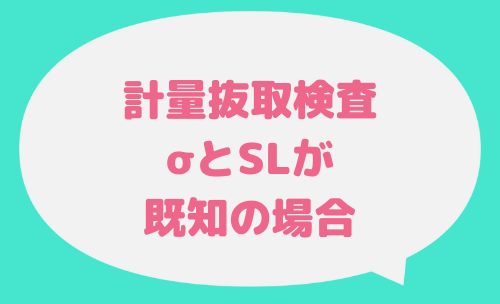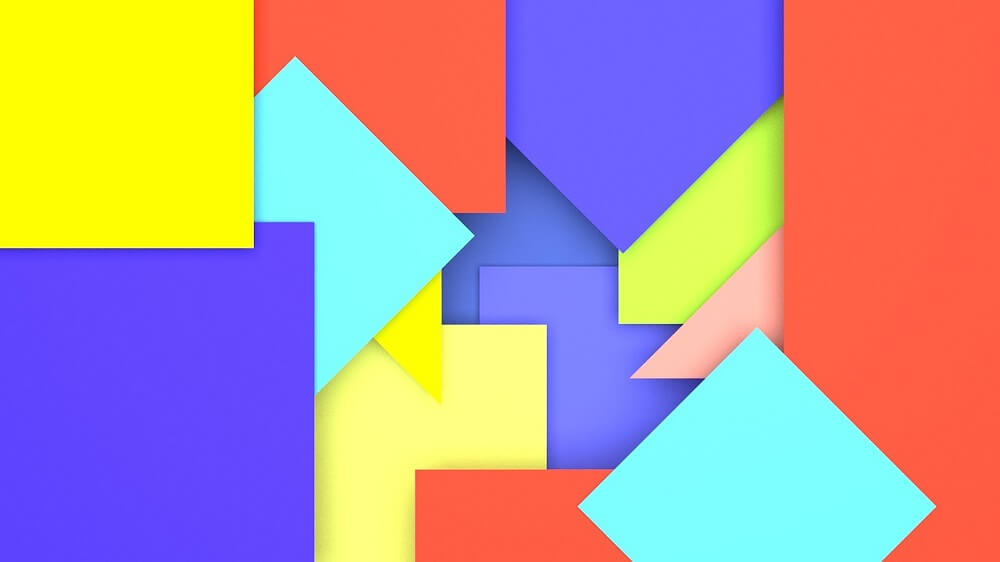「計量抜取検査(標準偏差既知) (JISZ9003)がよくわからない」、「サンプル数n,合格判定係数kはどうやって求めるの?」など困っていませんか?
こういう疑問に答えます。
本記事のテーマ
JISZ9003計量抜取検査(標準偏差既知)で上限規格値が既知の抜取方式がわかる
- ①上限規格値と合格判定値についての関係式を導出
- ②サンプル数nと合格判定係数kを導出
- ③演習問題
- ④OC曲線を描く
下限規格値については、関連記事で確認ください。
 |
JISZ9003計量抜取検査(標準偏差既知)で下限規格値が既知の抜取方式 JISZ9003計量抜取検査(標準偏差既知)で下限規格値が既知の抜取方式について解説します。サンプル数n、合格判定個数k、下限合格判定値の導出やOC曲線の描き方を解説します。計量抜取検査をマスターしたい方は必見です。 |
本物の「抜取検査」問題集を販売します!
 |
今回、【QC検定®合格】「抜取検査」問題集を販売します! 内容は、①二項分布・ポアソン分布、OC曲線、➁多回抜取検査、➂選別型抜取検査、➃計量抜取検査、⑤逐次抜取検査、⑥調整型抜取検査、⑦抜取検査まとめ の7章全47題を演習できる問題集です。しっかり勉強しましょう。 |
①上限規格値と合格判定値についての関係式を導出
関係式を導出するためのモデル図を作成
次のような計量抜取検査を考えます。
● p ≤ p0の不良率をもつロットは合格
● p > p1の不良率をもつロットは不合格
とする。前者はできるだけ合格させたいが、後者はできるだけ不合格にさせたいような抜取検査を考えたい。
モデル図を下図のように作ります。
このモデル図がしっかり作りこむことが意外と重要です。よく眺めてください。

できるだけ合格させたいp0はα=0.05(生産者危険)
できるだけ不合格にさせたいp1はβ=0.1(消費者危険)
の確率になるような抜取方式を検討します。
関係式を導出
モデル図から次の式が導かれます。見たらわかりますね。
計量抜取検査の理論は、モデル図から式を導出します
①\(σ_{\bar{x}}\)=\(\frac{σ}{\sqrt{n}}\)
②上限規格値Lの関係式を作ります。
●\(μ_0\)=U-\(K_{p0}σ\)
●\(μ_1\)=U-\(K_{p1}σ\)
③合格判定値\(\bar{X_U}\)の関係式を作ります。
●μを使う場合
・\(\bar{X_U}\)=\(μ_0\)+\(K_{α}σ_{\bar{x}}\)
・\(\bar{X_U}\)=\(μ_1\)-\(K_{β}σ_{\bar{x}}\)
●Uを使う場合
・\(\bar{X_U}\)=U-\(K_{p0}σ\)+\(K_{α}σ_{\bar{x}}\)
・\(\bar{X_U}\)=U-\(K_{p1}σ\)-\(K_{β}σ_{\bar{x}}\)
②サンプル数nと合格判定係数kを導出
関係式からサンプル数nと合格判定係数kを導出します。
サンプル数nを導出
ただし、わかっている値で表現します。
わかっている値は
\(K_{α}\)
\(K_{β}\)
\(K_{p0}\)
\(K_{p1}\)
です。
●Uを使う場合
・\(\bar{X_U}\)=U-\(K_{p0}σ\)+\(K_{α}σ_{\bar{x}}\)
・\(\bar{X_U}\)=U-\(K_{p1}σ\)-\(K_{β}σ_{\bar{x}}\)
の2式を引きます。
0=0-\(K_{p0}σ\)+\(K_{p1}σ\)+\(K_{α}σ_{\bar{x}}\)+\(K_{β}σ_{\bar{x}}\)
(\(K_{p0}-K_{p1}\))σ=(\(K_{α}+K_{β}\))\(σ_{\bar{x}}\)
この式に、\(σ_{\bar{x}}\)=\(\frac{σ}{\sqrt{n}}\)を代入します。
(\(K_{p0}-K_{p1}\))σ=(\(K_{α}+K_{β}\))\(\frac{σ}{\sqrt{n}}\)
両辺をσで割って,2乗します。
n=\((\frac{K_{α}+K_{β}}{K_{p0}-K_{p1}})^2\)
上限、下限規格値どちらも、サンプル数nは同じ式ができます。
合格判定係数kを導出
初登場のkですが、
・\(\bar{X_U}\)=U-kσ
と置きます。
\(\bar{X_U}\)は
・\(\bar{X_U}\)=U-\(K_{p0}σ\)+\(K_{α} σ_{\bar{x}}\)
= U-\(K_{p0}σ\)+\(K_{α} \frac{σ}{\sqrt{n}}\)
ですから、
k=\(K_{p0}\)-\(K_{α} \frac{1}{\sqrt{n}}\)
です。
なお、OC曲線を描くために、β,p1を使った関係式も導出します。
・\(\bar{X_U}\)=U-\(K_{p1}σ\)-\(K_{β} σ_{\bar{x}}\)
= U-\(K_{p1}σ\)-\(K_{β} \frac{σ}{\sqrt{n}}\)
ですから、
k=\(K_{p1}\)+\(K_{β} \frac{1}{\sqrt{n}}\)
です。
nは先ほど導出しました、
n=\((\frac{K_{α}+K_{β}}{K_{p0}-K_{p1}})^2\)
を、
\(\sqrt{n}\)=\(\frac{K_{α}+K_{β}}{K_{p0}-K_{p1}}\)
とします。
k=\(K_{p0}\)-\(K_{α} \frac{1}{\sqrt{n}}\)
=\(K_{p0}\)-\(K_{α} \frac{ K_{p0}-K_{p1}}{ K_{α}+K_{β}}\)
よって、
k=\(\frac{K_{p0}K_{β}+K_{p1}K_{α}}{ K_{α}+K_{β}}\)
となります。
③演習問題
不良率p0,p1と上で求めた、サンプル数nと合格判定係数kを使って、計量抜取検査のOC曲線が描けます。その前に演習問題を出して考えましょう。
あるプラスチック板の厚さの上限規格値が1.6mmとする。厚さが1.6mm超過のものが1%以下のロットはなるべく検査で合格させたいが、3%以上もあるロットはなるべく検査で不合格としたい。厚さの値は標準偏差σ=0.3mmの正規分布に従うとする。このとき、第1種の誤りであるα=0.002,第2種の誤りであるβ=0.10とした場合の抜取方式を決めよ。
うん、難しそう。。。でも1つずつ見ていきましょう。
まず、検査は抜取検査をやろうとしていますね。
次に、扱う変数は厚さという計量値を検査しようとしていますね。
最後に、上限規格値が決まっていますね。
サンプル数nと、合格判定係数kを導出した公式から求めましょう。
まず、確率から\(K_{α}\)、\(K_{β}\)、\(K_{p0}\)、\(K_{p1}\)
がわかります。正規分布表を活用します。
\(K_{α}\)=2.878 (α=0.002のときのK値)
\(K_{β}\)=1.282(β=0.10のときのK値)
\(K_{p0}\)=2.326(p0=0.01のときのK値)
\(K_{p1}\)=1.881(p1=0.03のときのK値)
正規分布表に苦手意識があれば関連記事で復習しましょう。
 |
【簡単】正規分布は怖くない!正規分布表や確率計算の求め方がすぐわかる 「正規分布とは何か?」、「正規分布の難解な式が理解できない」、「正規分布表の意味がわからない」など困っていませんか?本記事では、教科書やwebサイトより正規分布の基本やポイントをわかりやすく解説します。最も重要な正規分布を理解したい方は必見です。 |
サンプル数nは
n=\((\frac{K_{α}+K_{β}}{K_{p0}-K_{p1}})^2\)
= n=\((\frac{2.878+1.282}{2.326-1.881})^2\)
=85.3≒86
と計算できます。
合格判定係数kは
k=\(\frac{K_{p0}K_{β}+K_{p1}K_{α}}{ K_{α}+K_{β}}\)
=\(\frac{2.326×1.282+1.881×2.878}{ 2.878+1.282}\)
=2.02
ちなみに、上限合格判定値\(\bar{X_U}\)は、
\(\bar{X_U}\)=U-kσ
=1.6-2.02×0.3=0.995
まとめると
(n,k)=(86,2.02)の値で、
平均値が0.995mm以下ならロット合格、超過ならロット不合格
となります。
④OC曲線を描く
上の演習問題の結果をOC曲線で描きます。
OC曲線を描くための準備
なお、OC曲線を描くために、k,β,p1の関係式を再度書きます。
k=\(K_{p1}\)+\(K_{β} \frac{1}{\sqrt{n}}\)
変形して
(k-\(K_{p1}\))\(\sqrt{n}\)=\(K_{β}\)
ここで、p1,βを一般化して、
p1⇒p
β⇒L(p)
に変えます。慣れないとここの変化は無理矢理感がありますけど。
L(p)の作り方
- 不良率pを変数として0から値を振る。
- pから正規分布表を使って\(K_{p}\)に変換する。/li>
- サンプル数n,合格判定係数kを代入し、\(K_{L(p)}\)を計算する。
- \(K_{L(p)}\)を満たす確率L(p)を求める。
- pとL(p)の関係からOC曲線を描く。
では、実際にやってみましょう。表にまとめます。
| p | Kp | k-Kp | (k-Kp)\(\sqrt{n}\)=K_{L(P)}\) | L(p) |
| 0.01 | 2.33 | -0.31 | -2.84 | 1 |
| 0.015 | 2.17 | -0.15 | -1.39 | 0.92 |
| 0.02 | 2.05 | -0.03 | -0.31 | 0.62 |
| 0.025 | 1.96 | 0.06 | 0.56 | 0.29 |
| 0.03 | 1.88 | 0.14 | 1.29 | 0.1 |
| 0.035 | 1.81 | 0.21 | 1.93 | 0.03 |
| 0.04 | 1.75 | 0.27 | 2.5 | 0.01 |
| 0.045 | 1.7 | 0.32 | 3.01 | 0 |
| 0.05 | 1.64 | 0.38 | 3.48 | 0 |
ここで、表の計算式をExcelの式を使って表現しています。
Kp=ABS(NORM.INV(pの値,0,1))
L(p)=1-(NORM.DIST(\(K_{L(p)}\)の値,0,1,TRUE))
OC曲線を描く
OC曲線です。計数抜取検査と似たような曲線になります。

計量抜取検査は式変形が多いですが、慣れましょう。
まとめ
JISZ9003計量抜取検査(標準偏差既知)で上限規格値が既知の抜取方式について、サンプル数n、合格判定個数k、上限合格判定値の導出やOC曲線の描き方を解説しました。
- ①上限規格値と合格判定値についての関係式を導出
- ②サンプル数nと合格判定係数kを導出
- ③演習問題
- ④OC曲線を描く