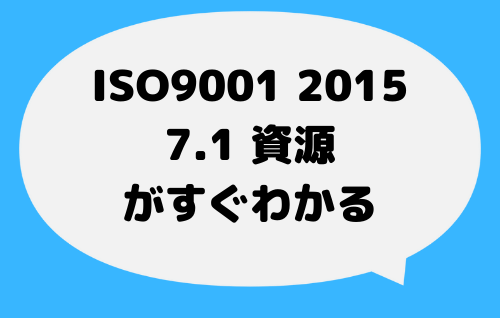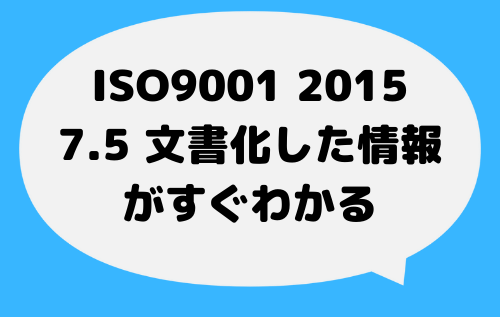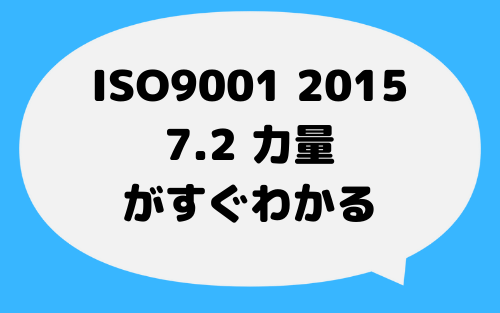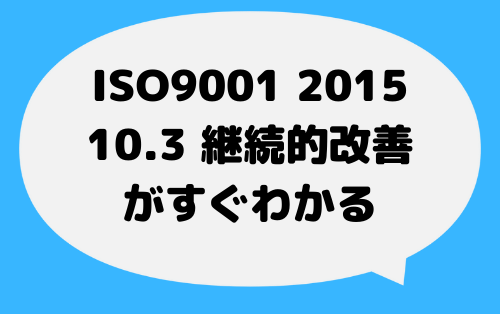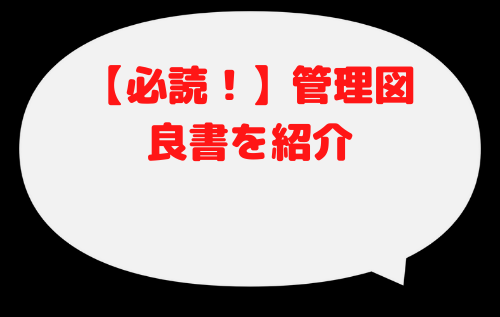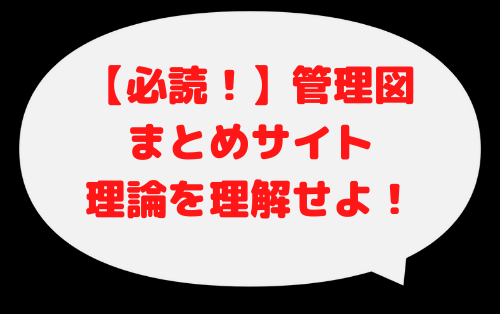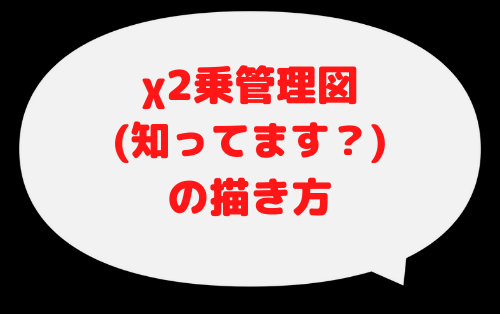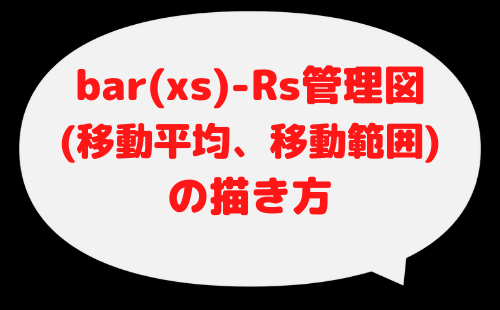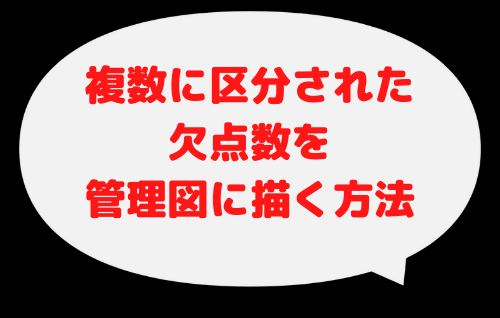QCプラネッツのISO9001 2015関連ブログを多くの方に読んでいただき、とてもうれしいです。ブログの内容をさらにパワーアップして更新しました。
★ 本記事のテーマ
- ①ISO9001要求事項、JISハンドブックISO9001の解説
- ②資源は経営資源「ヒト・モノ・カネ」から理解する
- ③経営をよくするには、ヒト・モノに何が必要なのかを考えればよい。
①ISO9001要求事項、JISハンドブックの解説
ISO9001要求事項
7.1.1 一般 組織は,品質マネジメントシステムの確立,実施,維持及び継続的改善に必要な資源を明確にし,提供しなければならない。 組織は,次の事項を考慮しなければならない。
a) 既存の内部資源の実現能力及び制約
b) 外部提供者から取得する必要があるもの
7.1.2 人々 組織は,品質マネジメントシステムの効果的な実施,並びにそのプロセスの運用及び管理のために必要な人々を明確にし,提供しなければならない。
7.1.3 インフラストラクチャ 組織は,プロセスの運用に必要なインフラストラクチャ,並びに製品及びサービスの適合を達成するために必要なインフラストラクチャを明確にし,提供し,維持しなければならない。 注記 インフラストラクチャには,次の事項が含まれ得る。
a) 建物及び関連するユーティリティ
b) 設備。これにはハードウェア及びソフトウェアを含む。
c) 輸送のための資源
d) 情報通信技術
7.1.4 プロセスの運用に関する環境 組織は,プロセスの運用に必要な環境,並びに製品及びサービスの適合を達成するために必要な環境を明確にし,提供し,維持しなければならない。 注記 適切な環境は,次のような人的及び物理的要因の組合せであり得る。
a) 社会的要因(例えば,非差別的,平穏,非対立的)
b) 心理的要因(例えば,ストレス軽減,燃え尽き症候群防止,心のケア)
c) 物理的要因(例えば,気温,熱,湿度,光,気流,衛生状態,騒音)
これらの要因は,提供する製品及びサービスによって,大いに異なり得る。
7.1.5 監視及び測定のための資源
7.1.5.1 一般 要求事項に対する製品及びサービスの適合を検証するために監視又は測定を用いる場合,組織は,結果が妥当で信頼できるものであることを確実にするために必要な資源を明確にし,提供しなければならない。 組織は,用意した資源が次の事項を満たすことを確実にしなければならない。
a) 実施する特定の種類の監視及び測定活動に対して適切である。
b) その目的に継続して合致することを確実にするために維持されている。 組織は,監視及び測定のための資源が目的と合致している証拠として,適切な文書化した情報を保持しなければならない。
7.1.5.2 測定のトレーサビリティ 測定のトレーサビリティが要求事項となっている場合,又は組織がそれを測定結果の妥当性に信頼を与えるための不可欠な要素とみなす場合には,測定機器は,次の事項を満たさなければならない。
a) 定められた間隔で又は使用前に,国際計量標準又は国家計量標準に対してトレーサブルである計量標準に照らして校正若しくは検証,又はそれらの両方を行う。そのような標準が存在しない場合には,校正又は検証に用いたよりどころを,文書化した情報として保持する。
b) それらの状態を明確にするために識別を行う。
c) 校正の状態及びそれ以降の測定結果が無効になってしまうような調整,損傷又は劣化から保護する。 測定機器が意図した目的に適していないことが判明した場合,組織は,それまでに測定した結果の妥当性を損なうものであるか否かを明確にし,必要に応じて,適切な処置をとらなければならない。
7.1.6 組織の知識 組織は,プロセスの運用に必要な知識,並びに製品及びサービスの適合を達成するために必要な知識を明確にしなければならない。 この知識を維持し,必要な範囲で利用できる状態にしなければならない。 変化するニーズ及び傾向に取り組む場合,組織は,現在の知識を考慮し,必要な追加の知識及び要求される更新情報を得る方法又はそれらにアクセスする方法を決定しなければならない。
注記1 組織の知識は,組織に固有な知識であり,それは一般的に経験によって得られる。それは,組織の目標を達成するために使用し,共有する情報である。 注記2 組織の知識は,次の事項に基づいたものであり得る。
a) 内部の知識源(例えば,知的財産,経験から得た知識,成功プロジェクト及び失敗から学んだ教訓,文書化していない知識及び経験の取得及び共有,プロセス,製品及びサービスにおける改善の結果)
b) 外部の知識源(例えば,標準,学界,会議,顧客又は外部の提供者からの知識収集)
資源の要求事項が長いですが、わかりやすく明快に解説します!
JISハンドブックの解説
- JIS Q9001品質マネジメントシステム-要求事項
- JIS Q9002 品質マネジメントシステム-JIS Q 9001の適用に関する指針
- JIS Q9004 品質マネジメント-組織の品質-持続的成功を達成するための指針
それぞれを読んだ印象をまとめます。
| JIS | 名称 | 単元 | 感想 |
| JIS Q9001 | 品質マネジメントシステム -要求事項 |
7.1 資源 | ISO9001 2015 7.2 と同じ内容 |
| JIS Q9002 | 品質マネジメントシステム -JIS Q 9001の適用に関する指針 |
7.1 資源 | JIS Q9001 7.1 の補足 わかった感じにはなる。 |
| JIS Q9004 | 品質マネジメント-組織の品質 -持続的成功を達成するための指針 |
9 資源のマネジメント | さらに詳細説明がある。 わかった感じになるが、 自分の言葉では説明できないはず |
なので、結論は、
②資源は経営資源「ヒト・モノ・カネ」から理解する
経営学から入るとわかりやすい
経営学では、経営の資源をよく
の3つにまとめることがあります。
品質管理では「カネ」は対象外なので、
の2つの資源に着目します。
ヒト
ヒトの資源を詳しく分解すると例えば、次の4つに分解できます。あなたらしい項目に分解してもOKです。一例をあげます。
- 人の数
- 各人の能力(業務経験、力量)
- 働きやすさ(雇用体制、労働時間、システムの利便性)
- メンタルヘルス、多様性
一昔前なら、KKD(気合、根性、度胸)で「24時間戦えますか?」というCMがあり、
それが日本の強さとか言っていましたが、今はそんな環境には人は行きたいと思いません。
人が自ら成長したい、そうエンパワーメントする環境が必須な時代です。
この4項目を理解してからISO9001 2015 7.1資源を読み直すと
①7.1.6 組織の知識 a) 内部の知識源、b) 外部の知識源
②7.1.4 プロセスの運用に関する環境 a) 社会的要因、b) 心理的要因、c) 物理的要因
に該当することがわかります。
モノ
モノの資源を詳しく分解すると例えば、次の4つに分解できます。あなたらしい項目に分解してもOKです。一例をあげます。人が働いて、高い業務成果を出すには、何が必要かを考えましょう。
- 施設(事務所、工場の建屋)
- 設備(机、椅子、照明、空調、トイレ)
- 機械、計測器(工場)
- 情報通信(PC,サーバー)
建屋がないと、仕事になりませんよね。建屋の設備がないと困りますよね。PC,機械、計測器がないと仕事できませんよね。当たり前じゃん!なのですが、その当たり前なモノが十分あるか?十分機能を果たしているか?が重要です。
照明が暗い、空調がなければ、人への影響が出て、よい仕事ができませんし、熱中症などの事故、感染症の問題など、その職場の問題がいっぱい発生するから、モノの資源をしっかりおさえておくことは重要なのです。
この4項目を理解してからISO9001 2015 7.1資源を読み直すと
①7.1.3 インフラストラクチャ
②7.1.4 プロセスの運用に関する環境 a) 社会的要因、b) 心理的要因、c) 物理的要因
③7.1.5.2 測定のトレーサビリティ 機械、測定器の校正管理
に該当することがわかります。
③経営をよくするには、ヒト・モノに何が必要なのかを考えればよい。
経営の資源「ヒト・モノ」を良くしていけばいいとすぐわかりますよね。個別にみていきましょう。
資源の現状と、資源を高める活動をしているかを品質監査でもチェックします。
ヒト
ヒトは4つの資源に分解して考えました。それぞれをよくしていけばいいわけです。
- 人の数
- 各人の能力(業務経験、力量)
- 働きやすさ(雇用体制、労働時間、システムの利便性)
- メンタルヘルス、多様性
どうやって、良くしていきますか?
★改善方法
●人の数:採用強化が必須ですが、会社の評価が高くないと良い人財が来ません。
●各人の能力:将来の力量向上につながる業務を、メンターをつけて育成できるチーム体制が必要です。
●働きやすさ:時短勤務、フレックス、最新のシステム導入、残業時間低減による生産性向上などの体制構築が必要です。
●メンタルヘルス、多様性:労働環境・労働時間の適正化、産業医などのサポート体制が必要です
改善方法をいろいろ上げると、会社・組織に必要な体制や制度がいっぱいあり、それらが有効的に機能させる必要があります。資源をそろえるのは、結構大変であることがわかりますね。
モノ
モノは4つの資源に分解して考えました。それぞれをよくしていけばいいわけです。
- 施設(事務所、工場の建屋)
- 設備(机、椅子、照明、空調、トイレ)
- 機械、計測器(工場)
- 情報通信(PC,サーバー)
どうやって、良くしていきますか?
★改善方法
●施設:利便性高い立地。最新の施設など。
床がすべりやすく、段差があるとか、雨漏りするとかはNG。労働災害につながります。
●設備:照明・空調・圧迫感のない職場、風通しの良い職場作り。
●機械、計測器:校正管理ができていることや、メンテナンスが適正であること。機械が壊れたまま稼働すると大事故につながります。
●情報通信:PCの使いやすさとか、サイバーセキュリティ対策など
改善方法をいろいろ上げると、会社・組織に必要な体制や制度がいっぱいあり、それらが有効的に機能させる必要があります。資源をそろえるのは、結構大変であることがわかりますね。
品質監査で「資源」を監査
監査員として、「7.1資源」を監査する場合、どんな質問をしたらよいか?考えましょう。いい勉強になります。
先ほどから
●ヒト:人数、力量、働きやすさ、労働衛生
●モノ:施設、設備、機械、情報通信
を資源として考えてきましたので、これらが十分あるか、十分機能しているかを質疑すればよいです
★質疑内容の例
●組織内の人数は十分か? 人的リソースにおける課題を挙げよ。
●力量向上に必要なリソースは何か?いくつか挙げよ。
●平均残業時間はどれくらいか? 半減するにはどうすればよいか提示せよ。
●職場の人のメンタルケアをカバーしているか?
●職場内は働きやすい環境か?職場における不満を挙げよ。
●労働生産性を向上させるために、どんな工夫をしているか?
●事業の今後の変革に対応して、どんなリソースが必要か?
●セキュリティ対策は何をしているか?
など、質疑すると、
●現状のリソースの課題とその解決策
が見えてきます。
同時に収益の源泉でもある。
資源戦略をしっかり整えることが事業成長に必須
資源のエッセンスが十分、理解できましたね!
まとめ
ISO9001 2015 7.1 資源をわかりやすく解説しました。
- ①ISO9001要求事項、JISハンドブックISO9001の解説
- ②資源は経営資源「ヒト・モノ・カネ」から理解する
- ③経営をよくするには、ヒト・モノに何が必要なのかを考えればよい。