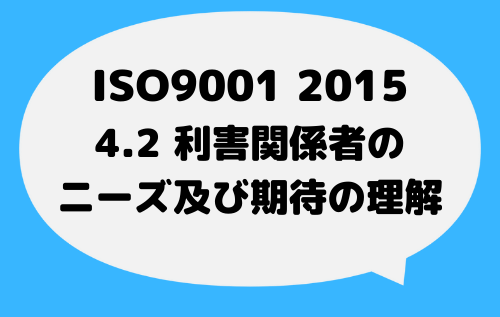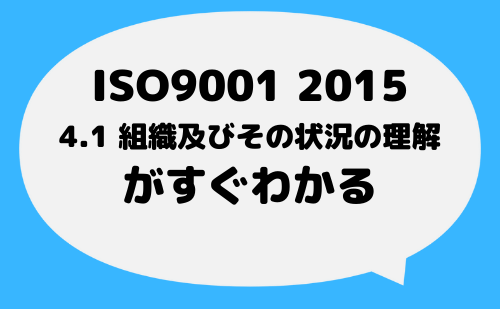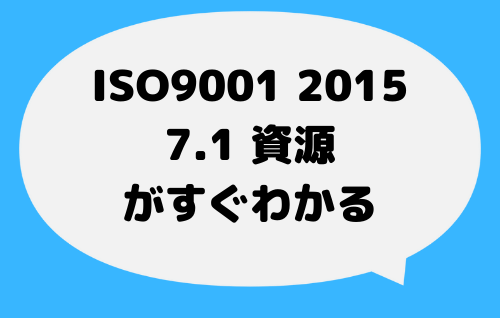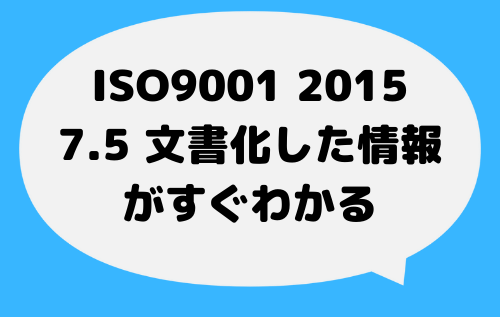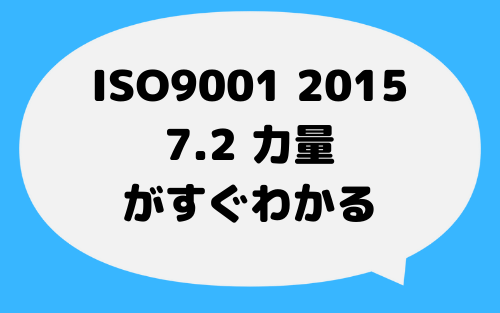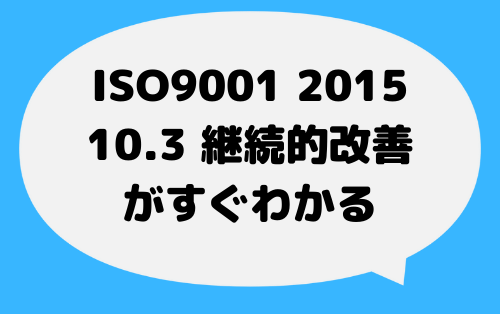QCプラネッツのISO9001 2015関連ブログを多くの方に読んでいただき、とてもうれしいです。ブログの内容をさらにパワーアップして更新しました。
★ 本記事のテーマ
- ①ISO9001要求事項、JISハンドブックISO9001の解説
- ②利害関係者をマーケテイングから学ぶ
- ③利害関係者のニーズ及び期待の理解とは?
- ④品質監査で質疑されること
①ISO9001要求事項、JISハンドブックの解説
ISO9001 2015の要求事項、JISのハンドブックを読みましょう。
ISO9001要求事項
次の事項は,顧客要求事項及び適用される法令・規制要求事項を満たした製品及びサービスを一貫して提供する組織の能力に影響又は潜在的影響を与えるため,組織は,これらを明確にしなければならない。
a) 品質マネジメントシステムに密接に関連する利害関係者
b) 品質マネジメントシステムに密接に関連するそれらの利害関係者の要求事項 組織は,これらの利害関係者及びその関連する要求事項に関する情報を監視し,レビューしなければならない。
4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解 で大事なのは、
●「利害関係者」って何?誰?がわかることと
●「利害関係者のニーズ及び期待」って何?と
●「利害関係者のニーズ及び期待の理解」ってどうやって理解するの?が
自分の言葉で説明できることです。
JISハンドブックの解説
次のように規定されています。
- JIS Q9001品質マネジメントシステム-要求事項
- JIS Q9002 品質マネジメントシステム-JIS Q 9001の適用に関する指針
- JIS Q9004 品質マネジメント-組織の品質-持続的成功を達成するための指針
それぞれを読んだ印象をまとめます。
| JIS | 名称 | 単元 | 感想 |
| JIS Q9001 | 品質マネジメントシステム -要求事項 |
4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解 | ISO9001 2015 4.2 と同じ内容 |
| JIS Q9002 | 品質マネジメントシステム -JIS Q 9001の適用に関する指針 |
4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解 | 具体例:顧客、エンドユーザー、パートナー、銀行、従業員、地域団体、競合組織、などなど |
| JIS Q9004 | 品質マネジメント-組織の品質 -持続的成功を達成するための指針 |
5.2密接に関連する利害関係者 | ●関連するニーズ・期待を満たすよう要求すること ●組織の持続的成功を強化する機会を提供できること |
あなたの事業活動における利害関係者と、どんな点において、利益・損害を受けるかを広く考えることが大事です。

②利害関係者をマーケテイングから学ぶ
利害関係者とは?
利害関係者は、ステークホルダーという言い方もします。経営者ならよく使う言葉です。
利害関係者を書き出してみる
●あなたの仕事に直接、間接的に関わる相手すべてを書けばOKですが、
●直接的に関わる相手
●間接的に関わる相手
がいます。
★直接的な利害関係者
●調達元
●あなた
●あなたがいる自社の部課の人、関係部門
●顧客
●エンドユーザー
などですね。
★間接的な利害関係者
直接会うことはないが、関わる相手や、ルールなどです。
●銀行、株主
●法的機関
●ISOなどの標準規格
●近隣住民
などですね。
あなたにとっての利害関係者(ステークホルダー)をまとめると下図のようになるでしょう。もちろん、あなたの立場によって、利害関係者は変わってきます。

③利害関係者のニーズ及び期待の理解とは?
相手はわかりましたね。では、相手は何を求めているのか? それを理解するとはどういうことかを考えます。
利害関係者のニーズ及び期待
あなたから見て、いろいろな角度をもった利害関係者がいます。
彼らはあなたに何を求めて、期待しているでしょうか?
直接的な利害関係者と、間接的な利害関係者に分けて分析します。
★直接的な利害関係者
●具体的なアウトプット(製品出荷、工事完了など)ですね。
相手から求められたことを完遂すればよいのです。直接お金のやり取りある相手なので、成果と報酬から考えたら、すぐわかることです。
★関接的な利害関係者
特に、求められてはいないが、当然対応するよね!、当然守るよね!という内容が該当します。
●法的ルールを遵守
●安全、環境を第1に考えた業務
●近隣住民に不安を与えない仕事
などですね。
間接的な利害関係者だから、関係ない!としても、新聞、テレビ、SNSなどで抗議が出ると、あなたの仕事に悪影響が出ます。
直接見ていないから、逆に注意して仕事しましょう。
例えば、
●コロナ禍だった2020年~2022年と、現在2025年を比較すると、比較的コロナ禍前の状況に戻りつつあること
●報道側のコンプライアンスがさらに厳しくなり、数年前まで放送できたことができないこともしばしば
●今後、どういう方向に求められるか? 当たり前とされる考えもどのように変わっていくかをよく肌で感じる必要があります。
ニーズ及び期待を理解するにはどうするの?
あなたの利害関係者のニーズ及び期待は何となく把握しました。しかし、これも明記した文書があって初めて、ニーズ及び期待を理解するとなります。どんな文書や取り決めが必要かを考えましょう。
また、利害関係者を直接的、間接的に分けて考えます。
★直接的な利害関係者
●顧客要求事項文書(Q,C,D)
●要求仕様書
●契約書
●基本設計図
など、何をいつまでに、どのレベルでアウトプットするかが書かれた仕様書類ですね。
ニーズと期待をおさえつつ、その変化を読み取ることが大切です。
★関接的な利害関係者
●標準規格
●法令
●認可
●免許
●当たり前とされる基本行動(近所に迷惑かけない、ごみは所定の場所に捨てるとか)
など、ルールは暗記ではなく、自分の言葉で説明できることや、高い倫理観が必要です。
仕様書に書いていないけど、やるべきことは何かに気が付く嗅覚と経験が求められます。
ニーズ・期待の変化をどうやって感じ取ればよいか?
このブログは2022/1/26に書いて、2025/8/29に内容を見直しています。約4年経過し、QCプラネッツも経験や周囲の環境が変化しています。数年経過すれば、たくさんの当たり前が変化しますが、日々の変化は微々たるものなので、気が付きません。
長期的には変化するわけだから、
どうやって変化に気がつけばよいか?
それは、いくつか解があります。
●「あれっ?」という違和感を周囲が反対・否定しても大事にすること
です。
長年同じ職場にいると、気が付きにくくなります。それこそ、リスクです。
④品質監査で質疑されること
「4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解」単独で質疑されることはあまりありません。
利害関係者については、
【リンク!関連記事】ISO9001 2015 4.1 組織及びその状況の理解 がわかる
のところで、まとめて質疑されます。
★主に質問される内容
- マネージメントレビューのインプット情報を監査しつつ、各年度の環境の変化を質問し、さらに、あなたが管轄する事業・部門・職場における周囲の利害関係者との関わりや彼らが求める要求の変化が何かを聞いてくる。
- あなたの事業、ビジネスにおいて、一般的に求められる要求品質をベースにあなたが関わるパートナをいくつか挙げて、彼らに求めることや求められることを聞いてくる。
- 自前で事業せず、パートナーとの連携や購買が多くかかわるであろう。なぜ、自前ではないのか?利害関係者と関わることのメリットやデメリットは何か、それを解決するすべがどんなものがあり、どのように評価、PDCAを回しているか?を聞かれる。
ニーズ及び期待、理解は、業務プロセスにて、具体的な業務内容を監査するときに、利害関係者が求めることやあなたに期待していることを確認します。そのインプット情報をもとに、業務プロセスによって要求されるアウトプットかどうかを審査します。
利害関係者のニーズ及び期待の理解を十分、理解できましたね!
まとめ
ISO9001 2015 4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解をわかりやすく解説しました。
- ①ISO9001要求事項、JISハンドブックISO9001の解説
- ②利害関係者をマーケテイングから学ぶ
- ③利害関係者のニーズ及び期待の理解とは?