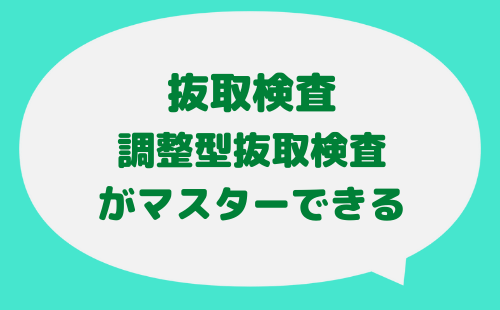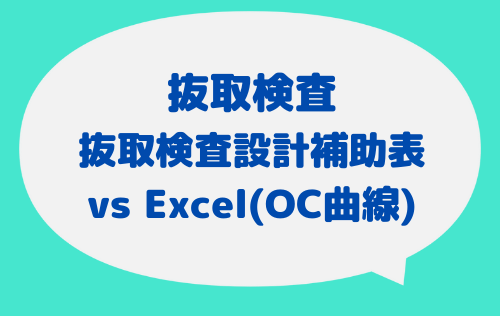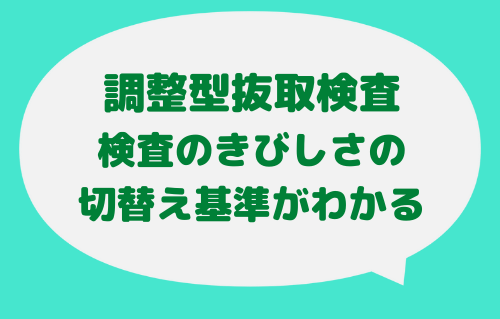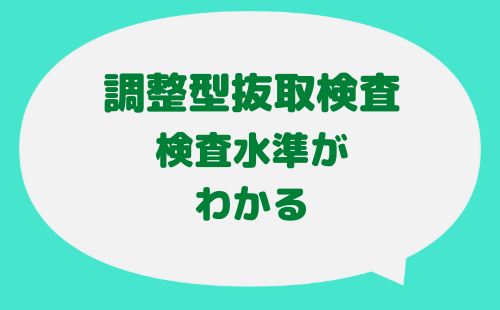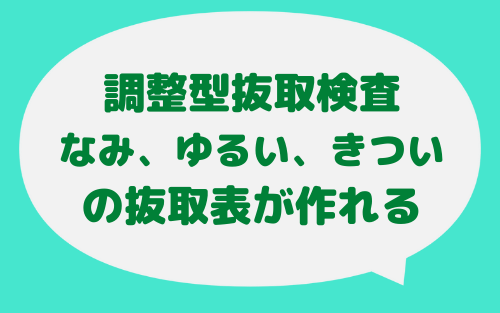「抜取検査がわからない」、「OC曲線、AQLとか難しそう」など困っていませんか?
こういう疑問に答えます。
本記事のテーマ
- ①検査の種類を理解する
- ②抜取検査はOC曲線で考える
- ③抜取検査とOC曲線で理解しておくべきこと
本物の「抜取検査」問題集を販売します!
 |
今回、【QC検定®合格】「抜取検査」問題集を販売します! 内容は、①二項分布・ポアソン分布、OC曲線、➁多回抜取検査、➂選別型抜取検査、➃計量抜取検査、⑤逐次抜取検査、⑥調整型抜取検査、⑦抜取検査まとめ の7章全47題を演習できる問題集です。しっかり勉強しましょう。 |
抜取検査の初歩ですが、とても重要です。なぜなら、この記事の内容が抜取検査のベースだからです。
関連記事をご紹介します。
抜取検査(1回抜取)の関連記事
●全数検査と抜取検査と無検査の違いがわかる
●抜取検査はすべてOC曲線をベースに考える
●OC曲線(二項分布、ポアソン分布)を描こう
●OC曲線を作る超幾何分布、二項分布、ポアソン分布をマスターする
●【重要】計数規準型一回抜取検査表(JISZ9002)はOC曲線から作れる
●【簡単】AQL(合格品質水準)がすぐわかる
●【重要】抜取検査に欠かせない標準数がわかる
●抜取検査設計補助表(JISZ9002)はすごい!
●【重要】検査の誤りがOC曲線へ与える影響がわかる
①検査の種類を理解する
抜取検査の前に、検査とは何で、どんな検査があるかを理解しましょう。抜取検査の特性や適用場面が理解できます。最初に確認してほしい関連記事です。
 |
全数検査と抜取検査と無検査の違いがわかる 抜取検査を学ぶ前に、無検査、全数検査、抜取検査の違いを理解しましょう。それぞれの検査の用途が答えられ、また、検査の違いを不良率とコストの観点からまとめました。さらに臨界不良率の導出も説明します。抜取検査の序章を理解しましょう。 |
②抜取検査はOC曲線で考える
これが、抜取検査で最も重要です。抜取検査の関連記事のすべてにOC曲線が出てきます。
OC曲線の描き方を解説した関連記事です。ロット合格率の立式、OC曲線で重要な値の読み方を理解しましょう。
 |
抜取検査はすべてOC曲線をベースに考える 抜取検査はすべて、OC曲線をベースに考えていきます。OC曲線を構成する二項分布の導出や式の意味、OC曲線の描き方や描くために必要な制約条件について解説します。教科書では表面的な理解しかできない本当のOC曲線の意味がわかるようになり、自分で抜取検査が設計・計画できるようになります。 |
ぜひ、OC曲線の描くプログラムを活用ください。このプログラムがあれば、サンプル数nと合格判定数cを入れるだけでOC曲線が一瞬で描けます。OC曲線をいっぱい描かないと抜取検査の全容が理解できません。関連記事からプログラムを活用しましょう。二項分布も苦手なポアソン分布もあります。
 |
OC曲線(二項分布、ポアソン分布)を描こう 抜取検査はすべて、OC曲線をベースに考えます。OC曲線をすぐ描けるようプログラムを用意しました。二項分布、ポアソン分布両方のOC曲線を実際に描いて感触を確かめましょう。 |
OC曲線をマスターするには、二項分布、ポアソン分布、超幾何分布を理解する必要があります。3つの確率分布関数についてわかりやすく解説しています。ポアソン分布は、抜取検査とOC曲線に慣れると理解は早まります。
 |
OC曲線を作る超幾何分布、二項分布、ポアソン分布をマスターする 抜取検査はすべて、OC曲線をベースに考えます。OC曲線を構成する3つの確率分布は超幾何分布、二項分布、ポアソン分布です。それぞれの分布の関係を理解し、不良率または不良個数からOC曲線が描けるようになりましょう。 |
抜取検査の要である、OC曲線と描くプログラムが入手できたところまで来ました。
③抜取検査とOC曲線で理解しておくべきこと
抜取検査でよく使う表や変数について、関連記事で解説します。
抜取検査の最も基本である、計数規準型一回抜取検査の抜取表を解説します。単に抜取表の読み方だけ理解して終わるのではなく、抜取表の値を導出する過程を解説します。自分で計算できてはじめて、抜取表が習得できます。
 |
【重要】計数規準型一回抜取検査表(JISZ9002)はOC曲線から作れる 計数規準型一回抜取検査表(JISZ9002)は自分で作れることを知っていますか?検査表の見方を覚えるのではなく、検査表を自分で作ることで抜取検査の理論を理解することが重要です。抜取検査をマスターしたい方は必見です。 |
その他、たくさんの抜取検査を解説しますが、すべて抜取表の中の値を実際に計算していきます。
合格品質水準(AQL)は抜取検査の重要な変数です。JISや教科書も詳しくAQLの定義が解説しています。しかし、実際にどの値がAQLかがはっきり書いていません。関連記事でAQLの定義について、白黒はっきりさせました。
 |
【簡単】AQL(合格品質水準)がすぐわかる AQL(合格品質水準)はOC曲線上でどの値なのかが説明できますか?JISや教科書の説明ではよくわからないはずです。本記事では、AQLの定義をわかりやすく解説します。調整型抜取検査をマスターしたい方は必見です。 |
主抜取表のAQLと不良率の間隔がある一定の倍数になっています。これは何か?「標準数」です。なじみのない標準数について解説します。
 |
【重要】抜取検査に欠かせない標準数がわかる 規準型抜取検査や調整型抜取検査の抜取表の範囲や区分はどのように決めているかご存じですか?本記事は、抜取表の範囲や区分や、抜取表を自分で作る方法を解説します。抜取表の作り方が知りたい方は必見です。 |
抜取検査に慣れると、目にするのが抜取検査設計補助表です。この表と値の精度が高いので驚きました。計算機が未発達な時代でも近似式を使って正確な値を求める昔の先輩方に脱帽です。JIS規格の値とExcelから計算した値を比較しました。
JISの表は魔法の表ではなく、自分で計算して確かめる習慣をつけましょう。
 |
抜取検査設計補助表(JISZ9002)はすごい! 抜取検査にある抜取検査設計補助表の式やサンプル数の求め方を説明できますか?本記事では、サンプル数を導出する近似式とExcelを使ってOC曲線からサンプル数を導出する方法の2つを解説します。抜取検査をマスターしたい方は必見です。 |
検査の誤りによるOC曲線に与える影響を解説します。検査対象以外で検査ミスがある場合のOC曲線に与える影響を考えます。実務向きな関連記事です。
 |
【重要】検査の誤りがOC曲線へ与える影響がわかる 抜取検査のOC曲線は通常、試料の不良率pだけ考えて作ります。しかし、検査のミスの影響も調べたい場合もOC曲線で評価したいはずです。本記事は、試料の不良率以外の不良を含んだ場合のOC曲線への影響について解説します。 |
最も基本で重要な1回抜取方式の抜取検査を
マスターしましょう
まとめ
抜取検査(1回抜取)の基礎について解説しました。
- ①検査の種類を理解する
- ②抜取検査はOC曲線で考える
- ③抜取検査とOC曲線で理解しておくべきこと
抜取検査(1回抜取)の関連記事
●全数検査と抜取検査と無検査の違いがわかる
●抜取検査はすべてOC曲線をベースに考える
●OC曲線(二項分布、ポアソン分布)を描こう
●OC曲線を作る超幾何分布、二項分布、ポアソン分布をマスターする
●【重要】計数規準型一回抜取検査表(JISZ9002)はOC曲線から作れる
●【簡単】AQL(合格品質水準)がすぐわかる
●【重要】抜取検査に欠かせない標準数がわかる
●抜取検査設計補助表(JISZ9002)はすごい!
●【重要】検査の誤りがOC曲線へ与える影響がわかる