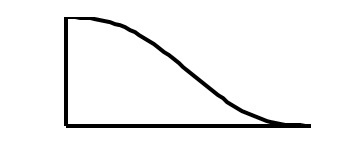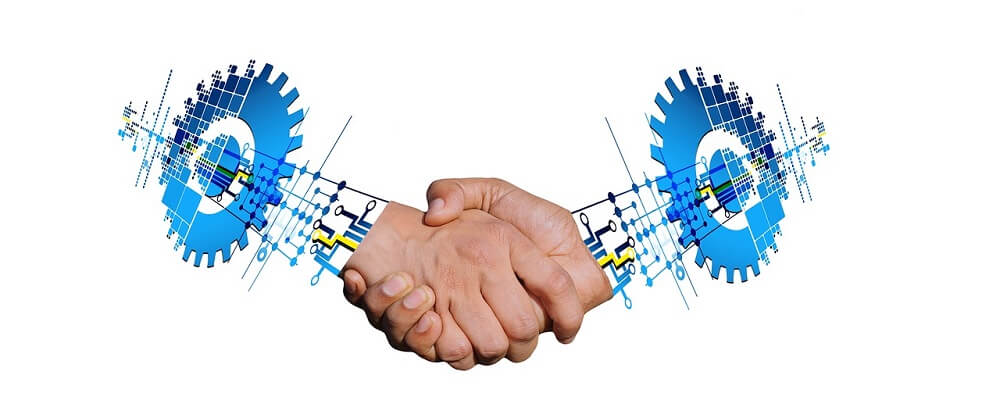「合格率5%程度のQC検定®1級をどうやったら合格できるかわからない」、「合格するために何が必要かがわからない」など、疑問に思いませんか?
こういう疑問に答えます。
本記事のテーマ
おさえておきたいポイント
- ➀QC検定®1級の合格率からわかる受験戦略(⇒その1で解説)
- ②QC検定®1級の難しさとは何か?(⇒その1で解説)
- ③QC検定®1級合格作戦
- ④私のQC検定®1級合格体験談
記事の信頼性
記事を書いている私は、QC検定®1級を一発合格したので、その秘訣をわかりやすく解説します。
QC検定®2級は合格した方の2割程度しか1級を受験されないのは、非常にもったいないです。上級リーダーとして活躍していただくため、より多くの方がQC検定®1級を受験、合格していただきたいです。
QC模試受験しよう!
 |
QC模試(品質技量の腕試し&QC検定®対策) 品質技量の実力を試したい! QC検定®合格対策に活用したい! 1,000円で提供します! 公式、暗記で終わらず、自分のものにできているかを試すオリジナル試験問題です! |
品質力が鍛えられる「QC塾」を是非ご利用ください。
 |
【2022/4/22up!】QC塾(有料)開設します! ブログでは、品質の勉強、実務、QC検定®に役立つ情報をアップして 「わかる」価値を提供していますが、「わかる」を「できる」に変える トレーニング塾「QC塾」を是非ご利用ください。 難解な品質が、すっきりわかり、指導できるレベルまで上達できます! |
合格戦略
その1では、試験合格の難しさを解説しました。本記事では、合格戦略を立てていきます。
 |
QC検定®1級合格戦略を伝授 その1【何が難しいのかを知る】 QC検定®1級は合格率が数%と難しいのは皆さんご存じです。でも、何がどのように難しいのかを知らず、闇雲に試験勉強していませんか?勝つには、相手をまず知ることです。QC検定®1級を一発合格した私が、試験の難しさを解説し、合格戦略を提案します。 |
- 合格できる戦略を立てること(本記事)
- 私の体験談を見て参考いただくこと(本記事)
①QC検定®と品質管理検定®は、一般財団法人日本規格協会の登録商標です。
➁このコンテンツは、一般財団法人日本規格協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。
➂QCプラネッツは、QC検定®と品質管理検定®の商標使用許可を受けています。
●リンクページ
③QC検定®1級合格作戦
下の5つが重要です。
- 準1級合格狙いは無意味
- 十分な演習問題を確保すること
- 解くスピードを上げる練習が必要
- 試験時間内に解くテクニック
- 勉強方法
準1級合格狙いは無意味
下の記事に書いたとおり、1問にかけてよい制限時間が全く異なるため、勉強方法が全く違います。準1級合格したら、次は1級とはなかなかできません。最初から1級合格を狙うべきです。
 |
QC検定®1級合格戦略を伝授 その1【何が難しいのかを知る】 QC検定®1級は合格率が数%と難しいのは皆さんご存じです。でも、何がどのように難しいのかを知らず、闇雲に試験勉強していませんか?勝つには、相手をまず知ることです。QC検定®1級を一発合格した私が、試験の難しさを解説し、合格戦略を提案します。 |
十分な演習問題を確保すること
QC検定®2級なら、市販の過去問題集(6回分収録)で十分ですが、1級は全然足りません。そこで、2つの方法が必要です。
- 絶版である1回目からの過去問題集を入手する
- QCプラネッツの記事を全部読むこと
私が書いている、QCプラネッツではQC1級合格以上の高いレベルを目指して、上級の品質管理・品質保証技術者になるために必要な記事をどんどん書いていきます。各単元の演習問題や応用問題も載せていきますので、活用ください。
解くスピードを上げる練習が必要
の3段階でレベルアップしましょう
①わかる!
QC検定®1級の試験範囲は広く、内容も難解です。まず、概念や公式の使い方を何度か読んで、「理解できる!」を増やしましょう。
回帰分析、検定、確率分布、文章題から入って理解を増やし慣れてきましょう。慣れたら、難しい実験計画法、パラメータ設計に進んでいきましょう
②できる!
問題集を解く段階ですが、最初は答えを見て解き方をほぼ暗記しましょう。最初からできなくて問題ありません。何問か解き方を見て、頭で整理しながら理解を深めて、手で計算しながら感触を確かめましょう。
③時間内にできる!
②のできる!で解いた問題を何度も復習しましょう。新たな問題に手を出さず、過去問題集をできるだけ集めて解いていきましょう。少しずつスピードが上がってきます。
試験時間内に解くテクニック
問題数が多く、文章も長い問題をどうやって1問数十秒以内で解くのか?ですが、別途解説します。
QC検定®2級受験の方で、時間が余った人は読み飛ばしてもOKです。でも、一度でも時間が足りない方は解説を読んでください。1級はもっと時間が足りないはずです。
解説を読んだあとは、反復練習量で解くスピードが決まります。頭の良さより反復練習量です。
勉強方法
勉強時間を作ること
仕事が、家事が、育児が、…と仕事と家庭が忙しい方が受験されるQC検定®です。
時間は自ら作り出しましょう。忙しい人ほど合格しているのも事実です。
●早朝勉強時間を作る
●通勤時間に勉強時間を作る
●出張や客先への移動時間は最強の勉強時間
●友人や同僚の飲み会を控えて勉強時間に充てる
●その他アイドリング時間を勉強時間にできないかを考える
私の考えですが、
結構、時間ができるものです。QC検定®1級の合格以上に、勉強時間捻出によって人生がより高いレベルに変わるはずです
勉強方法
の3段階でレベルアップしましょう
まず、①わかる 内容を増やして自信つけながら楽しみましょう。
②③は反復練習が重要です。何度も解きましょう。
QCプラネッツでは上級品質管理技術者を目指す方のための役立つ記事をどんどん書きますので、どんどん活用ください。
④私のQC検定®1級合格体験談
私の体験を参考にいただけると幸いです。
合格までの1年間
| ヶ月 | やったこと | 感触 | 完成度% |
| -12 | QC検定®2級合格 | 1級合格は無理! | 1 |
| -11 | QC検定®1級市販教科書 すべて購入 |
とりあえず買っておこう。 | 1 |
| -10 | 教科書を読むが理解できず | 1級合格は無理! | 1 |
| -9 | 教科書を読むが理解できず | 1級合格は無理! | 1 |
| -8 | 教科書を読むが理解できず | 1級合格は無理! | 1 |
| -7 | 多変量解析、実験計画法の練習 | 1級合格は無理! | 1 |
| -6 | 3月受験を諦める | 1級合格は無理! | 5 |
| -5 | 少し教科書の内容がわかってきた | 会社の目標管理に 受験と書いたので、決心。 |
10 |
| -4 | 論述問題の過去問を解いた | 書けることはかけたが、 受かるレベルではない。 |
15 |
| -3 | 過去問4回分を解いた | 4回分解いても足りない。 中古で全回過去問収集。 |
25 |
| -2 | 過去全回を解いた | 10回分解いて、 ようやくコツがつかめた。 |
40 |
| -1 | 過去全回を解いた | 試験半月前に全問クリア、 さらに問題研究へ。 |
85 |
| 0 | 受験 | 疲れた。難しく、 不合格を確信したが合格。 |
100 |
まず、次回受験としたが、1回はパスしました。それで1年間の流れとなっています。半年で合格はよほど試験範囲の基礎が分かっていないと厳しいと思います。
最初の半年間(-12~-6か月)までは、合格の感触が全くありませんでした。教科書を読んでもわからないものが多かったためです。
途中で、過去問を集めた者勝ちとわかり、Amazon,楽天、メルカリを駆使して中古の絶版過去問を買いあさり全問解こうと決意しました。
試験-1.5か月までに、最もできなかった実験計画法がスムーズに解けるようになり、合格を確信しました。
論述は、技術士2次試験を何度か挑戦しているため、文章の書くことにはそれほど問題はありませんでした。
勉強で苦労した点
- 内容がわからないものが多かったこと
- できる!という感触がなかなか出なかったこと
- 周りに1級合格者がいないためモチベーションの維持が大変
内容がわからないものが多かったこと
わからないは2つあります。
- 解き方がマスターできていない場合
- 公式や理論の成り立ちがなぜそうなっているのかがわからない場合
1.解き方がマスターできていない場合は、試験勉強の初期中期によくあったため、何度も公式を練習して、意味はわからないけど答えは出る状態になるようにして自信をつけていきました。
2.公式や理論の成り立ちは、合格後もほとんど理解しておらず、単に試験合格しただけでした。そのため、さらに研究してわかった知見を、わかりやすくブログで紹介するように決意しました。
できる!という感触がなかなか出なかったこと
「サンプリングの分散の公式がなかなか覚えられない」、「実験計画法の直交表の意味がわからない」、「信頼性工学の信頼性区間はなぜχ2乗分布使うの?」などなど、わけのわからない内容が多く、解ける問題が増えても何をやっているのかさっぱりわからない感触がしばらく続きました。
私と同じ悩みを抱えないためにも、QCプラネッツでどんどん記事を書いて解説します。
周りに1級合格者がいないためモチベーションの維持が大変
品質管理部門の人の多くがQC検定®2級で終わっていて、1級対策を教えてくれる人がいませんでした。自分なりに仮説を立てて、勉強方法や必要なものを集めて仕上げていくしかありませんでした。
QC検定®2級合格者の80%の人が1級を受験しないので、その方々にも是非受験していただき、品質管理のレベル向上につなげるべく、私もできるだけ努力させていただきます。
勉強で困ったら、お問い合わせで書いていただいてもOKです! 応援させていただきます!!
受験するだけでも偉い!
頑張っていきましょう!よろしくお願いいたします。
まとめ
QC検定®1級を合格するための戦略を解説しました。本記事では、合格に必要な戦略と私の体験談について解説しました。
- ➀QC検定®1級の合格率からわかる受験戦略(⇒その1で解説)
- ②QC検定®1級の難しさとは何か?(⇒その1で解説)
- ③QC検定®1級合格作戦<1li>
- ④私のQC検定®1級合格体験談
合格戦略
その1では、試験合格の難しさを解説しました。本記事では、合格戦略を立てていきます。
 |
QC検定®1級合格戦略を伝授 その1【何が難しいのかを知る】 QC検定®1級は合格率が数%と難しいのは皆さんご存じです。でも、何がどのように難しいのかを知らず、闇雲に試験勉強していませんか?勝つには、相手をまず知ることです。QC検定®1級を一発合格した私が、試験の難しさを解説し、合格戦略を提案します。 |