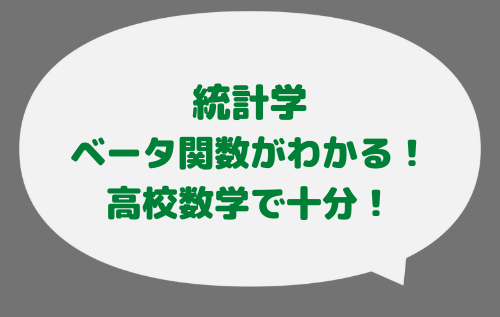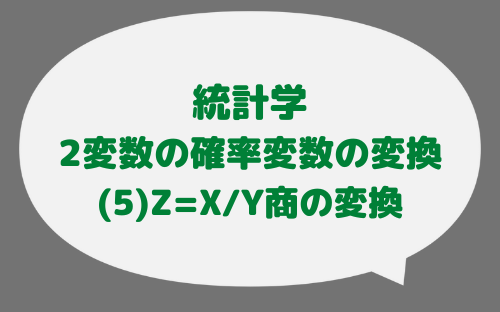★ 本記事のテーマ
- ①不完全ベータ関数とは
- ➁不完全ベータ関数は手計算できない
- ➂プログラムを使って不完全ベータ関数を計算しよう
★ QCに必要な数学問題集を販売します!
 |
QC検定®1級、2級、統計検定2級以上の数学スキルを磨くのに苦戦していませんか? 広大すぎる統計学、微分積分からQC・統計に勝てるための60題に厳選した問題集を紹介します。勉強してスキルを高めましょう。 |
①不完全ベータ関数とは
ベータ関数とは
詳細は関連記事をご覧ください。
 |
ベータ関数がよくわかる 本記事ではベータ関数の導出方法や性質、ガンマ関数との関係をわかりやすく解説します。大学の数学のような難解な説明は一切しません。ベータ関数は受験でも統計学でも重要です。 |
式は
=\(\frac{(m-1)!(n-1)!}{(m+n-1)!}\)
不完全ベータ関数とは
積分区間が違います。
=??
大した差ではないですが、計算の大変さに違いがあります。
不完全ベータ関数はメジアンランク法に使う
信頼性工学のメジアンランク法で不完全ベータ関数を使うので、解説します。
詳細は関連記事をご覧ください。
 |
メジアンランク法は説明できますか? 本記事では順序統計量をベースにメジアンランク法をわかりやすく解説し、実際に解析しながら、公式の理解が深める事ができます。信頼性工学を学ぶ人は必読です。 |
➁不完全ベータ関数は手計算できない
完全なベータ関数を部分積分する
まず、部分積分すると、漸化式が作れます。
\(\displaystyle \int_{0}^{1} x^{m-1}(1-x)^{n-1} dx\)を部分積分すると、
\(\left[ \frac{1}{m}x^{m} (1-x)^{n-1} \right]_{1}^{0}\)
=\(\displaystyle \int_{0}^{1} x^{m-1}(1-x)^{n-1} dx\)
+\(\frac{n-1}{m}\displaystyle \int_{0}^{1} x^{m}(-1)(1-x)^{n-2} dx\)
(左辺)= \(\left[ \frac{1}{m}x^{m} (1-x)^{n-1} \right]_{1}^{0}\)は0です。
(右辺)=\(I(m.n)\)-\(\frac{n-1}{m}I(m+1,n-1)\)
となり、
0=\(I(m.n)\)-\(\frac{n-1}{m}I(m+1,n-1)\)
から漸化式が作れて、
積分\(I(m.n)\)= \(\displaystyle \int_{0}^{1} x^{m-1}(1-x)^{n-1} dx\)が計算できます。
不完全なベータ関数を部分積分する
同様に積分区間が[0,z]においても、部分積分すると、漸化式が作れます。
\(\displaystyle \int_{0}^{z} x^{m-1}(1-x)^{n-1} dx\)を部分積分すると、
\(\left[ \frac{1}{m}x^{m} (1-x)^{n-1} \right]_{z}^{0}\)
=\(\displaystyle \int_{0}^{z} x^{m-1}(1-x)^{n-1} dx\)
+\(\frac{n-1}{m}\displaystyle \int_{0}^{z} x^{m}(-1)(1-x)^{n-2} dx\)
(左辺)= \(\left[ \frac{1}{m}x^{m} (1-x)^{n-1} \right]_{z}^{0}\)は0にならず、zの変数になります。です。
(右辺)=\(I(m.n)\)-\(\frac{n-1}{m}I(m+1,n-1)\)
となり、
(左辺のzの式)=\(I(m.n)\)-\(\frac{n-1}{m}I(m+1,n-1)\)
から漸化式が作れますが、
なので、
➂プログラムを使って不完全ベータ関数を計算しよう
二項定理を使って、不完全ベータ関数の計算式を作る
では、やってみましょう。
\(B(m,n)= \displaystyle \int_{0}^{z} x^{m-1}(1-x)^{n-1} dx\)
ここで、\((1-x)^{n-1}\)を二項定理で展開します。大丈夫ですか?
QCには欠かせない二項定理、統計学、抜取検査、信頼性工学と大活躍です。
\((1-x)^{n-1}\)=\(\sum_{r=0}^{n-1} {}_{n-1}C_r 1^r (-x)^{n-1-r}\)
これを積分式に代入します。ちょっと難しいけど、頑張りましょう。
\(B(m,n)= \displaystyle \int_{0}^{z} {}_{n-1}C_r x^{m-1}(1-x)^{n-1} dx\)
= \(\displaystyle \int_{0}^{z} x^{m-1} \sum_{r=0}^{n-1} {}_{n-1}C_r 1^r (-x)^{n-1-r} dx\)
\(x\)の次数を合計します。
= \(\displaystyle \int_{0}^{z} \sum_{r=0}^{n-1} {}_{n-1}C_r (-1)^{n-1-r} x^{n+m-2-r} dx\)
\(x\)の整式なので、積分すると、
\(\left[ \sum_{r=0}^{n-1} {}_{n-1}C_r (-1)^{n-1-r} \frac{1}{n+m-1-r} x^{n+m-1-r} \right]_{z}^{0}\)
=\( \sum_{r=0}^{n-1} {}_{n-1}C_r (-1)^{n-1-r} \frac{1}{n+m-1-r} z^{n+m-1-r} \)
となります。これをプログラムに入れて計算させます。
プログラム(Excel VBA)を使って不完全ベータ関数を計算しよう
では、プログラムを公開します。実際、いじってみてください。
★ VBAプログラム例
1. Sub gam()
2.
3. gok = 0 ‘B(m,n) 初期化
4.
5. Dim nn As Long, mm As Long
6. nn = Cells(2, 3): mm = Cells(3, 3): zz = Cells(4, 3)
‘自然数n,mと、実数(0~1)zをセルに代入
7.
8. For i1 = 1 To nn ‘nの値 1~nまで
9. Cells(i1 + 6, 2) = i1
10. For j1 = 1 To mm ‘mの値 1~mまで
11. Cells(6, j1 + 2) = j1
12. gok = 0 ‘初期化
13. For k1 = 0 To i1 – 1
‘rの値 0~n-1まで(二項定理)
14.
15. ‘積分の計算
16. gok = gok + WorksheetFunction.Combin(i1 – 1, k1) *
((-1) ^ (i1 – 1 – k1))
* (1 / (i1 + j1 – k1 – 1))
* (zz ^ (i1 + j1 – k1 – 1))
17. Next k1
18. Cells(i1 + 6, j1 + 2) = gok ‘結果を出力
19. Next j1
20. Next i1
21.
22. End Sub
計算例
★ z=1のとき
z=1のときは、完全なベータ関数ですから、
=\(\frac{(m-1)!(n-1)!}{(m+n-1)!}\)
の値と一致します。
上のプログラムの計算結果は

となり、
\(B(m,n)\)= \(\frac{(m-1)!(n-1)!}{(m+n-1)!}\)
と一致します。
確かに、\(m=4,n=5\)を代入するとB(m,n)は
\(B(4,5)\)= \(\frac{(4-1)!(5-1)!}{(4+5-1)!}\)
= \(\frac{3!・4!}{8!}\)
=\(\frac{1}{280}\)
=0.003571
図を見ると確かに、 \(m=4,n=5\)のときは、0.003571となり、計算結果が一致しています。
★ z=zのとき
テキトウな値を入れて、確認しましょう。

z=0.5の場合を計算しましたが、0から1の間の実数を入れれば、上のプログラムで一瞬で計算してくれます。是非活用ください!
できましたね。
まとめ
「不完全ベータ関数が計算できる」を解説しました。
- ①不完全ベータ関数とは
- ➁不完全ベータ関数は手計算できない
- ➂プログラムを使って不完全ベータ関数を計算しよう
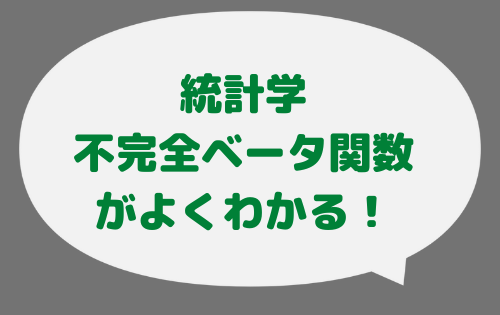
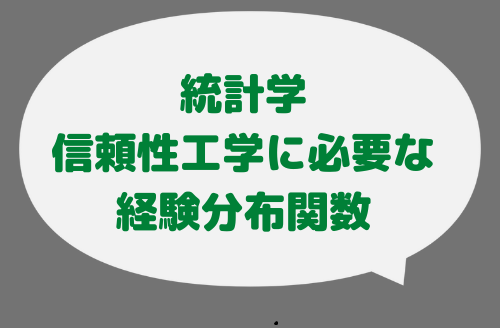



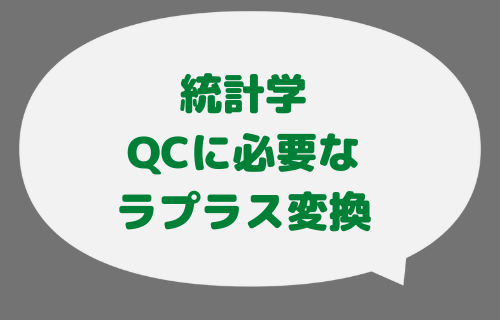


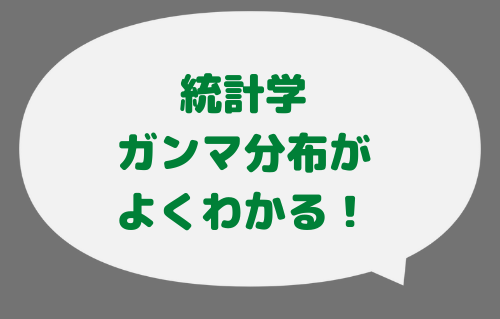


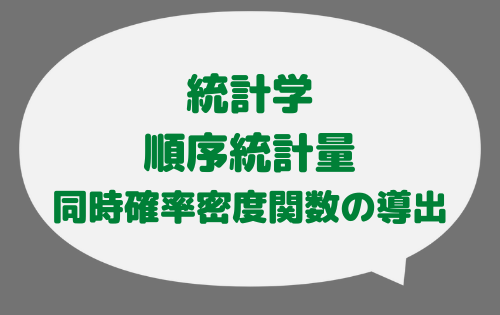






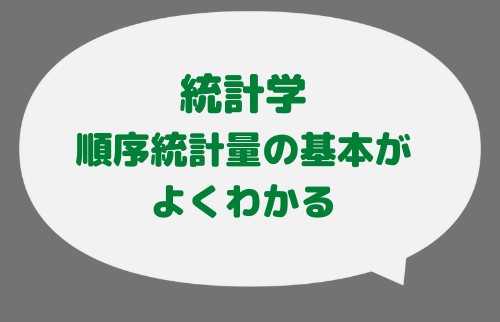


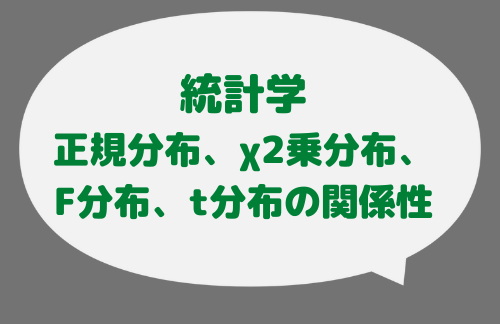







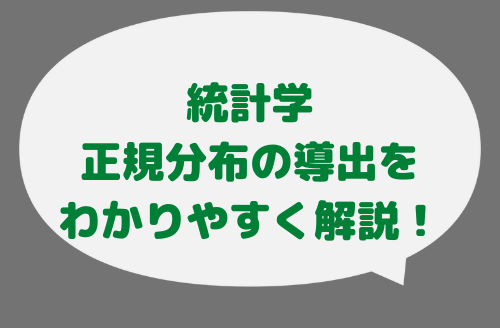
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/21e91abf.1d5906ad.21e91ac0.35595f72/?me_id=1213310&item_id=15782065&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1889%2F9784254121889.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)