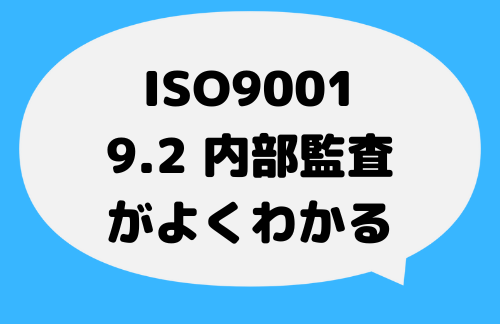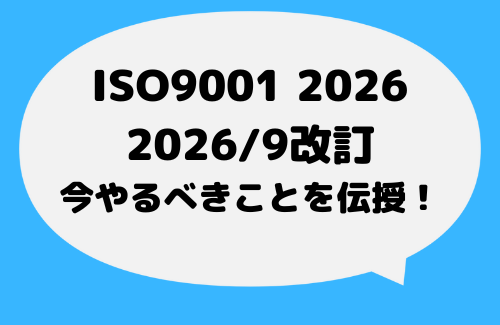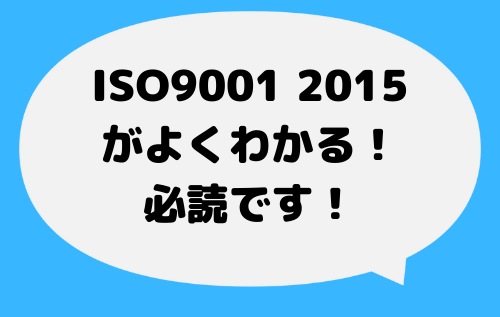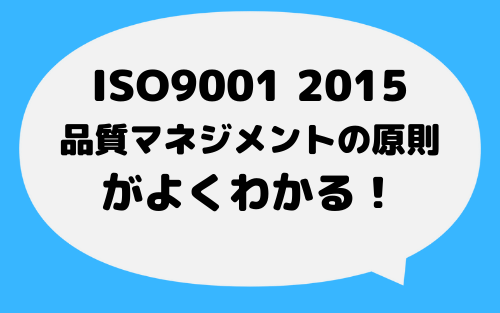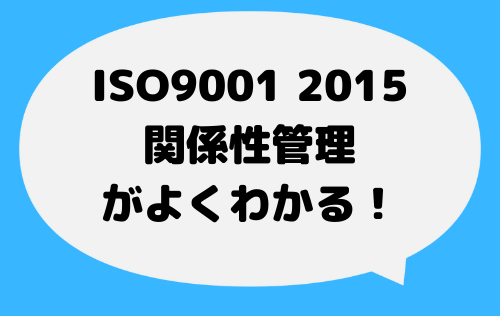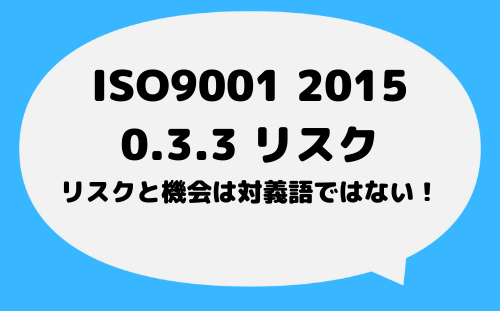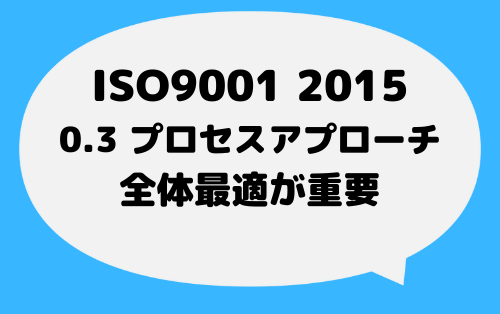QCプラネッツのISO9001 2015関連ブログを多くの方に読んでいただき、とてもうれしいです。ブログの内容をさらにパワーアップして更新しました。
★ 本記事のテーマ
ISO9001 2015 0.3 プロセスアプローチがわかる
- ①要求事項を見る
- ②「プロセスアプローチ」は言葉がおかしい
- ③「プロセスアプローチ」とは全体最適化
- ④目標への活動は全体最適化を考えること
プロセスアプローチは重要な用語。
でも言葉の意味がわからないし、理解できない。
何をしたらよいかイメージがつかない。
プロセスアプローチって何なん?
ISO,品質の人に聞いても、意味不明だし。
わかりやすく解説します。
①ISO9001要求事項、JISハンドブックの解説
ISO9001要求事項
0.3 プロセスアプローチ
0.3.1 一般
この規格は,顧客要求事項を満たすことによって顧客満足を向上させるために,品質マネジメントシステムを構築し,実施し,その品質マネジメントシステムの有効性を改善する際に,プロセスアプローチを採用することを促進する。プロセスアプローチの採用に不可欠と考えられる特定の要求事項を4.4に規定している。 システムとして相互に関連するプロセスを理解し,マネジメントすることは,組織が効果的かつ効率的に意図した結果を達成する上で役立つ。組織は,このアプローチによって,システムのプロセス間の相互関係及び相互依存性を管理することができ,それによって,組織の全体的なパフォーマンスを向上させることができる。 プロセスアプローチは,組織の品質方針及び戦略的な方向性に従って意図した結果を達成するために,プロセス及びその相互作用を体系的に定義し,マネジメントすることに関わる。PDCAサイクル(0.3.2参照)を,機会の利用及び望ましくない結果の防止を目指すリスクに基づく考え方(0.3.3参照)に全体的な焦点を当てて用いることで,プロセス及びシステム全体をマネジメントすることができる。 品質マネジメントシステムでプロセスアプローチを適用すると,次の事項が可能になる。
a) 要求事項の理解及びその一貫した充足
b) 付加価値の点からの,プロセスの検討
c) 効果的なプロセスパフォーマンスの達成
d) データ及び情報の評価に基づく,プロセスの改善
結局、プロセスアプローチって何なん?
②プロセスアプローチは言葉がおかしい
理解しにくい理由は言葉がおかしい
まず、アプローチは「近づける」で、プロセスはインプットとアウトプットへ「近づける」と同じ用語なんです。
変な用語を、専門用語のように解釈するから、さらにわからなくなります。
変な言葉なので、自分なりにわかりやすい別の用語を使えばよいです。
相手に伝えて品質を向上するのが目的だから。言葉の定義は所詮、手段にすぎない。
せっかくなので、3つ考えてみましょう。
- アプローチって何?
- プロセスって何?
- プロセスをアプローチって何?
アプローチって何?
そもそも、「アプローチ」は、目的語が必要ですよね。
○○を「アプローチ」
(ゴルフのように、カップへアプローチとか言います)
また、目的語の○○はゴールを意味する言葉が入りやすいですよね。
●顧客へアプローチする(顧客ターゲットがゴール)
●ゴルフの、カップへアプローチ(勝つことがゴール)

じゃー、
●プロセスのアプローチ(ん! 何がゴールなんだ!)
プロセスのアプローチ(ん! 何がゴールなんだ!)
まだ、よくわからない。
プロセスって何?
プロセスは、関連記事【ISO9001 2015 8_1 運用の計画及び管理がわかる】で解説したように、
プロセスは、インプットをアウトプットに変換(アプローチ)するもの。

プロセスは工程だけでなく、広い意味でとらえる。
ある意味、プロセスもアプローチするものなんです。
「プロセス」=「アプローチ」だから
プロセスアプローチは
●アプローチをアプローチする?
●プロセスをプロセスする?
さらに、わけがわからなくなってしまった!
プロセスをアプローチって何?
そろそろ、プロセスアプローチと言う変な用語は、概念だけ理解して、別の用語に変えましょう。
「あるプロセス」を「あるプロセス」へアプローチすると考えると
「イケてない現状のプロセス」を
「イケてる理想のプロセス」へ
「アプローチ」する
となる。

「プロセスアプローチ」が理解しやすいはずです。
③プロセスアプローチとは全体最適化
プロセスアプローチは、「イケてない現状のプロセス」を「イケてる理想のプロセス」へ「アプローチ」すると解釈しました。
品質活動すると、プロセスアプローチの意味はもう少し味付けが必要です。
品質目標達成するためのプロセスアプローチ
品質目標を達成するために、「イケてない現状のプロセス」を「イケてる理想のプロセス」へ「アプローチ」する必要があります。
大事なのは、
品質目標達成のためには、全体最適化が必須
プロセスアプローチは「全体最適」の意味合いが強くなる。
つまり、組織全体を最適化した状態が「イケてる理想のプロセス」の集まりとなるのです。
組織で運用する品質マネジメントシステムは
組織全体をよくするため、つまり、組織全体を最適化するためにある。
部分最適ではダメで、全体最適を考えるように、各プロセスを改善していく必要があります。
④品質目標は全体最適化を考えること
ここで、プロセスアプローチの例を挙げます。
歩留まりが70%で良品が出ず困っている。
歩留まりを99%に向上するように、品質目標を掲げて活動してほしい。
と、トップから指示が下りました。
部分最適と全体最適の結果の違いを見てみましょう。
品質目標を部分最適化しても効果が出ない

プロセスアプローチの概念「全体最適にアプローチする」が無いと、各部門は、自分たちの領域内で最適化(ベストをつくす)します。
これ自体は良い事ですが、ある部門の最適化と別の部門の最適化が必ずしもつながるわけではありません。
上図のように、
●受注・仕様では、顧客要求事項の確実な伝達を達成した。
●設計・開発では、設計精度を飛躍的に向上させた。
それぞれいい感じですが、
設計・開発しにくい顧客要求事項があれば、歩留まりは向上しませんよね。
上図のように、
●設計・開発では、設計精度を飛躍的に向上させた。
●製造では、ポカミス防止に成功した。
それぞれいい感じですが、
製造しにくい設計図なら、歩留まりは向上しませんよね。
部分最適しても、全体で結果が出ないのは、やってても意味が無い。
全体で良い結果になるように品質マネジメントシステムは要求してきます。
品質目標を達成するために全体最適を狙う
品質目標を達成するために、全体を俯瞰してから各部門がやるべき施策を考えると、下図のように変化します。

- 歩留まり低下する原因を全体で考える
- 仮に力量ばらつきが原因と決めたら、力量ばらつき低減策を全体で講じる
- 各部門へ最適化が伝播するので、全体最適化できる
たしかに、各部門の施策がかわりましたよね。
| – |
部分最適 |
全体最適 |
| 受注・仕様 |
顧客要求事項の
確実な伝達 |
顧客要求提案 |
| 設計・開発 |
設計精度向上 |
作業標準
自動設計 |
| 購買 |
部材検査厳格化 |
製品知識強化 |
| 製造 |
ポカミス防止 |
作業標準化
技量継承 |
●受注・仕様は、顧客要求の伝達から、力量ばらつき低減のために要求提案に変わり、
●設計・開発は、精度向上から、力量を考慮した標準化や自動化に変わり、
●購買は、検査から力量向上のための製品知識強化に変わり、
●製造は、ミス防止から、力量向上のための標準化、技量継承に変わりました。
ばらばらに動くのではなく、1つの課題を全体で解決した方が確かに目標達成できるとわかります。全体最適化へアプローチするのがプロセスアプローチです。
プロセスアプローチが理解できましたね!
⑤プロセスアプローチができる組織になるには
プロセスアプローチができる組織になるには、何が必要なのか?
3点あります。
- 各部門へ指示するトップの本気とトップへの尊敬
- 各部門間の密な情報共有
- 仕組みづくりより、日々の業務の積み重ね
各部門へ指示するトップの本気とトップへの尊敬
全体最適化するためには、関係部門の関係者が自発的に行動する必要があります。それを後押しする上の姿勢が必要です。
担当に丸投げ、任せっきりなると、部門間に壁が生まれ、部分最適に陥りやすくなります。
全部門を横断した会議、情報収集や、トップからのメッセージを定期的に出していくことが重要です。
仕組みだけ作っても、有機的に動きません。ドライブするためのリーダシップが求められます。
各部門間の密な情報共有
営業は営業、設計は設計、製造は工場と切り分けるのではなく、レビューや顧客打合せ対応にて、それぞれの担当者が同席して随時情報共有する必要があります。
技術的な課題、工程の課題があり、それが仕様を変えることで解決するならば、顧客へ仕様提案することができます。上流⇒下流の流れに限らず、全組織が目標達成するためのネックとなる箇所をともに解決することが重要です。
受注の打合せに、設計・製造担当者を同席させたり、製造の検査に営業を立ち会わせるなど、常に1つの目標に対してバラで活動しないことが重要です。
担当者どうしの課題が見えることでそれぞれの課題を解決する策を見つけ出すようになり、全体最適につながります。
仕組みづくりより、日々の業務の積み重ね
すぐれた仕組みを作りこむのも大事ですが、仕組みだけで自動的に品質を作りこむことはできません。
泥臭いですが、人々が積極的に参加して、自分たちのアウトプットが最大になるように日々業務をこなすことが大事です。
自分の業務範囲だけで考えずに、担当業務が製品全体のどこに影響を受けるかを意識して取り組んでいきましょう。
プロセスアプローチを機能させる秘訣は、仕組みではなく、泥臭いけど、全体を意識して行動する人々にかかっています。
まとめ
ISO9001 2015 0.3 プロセスアプローチ をわかりやすく解説しました。
- ①要求事項の簡略化
- ②プロセスアプローチは言葉がおかしい
- ③プロセスアプローチとは全体最適化
- ④品質目標は全体最適化を考えること
- ⑤プロセスアプローチができる組織になるには