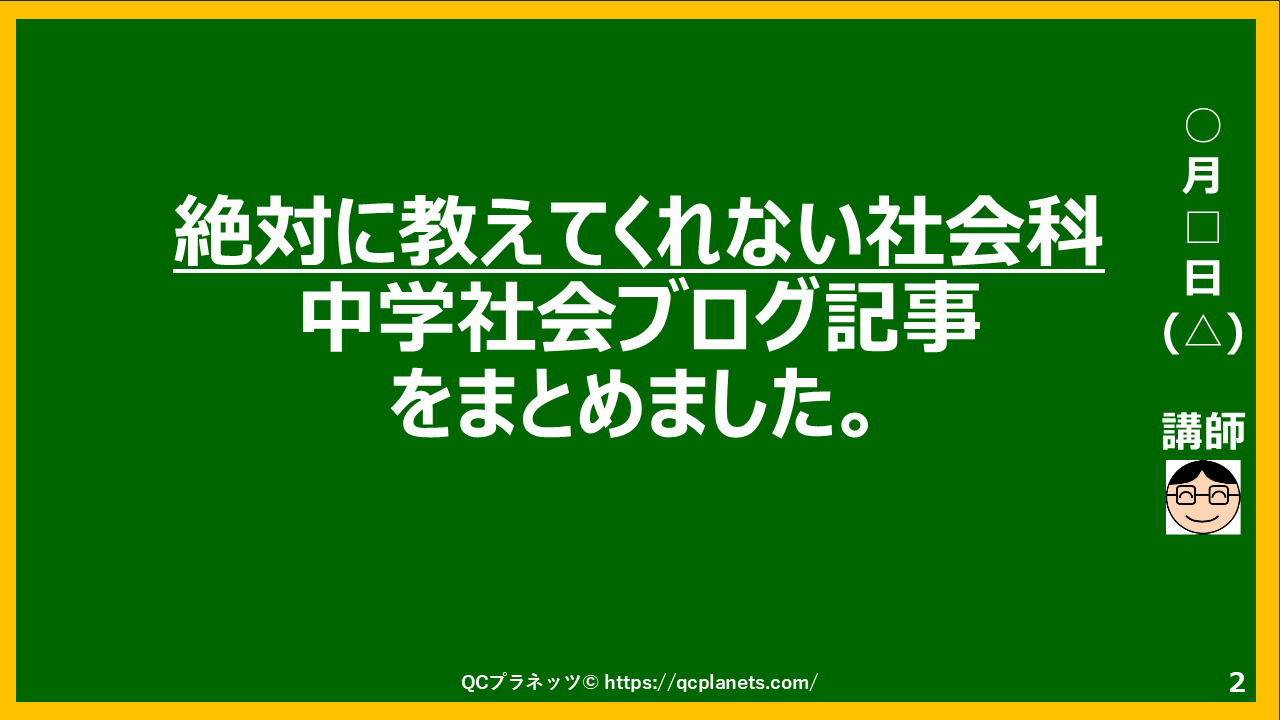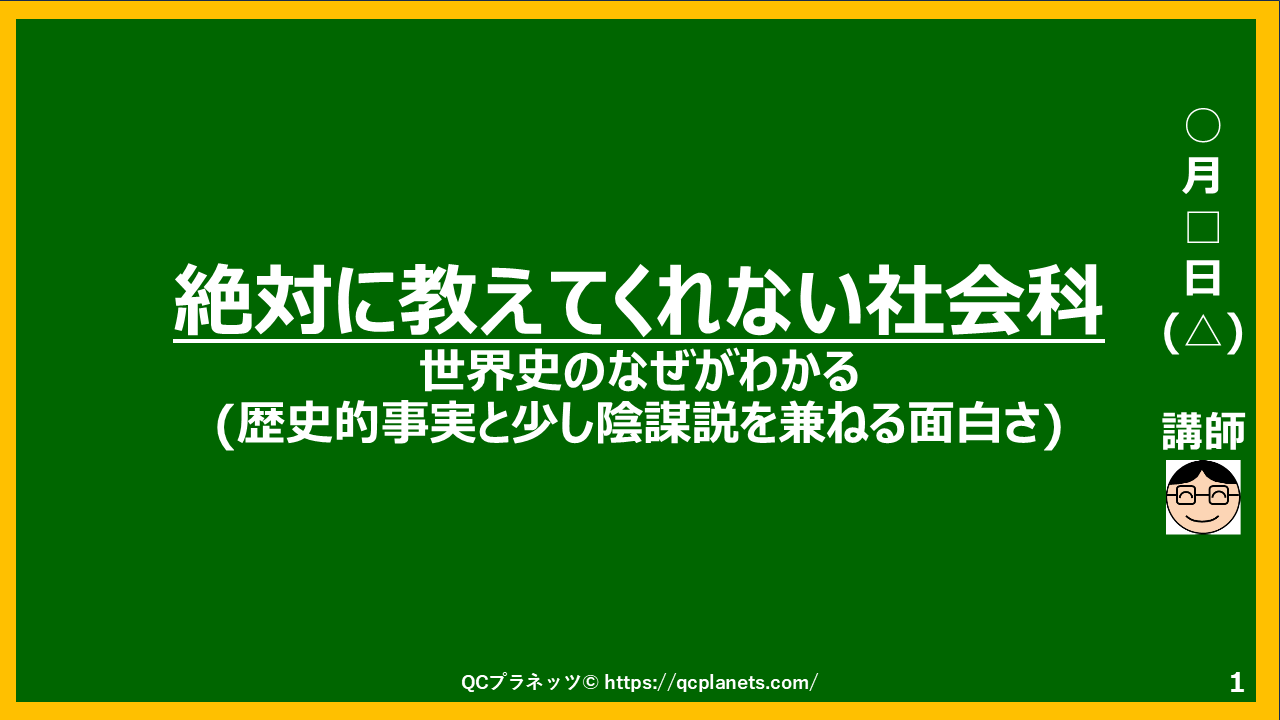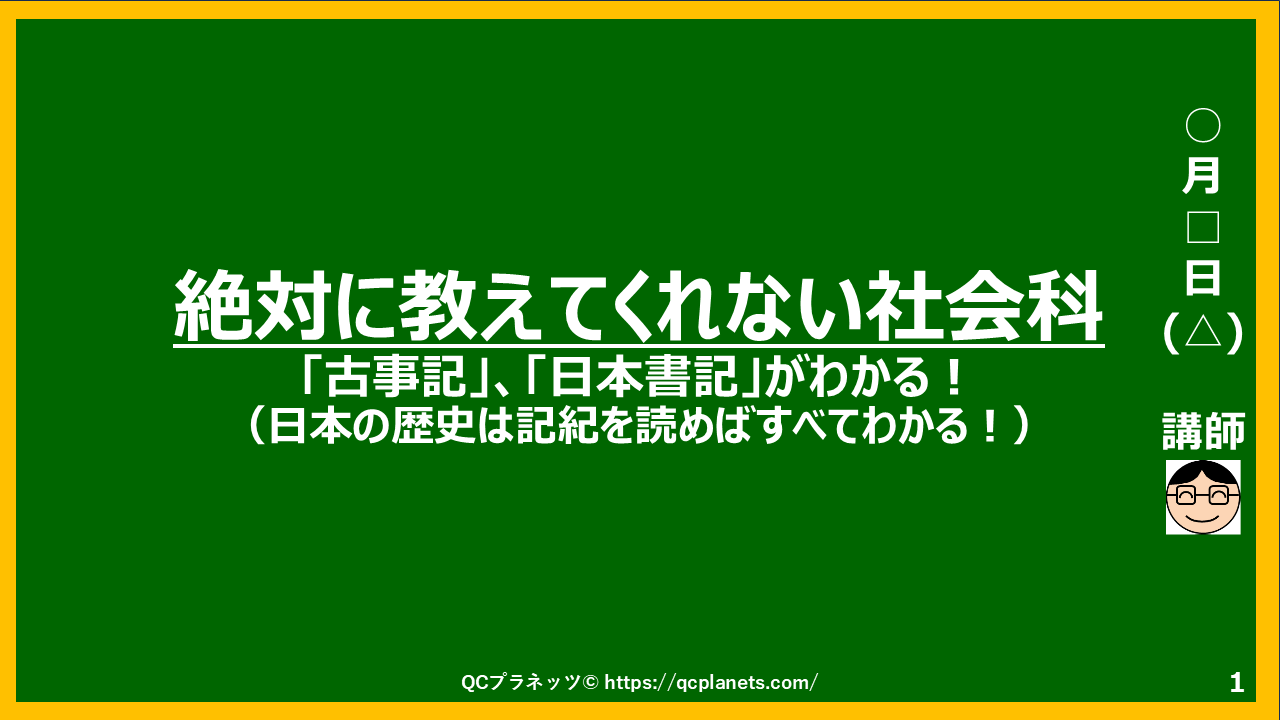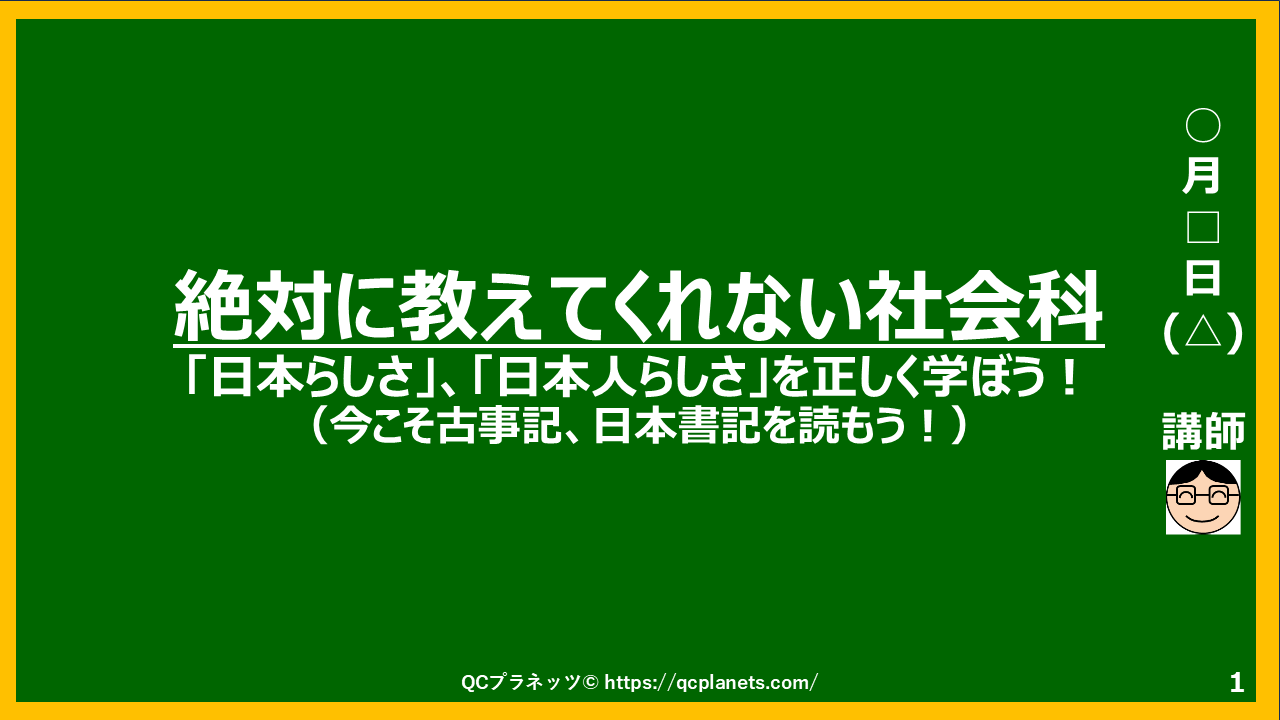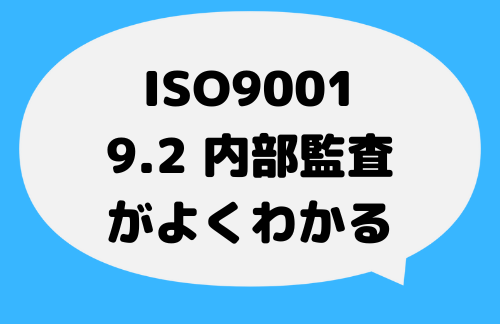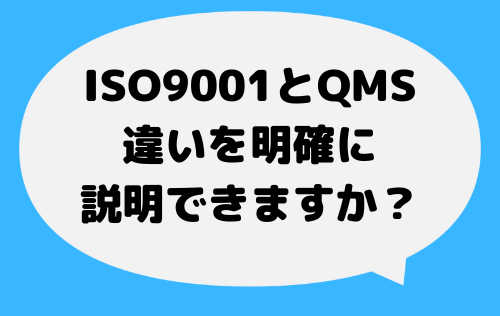★ 本記事のテーマ
古事記、日本書記(記紀)がわかる
★おさえておきたいポイント
学校や試験対策の社会では、
真相はわからない!
自分で調べて考え抜く
本当の社会科を勉強しよう!
★ 先に言っておきます!
以下、「ですます調」から「である調」に変えて解説します。
長文になりますが、記紀を何度も読んでも理解が難しいため、概要を先にこの記事を読んだ方が良いと思います。記紀の概要を理解するまで、QCプラネッツは数カ月かかりました。

①古事記、日本書記を読む理由
世界の歴史、日本の歴史を学ぶとは、出来事を暗記することではなく、それが起きた理由・背景を学ぶことです。「What,Where,When,How」ではなく、「Why?」が大事です。特に日本史(国史)に対して、あらゆる出来事を「Why?」で考え抜いた先に、見えたのが、
「日本、日本人固有の理由や背景によって、他地域ではありえない出来事の結果が起きている。それはなぜか?」
具体的には、
- 初めての武家政治。承久の乱後、北条氏は国の支配者ではなく執権としてい続けたこと。
- 武家政治による支配が700年も続いたが、京では天皇と朝廷がいた。海外から見たらトップが2人いることになること。
- GHQにとって、敵国のトップ天皇を戦後も維持したこと。
他地域なら、天皇というトップはいなくなる歴史になります。でも日本はそうならなかった。だからといって、天皇は神でなく、支配者でもありません。日本って不思議ですよね。
それは「日本、日本人らしさ」という独特な理由があるからです。
では、それがわかる書物はないのでしょうか? いやあります。それが700年代に編纂された古事記と日本書記です。
我々の疑問はすでに1300年前の先輩たちが教えてくれています。
人間の本質は1000年経過しても変わりません。先輩からのメッセージを今、正しく理解する時期です。
②(結論)記紀から学ぶこと
本記事は長文なので、先に結論を挙げます。その後、あらすじを紹介します。
編纂された経緯を理解する
編纂は飛鳥時代の西暦700年代です。
国外、国内に対して、国家戦略があったため編纂された国家プロジェクトでした。
国外対策は、超大国中国(隋、唐)の支配リスク、そして、朝鮮半島との関わりによる日本の防衛戦略が必要であり、国内対策は、蝦夷(東北)など、まだ日本列島で大和朝廷が平定していない地域を含めた統治強化が必要だったことがあります。
★国外対策
巨大国家中国(隋、唐)が世界の中心として、「冊封体制」をとっており、周辺諸国は「属国」として扱う傾向があった。日本は外部(中国、朝鮮)からの侵略を防ぐために、独立した王朝としての正統性を示し、 大国より古い時代に日本が建国した古い歴史を示し、外交戦略に活かす狙いがあった。
★国内対策
当時地方豪族が政治力を強め、権威を主張するため各々の家に伝わる歴史をまとめたが、自分たちに都合のよい歴史ばかりと偽りが多かった。我が国の歴史の真実が失われていくリスクがある。国の歴史を正しく伝え続けるために、正しい歴史と天皇の事情を記録するよう編集者へ指示した。
何が書いているかを理解する
端的にまとめると以下の5点です。
- 天皇は人間であるが、国の最高権威を示すため、日本を形成した人間技を超えた神々の子孫と伝えていること。
- 天皇が国を戦いより話し合い中心に平定し、橿原にて建国を発したこと。
(実際遺跡から戦争の跡がほとんどないことも伺えられる)
- ヤマトの国が国内のさらなる平定したことや、当時から朝鮮との関わりを記録したこと。
(教科書以上に隣国との関わりが重要だったことがわかる)
- 日本の統治は権力者が民を支配するのではなく、広く国の事情を知ると自然と国民や国が統合する「シラス統治」であること。
(全てを支配し、力で支配する海外とは一線を画すため、理解が難しいがこ日本の根幹といえよう。)
- 記紀の記述はないが、日本の外交戦略は防衛のためであり、他地域への積極的進出はないことが記紀を読めばわかること。
何を学ぶのかを理解する
記紀に書いていることからわかること、記紀に書いていないことがわかることから端的まとめると以下3点になります。
- 記紀にある、神々の日本形成から初代神武天皇の建国の詔までは戦前の歴史教科書の最初の章に書いてあった。縄文時代、弥生時代という記述は戦前の教科書にはないこともわかる。
- なお、記紀を読めばわかるが、天皇は人間であり、神々のお告げを聞き、国民を知る立場である(記紀には、天皇に寿命という制約を与えた物語が記載されている)。
- 記紀には大日本帝国のような軍国主義を煽る表現はない。明治時代まで海外より平和な国家運営ができたのが何よりも証拠である。本来の日本を正しく理解しながら大日本帝国の誤った道へ踏み外す失敗も理解する。
➂記紀の読み方(参考文献)
本記事は長文なので、先に結論を挙げます。その後、あらすじを紹介します。
1. 読んだ本(参考文献)
この記事を書く際に学んだ本を紹介します。
- 現代語古事記 単行本 – 2011/9/1 竹田恒泰 (著)
- 決定版 日本書紀入門――2000年以上続いてきた国家の秘密に迫る 単行本(ソフトカバー) – 2019/7/2
竹田 恒泰 (著), 久野 潤 (著)
- 国史教科書 第7版 検定合格 市販版 中学校社会用 単行本(ソフトカバー) – 2024/6/16 竹田恒泰 (著)
- 地図でスッと頭に入る 古事記と日本書紀 単行本(ソフトカバー) – 2020/7/22 昭文社 出版 編集部 (編集)
- よくわかる古事記 【マンガと図解で身につく】 単行本(ソフトカバー) – 2025/6/13 鉄野 昌弘 (監修), 入谷 いずみ (著), 岩田 芳子 (著), 木下 優友 (著), 阪口 由佳 (著)
- 日本建国史 単行本(ソフトカバー) – 2021/2/5 小名木善行 (著)
- 「日本人とは何か」がわかる 日本思想史マトリックス 単行本(ソフトカバー) – 2023/9/16 茂木 誠 (著)
- マンガ遊訳 日本を読もう わかる日本書紀1 神々と英雄の時代 単行本 – 2018/12/18 村上 ナッツ (著), 村田 右富実 (監修), つだ ゆみ (イラスト)
- ●マンガ遊訳 日本を読もう わかる日本書紀2熱闘エンドオブエイジア 単行本 – 2019/12/16 村上 ナッツ (著), 村田 右富実 (監修), つだ ゆみ (イラスト)
- ●マンガ遊訳 日本を読もう わかる日本書紀3 慈愛と残虐の帝 単行本 – 2020/4/22 村田 右富実 (監修), 村上 ナッツ (著), つだ ゆみ (イラスト)
- ●マンガ遊訳 日本を読もう わかる日本書紀4 仏教伝来と聖徳太子の夢 単行本 – 2021/8/3 村上 ナッツ (著), つだゆみ (著), 村田 右富実 (監修)
- ●マンガ遊訳 日本を読もう わかる日本書紀⑤ 蘇我氏の滅亡と大化の改新 単行本(ソフトカバー) – 2025/7/11 村田 右富実 (監修), 村上 ナッツ (著), つだゆみ (イラスト)
文献の図




2.読み方
多くの本を参考にしましたが、
●竹田氏の本・考えを軸に本記事をまとめた。
●その理由は竹田氏の考えをベースとする教科書が文科省の検定に合格したため。
●歴史に対して様々な仮説を唱える人の考えや本より
竹田氏の知見が客観的に正しいと評価。
では、あらすじに行きましょう。
④あらすじの前に
●神々の誕生からスタートするが現実感がないため、事実に基づいて解釈するとわかりやすい。
●神話、歴史的事実とはいえ、伝えやすくするために物語な面があるが、キーポイントだけ抜き取る。
●わかりやすく伝えるため、記紀とおり書かない点があるがご了承いただきたい。
⑤あらすじ(長文)
大きく7つの章に分けました。
- (1)八百万の神々の登場と日本の形成
- (2) 出雲の国譲り(神々によって出雲国と統合)
- (3) 天皇の最高権威「シラス統治」
- (4) 日本の平定は争いより話し合いの平和的解決方法が主だった
- (5) 天孫降臨と天壌無窮の神勅
- (6) 日本平定のために神武天皇は大和を目指す
- (7) 記紀の中盤以降は各天皇での出来事がまとめられている
(1)八百万の神々の登場と日本の形成
・日本列島の形成なり、日本の豊かな自然(火山、急峻な山地、温暖湿潤な気候、四季、豊かな森、水、生態系)の形成、日本人口増減、など人間を超えた出来事は神々によってなされた。
–
(現代では、地学・生物・地理などの科学的知見があるので、神々が享受した点に違和感があるが、古代は科学がないため、人間技を超えた出来事は神様の恵みと考えるのが自然である)
–
・キリスト教、イスラム教のような一神教ではなく、日本は豊かな自然があるため、至る所に神様が宿ると信じてきた。八百万は800万いるではなく、たくさんいるという意味。
–
・海幸山幸の話から、縄文時代では漁労民族と狩猟民族がいることがわかるが、農耕はまだ始まっていなかったことが垣間見れる。その後、縄文時代の終わりに地球が寒冷化し、水稲耕作ができる場所にその技術を持った人が集まり農耕が始まった。
(2) 出雲の国譲り(神々によって出雲国と統合)
・神々が高千穂へ天孫降臨する前に、出雲国との関わりが深く、出雲国の国譲りによる統合された。当時、たくさんの小国が日本にあったはずだが、出雲国だけは特別扱いだったことがわかる。
–
・出雲は狂暴な民の渡来が到着しやすい地理的位置にある。農耕社会が浸透する中、国内の狩猟民や渡来してきた遊牧民が農耕を荒らす様子が、スサノオが高天原で暴れる様子と重なる。
–
・出雲を統合する際、神々の質疑の中、統治方法を聞くシーンがある。
神々が暮らす高天原は、政治の権力を持つ神が神々を支配する形(ウシハク統治)ではない。広く国の事情を知り、自然と国民が統合され、国も統合されていく形であり(シラス統治)、基本は不親政の原則であり、政治の権威がアマテラスである。
–
・ウシハクは政治の権力をもって、政治をする。朝廷・幕府・政府が該当する。
・シラスは、統治権力は持たず、広く国の事情を知り、自然と国民の幸せを願う。
神々の最高権威はアマテラスであり、アマテラスを引き継ぐ天皇も国の最高権威として引き継いでいる。
–
・出雲国が古墳時代に大和朝廷の勢力下に組み込まれたが、戦争があったことを示す資料や遺跡がないため、戦争ではなく話し合いで統合したと考えられる。
・古墳時代初頭は小国が分立していたが、出雲だけ記紀にあるくらい特別扱い。大国主神は周辺諸国を従う立場だったかもしれない。
・国ごとに個別の信仰があっただろうが、記紀で神々の繋がりを活かして1つの物語にまとめている。
(3) 天皇の最高権威「シラス統治」
●天皇は国の最高権威であるが、これは政治や国家を支配する独裁者ではない。
●政治をするものを任命し、任命したものが政治を行うのが日本のやり方である。
●「最高権威とは偉い!という意味ではなく」、平時は特に何も気にしなくてよいが、国難などの有事の際は国民が納得する人である。
●これが権威である・権威は武力ではなく血統によるものである。
ここが記紀で学ぶべき大事なポイントです。
●天皇制を崩壊させると、国民の判断が精神的に統合できず不安定な国家になる恐れがあり、建国以来、天皇制を維持してきたゆえんである。
(承久の乱、幕末の開国、GHQと制度崩壊の危機があったが難を逃れている)
何度も書きますが
●「知らす」天皇が自ら(指示でもなく)国・国民の事情を知ること(真心から国民の幸せを祈り続ける)であり、これが日本の統治の本質。支配するのとは異なる。
●天皇が国民(大御宝)を我が子のように愛し、幸せを祈り、国民は自分たちのことを大切に思って下さる天皇を親のように慕い、皆で力を合わせて国を支えてきた。
●これを2000年以上継続しているのが日本の国柄。
軍事力やカリスマで国家を統治・支配するのではなく、祈りを通じて国家を統治。
日本と同じ「シラス統治」で長年つながってきた地域や国がないため、なかなか理解しにくいところですが、これこそ、日本です。
・古代、青銅器、鉄器の技術が先行していたことが重要だった。鉄器は北九州が先行し、近畿は遅れていた。大和王権成立を検討する上で重要な意味をもつ。
・九州吉野ケ里遺跡では防衛を目的とした環濠を持ち、傷ついた人骨や金属製の武器が出土された。弥生時代の北九州が戦乱の時代とわかる。
・吉野ケ里は周辺の集落を束ねる王がいた。漢書地理志でも、日本は100以上の国に分かれていた。いずれかの国がシナ王朝に貢物を献上していた。弥生時代は戦乱の時代だった。
(4) 日本の平定は争いより話し合いの平和的解決方法が主だった
・だからこそ建国の詔では、
●八紘為宇は 私たち日本人は皆家族であり、日本列島は私たち日本人の家である。仲良く1つの家で暮らそうという思いが出てくるのは当然である。
●日本同士が殺し合いに明け暮れていた動乱の時代に、このように呼びかけ「奪えば足りなくなるが分け合えば余る」という和の精神を皆で実践し、平和で豊かな国を目指そうとした。これが我が国の建国の精神。戦わずして統合できていったのではないか?
●一方、八紘為宇は大東亜戦争を正当化する政治スローガンに曲解された悲劇もある。意味を正しく理解しければならない戒めである。
・世界史の常である武力で統合する手法ではなく、力のある勢力を取り込んで身内にしてしまう発想は、日本建国と日本の未来に絶大なる安定をもたらすことになる。
–
●攻め滅ぼすのではなく、身内にする手法は和の国の建国にふさわしい。敵将を倒すだけではその地域の人々の心を従えることはできない。地域の人々が大切にしている首領の家族になれば戦いを経ず地域を治めることができる。
●血統が重要(天皇はアマテラス、山、海、大和の神の子孫)という説得力で多くの人から慕われる。
・自然の豊かさもあり、縄文時代は戦争の跡がほとんどない。自然の豊かさが人の心の豊かさを育み、大自然の調和を重んじる独特の世界観を作り上げた。
・その分農耕の移行が大陸より遅れたが、農耕を必要としない世界観がシラス統治という独特な統治に繋がっているのではないか。
・寒冷化によって農耕に移ったが、余裕をもって農耕社会に移行していった。農耕により既存の縄文文化が破壊されたわけではない。
・日本は自然豊かで人口密度が他地域(海外)より高かった可能性がある。人口密度の高さ、縄文式生活(狩猟・採集・あまり定住しない生活)が武力より話し合いによる平定などシラス統治のベースを築いていったと考えらえる。
・日本の平定には、血縁関係の構築と食糧危機・飢饉回避のためのコメの融通が重要であったことは古代からわかっていた。
・地方の豪族と次々と同盟関係を結ぶ。恋愛結婚はあるはずもなく、政略結婚である。当時のヤマト王権がどの地域のどの豪族と関係を深めていったかが手に取るようにわかる。/b>
●戦争による華々しい成果を上げることが天皇の事績ではない。周辺諸国と友好関係を樹立して強固な同盟関係に発展させることが立派な事績である。
●大和朝廷が戦争を経ずにその統治範囲を全国に拡大したことは考古学的事実と一致する。
●武力で周辺諸国を統合した欧州や支那の列強と異なり、大和朝廷は話し合いで国を統合を選び、政略結婚を通じて全国の豪族と血縁関係を結んでいった。
(旧約聖書と比べると日本神話には殺戮の話はほとんどなく、先住民の王と皇室との婚姻関係を結ぶような妥協点をみつけうまく融和していった)
・記紀の中で、出雲国を治める大国主神は試練で幾度かつらい目に合うが周囲の協力を得て国作りを果たす 独裁者、強靭さより周囲の協力を得られる点がまとめ役として重要。
・婚姻関係は1000近い豪族が古墳時代末期に天皇との血縁関係となった。
・日本にあった小国がなぜヤマト王権体制に組み込まれたのか? 利点や必要性がないとそうならない。
鉄の原料は朝鮮半島南部から、鏡や剣などの威信財はシナや朝鮮から入手するか自分で作るしかないがそれをつくる地域はなかった。
・各地の首長たちは自分の権力を維持するために、日本列島規模の政治センターへの求心力を持たざるを得なかったという考えがある。
●弥生時代は鉄の原料は朝鮮半島南部に依存していたため、北部九州はその原料の受け入れ口であり重要拠点であった。
●北部九州はヤマト王権との関係を深めた。記紀では朝鮮南部の日本が統制した記述もあり、実際朝鮮南部に日本と同じ古墳が出土している。
・九州火山噴火の時期からみて、神武天皇の東征の時期は紀元前後とみれる。噴火によって農耕に大きな被害が生じ、九州や西日本で小国同士の争いが生じ、戦乱の時代だった。
・とはいっても、協力しない地域もある。記紀ではアマテラスが直接指示・対処するのではなく、神々と協議した結果をアマテラスの詔を出すシーンがある。
これは神とつながる天皇の【天皇不親政の原理】の元となっている。
(5) 天孫降臨と天壌無窮の神勅
・神々が日本の土台を作り上げた後、高天原から九州の高千穂へ降臨された神と海幸山幸の神との子孫が後の神武天皇であり、九州から近畿大和への平定の旅が始まる。
日本がいつまでも幸せであるよう、見守りようにと「天壌無窮の神勅」が下りた。「天壌無窮の神勅」の記紀での意味と、曲解された内容を理解しておく必要がある。
●弥生時代は鉄の原料は朝鮮半島南部に依存していたため、北部九州はその原料の受け入れ口であり重要拠点であった。
●北部九州はヤマト王権との関係を深めた。記紀では朝鮮南部の日本が統制した記述もあり、実際朝鮮南部に日本と同じ古墳が出土している。
【天壌無窮の神勅】
●本来:「いつまでもお幸せに!」 という意味で「皇室が永遠に続いてね!」という意味
●戦時:天壌無窮の神勅 「皇室を永遠に守り通せ」と解釈し、「国民は皇室を守るために死ね」と曲解した結果
(戦前の学界でもこのような解釈は一般的ではなかった。皇室を守るために国民を家来として命令する内容ではない。)
・古代の漢字が難しいからではあるが、
【天壌(皇室に対して)無窮(ずっと永久に)の神勅(神からの絶対命令)】
と部分的に解釈すると、本来の意味からずれてしまい、危険な思想に走りやすくなる。
「神」=「絶対」は西洋などの思想であり。明治時代の近代化、帝国主義化に都合がよかった。
・古墳時代、鉄器の鋳造は国家規模の事業で、弥生時代に九州地方で見られた鉄器が後で大和で見られる。王権を象徴するものが九州から大和に移動した。2世紀後半に瀬戸内海を中心に防衛を意図した高地性集落遺跡が集中する。王朝成立のきっかけとなった軍事的な勢力が南九州から畿内に移動したとみられる。
(6) 日本平定のために神武天皇は大和を目指す
・平和に天下を治めるために東へ 福岡1年、広島7年、吉備岡山に8年留まった。浪速で戦いになった。大阪から大和に入るが苦戦し、回り込んで背に日を負って戦う。五瀬命は和歌山の竈山に眠っている。天つ神の援助をうけて(剣をさずけて)熊野から上り、大和平定した。平定したとはいえ日本全国ではまだない。
●皇位継承は男系の子孫によって継承されるべきという原則である。竹田氏の意見のとおり、これは今も変わっていない。女系の提案もあるが、2600年の歴史を変える危険性があり、
日本が日本でなくなってしまい、不安な時代を迎えるかもしれない。過去の遺産は変えるべきと変えてはいけないものがある。
(7) 記紀の中盤以降は各天皇での出来事がまとめられている
その中で、注目すべき内容を列挙する。
【10代 祟神天皇】
・大和朝廷に従わない人々を和らげて平定した。伯父のオオビコを派遣し、 平定範囲が北陸 会津、東海道、丹波と広がった。徴税が始まった。
・古事記では皇位継承を巡って多くの反乱物語がある。そのような反逆を退け勝利することが即位した天皇の正統性を保証した。反逆者を確実に討ち滅ぼすことが天皇の資質として求められた。
【11代 垂仁天皇】
・天下泰平のため、天神地神を祭るアマテラス大神を鎮座させるために伊勢神宮を作った。
【12代 景行天皇】
・ヤマトタケルによる西征を命じる(熊曾建の討伐)、出雲建の討伐後、東征した。征討の際、三種の神器の1つである草薙剣(伊勢にあった)を持っていく。
・各拠点での戦い後、熱田神宮に剣が祀られている。
●南九州の熊曾国が打てずに苦戦した大和王朝。その原因は海の向こうの国(朝鮮・新羅)が支援していたためであり、それを討たなければならなかった。
●記紀は朝鮮三国との外交の記述が多く、教科書以上に新羅 百済 高句麗 との外交、争いが過去からあることがわかる。
●新羅の人々が渡って来た。百済王が馬を天皇に献上。機織り、養蚕、土木などの技術が日本に伝えられ、大和朝廷において、一定の地位を占める。天皇の統治が南九州から東北、朝鮮に及んだ経緯ことがわかる。
【16代 仁徳天皇(民のかまど)】
・治水は権力者の実力を示す最高の手段。自然をも従わせることができると信じさせ、民に豊かさをアピールできる。
・前方後円墳は、天皇と血縁関係になった豪族も合わせた大きな墓でもあり、大阪平野一帯を水田開発した際の残土を集めた灌漑設備でもあると考えられる。
・豪族の氏姓がいい加減であり統制がとれなくなったため、氏姓の定めとして盟神探湯で氏姓を決めた。
盟神探湯ってちょっと怖いですね、ヤキいれるわけですからね、はっきりする方法ではありますけど。
【21代 雄略天皇】
・埼玉、熊本の古墳から「雄略天皇を示す名前が刻まれた剣」が出土。関東から九州まで勢力範囲としたことが明らか。
【23代 顕宗天皇】
・雄略天皇に対する恨みがあった。そのため、雄略天皇の御陵を破壊するよう命じた。しかし天皇に対して皇太子であり兄がいさめる美談がある。
・仇をとっても天皇の権威が保てないため、おさえるよう助言し、天皇の権威を守った。
●天皇が過ちをおかしそうになったとき、そばに仕えるものがいさめることができた一例である。
●なお、中国では、「墓を掘り返して屍に鞭打ちする。死屍に鞭打つ」ことが多い。これと同じなってしまうのを回避した。
●ここがシラス統治、天皇の権威を守る点では大事な話である。
・継体天皇の時代(西暦500年ごろ)から大和朝廷が勢力を拡大し、急速に発展。大和から離れて、越国、近江国、美濃国、尾張国、若狭国など勢力を統合。本来それなりの戦争があるが、大規模な戦争の形跡がない。地方豪族が武力だけで政権を倒し、広く豪族たちに大王として認めさせることは不可能だった。天皇のシラス統治が大和朝廷として定着したことがわかる。
記紀のあと、政治を朝廷や豪族・貴族に任せて、天皇は祭祀のみ司るようになり、現代にいたる。
⑥総評
●世界の歴史では大規模な戦争を経て統一国家となるが、日本は平和な時代に統一国家が成立した。通常、大規模戦争を指揮して勝利を収めた者が国王となり、国と民を自分のものとして所有する。しかし、大きな戦争を経ず国が統合したのは、日本とEUだけである。
古墳時代にヤマト王権と出雲国が統合したが、軍事力ではなく話し合いによるもの。国同士が連携を深めて強固な国家へと統合。列島各地に個性豊かな文化が残った。出雲国が国譲りの条件として宗教の自由を挙げヤマト王権はそれを認めた。
●鉄資源獲得、先端文化のため朝鮮との交流が重要だった。朝鮮半島南部は日本の生命線と言えるほど重要だった。672年白村江の戦いまで何度も朝鮮に出兵したのは百済を守るためであった。
●百済は新羅と高句麗から守るために大和朝廷が必要とwin-winの関係。大和朝廷と新羅高句麗のとの関係も少なからずあった(大和朝廷の三韓征伐)。
●百済が滅亡し、中国に巨大な隋や唐ができたため、外交的に日本は脅威に立たされた。隋と高句麗の関係性から日本へ侵略を回避するために記紀、国家体制、遣隋使、遣唐使など対応し、日本の防衛にあたってきた。
●飛鳥時代からも現代と同様に国家を守る体制をきちっととってきたことが記紀からわかる。
●記紀から日本の成り立ち、シラス統治、実力より血縁関係による強い連携による日本の統治、外敵からの防衛がわかる。
●一方、「海外への侵略、野望」という概念は一切ないこともわかる。
●確かに、朝鮮の一部を支配した時期があるが、鉄の確保や海外からの文化の輸入という目的があり、百済を支えていた。
●天皇が血統体系の中枢になったが故に、天皇は自然と普遍的精神の中枢として仰がれる。天皇は日本人にとって精神の拠り所。
●歴代の天皇が民の幸せを祈り、民が力を合わせて天皇の統治を支えてきた。
●血縁と心縁の中枢に万世一系の天皇がある。これが日本。
●天皇は神だから尊いのではない。日本の伝統的地位が神聖であるから天皇は尊い。
●天皇と国民が「血縁、心縁、治縁」でつながってきた。
この繋がりが国体。
損得利害ではなく、3つの縁によって結び付けているから日本人は結束が強い。
●記紀を読むと、やっていることは現代と変わらず、「日本を平和である続けるための努力の賜物」とわかる。
●日本独特の「シラス統治」、皇帝ではない「天皇」という独特な存在。
武力や実力ではなく、血縁で日本を守って来た歴史とわかる。
●一方で、近代化を急ぐあまり、記紀を曲解し戦禍に合う歴史もある。
記紀を正しく理解し、片一方の思考・思想に寄るのではなく、本来の日本・日本人を正しく知るとことが今必要である。
長文でしたが、記紀のあらすじや学ぶべきポイントをまとめました。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
正しく、日本らしさを再認識しましょう。
まとめ
「古事記、日本書記(記紀)がわかる」を解説しました。