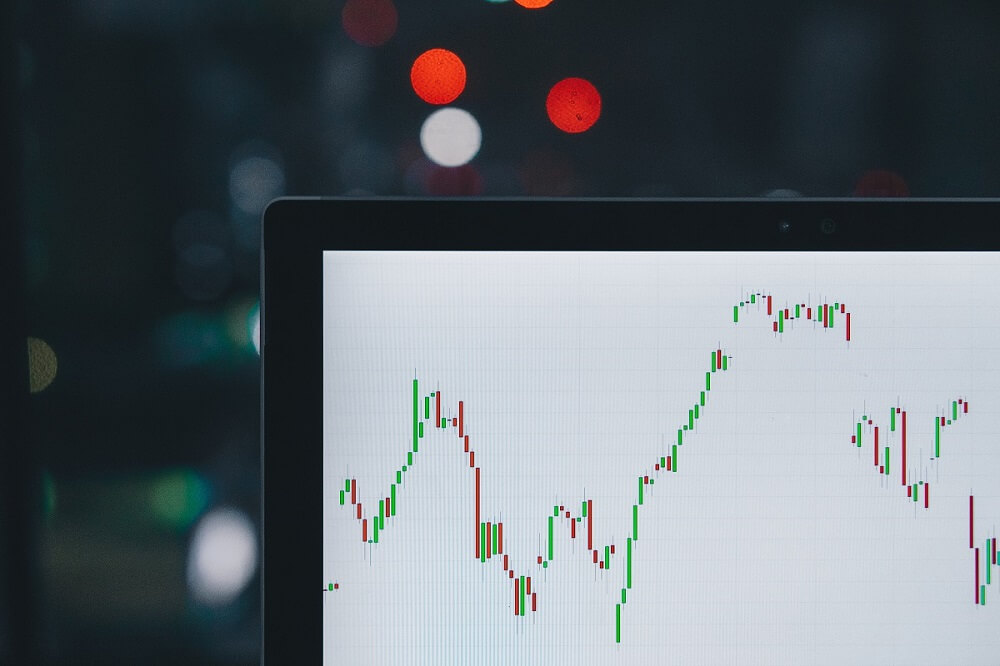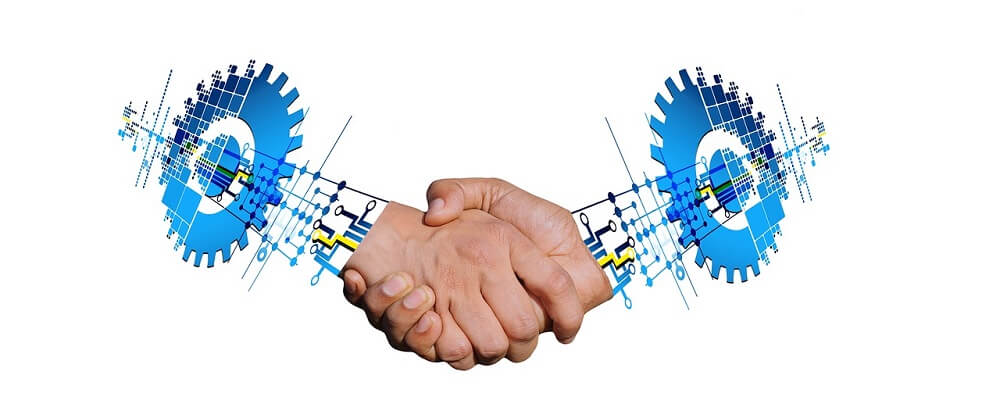★ 本記事のテーマ
- 問1. 管理図の種類を答える演習問題1
- 問2. 管理図の種類を答える演習問題2
- 問3. Xbar-R管理図の演習問題
- 問4. pn管理図の演習問題
- 問5. 異常パターンの演習問題
なお、QC検定®2級合格対策本や参考書は1冊までにしてください。
たくさん本を持っている人ほど、合格しません。
合格する方法が重要で、対策本や参考書にはその方法が書いていません。
品質管理・統計の初心者にとって分厚い本はキツイです。
★ QC模試受験しよう!
 |
QC模試(品質技量の腕試し&QC検定®対策) 品質技量の実力を試したい! QC検定®合格対策に活用したい!オリジナル試験問題を提供します! |
★【QC検定® 2級合格対策講座】で必勝!
 |
QC検定® 2級合格対策講座を販売します。合格だけでなく、各単元の本質も理解でき、QC検定® 1級合格も狙える59題をぜひ活用ください。 |
★【必勝メモ】と【必勝ドリル】のご紹介
試験合格に必要最小限エッセンスをまとめた「必勝メモ」と
何度も解いて合格に導く「必勝ドリル」
何度も繰り返すから力になる!
| a | a | a | ||
| a |  |
a |  |
a |
| a | a | a | QC検定®2級必勝メモ 1000円 |
QC検定®2級必勝ドリル 1000円 |
★品質管理(QC)を究める数理問題集(初級・中級向け)
QC検定®3級、QC検定®2級受験の方、QC検定®1級受験挑戦する方への問題集(80問)です。
数学が苦手で品質管理の数理で苦戦していたら是非勉強しましょう!
| a | a | |
| a |  |
a |
| a | a | 品質管理(QC)を究めるを 数理問題集 (初級・中級向け) 3000円 |
①QC検定®と品質管理検定®は、一般財団法人日本規格協会の登録商標です。
➁このコンテンツは、一般財団法人日本規格協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。
➂QCプラネッツは、QC検定®と品質管理検定®の商標使用許可を受けています。
●リンクページ
●You tube動画でも解説しています。ご覧ください。
問1. 管理図の種類を答える演習問題1
(1) 非常に高価な原価である部品を毎日製造している。日々の部品の特性値を確認したいが、1日1部品のみ計測で検査コストを安く済ませたい場合。
(2) 大きさの異なるパネル板1m2あたりの傷の数を管理したい場合。
(3) 1日1000個製造する部品から出る不適合品数を日ごとに管理したい場合。
(4) 2種類の織物(4m2,6m2)を製造しているラインで、1m2あたりに発生するシミの数を管理したい場合。
(5) DVD-ROMを生産している。毎日生産枚数が異なる。日ごとの不良率を管理したい場合。
(6) 1箱10瓶入った液体の重要を管理している。毎日100箱納品しているが、重量の異常値がないかどうかを管理したい場合。
回答欄
| (1) | (2) | (3) | |||
| (4) | (5) | (6) |
★解説(クリックで開きます)
計数値なら、平均、データの判断
計量値なら、率・割合、個数の判断
で管理図を区別します。
<回答>
| (1) | X-Rs管理図 | (2) | c管理図 | (3) | pn管理図 |
| (4) | u管理図 | (5) | p管理図 | (6) | Xbar-Rs管理図 |
★【管理図の演習問題クイズ】
200円有料ですが、36問あります。是非チャレンジください! いい練習になります!
問2. 管理図の種類を答える演習問題2
回答欄
| データ | 管理図 | 項目 | 分布 |
| 計量値 | X-R管理図 | ― | |
| 計数値 | pn管理図 | ||
| p管理図 | |||
| c管理図 | |||
| u管理図 |
★解説(クリックで開きます)
管理図の種類は項目と分布もまとめて覚えると良いです。
| データ | 管理図 | 項目 | 分布 |
| 計量値 | X-R管理図 | ― | 正規分布 |
| 計数値 | pn管理図 | 不良個数 | 二項分布 |
| p管理図 | 不良率 | 二項分布 | |
| c管理図 | 欠点数 | ポアソン分布 | |
| u管理図 | 単位当たりの欠点数 | ポアソン分布 |
問3. Xbar-R管理図の演習問題
(1) 各群の平均X ̅と範囲Rを求めよ。
(2) X ̅管理図のLCL,UCLを計算せよ。ただし管理図係数一覧表を用いよ。
(3) R管理図のLCL,UCLを計算せよ。ただし管理図係数一覧表を用いよ。
(4) 管理図を描くと以下になった。管理状態を評価せよ。
<データ>
| No. | X1 | X2 | X3 | X4 | 平均Xbar | 範囲R |
| 1 | 30.3 | 32.3 | 34.4 | 25.7 | 30.7 | 8.7 |
| 2 | 31 | 36 | 33.5 | 36 | 34.1 | 5 |
| 3 | 27.5 | 34.5 | 35 | 26.7 | 30.9 | 8.3 |
| 4 | 23 | 26 | 23 | 26 | 24.5 | 3 |
| 5 | 28 | 28 | 29.2 | 28 | 28.3 | 1.2 |
| 6 | 30 | 30 | 26.5 | 31 | 29.4 | 4.5 |
| 7 | 35.2 | 24.8 | 32.9 | 27.3 | 30.1 | 10.4 |
| 8 | 30 | 30 | 26.3 | 29 | 28.8 | 3.7 |
| 9 | 33 | 26.8 | 33.5 | 27.5 | 30.2 | 6.7 |
| 10 | 30.6 | 30 | 33.2 | 31.8 | 31.4 | 3.2 |
| ― | ― | ― | ― | 平均 | 29.8 | 5.5 |
管理図係数一覧表
| n | A2 | D4 | D3 |
| 2 | 1.88 | 3.267 | – |
| 3 | 1.023 | 2.574 | – |
| 4 | 0.729 | 2.282 | – |
| 5 | 0.577 | 2.114 | – |
| 6 | 0.483 | 2.004 | – |
| 7 | 0.419 | 1.924 | 0.076 |

回答欄
| (1) | \(\bar{\bar{x}}\) | \(\bar{R}\) | ||
| (2) | LCL | UCL | ||
| (3) | LCL | UCL | ||
| (4) | ||||
★解説(クリックで開きます)
頻出問題です。確実に点数化しましょう。
(1) \(\bar{\bar{x}}\)=29.8
\(\bar{R}\)=5.5
(2)LCL=29.8+0.729×5.5=33.83
UCL=29.8-0.729×.5=25.85
(3)LCL=2.282×5.5=12.483
UCLは無し
(4)Xbar管理図で管理限界値を超えた異常値がある。
まとめると、
| (1) | \(\bar{\bar{x}}\) | 29.8 | \(\bar{R}\) | 5.5 |
| (2) | LCL | 33.83 | UCL | 25.85 |
| (3) | LCL | 12.483 | UCL | 無し |
| (4) | Xbar管理図で管理限界値を超えた異常値がある。 | |||
問4. pn管理図の演習問題
(1) pn管理図のLCL,UCLを計算せよ。
(2) 管理図を描け
(3) 管理図から管理状態を評価せよ。
| Day | pn | p% |
| 1 | 20 | 20 |
| 2 | 9 | 9 |
| 3 | 8 | 8 |
| 4 | 8 | 8 |
| 5 | 9 | 9 |
| 6 | 9 | 9 |
| 7 | 9 | 9 |
| 8 | 8 | 8 |
| 9 | 2 | 2 |
| 10 | 8 | 8 |
| 平均 | 9 | 9 |
回答欄
| (1) | LCL= |
| UCL= | |
| (2) | |
| (3) |
★解説(クリックで開きます)
pn管理図も頻出問題です。
(1)LCL: pn-3\(\sqrt{pn(1-p)}\)=9-3\(\sqrt{9(1-0.09)}\)=0.415
UCL: pn+3\(\sqrt{pn(1-p)}\)=9-3\(\sqrt{9(1-0.09)}\)=17.585
(2)管理図

(3)上方管理限界値以上の異常値と、中心に寄りすぎる傾向がある。
まとめると
| (1) | LCL=0.415 |
| UCL=17.585 | |
| (2) | 解説参照 |
| (3) | 上方管理限界値以上の異常値と、 中心に寄りすぎる傾向がある。 |
問5. 異常パターンの演習問題
回答欄
| (1) |
| (2) |
| (3) |
| (4) |
★解説(クリックで開きます)
●限界線を越えるもの
●偏った分布になるもの
など
| (1)管理限界線を越えるものがある。 |
| (2)連が現れる。 |
| (3)連続して上昇傾向または下降傾向がみられる。 |
| (4)交互に上下する点が現れる。 |
まとめ
QC検定®2級で、分散に関する検定と推定の解法を解説しました。
10問を1回ずつ解くのではなく、1問を10回解いて解法を覚えてしまいましょう。
試験本番に緊張した状態でも解けるよう何度も練習しましょう。
- 問1. 管理図の種類を答える演習問題1
- 問2. 管理図の種類を答える演習問題2
- 問3. Xbar-R管理図の演習問題
- 問4. pn管理図の演習問題
- 問5. 異常パターンの演習問題