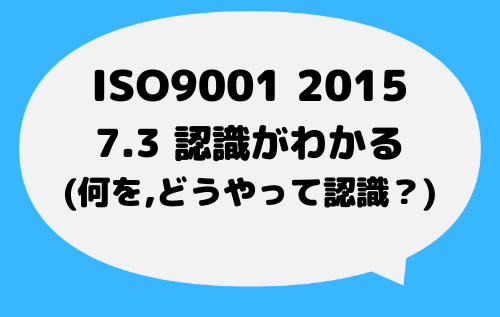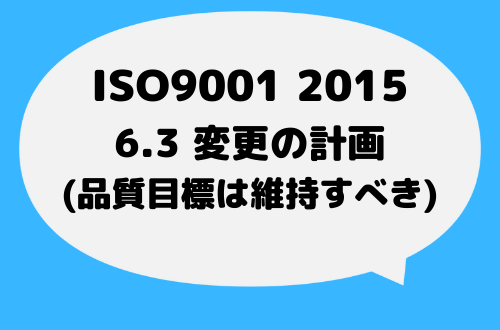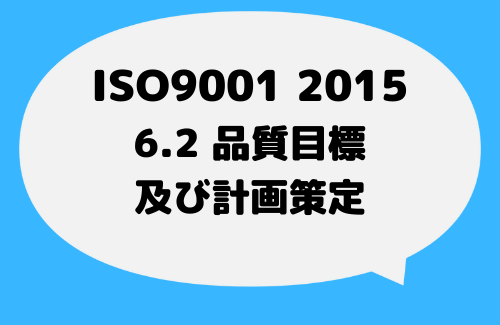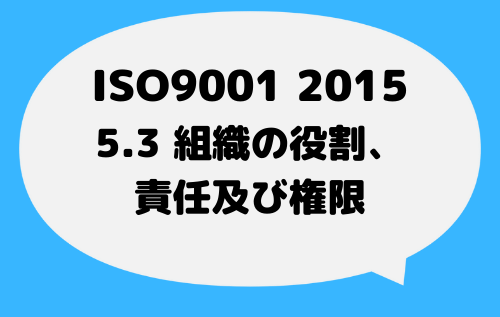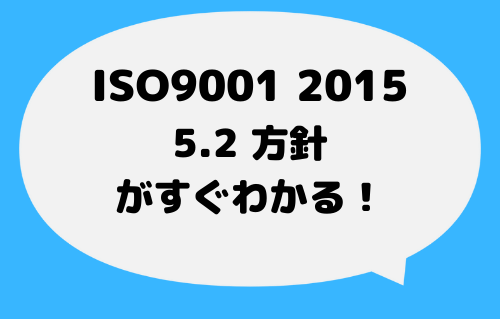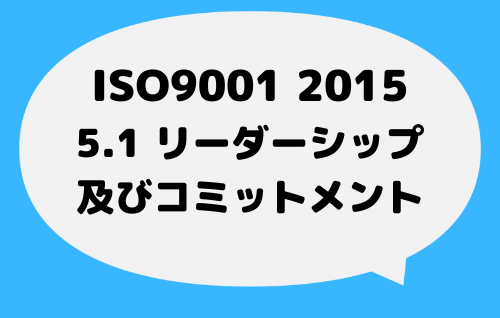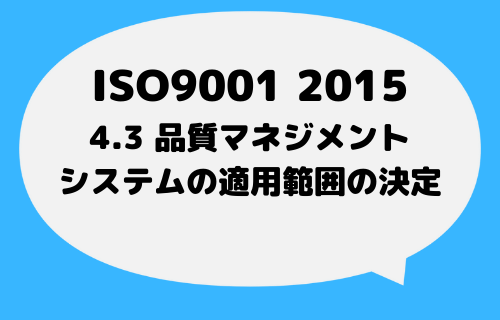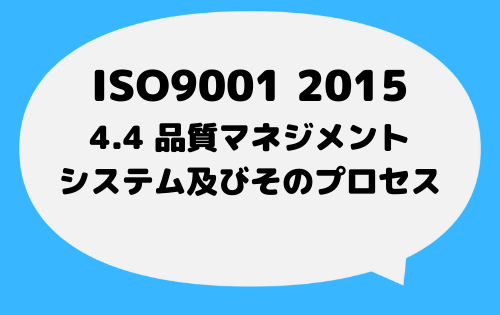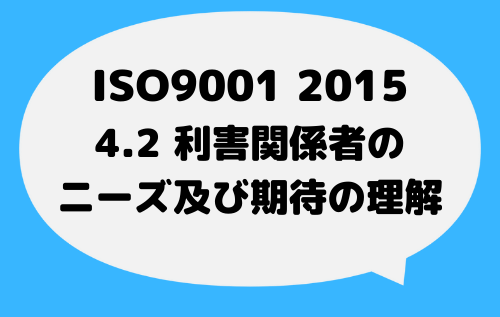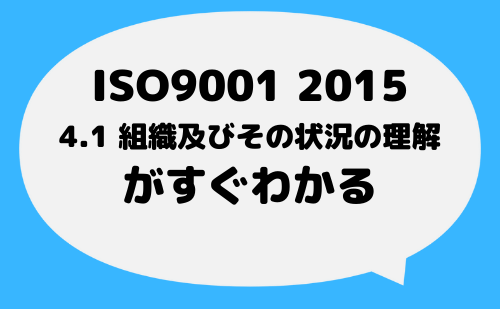QCプラネッツのISO9001 2015関連ブログを多くの方に読んでいただき、とてもうれしいです。ブログの内容をさらにパワーアップして更新しました。
★ 本記事のテーマ
ISO9001 2015 5.1 リーダーシップ及びコミットメント がわかる
ここでは、いくつか用語の概念を理解する必要があります。1つずつ解説していきます。
●トップマネジメントって何?誰?
●品質マネジメントシステムのリーダーシップって何をすればいいの?
●コミットメントって何?
●トップマネジメントのコミットメントって何?
- ①ISO9001要求事項、JISハンドブックISO9001の解説
- ②トップマネジメント
- ③リーダーシップ
- ④リーダーシップは誰でも身につく
- ⑤エンパワーメントして巻き込む
- ⑥コミットメント
①ISO9001要求事項、JISハンドブックの解説
ISO9001 2015の要求事項、JISのハンドブックを読みましょう。
ISO9001要求事項
5.1 リーダーシップ及びコミットメント
5.1.1 一般 トップマネジメントは,次に示す事項によって,品質マネジメントシステムに関するリーダーシップ及びコミットメントを実証しなければならない。
a) 品質マネジメントシステムの有効性に説明責任(accountability)を負う。
b) 品質マネジメントシステムに関する品質方針及び品質目標を確立し,それらが組織の状況及び戦略的な方向性と両立することを確実にする。
c) 組織の事業プロセスへの品質マネジメントシステム要求事項の統合を確実にする。
d) プロセスアプローチ及びリスクに基づく考え方の利用を促進する。
e) 品質マネジメントシステムに必要な資源が利用可能であることを確実にする。
f) 有効な品質マネジメント及び品質マネジメントシステム要求事項への適合の重要性を伝達する。
g) 品質マネジメントシステムがその意図した結果を達成することを確実にする。
h) 品質マネジメントシステムの有効性に寄与するよう人々を積極的に参加させ,指揮し,支援する。
i) 改善を促進する。
j) その他の関連する管理層がその責任の領域においてリーダーシップを実証するよう,管理層の役割を支援する。
注記 この規格で“事業”という場合,それは,組織が公的か私的か,営利か非営利かを問わず,組織の存在の目的の中核となる活動という広義の意味で解釈され得る。
–
5.1.2 顧客重視 トップマネジメントは,次の事項を確実にすることによって,顧客重視に関するリーダーシップ及びコミットメントを実証しなければならない。
a) 顧客要求事項及び適用される法令・規制要求事項を明確にし,理解し,一貫してそれを満たしている。
b) 製品及びサービスの適合並びに顧客満足を向上させる能力に影響を与え得る,リスク及び機会を決定し,取り組んでいる。
c) 顧客満足向上の重視が維持されている。
長いですね。いっぱい要求事項があって、頭の中が整理できないですね。
5.1 リーダーシップ及びコミットメントで、理解しにくい用語がいくつかあります。
- トップマネジメントって何?誰?
- 品質マネジメントシステムのリーダーシップって何をすればいいの?
- コミットメントって何?
- トップマネジメントのコミットメントって何?
JISハンドブックの解説
次のように規定されています。
- JIS Q9001品質マネジメントシステム-要求事項
- JIS Q9002 品質マネジメントシステム-JIS Q 9001の適用に関する指針
- JIS Q9004 品質マネジメント-組織の品質-持続的成功を達成するための指針
それぞれを読んだ印象をまとめます。
| JIS |
名称 |
単元 |
感想 |
| JIS Q9001 |
品質マネジメントシステム
-要求事項 |
5.1 リーダーシップ及びコミットメント |
ISO9001 2015 5.1
と同じ内容 |
| JIS Q9002 |
品質マネジメントシステム
-JIS Q 9001の適用に関する指針 |
5.1 リーダーシップ及びコミットメント |
具体的な場面を説明がたくさん解説している。 |
| JIS Q9004 |
JIS Q9004 品質マネジメント
-組織の品質-持続的成功を
達成するための指針 |
7 リーダーシップ |
JIS Q9001 5.1の補足 |
●品質マネジメントシステムはまず、全体像を自分で説明できることが重要です。
●品質マネジメントシステム全体像は、他人のものでなくてもいいし、
常に最新の考えに更新してもOKです。
●常にあるべき姿を考えることが重要です。
ISO,JISのとおり仕事するのではなく、自分で考えて仕事すべきです。その考え方を本記事で解説します。
②トップマネジメント
トップマネジメントは誰か?
これは2つ答えがあります。
- 基本的には経営者、経営陣、トップ責任者
- ローカルには部門長
基本的には、経営者、経営陣、トップ責任者がトップマネジメントに該当します。トップの責任者ですね。
社長がトップマネジメントになります。大きな会社ですと、経営陣として、部長より上の役職をすべてトップマネジメントと呼んだりします。
なお、品質監査で、個別の部門を調べるときに、ローカルな意味で、そこの部門長(部長)をトップ責任者としてトップマネジメントとして扱う場合もあります。
品質マネジメントシステムを見る場合、
対象となる領域の中でトップに該当する人を
トップマネジメントとします。
トップマネジメントとは何をすればよいのか?
経営者や部門長がやるべき仕事をすればよいですが、品質マネジメントシステムにおける仕事とは何か?を考えます。
トップがやるべきことは、
- 対外は利害関係者への説明責任
- 対内へ品質方針・品質目標を確立
- 対内は品質をとりかかるための仕組み、ルールの整備
★利害関係者への説明責任
●利害関係者への説明責任は、経営者が常に求められる説明責任そのものです。品質マネジメントシステムやISO9001と関係なく、会計、安全などの観点からも説明責任が求められます。
★品質方針・品質目標を確立
品質マネジメントシステム、ISO9001は
トップマネジメントの指示からスタートして、
期末の結果のトップマネジメントへの報告で終わる
品質マネジメントシステムは、品質管理部門や担当が勝手にやっているのではありません。必ず、
①経営陣であるトップマネジメントの指示を受けてから期初がスタートし、
②結果報告を期末にして、次年度の指示を受けます。
期初の指示として、品質方針、品質目標を掲げて、各部門に指示します。品質方針は数行の内容なので、トップマネジメントが作成し、細かい内容が書かれた品質目標は品質管理部門が代行することがあります。
また、期末に、品質活動の結果をトップマネジメントへ報告し、次期への活動指示を受けるための、マネジメントレビューなどの会議が開催されます。
③リーダーシップ
リーダーシップとは何か?
「リーダー」、「リーダーシップ」などよくビジネスに活用されますね。
「リーダーシップ」とは何か?簡単に説明できますか?
と聞かれると、「うーん」と困りませんか?
品質マネジメントシステムやISO9001には、リーダーシップをわかりやすく解説したものがありません。ISOコンサルタントなどが書いた本には書いていますが、それも難しいです。
なので、簡単に解説します。
ISO9001のリーダーシップは経営学や組織論に書いているリーダーシップと同じです。
★リーダーシップとは、
- メンバーを目標に向かうよう努力すること
- ビジョンを提示し、メンバーと共有する
- 意見、考えが異なるメンバーに動機づけする
- 前向きな姿勢や相手を理解する
などがあります。要するに、
みんなをリードするマインドがリーダーシップ
役職や担当範囲に関係なく、各自が持ってほしいマインドです。
品質マネジメントシステムのリーダーシップは何をすればよいのか?
品質活動を社内や組織内で活発にするように導くこと
社内や組織内で、品質マネジメントシステムがあるとか、ISO9001 認証だからといって、品質目標、品質活動、品質に関する会議、品質監査などを自ら進んで実行する人はほとんどいません。
なぜなら、面倒だし、品質管理の概念が難しいし、「あれこれやれ!」と言われてうっとうしいからです。
品質管理は、ダイエットや成績を上げる勉強などのような、苦しいものです。それを導くリーダシップがないと誰もやりませんね。
●品質マネジメントシステムのリーダーシップの具体的な活動は
- 品質活動を各部門へ指示しつつ、活動のポイントをわかりやすく解説
- 各部門からの質問、悩みごとを親身になって聞き、提言する
- 良い報告もそうでない報告も感謝し、一緒に解決する姿勢で取り組む
- 品質活動の良い点を褒めて、改善すべきポイントがあれば取り掛かりやすくするよう工夫して伝える
- 品質活動する部門と敵対しないこと
- 相手を思いやる心と客観的かつ冷静な目で見る
などがあります。
品質活動を社内や組織内で活発にするように導くこと
強制的なやらされ感ではなく、
自発的に取り組みやすくなるようエンパワーメントすることが大事です。
この優しいマインド(易しいではないのがポイント)!で接するには
自分がトラブルや品質改善に出くわしたらどんなに大変か!という気持ちをもって相手に接する事です。
私がよくやる手は、
「お疲れ様です。」
「(相手の状況を傾聴して)大変だったですね!」
と同調しつつ、冷静に分析する。
「○○○○などの案はいかがでしょうか?」
と決めつけせず、相手に選ばせる手段をいくつか提言する。
よく、手段を質問されることが多いので、手段より達成したい目的を明確にして共有します。
品質活動を社内や組織内で活発にするように導くこと
品質管理担当ですが、相手を目標に導くマインド、行動も立派な
リーダシップです。
④リーダーシップは誰でも身につく
リーダーシップは天性的と思われがち
●子供の頃とかを思い出すと、クラスのリーダー的な人って決まっていたし、自分には縁遠い話と思われがちです。
ちょっと昔の昭和なドラマなど見ると、「みんな、俺について来い!」的なかっこいいヒーローが1人いるのがリーダシップのイメージです。
その割に、自分の会社には、「冴えない上司ばかり。なんでコイツが自分の上司なの?」が現実です。
リーダーシップは天性的で、性格・キャラで決まるような環境で育ったので、ピントと来ません。
ですが、目立たなかったあなたも本来、リーダーシップを兼ね備えています。そのリーダーシップを発揮して組織・社会に良い効果をもたらせることができます。
行動理論でリーダーシップは誰でも習得できる
●経営学、組織論では、「リーダーシップは後天的に鍛え上げれば伸ばせるもの」としています。
●天性的なものではなくても、次のスキルがあれば、少しずつですが、あなたらしいリーダーシップが身に付きます。
- 自分を取り巻く環境を理解
- 相手を思いやる配慮
- 目標に向かって周囲と一緒に走る情熱
- 知性、経験
●業務で得た、知識・スキル・経験などを駆使すれば、行動理論で挙げているリーダーシップを習得することができます。上の4つはどれも、先天性ではなく、後発性なものばかりです。
「みんな、俺について来い!」ではなく、
目標(ゴール)を達成する道筋を示し、周囲をエンパワーメントするのがリーダーシップ
リーダーシップを取る前に理解しておくこと
●組織が向かうべき方向を理解することです。組織が向かうべき方向を考える上で大事なのが、
経営分析としてマーケティングのフレームワーク主に駆使しながら、組織の課題、施策を考えていきます。
>面白いことに、経営分析内容とISO9001 2015の要求事項がそれぞれ対応関係になっています。
⑤エンパワーメントして巻き込む
エンパワーメントリーダシップのやり方
●難しそうに見えますが、簡単です。コツは1つだけ
相手がやりたくなる方向を示せばよい!
部下、周囲の人も自分にとっての大事な顧客と思えば、相手が満足するように仕向けたら勝ちです!
一歩引いて、みんなが主役として自発的に成果を出すように仕向けるのが、エンパワーメントリーダシップ!
エンパワーメントリーダシップのステップ
5つあります。
- 目標・ビジョンの共有
- 相手を把握
- 適切な業務の割り振り
- コーチング・動機付け
- 支援
どのステップも、「命令」、「指示」のニュアンスがありませんね。
★ (i)目標・ビジョンの共有
●組織の方向性と、相手・部下の方向性をそろえることが大事です。あまりに合わない場合は異動など、環境を変える必要があります。
方向性を確認することで、互いの納得感を増すことができるし、逆に部下・周囲からの提案ももらうことができる。
組織は上下関係と言いますが、上の人からすると、下から提案が欲しいというのも現実です。良い提案がいつでも出る環境を作る事が大事です。
★(ii)相手を把握
●伝える相手を理解することが大事です。
・能力、スキル、経験、適性
・家族、健康面などのケア
・相手が求めていること
相手がわかっていると、相手も納得して話を聞いてくれます。話を聞いてくれない、一方的な人がリーダーになると、誰も相手にしません。
「お前に言っても無駄だろ!」と期待値0なリーダではNGです。
★(iii)適切な業務の割り振り
●なかなか適切な業務を質・量で割り振るのは、難しいですが、常に対話して相談を受けながら進めていくことですね。
業務量が多い、難しい仕事でも、相談を常に乗るだけでも、上手にエンパワーメントできています。
★(iv)コーチング・動機付け
●コーチングといっても、「命令・指示」ではありません。アドバイスを求められますが、あくまで自分で考えさせて振り返ってもらうように質問を工夫して、傾聴することです。
自発的に動けるまでが非常に時間と手間がかかりますが、ここを乗り切れば、自然とみんなが自発的に目標に向かって進んでくれます。それを見守ればよいのです。
★(v)支援
●支援、援助も時には必要です。やり方がわからなければ指導すればよいですが、本人に考えさせて、失敗してもいいから、自分でやらせることです。
エンパワーメントリーダシップは子育てと同じ。
・命令・指示で育った子供は、ストレスが多く、指示待ち型になる
・エンパワーメントで育った子供は、ストレスが少なく、自分から行動する。
家も組織も同じですね。
⑥コミットメント
コミットメントとは何か
あまり使わない言葉なので、理解が難しいです。英語を直訳すると「約束する」です。
品質マネジメントシステムやISO9001のコミットメントはもう少し、気合いが入った意味で使われています。
コミットメントとは、絶対やり遂げる!と覚悟をもって取り組むこと。
とりあえず、やってみます。途中で辞めることもあります!は絶対NGです。
トップマネジメントのコミットメントとは何か
トップがコミットメントすることは重要です。
★トップマネジメントのコミットメントとは
トップ自ら、品質マネジメントシステムを絶対やり遂げる!と覚悟をもって取り組むことです。できないならクビ!くらい、クビをかけてガチでやると覚悟をもってやるということです。
トップがクビをかけて活動する意味であるくらい、重要です。その理由を説明します。
★トップマネジメントのコミットメントする意義
トップがこんな考えだったら、部下はついてきますか?
品質は最後の砦で、重要だ。
あとは、お前らでやっとけ!
俺の出世に傷がつかないようにちゃんとやれよ!
こんなトップじゃ、「お前がやれよ!」ってみんな心底思いますよね。実は、こんなトップは2000年ごろまで、そこら中にうじゃうじゃいました。
品質不正がばれて、優良企業でもつぶれる怖さがわかったご時世から、徐々にトップが覚悟をもって品質活動を指示する風潮になってきました。
トップが覚悟をもって、取り組まなければ、
組織、担当者はついてこない。
理念の言葉や社内ルールを整備しても、
トップが覚悟をもって取り組む姿勢を見せなければ、
組織、担当者はついてこないし、
品質マネジメントシステムを回そうとしない。
結構大変なんですね。
品質マネジメントシステムやISO9001が組織内で有機的に機能するには、トップへの信頼などの人間系、心情的要素が強いです。
ルール、契約、ギャラで縛っても、人や人の心は動きません。だから、品質マネジメントシステムを回すには、人の心をつかむことが大切です。心をつかむくらいの覚悟がトップマネジメントのコミットメントなのです。
品質が悪化したり、不正に走る組織は、人の心がつかめていない場合がほとんどです。
品質マネジメントシステムやプロセスについて十分、理解できましたね!
まとめ
ISO9001 2015 5.1 リーダーシップ及びコミットメントをわかりやすく解説しました。
- ①ISO9001要求事項、JISハンドブックISO9001の解説
- ②トップマネジメント
- ③リーダーシップ
- ④リーダーシップは誰でも身につく
- ⑤エンパワーメントして巻き込む
- ⑥コミットメント