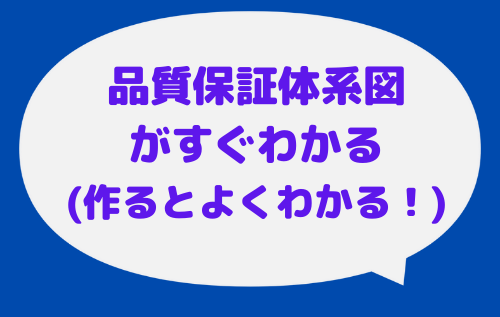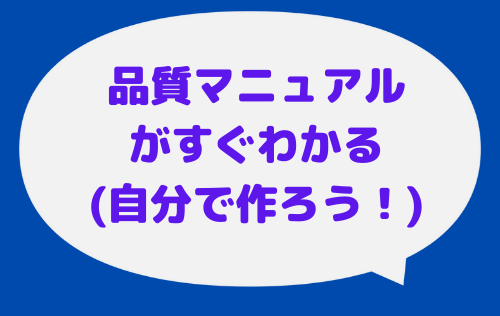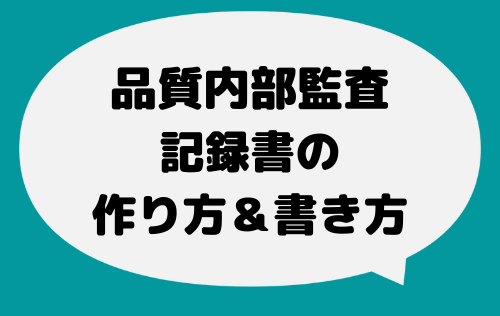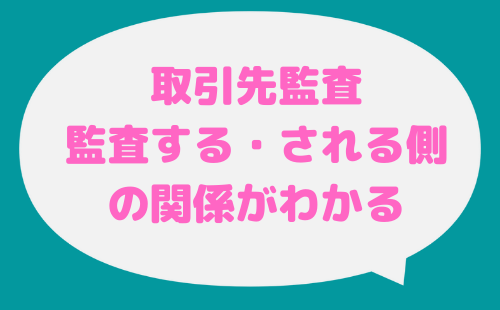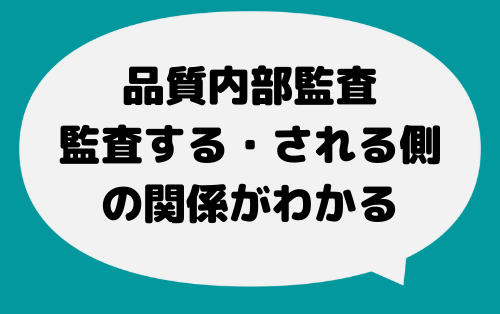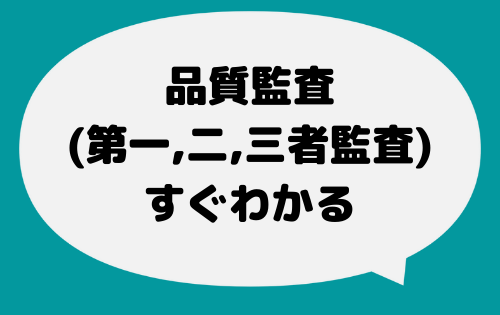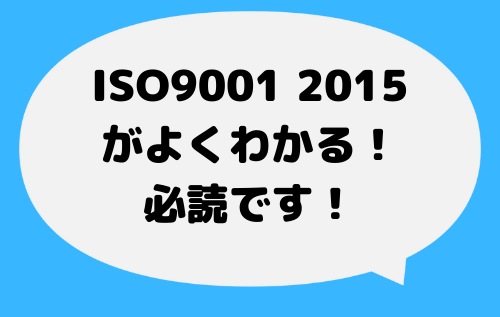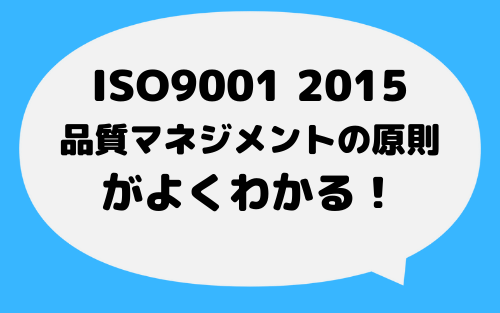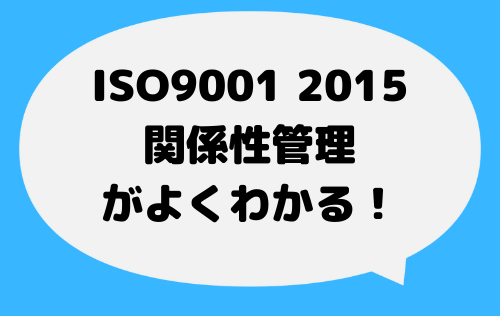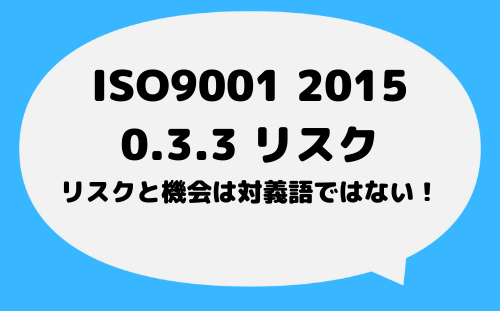★ 本記事のテーマ
- ①品質保証体系図とは
- ②品質保証体系図を作ろう!
- ③品質保証体系が機能するための条件
➀品質保証体系図とは
品質保証体系図
つまり、
●営業部門はどんな業務をしたらよいか?
●設計部門はどんな業務をしたらよいか?
●製造部門はどんな業務をしたらよいか?
…
と各部門のやるべきことを決めた図です。
●品質保証体系図の具体例は下図に挙げます。

●要は、
品質保証体系図のポイント
●まずは、下の3点が細かくぎっしり定義されています。
- 各工程の業務・作業内容
- 各工程で担当する部門
- 工程で必要な会議、標準類(ルールや文書)
★品質保証体系図が嫌われる3つの理由
●本来は、組織活動において、最も重要な図なので、新人さんの頭に叩き込んでから業務開始としたいです。でも、できません。その理由は
実際は、組織に入って5年以上経験した中堅者以上が、読んで初めて「重要な体系図だ!」と思うものです。
品質保証体系図は業務経験で覚える
●新人や若手は、まずは先輩・上司からのOJTで一連の業務を経験しましょう。何回かサイクルを回して自分でできるようになってくると、全体のプロセスが理解できるようになります。
★1つの専門を経験すれば、他分野にも展開できる
●組織の都合で異動になったり、転職で異業種に行くこともあるでしょう。しかし、どこかで1つの専門を経験しておけば、品質保証体系図はどの分野にも理解できます。
業種が違っていてもそれほど、大きく体系図は変わりませんし、変わったとしても、
・量産型か、受注型か
・BtoCか、BtoBか
・vソフトウェアかハードウェアか
くらいでしょう。
一度、1つの専門性を磨けば、どの領域にも展開できます。
品質保証体系図を作ろう!
品質保証体系図は自分で作ってみると、とても良い勉強になります。作ってみよう!
●最初から下図のような複雑な図にはなりません。

なので、
●品質保証体系図の最初は、ただの表です。
●品質保証体系図はどういう経緯で、細かい図表になるか?
を見ていきましょう。
最初はただの表
●品質保証体系図の最初は、ただの表です。
●事例として、営業部門、設計部門、製造部門、品質部門が組織にあったとします。この情報だけで品質保証体系図を作ると、おそらく下表になるはずです。
| プロセス | 部門 |
| 販売 | 営業部門 |
| 設計開発 | 設計部門 |
| 製造 | 製造部門 |
| 検査 | 品質部門 |
そうです!これで組織が回るなら、これも立派な品質保証体系図です!
各プロセスで要望が出て来る
上表はシンプルすぎです。なぜなら、各プロセスにおいて、部門内で閉じるからです。
●部門内に閉じる組織は、品質低下を懸念します。なぜなら、
- セクショナリズムに陥っている可能性がある(部門間の壁が厚い)
- リスクや情報が組織内で共有できていない可能性がある
- 各部門で全プロセスを理解できるプロはそもそもいない
●最初は、部門内で閉じていた組織でも、徐々に顧客要求品質を満たせず、各部門が困るようになるはずです。
困ったから相談した!⇒これが部門間の連携するきっかけですね!
その当たり前に「なぜ?」をツッコむと、「相談して解決したいから」とわかりますね。
各部門の連携の必要性が品質保証体系図を作る
分類しただけの品質保証体系図をもう少し、肉付けします。

●では、問題です!各青枠でくくった工程では、どの部門が参加すればよいでしょうか?
・マーケティング
・受注可否判断
・仕様検討
・設計開発
・納入仕様書
・製造
・部品調達
・出荷検査
・納入
・苦情・クレーム対策
「あなたはなぜそう考えたのか?」が最も大切です。
QCプラネッツでは、以下のように連携が必要としました。別に他の解でもOKです。
| 営業 | 設計 | 製造 | 品質 | |
| マーケティング | ● | |||
| 受注可否判断 | ● | ● | ● | |
| 仕様検討 | ● | ● | ● | |
| 設計開発 | ● | |||
| 納入仕様書 | ● | |||
| 製造 | ● | ● | ||
| 部品調達 | ● | |||
| 出荷検査 | ● | ● | ||
| 納入 | ● | |||
| 苦情・クレーム対策 | ● | ● | ● | ● |
●それぞれの理由を説明します。別の考えてもOKです。
●受注可否判断は技術がわからないと判断できないため、設計・製造部門も必要。
●仕様検討は顧客要求、技術力の両者をみないと検討できないため、営業・設計・製造部門が必要。
●製造引継を設計と製造の間に追加する。仕様のヌケモレが一番起こる場所だから。
●検査は品質部門に任せず、製造・品質で両方みる。ただし、癒着や品質不正がないよう品質は独立した立場をとること。
●苦情・クレーム対策は、顧客対応、設計・製造のフィードバックやそれを品質が指揮するので全部門とする。
以上をまとめると、下図のような品質保証体系図が出来上がります。実際の体系図に近づいてきました。

●あとは、どこまで細かく記載するかは組織にゆだれます。
③品質保証体系が機能するための条件
せっかく、頑張って作った品質保証体系図も
なので、品質保証体系が機能するための条件を考えましょう。3つ挙げます。
- 組織トップの方針と指示
- 各部門の連携力
- システムより人間力
組織トップの方針と指示
●組織を良くも悪くもするのは、トップです。トップの方針と強いトップダウンが必要です。そうしないと、組織の担当者は誰も動きません。
また、指示どおり強制しても、人は動きません。人は理念や思いに共感して初めて行動します。品質を作りこむ大切さを日々トップから伝えなければなりません。
各部門の連携力
●普段から連携できる必要があります。具体的には
- 日常会話もOK。
- 営業が行く顧客打合せに設計・製造担当を連れて行って、顧客要求を肌で感じとらせる。
- 設計・製造現場に営業も行って、自組織の実力を理解する。
- 営業、設計、製造、品質の部門間で人を入れ替えるなどの人事異動
システムより人間力
●品質保証体系図だけ作ってもダメで、それをうまく回すのは「人」です。
大事なのは、
組織がよりよい活動になるにはどうしたらよいか、仕組と人の観点で考える事
品質保証体系図をみれば、その組織の実力がわかってしまう理由もここにあります。
まとめ
「品質保証体系図がわかる」をわかりやすく解説しました。
- ①品質保証体系図とは
- ②品質保証体系図を作ろう!
- ③品質保証体系が機能するための条件