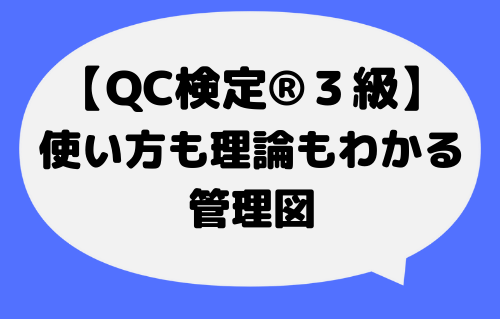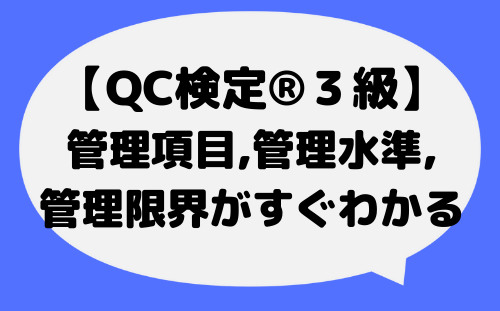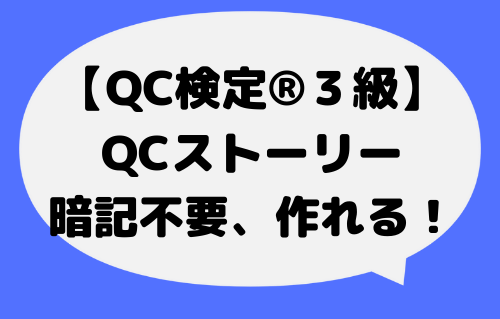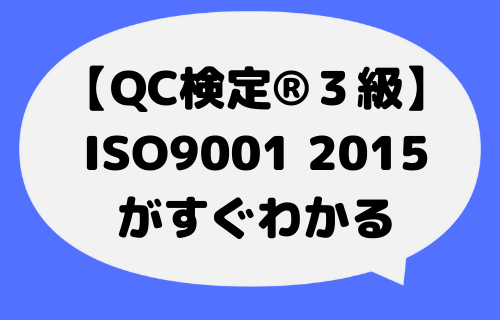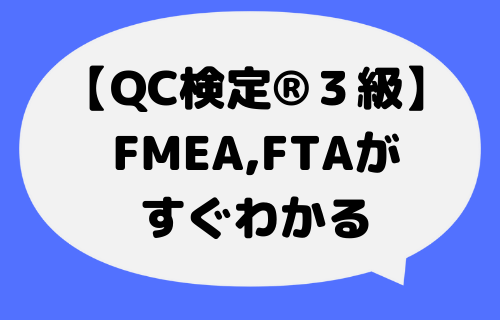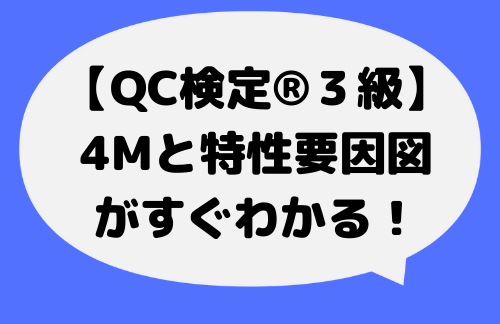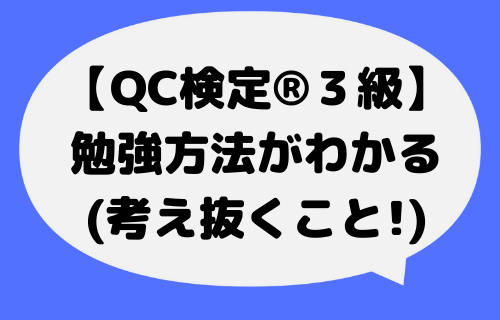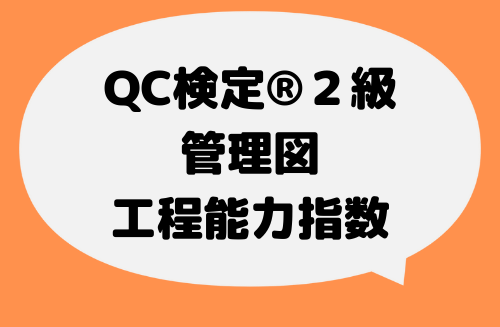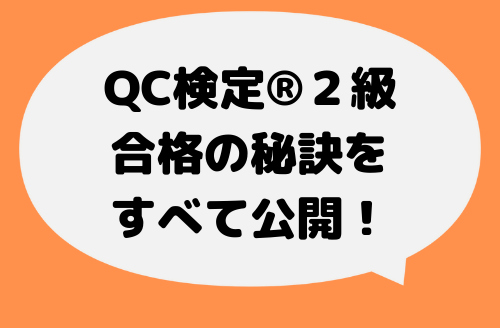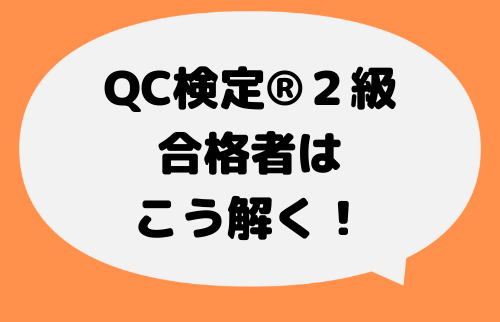★ 本記事のテーマ
【必読】QC検定®2級が合格できる解き方を解説(試験実践編)
①私の必勝テクニック
②実践編1(典型的な問題)
③実践編2(苦手な実験計画法)
④実践編3(文脈から解く文章問題)
本記事だけ読めば合格できます。
★ QC模試受験しよう!
★ 【QC検定® 2級合格対策講座】で必勝!
★ 【必勝メモ】と【必勝ドリル】のご紹介
試験合格に必要最小限エッセンスをまとめた「必勝メモ」と
★ 品質管理(QC)を究める数理問題集(初級・中級向け)
QC検定®3級、QC検定®2級受験の方、QC検定®1級受験挑戦する方への問題集(80問)です。
●商標使用について、
①QC検定®と品質管理検定®は、一般財団法人日本規格協会の登録商標です。
➁このコンテンツは、一般財団法人日本規格協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。
➂QCプラネッツは、QC検定®と品質管理検定®の商標使用許可を受けています。
●リンクページ
①私の必勝テクニック
●You tube動画にも説明しています。ご確認ください。
VIDEO
●全文を丁寧に読まない。
の3つだけです。この3つのテクニックがあれば、60分程度で16題100問解けます。
QC検定®1級受験直前に2級を解くと、20分くらいで解けます。(勉強しすぎ?)。ここまで来ると、答えが勝手に浮かび上がってきます。
これだけでは、「本当に速く正確に解けるの?」と疑問が残りますので、3題例を挙げて解説します。
②実践編1(典型的な問題)
●全文を丁寧に読まない。
では、
次の問題を5分以内で回答してください。
【1】工程能力に関する次の文章において、『』に入るもっとも適切なものを下欄の選択肢からひとつ選び、その記号を解答欄にマークせよ。ただし、各選択肢を複数回用いることはない。
工程能力指数\(C_p\)とは、製造工程が『(1)』状態にある場合に、その工程が作り出す品質の能力をはかる指標である。『(1)』した工程では、製品特性値は母集団分布が正規分布N(μ、σ^2)と仮定した場合に、工程能力指数をより詳しく求めるために、両側、片側を配慮した指数を計算することができる。
1)上側規格\(S_U\)だけわかっている場合
\(C_p\)と\(C_{pk}\)の使い分け方は、『(2)』は製品特性値の母平均が規格の中心である場合、または、中心と仮定しても良い場合に使用し、そうでない場合は『(3)』を用いる。
母平均μと母標準偏差σは未知であることが多い。実際は、工程から製品をサンプリングしたn個のデータ\(x_1\),\(x_2\),…, \(x_n\)を取り、母平均と母標準偏差を下の式のように『(4)』して考える。
工程能力を評価する場合、次の判断基準を使う。
ただし、ここで注意すべき点がある。工程能力指数の判断基準はσに照らし合わせるべきであるが、実際は標準偏差sの値を使った工程能力指数で判断するのは適切ではない。なぜなら、標準偏差sは統計量であり、ばらつきを持つからである。実際はばらつきを考慮した工程能力の区間推定を計算し、その信頼区間を考慮して判断基準を照らし合わせると良い。
【選択肢】
長い、長い文章、読むだけで時間オーバーなりそう。
長文の問題です。これを5分でどう解けばよいでしょうか?
ポイントは、全文読まない。必要なところだけ読む。
では、どこを読めばよいか、マークして再度問題を読みましょう。
【1】工程能力
に関する次の文章において、『』に入るもっとも適切なものを下欄の選択肢からひとつ選び、その記号を解答欄にマークせよ。ただし、 各選択肢を複数回用いることはない。
工程能力指数\(C_p\)とは、製造工程が『(1)』状態にある場合に、その工程が作り出す品質の能力をはかる指標である。『(1)』した工程では、製品特性値は母集団分布が正規分布N(μ、σ^2)と仮定した場合に、工程能力指数をより詳しく求めるために、両側、片側を配慮した指数を計算することができる。
1)上側規格\(S_U\)だけわかっている場合
\(C_p\)と\(C_{pk}\)の使い分け方は、『(2)』は製品特性値の母平均が規格の中心である 場合、または、中心と仮定しても良い場合に使用し 、そうでない場合は『(3)』を用いる。
母平均μと母標準偏差σは未知であることが多い。実際は、工程から製品をサンプリングしたn個のデータ\(x_1\),\(x_2\),…, \(x_n\)を取り、母平均と母標準偏差を下の式のように『(4)』して考える。\(\bar{μ}\)=\(\bar{x}\)=\(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i\)
工程能力を評価する場合、次の判断基準を使う。b) 『(5)』> (工程能力指数) ≥ 1.00 なら工程能力はやや不足している。
ただし、ここで注意すべき点がある。工程能力指数の判断基準はσに照らし合わせるべきであるが、実際は標準偏差sの値を使った工程能力指数で判断するのは適切ではない。なぜなら、標準偏差sは統計量であり、ばらつきを持つからである。実際はばらつきを考慮した工程能力の区間推定を計算し、その信頼区間を考慮して判断基準を照らし合わせると良い。
【選択肢】
読むところだけ抜き出します。ほとんど読むところはないですが、これでも十分回答できますね。
【1】工程能力,各選択肢を複数回用いることはない。
工程能力指数\(C_p\)とは、製造工程が『(1)』状態にある場合。
母平均μと母標準偏差σは未知であることが多い。実際は、工程から製品をサンプリングしたn個のデータ\(x_1\),\(x_2\),…, \(x_n\)を取り、母平均と母標準偏差を下の式のように『(4)』して考える。
【選択肢】
教科書のレベルなので、考える時間は必要ないでしょう。答えは
●全文を丁寧に読まない
③実践編2(苦手な実験計画法)
全文を読まないメリットは理解いただけと思います。では、最も難しく、受験者が苦しむであろう実験計画法(二元配置実験、繰返し有り)の場合を解いてみましょう。
次の問題を8分以内で回答してください。
【2】実験計画法に関する次の文章において、『』に入るもっとも適切なもの下欄の選択肢からそれぞれ一つ選び、この記号を解答欄にマークせよ。ただし、各選択肢を複数回用いることはない。
①ある製品特性値xを大きくしたい。因子A(2水準)、因子B(4水準)、繰返し2回の計16回の実験をランダムな順序で実施した。各因子の主効果と交互作用を調べる。AiBj水準で繰返しk番目のデータの構造式は『(1)』と書ける。なお、分散分析によって交互作用A×Bが小さく、有意でない場合、誤差項にプーリングした場合のデータの構造式は『(2)』と書ける。
●『(1)』,『(2)』の選択肢
②実験の結果、下表のデータを得た。表に、データの集計結果や平均値もある。
平方和S
自由度φ
不偏分散V
A
『(3)』
B
8
A×B
『(4)』
e
1.25
T
52
●『(3)』,『(4)』の選択肢
③分散分析表から、因子Aは有意水準1%,有意水準5%で有意となったが、交互作用A×Bは有意ではなかった。そこで、交互作用A×Bを誤差項にプーリングし、再度分散分析をおこなった。因子A,Bともに有意水準1%で『(5)』となった。
●『(5)』の選択肢
最適な水準の組み合わせは『(6)』で、その母平均の点推定値は、データの構造式『(2)』に基づき、データ表を代入して『(7)』が得られる。
●『(6)』の選択肢
●『(7)』の選択肢
④プーリング後の誤差の平均平方(不偏分散)\(V_E\)は『(8)』で有効繰返数\(n_e\)の逆数は『(9)』であり、最適な水準の組み合わせの母平均の信頼度95%の信頼区間は『(10)』である。
●『(8)』の選択肢
●『(9)』の選択肢
●『(10)』の選択肢
*ポイントは
●全文読まない。
では解いてみましょう。時間制限の中、速く解くことを意識しましょう。
【2】実験計画法
に関する次の文章において、『』に入るもっとも適切なもの下欄の選択肢からそれぞれ一つ選び、この記号を解答欄にマークせよ。ただし、 各選択肢を複数回用いることはない。
①ある製品特性値 xを大きくしたい 。因子A(2水準)、因子B(4水準)、繰返し2回の計16回の実験をランダムな順序で実施した。各因子の主効果と交互作用を調べる。AiBj水準で繰返しk番目の データの構造式は『(1)』と書ける。なお、分散分析によって 交互作用A×Bが小さく、有意でない場合、 誤差項にプーリングした場合のデータの構造式は『(2)』と書ける。
●『(1)』,『(2)』の選択肢イ.\(x_{ijk}\)=μ+\(α_i\)+\(β_j\)+\({αβ}_{ij}\)+\(ε_{ij}\) ウ.\(x_{ijk}\)=μ+\(α_i\)+\(β_j\)+\({αβ}_{ijk}\)+\(ε_{ij}\)
●解説教科書の式を目に焼き付けていれば、アとエはすぐにわかるはずです。何度も復習がここで力を発揮します。
②実験の結果、下表のデータを得た。表にた、データの集計結果や平均値もある。
ここで、分散分析をした結果、次の結果が得られた。
平方和S
自由度φ
不偏分散V
A
『(3)』
B
8
A×B
『(4)』
e
1.25
T
52
●『(3)』,『(4)』の選択肢
●解説分散分析を速く解くために、平方和を速く計算する必要が必須です。
●平方和\(S_A\),\(S_B\),\(S_{AB}\),\(S_{A×B}\)を速く解く練習と、
●分散分析表を埋めていきます。
●自由度はすぐにわかります。A =2-1=1B =4-1=3A×B =(2-1)(4-1)=3e =残り=8
平方和\(S_A\)と自由度を分散分析表に入れましょう。他の値も求められることがわかります。
平方和S
自由度φ
不偏分散V
A
16
1
B
3
8
A×B
『(4)』
3
e
8
1.25
T
52
15
自由度×不偏分散から平方和が計算できます。残りの平方和が計算できるので、分散分析表の値が埋まります。
平方和S
自由度φ
不偏分散V
A
16
1
16
B
24
3
8
A×B
2
3
0.67
e
10
8
1.25
T
52
15
–
分散分析表の穴埋め問題の解き方も重要です。平方和の計算を速くすることは重要ですが、分散分析表の穴埋めから簡単に求められないかも注視しましょう。
③分散分析表から、因子Aは有意水準1%,有意水準5%で有意となったが、交互作用A×Bは有意ではなかった。そこで、交互作用A×Bを誤差項にプーリングし、再度分散分析をおこなった。因子A,Bともに有意水準1%で『(5)』となった。
●『(5)』の選択肢
●F検定の計算です。
・\(F_A\)= \(V_A\)=/ \(V_e\)=16/1.09=14.67
・F検定は、
A,B両方計算しましたが、実際は1つで十分です。試験時間を有効活用しましょう。
最適な水準の組み合わせは『(6)』で、その母平均の点推定値は、データの構造式『(2)』に基づき、データ表を代入して『(7)』が得られる。
●『(6)』の選択肢
●『(7)』の選択肢
『(5)』は捨てても『(6)』、『(7)』は落とせません。
『(6)』は(キ) (7,8が最も大きな値)
実験計画法で、10問中7問自信があれば、あとは適当にマーク塗って1点ゲットできたらラッキーとして次の文章問題(こっちの方が簡単)でしっかり点数稼ぐことも重要です。
次の問いは、「不合格に陥れる罠」です。QC検定®2級を少し超えるレベルで、試験時間を消耗させる罠です。でも落としても3点です。どこかで取り返せるはず。試験時間を温存しましょう。
また、大問1から、ここまで来ると試験時間で40分程度かかるはずで、相当疲れているはずです。そろそろ小休止とってもよいでしょう。
一応解説しますが、捨てて次の問いに行きましょうね。合格すれば何でもOK。
④プーリング後の誤差の平均平方(不偏分散)\(V_E\)は『(8)』で有効繰返数\(n_e\)の逆数は『(9)』であり、最適な水準の組み合わせの母平均の信頼度95%の信頼区間は『(10)』である。
●『(8)』の選択肢
●『(9)』の選択肢
●『(10)』の選択肢
●解説
・『(9)』: 伊奈の式で一発計算ですが、これが難しいですよね。
・『(10)』:絶対捨てましょう
●全文を丁寧に読まない
④実践編3(文脈から解く文章問題)
次の問題を6分以内で回答してください。
【3】QCサークル活動における次の文章において、『』に入るもっとも適切なもの下欄の選択肢からそれぞれ一つ選び、この記号を解答欄にマークせよ。ただし、各選択肢を複数回用いることはない。
ある会社では、QCサークル活動を全社的への展開を推進しているが、各部門がどのように活動すればよいか悩んでいる。そこで、品質部門が各部門に出向き、QCサークル活動の進め方について検討会議を実施した。
①営業部門との協議
b)実際に、売上計画についてのテーマを挙げると、「顧客訪問回数倍増による売上計画達成」というテーマがうまくいかないことを聞いた。うまくいかないのはテーマ名に問題があるのではないか。テーマ名の中に『(3)』が入っているが、適切ではない。なぜなら、訪問回数と売上計画達成の間には因果関係があるかわからないからだ。メンバーで集まって、なぜ売上計画が達成できないか要因分析する必要がある。いろいろな検討方法が考えられるが、売上計画が達成できない問題では、原因や結果、目的や手段などが複雑に絡み合っている可能性が高い。そこで、『(4)』図を用いて、矢線で論理的につなぎ、整理することもよいことだ。
●『(1)』~『(4)』の選択肢
②間接部門
●『(5)』~『(8)』の選択肢
*ポイントは
文脈から回答せざるを得ない問ですが、それでも必要な箇所だけ読みます。文章問題の後半になると試験時間が60分超えで、疲れと試験終了の焦りが出てきます。ですから、なおさら、文章をポイントだけ見て回答していくことが重要となってきます。
では解いてみましょう。回答に必要な箇所だけ抜き出します。
【3】QCサークル活動
における次の文章において、『』に入るもっとも適切なもの下欄の選択肢からそれぞれ一つ選び、この記号を解答欄にマークせよ。ただし、 各選択肢を複数回用いることはない。
ある会社では、QCサークル活動を全社的への展開を推進しているが、各部門がどのように活動すればよいか悩んでいる。そこで、品質部門が各部門に出向き、QCサークル活動の進め方について検討会議を実施した。
①営業部門との協議そして、日ごろの営業活動は、その 『(1)』を生み出すための『(2)』である。確実に売上計画を達成するには、営業活動という『(2)』を改善していく必要がある。よって、テーマとして取り上げることで、個々のメンバーが単に『(1)』を追求するだけでなく、より効果的な営業『(2)』がどうあるべきかを考え、自ら改善する力を養うことが期待できる。営業部門としても、QCサークル活動は有効である。
b)実際に、売上計画についてのテーマを挙げると、 「顧客訪問回数倍増による売上計画達成」というテーマがうまくいかないことを聞いた。うまくいかないのはテーマ名に問題があるのではないか。テーマ名の中に『(3)』が入っているが、適切ではない。なぜなら、訪問回数と売上計画達成の間には因果関係があるかわからないからだ。メンバーで集まって、なぜ売上計画が達成できないか要因分析する必要がある。いろいろな検討方法が考えられるが、売上計画が達成できない問題では、 原因や結果、目的や手段などが複雑に絡み合っている可能性が高い。そこで、『(4)』図を用いて、矢線で論理的につなぎ、整理することもよいことだ。
②間接部門 間接部門では、各担当が少ないリソースの中で何とか仕事をしている。しかし、改善テーマと言われてもアイデアが出てこないという説明を受けた。品質部門は、各担当の業務については一見問題がないように見えるが、実際は問題が顕在化していないだけかもしれない。 製造部門では作業手順書などに基づいて業務しているが、間接部門の場合は製造部門と違い、仕事の内容と実施方法が『(5)』化しないことが多い。また、個々の業務を決まった担当者が行うことが多く、仕事が『(6)』されがちである。仕事が『(5)』化されず、『(6)』化された状態では、仕事のやり方に問題があっても、外部から改善を指摘されることはなく、ムダがあっても長期間そのままであることが多い。 改善すべきテーマ問題とは、『(7)』と『(8)』とのギャップである。まず、現在の業務の内容や実態をかき出し、『(7)』を可視化し、メンバーが『(8)』を設定し、共有することで、テーマを作るとよいだろう。
●『(5)』~『(8)』の選択肢
読むべきところだけ抜き出すと以下になります。
【3】QCサークル活動、各選択肢を複数回用いることはない。
アウトプット、すなわち『(1)』である。『(1)』を生み出すための『(2)』である。
「顧客訪問回数倍増による売上計画達成」というテーマがうまくいかないことを聞いた。うまくいかないのはテーマ名に問題があるのではないか。テーマ名の中に『(3)』が入っているが、適切ではない。なぜなら、訪問回数と売上計画達成の間には因果関係があるかわからないからだ。原因や結果、目的や手段などが複雑に絡み合っている可能性が高い。そこで、『(4)』図を用いて、矢線で論理的につなぎ、整理することもよいことだ。
これでも十分回答できますよね。
1分かかりませんね。
製造部門では作業手順書などに基づいて業務しているが、間接部門の場合は製造部門と違い、仕事の内容と実施方法が『(5)』化しないことが多い。また、個々の業務を決まった担当者が行うことが多く、仕事が『(6)』されがちである改善すべきテーマ問題とは、『(7)』と『(8)』とのギャップである。
●『(5)』~『(8)』の選択肢
これでも十分回答できますよね。
1分かかりませんね。これで8点ゲットしましょう。
大問3つを使って、試験時間で勝てる戦い方を解説しました。
勝つ解き方
●全文を丁寧に読まない
あとは実践! 頑張ってください。
試験時間が足りない無い方は
●全文を読んで時間がかかっている
の3つです。能力が十分あるのに勿体ないです。
勝てる方法を身に着けて、本番頑張ってください。合格しましょう。
まとめ
QC検定®2級で、試験で勝てるための解き方を解説しました。
①私の必勝テクニック
②実践編1(典型的な問題)
③実践編2(苦手な実験計画法)
④実践編3(文脈から解く文章問題)